|
|
| 宮宿(第41番) ~ 鳴海宿(第40番) |
'17.12.10 9:30
①七里の渡し舟着場跡・・・愛知県名古屋市熱田区神戸町
*先回は西から桑名の七里の渡し跡まで歩いたが、この間は海路のため、
今回は宮宿側の渡し場からのスタートとなった)
七里の渡しは、宮宿と桑名宿を結ぶ東海道唯一の海路で、その距離が七里(27.5km)であったことから、そう名付けられた。この海上ルートは、東海道の宿駅制度(制定は1616年頃といわれている)が設けられる以前、すでに鎌倉・室町時代から利用されており、古くから東西を結ぶ重要な交通インフラであった。もっと古くは、壬申の乱の際に、吉野から逃れた大海人皇子(後の天武天皇)の一族が桑名から海路、尾張に渡ったという説もある。
歌川広重による「東海道五十三次」の中にも宮の宿船着場風景が描かれており、当時の舟の発着の様子を知ることができる。 |
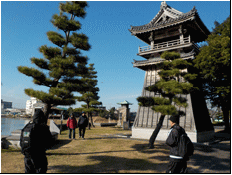 |
 |
②宝勝院・・名古屋市熱田区神戸町508
西山浄土宗、蓬寿山宝勝院。重要文化財の阿弥陀如来立像がある。聖徳寺のあとを継ぎ、熱田湊常夜燈の管理を明治中期まで務めた。 |
 |
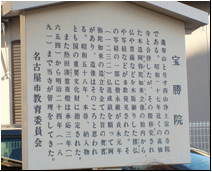 |
③宮宿陣屋跡(あつた蓬莱軒)
・・愛知県名古屋市熱田区神戸町503
「ひつまぶし」で有名な「あつた蓬莱軒」の本店があるこの地は宮宿陣屋跡地である。 |
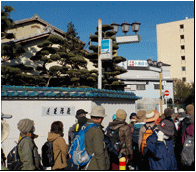 |
④三叉の道標
・・愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目
熱田伝馬町の西端は、江戸時代、東海道と美濃路(又は佐屋路)の分岐点で、重要な地点であり、この道標は建立当時〔寛政2(1790)年〕より三叉路東南隅にあったが平成27年に現在の位置に移設された。
なお、この三叉路の東北隅には、これより32年前(宝暦8年)に建立された道標があり、戦災で破損したが復元され、10mほど北側にある。 |
 |
 |
⑤熱田区伝馬町近辺の旧東海道
宮宿は熱田神宮のお膝元、本陣2、脇本陣1、旅籠248、家数2924軒、人口10342人の東海道でも最大規模を誇る宿場であった。伝馬町から神戸町にかけて本陣、脇本陣、問屋場、西浜御殿、船番所が建ち並んでおり、往来の人並みが途絶えなかった。 |
 |
⑥姥堂・裁断橋址・・愛知県名古屋市熱田区伝馬二丁目5番19号
姥堂は、延文3年(1358)の創建で、精進川を徒歩で渡ろうと溺死した僧侶の衣類を盗んだ貪欲な老婆が亡くなりその霊が夜になるとさまよったので縁者が供養のため像を安置したと言われている。本尊姥像は、熱田神宮から移したものと言われ、「おんばこさん」と親しまれてきた。第二次大戦で焼失したが、平成5年に復元された。
裁断橋は豊臣秀吉の小田原征伐に出陣し病死した堀尾金助の霊を弔うため金助の母が老朽化した橋の修築をおこなった。橋の擬宝珠(ぎぼし)には仮名で母が子を思う銘文が刻まれている。明治時代に河川改修により川筋が変わり大正末期には埋立られた |
 |
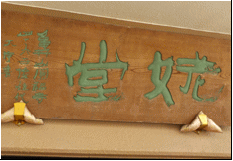 |
 |
⑦山崎城址・・愛知県名古屋市南区呼続元町16-22
築城年は定かではない。蔵人浄盤の居城であったが、その後、加藤与三郎が入る。
加藤与三郎の後、佐久間信盛の居城となるが、1580年「石山本願寺攻め」の際、積極的な働きが無かったことから信長に追放され、廃城となる。
現在は安泰寺に変わり、遺構は無い。 |
 |
⑧山崎の長坂・呼続・・愛知県名古屋市南区
山崎橋の先から始まる「山崎の長坂」と呼ばれる登り坂周辺はかつて立場で賑わった所で、宮宿から渡し船の出港を呼び継いだことから「よびつぎ」の地名が付いたと言われている |
 |
 |
 |
⑨長楽寺・・愛知県名古屋市南区呼続4丁目13-18
弘仁12年(821年)に空海が巡礼に訪れた際に見た夢のお告げで、呼続の浜に七堂伽藍を創建。真言宗戸部道場寛蔵寺と命名して「鎮守清水叱枳眞天」を安置したと言われている。
その後一旦寺勢が衰えたが、文明年間(1470年頃)に義山禅師が再興し、永正5年(1508年)に今川氏が諸堂を再建。この頃に曹洞宗の寺となり、明谷禅師が寺号を長楽寺と改めた。
|
 |
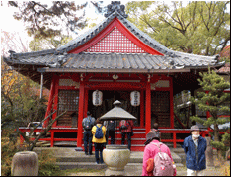 |
⑩笠寺観音・・愛知県名古屋市南区笠寺町上新町83番地
正式名は天林山笠覆寺。
天平5年(733年)、僧・善光が浜辺に打ち上げられた流木を以て十一面観音像を彫り、現在の南区粕畠町にその像を祀る天林山小松寺を建立したのが始まりであると伝わる。
その後1世紀以上を経て堂宇は朽ち、観音像は雨露にさらされるがままになっていた。ある時、旅の途中で通りかかった藤原兼平が、雨の日にこの観音像を笠で覆った娘を見初め、都へ連れ帰り玉照姫と名付け妻とした。この縁で兼平と姫により現在の場所に観音像を祀る寺が建立され、笠で覆う寺、即ち笠覆寺と名付けられたという。笠寺の通称・地名等もこの寺院名に由来する。 |
 |
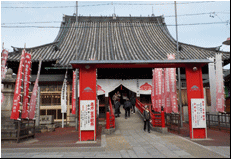 |
⑪丹下町常夜燈
鳴海宿の西口丹下町に建てられた常夜灯である。
表に「秋葉大権現」右に「寛政四年一一」左に「新馬中」裏には「願主重因」と彫られている。
寛政4年(1792)、篤志家の寄進により設置されたものである。
旅人の目印や宿場内の人々及び伝馬の馬方衆の安全と火災厄除などを秋葉社に祈願した火防神として大切な存在であった。
平部の常夜灯と共に、鳴海宿の西端と東端の双方に残っているのは、旧宿場町として貴重である。 |
 |
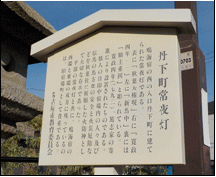 |
⑫鳴海宿本陣跡
鳴海は、江戸時代東海道五十三次の宿駅の一つとして栄えた。宿駅には、一般の旅人用の旅籠屋とは別に、勅使・公家・大小名など身分の高い人が、公的に宿泊する本陣が置かれた。鳴海宿の本陣は、ここにあり、幕末のころ、そのおよその規模は間口39m・奥行51m・建坪235坪・総畳数159畳であり、東海道で最大の規模であった。なお、天宝14年(1843)の調査によれば、宿駅内には、家数847軒・人口3643人・旅籠68軒(全体の8%)と記録され、当時の繁栄ぶりが推測される。また、予備の脇本陣は、2軒あった。 |
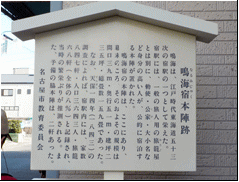 |
⑬誓願寺・・愛知県名古屋市熱田区白鳥2-10-12
浄土宗、天正元年(1573)僧俊空の開山。本尊は阿弥陀仏。
元禄7年(1694)10月に芭蕉が亡くなった翌月の命日に如意寺に建立し、その後移された供養塔がある。芭蕉の供養塔としては最も古いものである。また安政年間に永井士前とその門人が建立した芭蕉手植えの杉の古木に彫刻した芭蕉像が安置されている芭蕉堂がある。 |
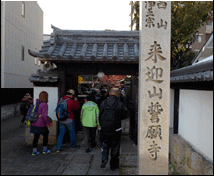 |
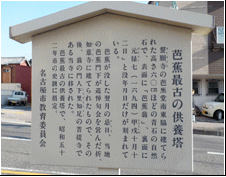 |
⑭鳴海城跡・・愛知県名古屋市緑区鳴海町城
根古屋城ともいい、応永年中(1394~)安原宗範の築城と言われている。永禄3年(1560)桶狭間の戦いでは今川方の猛将岡部元信がこの城に配され、義元が討たれた後も最後まで立てこもって奮戦した。
その後佐久間信盛、正勝らが城主となったが天正18年(1590)廃城になったと伝えられる。
「尾張志」は東西75間、南北34間で四面に堀跡、本丸と二・三の丸にも堀を残すと帰している。
現在、城址は鳴海城跡公園となっており遺構は残っていないが、周辺より高台となっており、要害であったことを偲ばせている。また近隣の鳴海神社に石碑や案内板が建てられている。 |
 |
 |
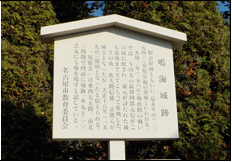 |
⑮高札場跡・・ 愛知県名古屋市緑区鳴海町字本町
東海道鳴海宿では、江戸時代、宿場の中央にあたる東海道と鳴海駅前通りの交差点東北角に大きな屋ね付きの高札場が作られ、高札が掲示されていました(ここより南に約70mの場所)。
この高札場の図面や絵図などは残されていないが、東海道宿村大概帳によると、高さ2間2尺、長さ3間、幅1間との記述が残されている(1間:約180m、1尺:約30㎝)。また、当時の高札8枚が名古屋市博物館に保管されている。宿場間の駄賃や人足賃を示した高札は、宿場町ならではのもので、当時の様子をうかがい知ることができる。 |
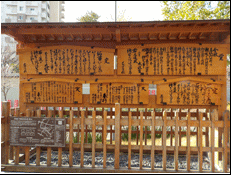 |
⑯千代倉・・愛知県名古屋市緑区鳴海町相原町27
「千代倉」と看板を掲げる蕎麦屋。
幕末まで鳴海宿本陣を務めた鳴海の豪族下郷家が営んでいた造り酒屋が「千代倉」
二代目当主は俳人で芭蕉とも懇意だったとのこと。 |
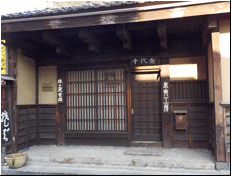 |
⑰瑞泉寺・・愛知県名古屋市緑区鳴海町字相原町4
応永三年(1396年)根古屋の城主安原宗範の創建、始め宗範の法名瑞松居士を取って瑞松寺と云った。その後瑞泉寺と改めた。 瑞泉寺は四國直傳弘法の第一番にふさわしい大きな寺院で、本堂にある御籠は古き昔を忍ばせてくれる。 巡礼の参拝者が気楽に経を上げる事が出来る雰囲気があるのは参拝者にとって嬉しい限りである。 |
 |
 |
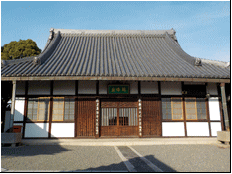 |
⑱平部町常夜燈・・愛知県名古屋市緑区鳴海町平部
鳴海宿の東の入口である、平部町に建てられたものである。
表に「秋葉大権現」右に「宿中為安全」左に「永代常夜燈」裏に「文化三丙寅正月」の文字が刻まれている。文化3年(1806年)に設置されたもので、旅人の目印や宿場内並びに宿の安全と火災厄除などを秋葉社(火防神)に祈願した。
大きく華麗な常夜燈であり、道中でも有数のものといわれ、往時の面影を偲ぶことができる。 |
 |
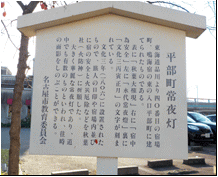 |
⑲有松の町並み・・愛知県名古屋市緑区有松
有松のまちは、慶長13年(1608)に尾張藩の奨励によってつくられた。
阿久井庄(現在の愛知県知多郡阿久井町)から移住した竹田庄九郎はじめ8名により開かれ、絞りの名産地として発展した。
天明4年(1784)、大火により村の大半が焼失するという災難に見舞われ、復興をはかるなか、建物は火災に備えて漆喰を厚く塗り込めた塗籠造とし、萱葺き屋根に替わって瓦葺が使用された。今も当時の面影を残した町家が並び、有松地区ならではの風情を漂わせている。 |
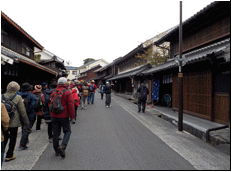 |
⑳小塚家住宅・・名古屋市緑区有松806番地
有松の町並み保存地区内にあり、名古屋市指定有形文化財。
主屋は1階が連子(れんじ)格子と腰は海鼠(なまこ)壁、2階は虫籠(むしこ)窓となっており、妻側に卯建(うだつ)のある白漆喰の塗籠(ぬりごめ)造りである。
土蔵も外壁は白漆喰による塗籠、腰は簓子(ささらご)下見板張りとなっている。
改造も少なく重厚広壮な絞問屋の形態をよく残している。 |
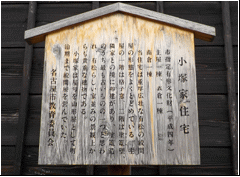 |
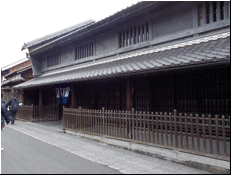 |
 |
21. 竹田家住宅
・・名古屋市緑区有松1802番地
小塚家住宅と同様に有松の町並み保存地区内にあり、名古屋市指定有形文化財。
主屋は1階が連子格子、2階は虫籠窓のある黒漆喰の塗籠造、腰は海鼠壁で土蔵も黒漆喰塗りである。
通りに面しては大和(やまと)張りの塀や長屋門、腕木門がある。
外観の偉容は、有松の町並み景観を形成する建物の一つである。
|
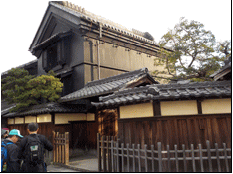 |
 |
22. 桶狭間古戦場・・名古屋市緑区桶狭間北3丁目
永禄3年(1560)5月19日、小勢の織田信長が今川義元の大軍を破った古戦場の史跡であり池鯉鮒宿と有松宿の間に位置する。
文化6年(1809)、秦鼎の撰文により津島の神主・氷室豊長が建てた「桶狭弔古碑」に「永禄3年、駿侯西征のため5月19日桶狭の山北に陣す、織田公奇兵を以って之を襲い、駿侯義元を滅す」の一文がある。
2万5千の兵をもって2千の織田軍に敗れ、首を討ち取られた義元の墓周辺は小さな公園として整備されている。近くの高徳院背後の丘陵を信長は駆け下って奇襲したとも伝えられている場所。 |
 |
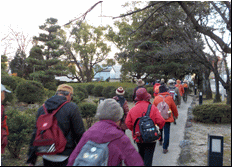 |
23. 高徳院・・豊明市栄町南舘3-2
高野山真言宗、桶狭間本山。弘仁元年(810)開創以来高野山上にあり、明治27年(1894)諦応が本尊および寺名をこの地に移し、本堂を建立して安置した。開基は智泉大徳。
境内には、今川義元の仏式墓所や本陣跡の石碑、今川軍の重臣・松井宗信の墓碑が残っている。 |
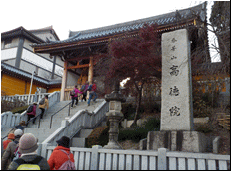 |
 |
24. 今回の終点・・豊明市前後町善江1735
今回はここまで。次回はここからスタートする。
'17.12.10 16:45 |
 |
|
|