|
|
| 鳴海宿(第40番) ~ 池鯉鮒宿(第39番) |
'18.1.21 9:30
①名古屋鉄道前後駅
・・・愛知県豊明市前後町善江1634-2
先回の終点
今回はここからスタート |
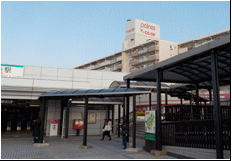 |
②阿野一里塚
・・・愛知県豊明市阿野長池下114
日本橋から86里目、京から39里目の一里塚 |
 |
③豊明駅近辺の東海道(現1号線)
・・・愛知県豊明市前後町善江
向こうに見えるのは伊勢湾岸自動車道 |
 |
④境橋 ・・・愛知県豊明市阿野町惣作36
江戸時代にここ境川に架けられていた境橋は尾張側は板橋、三州側は土橋の継ぎ橋だったといい、度々の洪水に流される度に修復された。そのうちに一つの土橋になり、明治になって欄干付きの橋になった。
尾張側には江戸時代前期の公卿で歌人だった烏丸光広の歌碑が立つ。
うち渡す尾張の国の境橋
これやにかわの継目なるらん
光廣 |
 |
 |
⑤お富士の松
・・愛知県刈谷市今川町1丁目
桶狭間の戦いで敗れた今川勢が退却した後、旅人がこの今川町を通ったときに今川勢は相手のまわしものだと思い、この旅人を誤って殺してしまった。それを見た住民は旅人を哀れに思い、葬った後にその場所へ1本の松を植えた。その松が成長しお富士の松と呼ばれるようになったと言われており、村名「富士松」はお富士の松に由来する。 |
 |
⑥「いもかわうどん」の碑
・・・愛知県刈谷市今岡町日向
江戸時代の東海道紀行文に「いも川うどん」の記事がよく出てくる。この名物うどんは「平うどん」でこれが東に伝わって「ひもかわうどん」として現代に残り、いまでも東京ではうどんのことを「ひもかわ」と呼ぶ。 |
 |
 |
⑦洞隣寺 ・・・愛知県刈谷市今岡町日向14
曹洞宗の寺で天正8年(1580)の開山といわれ、開基は刈谷城主水野忠重とされる。本堂の隣に地蔵堂・行者堂・秋葉堂が並んでいる。寺の入口にある常夜灯は寛政8年(1796)の年号が刻まれている。 |
 |
⑧一ツ木一里塚 ・・・愛知県刈谷市一里山町深田
日本橋から85里目、京から40里目の一里塚
国道1号線の開通によって当時の面影は無いが明治18年の地籍図を見ると東海道の両脇に塚と記載されている。 |
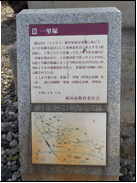 |
⑨池鯉鮒宿
池鯉鮒宿は江戸から数えて39番目の宿場町。
西三河一の名社「知立神社」の御手洗池に多くの鯉や鮒がいたことから「池鯉鮒」と名付けられた。天保14年の記録では宿場の家数292軒、本陣・脇本陣・問屋場とも1軒、旅籠屋35軒。
池鯉鮒宿は馬が数百頭も集まる馬市も開かれ、安藤広重の浮世絵「東海道五十三次・池鯉鮒」にもその模様が描かれている。またこの宿場は衣浦湾を挟んで知多半島をひかえ、また挙母、吉良、刈谷へ至る道の分岐点でもあったため西三河の交通の要として繁栄し、知立神社への参拝でも賑わった。
宿場の東には在原業平が折句で
か・・からころも(唐衣)
き・・き(着)つつなれにし
つ・・つま(妻)しあれば
ば・・はるばる来ぬる
た・・たび(旅)をしぞ思ふ
とカキツバタを読み込んで有名になった八橋があり、伊勢物語や更級日記に記されるなど、平安時代からこの地が親しまれていたことがうかがえる。
今も無量寿寺のカキツバタでその頃が偲ばれる。
|
⑩総持寺・・・愛知県知立市西町新川48
嘉祥3年(850)慈覚大師円仁が開基と伝えられる。
承應2年(1653)東叡山寛永寺末寺として再興され知立神社を統治していたが明治六年神仏分離に際し廃寺となる。
大正12年天台寺門宗として復興された。 |
 |
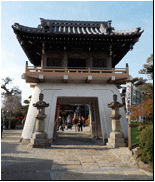 |
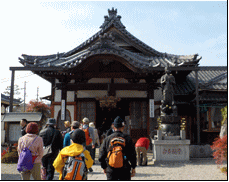 |
⑪知立神社・・・愛知県知立市西町神田12
知立神社は池鯉鮒大明神とも称し、延喜式に記される三河国二の宮で、碧海郡六座の一つ。創祀は第12代の景行天皇の時代とされる古社。江戸時代には東海道三社の一つに数えられ、「まむし除け」や「雨乞い」「安産の神」として信仰を集めた。
境内の多宝塔は嘉祥3年(850)に円仁という僧が知立神社の神宮寺を創建した際に建立したと伝わる。築500年を超える神宮寺の建築を知る貴重な遺構。国の重要文化財。 |
 |
重要文化財 多宝塔  |
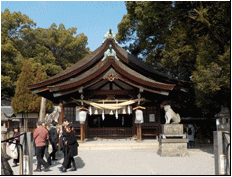 |
⑫知立古城址・・・愛知県知立市西町西10
築城年代は定かではないが永見氏によって築かれた。 永見氏は知立神社の神主で、その居館が知立城の始まりとされる。 戦国時代には刈谷城水野氏との関係を深め、台頭してきた松平清康、ついで今川義元に仕えるが、今川義元が桶狭間に倒れると敗走した今川軍を追った織田方によって落城した。
天正年間に刈谷城主水野忠重によって御殿が建てられ、将軍上洛時の宿泊施設となっていたが、元禄12年(1699年)の大地震により倒壊した。 |
 |
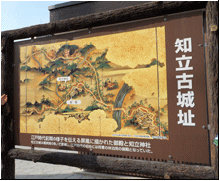 |
⑬山車の蔵
今でも毎年行われる知立神社の祭礼(知立まつり)で使われる山車の保管庫。
山車の奉納がいつから行われていたか定かではないが承応2年(1652)に行われた記述が残っている |
 |
⑭池鯉鮒宿本陣跡・・・愛知県知立市本町
池鯉鮒宿の本陣職は当初峯家が勤めていたが(杉屋本陣)、没落したため寛文2年(1662)からは永田家に引き継がれた(永田本陣)。敷地三千坪、建坪三百坪と広大な面積を有していたが明治8年に取り壊され、二百年近く続いた永田本陣もその使命を終えた。 |
 |
⑮松並木・馬市之跡碑
・・・愛知県知立市山町御林
慶長9年(1604)江戸幕府は五街道に一里塚と並木を設置することを命じた。この知立松並木は今も約500mに渡って残っている。
江戸時代には池鯉鮒宿東の野で馬市が立ち、今も残る松並木両側の側道は売買する馬を繋ぐために設けられたもの。 |
松並木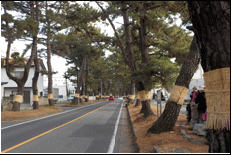 |
安藤広重の浮世絵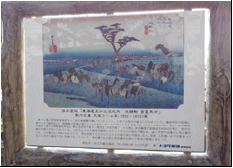 |
馬市之跡碑 |
⑯元禄の道標・・・愛知県知立市来迎寺町
「従是四丁半北 八橋 業平作観音有
元禄九丙子年六月吉朔日施主敬白」
と書かれている。
元禄9年(1696)に在原業平ゆかりの八橋無量寿寺への道しるべとして建てられたものであることが分かる。 |
 |
⑰来迎寺一里塚
・・・知立市来迎寺町古城24-1
日本橋から84里目、京から41里目の一里塚
来迎寺の集落を通る旧東海道の左右両側に設けられた一里塚。
一部崩れてはいるものの左右両方が残っているのは大変珍しい。 |
 |
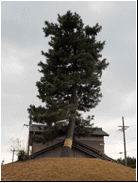 |
⑱知立市来迎寺町近辺の旧東海道 |
 |
⑲永安寺・雲竜の松・・・愛知県安城市浜屋町北屋敷17
永安寺は延宝5年(1677)に重い助郷役(すけごうやく)に苦しむ貧しい人々のために、その免除を願い出て刑死したと伝えられる柴田助太夫の霊を祀るお寺。
この寺を覆い包むように横に枝を広げたクロマツの巨木は樹齢300年程と推定される。力強い幹を周囲に伸ばす見事な枝ぶりの松で、樹高約4.5m、枝張りは東西約17m、南北約24m。県の天然記念物。 |
 |
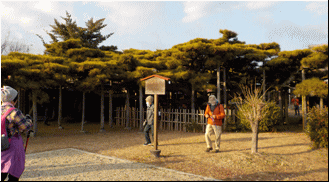 |
⑳熊野神社・・・愛知県安城市尾崎町亥ノ子
708年創建と伝わる |
 |
 |
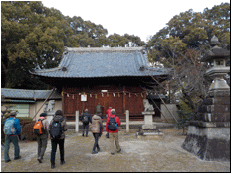 |
21. 尾崎一里塚 ・・・愛知県安城市尾崎町亥ノ子
日本橋から83里目、京から42里目の一里塚
熊野神社前にあり |
 |
22. 旧鎌倉街道跡 ・・・愛知県安城市尾崎町亥ノ子
建久3年(1192)鎌倉に幕府が開かれると京都と鎌倉の間に鎌倉街道が定められ、宿駅63ヶ所が設置された。
尾崎町では里町不乗の森神社から証文山の東を通り熊野神社に達していた。知立八橋から続く鎌倉街道がここで向きを変えるため、神社は「踏分の森」とも称される。 |
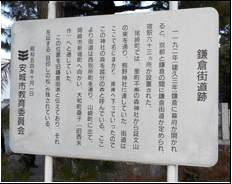 |
23. 今回の終点・・・愛知県岡崎市宇頭町山ノ神
今回はここ宇頭駅まで
次回はここからスタート
'18.1.21 16:30 |
 |
|
|