|
|
| 池鯉鮒宿(第39番) ~ 岡崎宿(第38番) |
'18.2.12 9:30
①宇頭駅・・・愛知県岡崎市宇頭町山ノ神
今回はここからスタート |
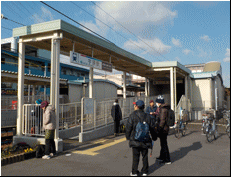 |
②和志王山薬王寺
・・愛知県岡崎市宇頭北町
1丁目2−3
古墳時代中期(5世紀)にこの地に勢力のあった皇孫の古代豪族の子孫が奈良時代に建立されたと考えられている由緒あるお寺。御本尊の薬師瑠璃光如来は17年に一度御開帳される秘仏として本堂に納められている。 |
 |
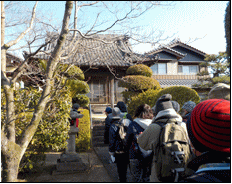 |
③この辺りは1号線を通る |
 |
④誓願寺・十王堂・・・愛知県岡崎市矢作町馬場4
承安4年(1177)、牛若丸は、奥州平泉の藤原秀衡を頼って旅を続ける途中、矢作の里を訪れ兼高長者の家に宿をとり、ふと聞こえてきた浄瑠璃姫の琴の音色にひかれ、持っていた笛で吹き合わせたことから、いつしか二人の間に愛が芽生えた。 しかし義経は奥州へ旅立ち、姫は義経を想う心は日毎に募るばかりで、添うに添われぬ恋に、ついに菅生川に身を投じて短い人生を終えた。
誓願寺は、義経が浄瑠璃姫に贈ったとされる笛「薄墨」が安置されている。浄瑠璃姫の父兼高長者が、義経と浄瑠璃姫の木像、姫の鏡などの遺品とともにここに葬り、十王堂を建てたといわれている。 |
 |
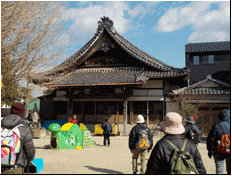 |
⑤岡崎市矢作町辺りの旧東海道 |
 |
⑥勝蓮寺・・愛知県岡崎市矢作町宝珠庵16
真宗大谷派の当寺は河原山と号し、天台宗の僧恵堯が師の恵心作の薬師如来を矢作の里の柳樹の元に御堂を建てて納め、柳堂薬師寺と称したことが起源といわれている。
その後、嘉禎元年(1235)に当寺の別当舜行が親鸞聖人の法弟となり、恵眼の法名を受け真宗に改められた。
松平8代広忠、家康、信康、石川日向守などの崇敬が厚く、特に17代住職行誓の時には松平信康候と関係が深く、現存する唯一の肖像画など、多くの遺品が保存されている。 |
 |
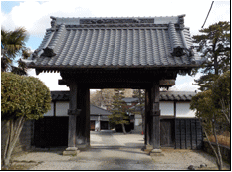 |
⑦小六・日吉丸出合之像・・・愛知県岡崎市矢作町市場
日吉丸(後の豊臣秀吉)と蜂須賀小六が出会ったと伝わる矢作橋のたもとにある石造。
西からはこの橋を渡ると岡崎宿に入る
<日吉丸と蜂須賀小六出合いの伝説>
8才で奉公に出された日吉丸は12才の時、奉公先の陶器屋を逃げ出した。家へ帰ることもできず東海道を東へ下る途中、空腹と疲れで矢作橋の上で前後不覚で寝てしまった。ここに海東群蜂須賀村に住む小六正勝(後の蜂須賀小六)という野武士の頭が手下をつれてこの付近を荒らし矢作橋を通りかかった。通りざまに眠りこけている日吉丸の頭をけったところ、日吉丸は、「頭をけり、ひと言のあいさつをしないのは無礼である。詫びて行け」と、きっとにらみつけた。小六は子どもにしては度胸があると思い、手下にするからその初手柄を見せよと言ったところ日吉丸はすぐさま承知し、橋の東の味噌屋の門のそばの柿の木によじ登り、邸内に入り扉を開けて、小六たちを引き入れた。目的を果たし逃げようとした時、家人が騒ぎだしたため日吉丸はとっさに石をかかえ井戸に投げ込み、「盗賊は井戸に落ちたぞ」と叫び、家人が走り集まるすきにすばやく門を抜け、小六たちの一行に追いついたと言われている。日吉丸と小六とのこの伝説は、後の太閤秀吉と、武将蜂須賀小六の人間的一側面を語る物語として、今なお私たちの心に生き続け、乱世の時代劇を垣間見る挿話となっている。
ただし実際には矢作橋が作られたのはもっと後らしく、あくまでも伝説ということらしい。 |
 |
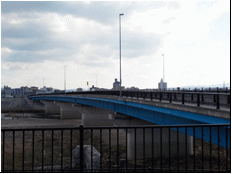 |
⑧岡崎宿
江戸から数えての三十八番目の宿場である岡崎宿は家康の祖父、松平清康が岡崎城を居城として以来、城下町として発展した。天正18年(1590)岡崎に徳川家康が関東に移封され、その後入城した田中吉政(豊臣家家臣)が南側を通っていた東海道を城下に引き入れ、様々な整備拡張を行い宿場町岡崎発展の原形を成した。
天保14年編纂の宿村大概帳によれば、本陣3軒、脇本陣3軒、旅籠112軒であり、旅籠数は53宿中3番目という有数の宿場町であったことがうかがえる。 |
⑨八丁味噌蔵・・愛知県岡崎市八帖町字往還通
江戸時代、徳川家康公誕生の岡崎城から西へ八丁(約870m)の距離にある八丁村(現在:愛知県岡崎市八帖町)で2軒の味噌蔵(現在の「カクキュー」と「まるや」)が造っていたことから、その地名より「八丁味噌」と呼ばれていた。
極力水分を少なく仕込む八丁味噌は保存性に優れていたため、三河武士の「兵糧(ひょうろう)」として岡崎藩に保護され、岡崎藩御用達となり、岡崎の伝統品である花火や石工とともにこの地の地場産業として発展してきた。
2軒の味噌蔵が旧東海道を挟んで向かい合って営業していたことにより、街道を往来する参勤交代やお伊勢参りの旅人を通じて「八丁味噌」の名が広く知られるようになり、その後の運送網の整備に伴い全国的に知られるようになった。 |
 |
 |
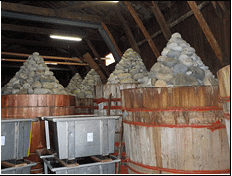 |
 |
<日吉丸石投の井戸> →→→
前述の「日吉丸が蜂須賀小六と押し入った味噌蔵は現在の「まるや」だと言われ、家人に追われて石を投げ込んだ井戸と伝わる井戸が保存されている |
 |
⑩岡崎城下二十七曲り
宿内の街道は曲がり角が多く、「岡崎城下二十七曲り」と呼ばれている。これは敵の侵入に対する防御の意味だけでなく、城下の東海道を長くすることで商業地を大きくする狙いもあり、城下発展に貢献した。
なお現在の曲がりは21箇所であり、戦災等の影響で変わったためと思われる。 |
 |
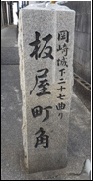 |
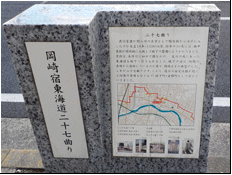 |
⑪新田白山神社・・・愛知県岡崎市康生町 345
新田白山神社は、永禄 9年(1566)、家康公が厄除開運祈願のため、源氏である新田氏のゆかりの地である上野国(群馬県)の新田より勧請した(祭神は白山姫命と新田義重)と伝わる。当初は岡崎城の城内にありその曲輪は白山曲輪と呼ばれ歴代岡崎城主から崇敬庇護された |
 |
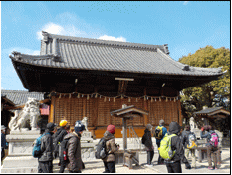 |
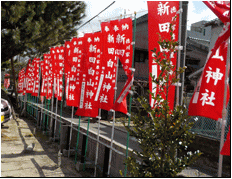 |
⑫籠田総門跡・・愛知県岡崎市籠田町
籠田総門は江戸時代に東海道を通り岡崎城の城郭内に入る東の入口であり、承応3年(1654)に西側の松葉総門とともに建てられた。 |
 |
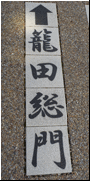 |
⑬籠田総門角常夜燈
この常夜燈は寛政10年(1798)岡崎城下3番目のものとして石工、七左衛門作により籠田総門付近に建立され町内と旅人往来安全の灯として、市井の人々に愛され温かく守護され続けてきたものである。 |
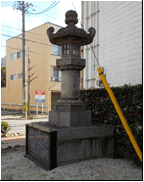 |
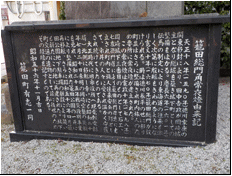 |
⑭西本陣跡
・・・愛知県岡崎市伝馬通2丁目35 |
⑮東本陣跡
・・・愛知県岡崎市伝馬通3丁目1  |
⑯秋葉山大権現常夜燈・・・愛知県岡崎市伝馬通4丁目5−1
享和3年(1803)に建立された常夜燈 |
 |
⑰根石寺(旧根石観音堂)
・・・愛知県岡崎市若宮町1-11
当寺の本尊である観世音菩薩は行基菩薩の作と言われ、和銅元年(708)に悪病が流行した際、元明天皇が行基法師に悪疫を絶やしてほしいと念願された。そこで法師は六体の観音像を彫り、内2体を根石の森に勧請して17日間祈祷を続け、悪病を治めたと伝わる。
天正元年(1573)、徳川信康が初陣の折にこの観音像を祈願して軍功をあげて以来、開運の守り本尊として崇められているとのこと。 |
 |
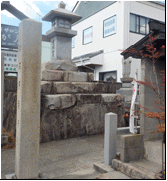 |
⑱愛知県岡崎市大平町欠下近辺
1号線の側道脇に松並木が残っている |
 |
⑲大平一里塚・・・愛知県岡崎市大平町
江戸から80里の一里塚 |
 |
⑳西大平藩陣屋・・・ 愛知県岡崎市大平町西上野95
大岡越前守忠相の陣屋跡。寛延元年(1748)、時代劇でもおなじみの大岡越前守忠相は当初旗本だったが72歳の時に前将軍吉宗の勧めもあり、寛延元年(1748)に三河国宝飯(ほい)・渥美・額田3郡内で四千八十石の領地を加増され、一万石の大名となった。忠相時代の所領は本貫地である相模国高座郡大曲村の他関東各地に分かれており、晩年には所領統合を申し出ている。しかし忠相は宝暦元年(1751)には亡くなったため藩主だったのは3年間だった。第3代藩主忠恒の頃には三河国への所領統合が完了。藩主は定府大名であり、江戸に居住し参勤交代をしなかったため、西大平村に陣屋のみが設置された。家臣団のほとんどは江戸藩邸に住んでおり、陣屋詰めの家臣は、多いときでも郡代1人、郡奉行1人、代官2人、手代3人、郷足軽4、5人程度だった。大岡氏の本領である大曲村は相伝され、忠相をはじめ歴代藩主の墓は神奈川県茅ヶ崎市の浄見寺にある。 |
 |
 |
21. 美合新町(愛知県岡崎市美合新町)
今回はここまで
'18.2.12 15:50 |
 |
|
|