|
|
| 岡崎宿(第38番) ~ 御油宿(第35番) |
'18.3.12 9:10
①愛知県岡崎市美合新町
今回はここから
(岡崎宿と藤川宿の間で先回のゴール地点) |
 |
②吉良道道標
・・愛知県岡崎市藤川町境松9
東海道は藤川宿の西端で土呂、西尾、吉良方面への道が分岐する。この道は吉良道と呼ばれており、ここ分岐点に「吉良道道しるべ」が立っている。 |
 |
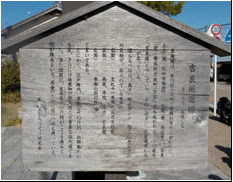 |
③藤川宿の一里塚
・・愛知県 岡崎市藤川町一里山南14
江戸日本橋から79里、京都から47里の一里塚跡。道の両側に植わっていた榎はなくなっている。 |
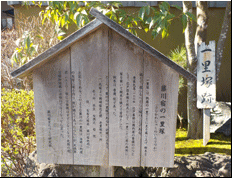 |
④藤川の十王堂・・愛知県岡崎市藤川町一里山南25
十王堂は十人の王を祀る堂。
「王」とは冥土で亡者(死んだ人)の罪を裁く十人の判官、「秦広王」「初江王」「宗帝王」「五官王」閻魔王」「変成王」「平等王」「太山王」「都市王」「五道転輪王」
の総称である。
現在の堂はH29年12月に復元されたもの。 |
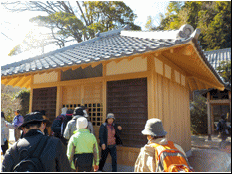 |
 |
⑤芭蕉句碑・・愛知県岡崎市藤川町一里山南25
碑は十王堂の敷地にあり、
「爰(ここ)も三河 むらさき麦の かきつはた」
と詠まれている |
 |
⑥西棒鼻跡
・・愛知県岡崎市藤川町西町北44
宿場の出入口は棒鼻と呼ばれており、ここは藤川宿の西の入口「西棒鼻」であった。 |
 |
 |
藤川宿
五十三次37番目の宿場町。
天保14年(1843)当時の藤川宿人口は1203人、家数302軒、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠36軒の小規模な宿場町であった。慶安元年(1648)増大する通行量に対処するため山中郷から住民を移して藤川村加宿の市町村が成立し、ここを藤川宿東町として中町、西町の3町で宿場を構成した。当初は2軒の本陣が置かれていたが、江戸期を通して退転と交代を繰り返し江戸時代後期には森川久左衛門の1軒が本陣を務め、大西喜太夫が経営する橘屋が脇本陣をつとめて本陣を補佐した。 |
 |
⑦脇本陣跡・・岡崎市藤川町字中町北6-1
脇本陣を営んでいたのは大西喜太夫で「橘屋」と呼ばれていた。
隣接する畑で「むらさき麦」が栽培されている。これは昔この一帯で作られていたが戦後作られなくなったもので、平成6年に地元の人々の努力で栽培が復活した。 |
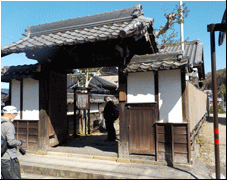 |
 |
⑧本陣跡・・岡崎市藤川町字中町北10
藤川宿の本陣は中心地の字中町北にあり、もともとは2件であったが退転を繰り返し江戸後期には「森川久左衛門」が務めていた。裏手には当時の石垣が残っている。 |
 |
 |
⑨高札場・・岡崎市藤川町字中町北10
藤川宿の高札は6枚が現存し、それらは正徳元年のもので、岡崎市の文化財に指定されている。内容は、
・藤川よりの駄賃並人足賃
・駄賃並人足賃荷物次第
・親子兄弟夫婦みな親しく
・切支丹禁制
・毒薬にせ薬種売買の事禁制
・火付け用心
もともと問屋場の東に設置されていたものをここに復元した。 |
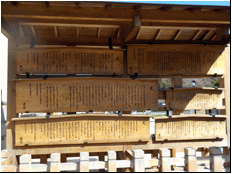 |
⑩藤川宿問屋場跡
・・愛知県岡崎市藤川町中町北
藤川宿の「問屋場」は、ここ宇中町北にあった。宿場町では最も中心となった場所で、人馬の継ぎ立て(伝馬)、書状の逓送(飛脚)などの業務を行う所が「問屋場」であった。藤川宿ではここを「御伝馬所」とも称していた。 |
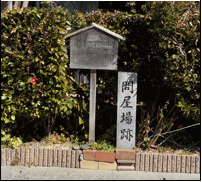 |
⑪明星院・・愛知県岡崎市市場町元神山16
本尊は不動明王立像で「片目不動尊」と呼ばれている。永禄5年、扇子山で蒲郡の鵜殿長持と松平軍を率いて戦い、劣勢となり敗走する家康を武士の姿となってかばい、矢を受けて片目になったと伝えられている。 |
 |
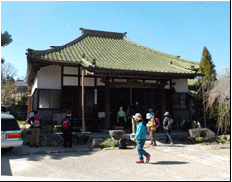 |
⑫東棒鼻跡・・愛知県岡崎市稲熊町8丁目
藤川宿の東の入口(東棒鼻)であった。
歌川広重の藤川宿棒鼻の版画は幕府が毎年八朔、朝廷へ馬を献上する一行がここ東棒鼻に入ってくるところを描いたものである。 |
 |
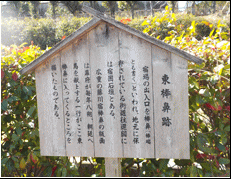 |
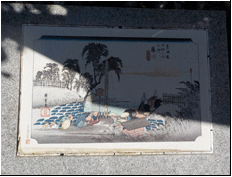 |
⑬山中八幡宮
・・愛知県岡崎市舞木町宮下8
家康公の父・広忠が再興したといわれ、家康公初陣の際に必勝祈願した神社。三河一向一揆の際に、追われた家康公が境内の洞窟(鳩ヶ窟)に身を隠して難を逃れるなど、尊崇した場所と伝わる。境内には推定樹齢650年、根回り14mの楠の大木がある。 |
 |
 |
⑭山中御宮常夜灯・・愛知県岡崎市舞木町宮下
山中八幡宮入口の鳥居近くに位置する |
 |
⑮是より東 本宿村
・・愛知県岡崎市本宿西2丁目
本宿村は街道とともに開けた地であり、赤坂宿と藤川宿の中間に位置する村としての役割を果たした。
家数121軒、立場茶屋が2軒あり、旅人の休息の場として栄えた。 |
 |
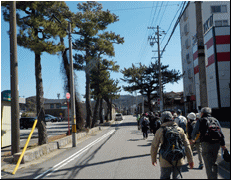 |
⑯宇都野龍碩邸跡
・・愛知県岡崎市本宿町森ノ腰
本宿村医学宇都野氏は古部村(現岡崎市古部町)の出といわれ、宝暦年間(1751〜63)三代立碩が当地で開業したのが始まりといわれている。七代龍碩はシーボルト門人青木周弼に医学を学んだ蘭方医として知られている。安政年間 当時としては画期的ともいわれる植疱瘡(種痘)を施している。 |
 |
⑰本宿一里塚跡・・愛知県岡崎市本宿町一里山8
江戸日本橋から78里に一里塚跡 |
 |
⑱秋葉常夜灯
・・愛知県岡崎市本宿町後畑2 |
 |
⑲本宿陣屋跡と代官屋敷
・・愛知県岡崎市本宿町南中町
元禄11年(1698)旗本柴田出雲守勝門(柴田勝家の子孫)が知行所支配のために本宿村に陣屋を設けた。
陣屋代官屋敷は冨田家が世襲し、現存の居宅は文政10年(1827)の建築である。 |
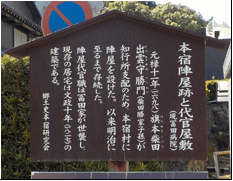 |
20.法蔵寺・・愛知県岡崎市本宿町寺山1
大宝元年(701)僧行基の開山と伝えられ、松平初代親氏が深く帰依して至徳4年(1387)に堂宇を建立し、寺号を法蔵寺としたと言われている。家康が幼い頃に手習いや漢籍を学んだとされ、数々の遺品が現存している。桶狭間の合戦以降家康は法蔵寺に守護不入の特権を与えるなど優遇した。 |
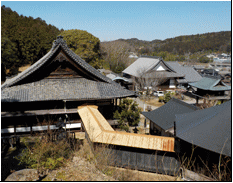 |
21.新撰組隊長近藤勇首塚・・法蔵寺境内
新撰組局長の近藤勇は、明治元年東京板橋で斬首された。京都三条大橋西に晒された首を同士が持ち出し、近藤が生前敬慕していた京都誓願寺住職に託した後、住職が転任したここ法蔵寺に運ばれた。
当初は、石碑を土で覆い、ひっそりと弔ったといわれている。 |
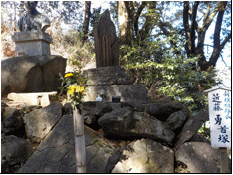 |
22.長沢一里塚・・・愛知県豊川市長沢町欠田
江戸から77里の一里塚 |
 |
23.杉森八幡社 ・・豊川市赤坂町西縄手15番地
起源は、古く西暦702年とされ、寛和2年(986年)の棟礼が現存。祭神は天照大神、誉田別尊、大鷦鷯尊、息長足姫尊。境内の楠の巨木は二樹の根株が一本化し、二本に成長していることから夫婦楠と呼ばれるようになった。
高さ約20メートルの楠は推定樹齢1,000年とされている。 |
 |
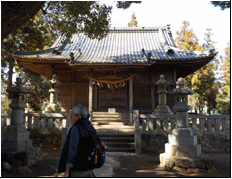 |
 |
赤坂宿
江戸から36番目の宿場町
赤坂宿と御油宿の間は1.7kmで五十三次の中でもっとも短い。
もともと御油宿と赤坂宿は赤坂御位という大きい宿場で、最大80の旅籠があった。東海道でも非常に大きい宿場町であったため五街道整備の際に徳川家康の命により中央に松を植え、赤坂宿と御油宿という二つの宿場に分けられた。
赤坂宿は人口1304人、本陣3軒、脇本陣1軒、旅籠62軒。宿内には赤坂陣屋が設けられ三河の天領支配の中心をなした |
 |
24.正法寺・・愛知県豊川市赤坂町西裏69
真宗大谷派の寺院。聖徳太子が三河を訪れた際、赤坂上宮に太子を祀る堂宇を建てたことが起源とされている。
宝徳年間(1449年〜1451年)に現在地に移されたが、明応年間(1492年〜1500年)に本堂が焼失。現在の本堂は万延元年(1860年)に改築されたもの。
境内には樹齢400年以上といわれるワビスケの木がある。 |
 |
 |
 |
25.浄泉寺・・愛知県豊川市赤坂町西裏88
赤坂薬師と石像百観音の霊場として有名である。
安永5年(1776年)に再建された本堂には、阿弥陀如来が安置されている。
境内にあるソテツは広重の赤坂「旅舎招婦図」と題された旅籠風景の浮世絵に描かれたソテツである。赤坂宿の旅籠にあったが明治になって当境内に移植された。 |
 |
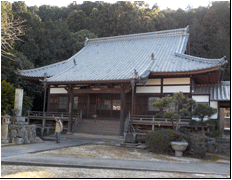 |
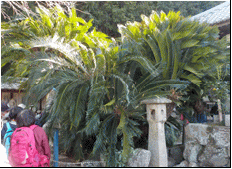 |
26.赤坂宿本陣跡・・愛知県豊川市赤坂町紅里
赤坂宿の本陣は宝永年間には4軒あった。江戸初期より本陣を務めていた松平彦十郎家の本陣は人馬継ぎ立てを行う問屋場も兼ねていた。
間口17間半、奥行き27間の立派なものであった。
近くに高札場跡のモニュメントがある。 |
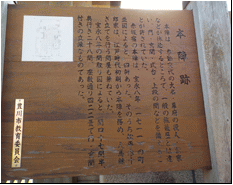 |
 |
27.関川神社 ・・愛知県豊川市赤坂町関川111
関川神社は、三河国司大江定基の命をうけた赤坂の長者宮道弥太次郎長富が、長保3(1001)年にクスノキのそばに市杵島媛命を祭ったのが始めとされ、かつては弁財天と呼ばれていたが、明治の神仏分離策により現在の神社名に改められた。境内にある楠の巨木は樹齢800年と言われている。 |
 |
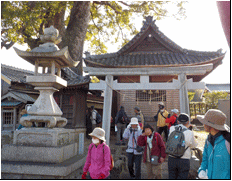 |
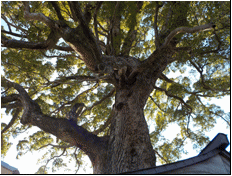 |
28.御油の松並木・・御油宿と赤坂宿の間にある松並木
日本の名松百選に選ばれた御油の松並木は慶長9年(1604)に家康が植樹させたものであり、当初は600本以上あった。昔日の姿をよく残すものとして昭和19年に国の天然記念物に指定された。 |
 |
 |
29.御油の十王堂・・愛知県豊川市御油町美世賜
藤川宿と同様に御油宿にも十王堂があった。
現在の建物は明治時代に焼失後、再建されたもの。 |
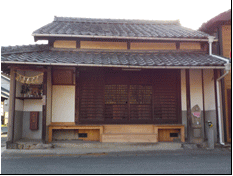 |
30.御関札立掛場・・愛知県豊川市御油町並松
御関札 とは、諸藩の大名が参勤交代等で出向く際、宿泊先となる宿場の本陣や問屋に事前に申し伝え、宿泊当日の三日前迄に本陣、町役人は宿場の出入り口に縦三尺半、横一尺半の板に宿泊年月日・藩主名・出向く先を記入し、長さ三間半の太い竹竿に取り付け立掛けられた看板を言う。
御関札は、大名の権威を誇示するばかりではなく、本陣前を往来する人々に無礼のない様、通行するように注意を促す目的を持って立掛けられた看板と云われる。 |
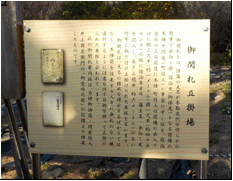 |
31.東林寺・・豊川市御油町今斉28
永享年間(1429~1441)龍月日蔵和尚によって創建され、寺号を洞言庵とし、80年後の永正年間(1504~1521)に堂宇を建立して伽藍を整え、名を白蓮院招賢山東林寺と改めた。500年近い歴史の中で、最も栄えたのは江戸時代であり、それは徳川家康がまだ三河の領主であったころ、二度当寺に立ち寄り休息している事実や、有名な芝増上寺の管長、裕天大僧正が度々訪れていることからもうかがい知ることができる。 |
 |
御油宿
江戸から数えて35番目の宿場町。
両隣の赤坂宿、吉田宿と並び多くの飯盛女を抱えて賑わった宿場だった。
歌川広重は「東海道五十三次之内御油 旅人留女」の題をつけ、強引に客引きをする女たちを浮世絵に描き、東海道中膝栗毛では弥次郎兵衛が客引きの女を振り切り足早に宿場を通り抜ける様子を描いている。
天保14年当時、御油の町並みの長さ9町32間(1040m)、人口1298人、本陣4軒、脇本陣なし、旅籠62軒であった。 |
32.本日のゴール
・・愛知県豊川市御油町美世賜185
御油の松並木資料館近くの交差点。
次回はここから。
'18.3.12 16:22
|
 |
|
|