|
|
| 御油宿(第35番) ~ 吉田宿(第34番) |
'18.4.8 9:35
本日のスタート地点
・・愛知県豊川市御油町美世賜185
御油の松並木資料館近くの交差点 |
 |
①御油宿問屋場跡
・・愛知県豊川市御油町美世賜
馬や人足を常備し、旅行者や荷物を次の宿場に継ぎ送る役目を担う問屋場がこの地にあった |
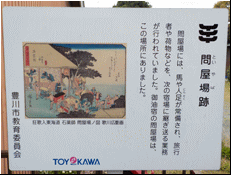 |
| 御油宿内の旧東海道 |
 |
②姫街道追分、秋葉常夜燈・・・愛知県豊川市御油町行力1-31
姫街道とは浜名湖の北側を通って御油宿と見付宿を結ぶ迂回ルートであり、ここは東海道と姫街道の西の分岐点である。
東海道は浜名湖の南岸を通るルートだが宝永4年(1707)の大地震で被害を受け一部が通行不能となり、海路を使うようになった。そのため海路を避けて北側の迂回ルートを使う人が増え、特に女性の利用が多かったため姫街道の名がついた。 |
 |
 |
③御油一里塚跡 ・・愛知県豊川市国府町流霞1
江戸日本橋から76里(京から50里)の一里塚 |
 |
④大社神社・・愛知県豊川市国府町流霞5
天元・永観(978~985)の頃、時の国司大江定基卿が三河守としての在任に際して、三河国の安泰を祈念して出雲大社より大国主命を勧請し、合わせて三河国中の諸社の神々をも祀られた。
社蔵応永7年(1400年)奉納の大般若経典書には、奉再興杜宮大社大神奉拝600年と有る事から、天元・永観以前より当社地には何らか堂宇が存在し、そこへ改めて出雲より勧請して、神社造営をしたものと考えられる。
当社には、徳川14代将軍 家茂が長州征伐に際して、慶応元年5月8日、戦勝祈願をされ、短刀の奉納をされている。
また明治5年(1872年)には、大社神社は国府村の総氏神となった。 |
 |
 |
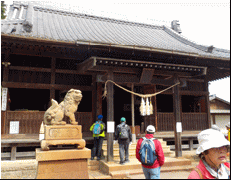 |
⑤秋葉山常夜燈
・・愛知県豊川市久保町葉善寺
寛政12年(1800)に国府村民が村内を火難より守るためこの秋葉山常夜燈を造った |
 |
⑥伊奈一里塚跡
・・愛知県豊川市伊奈町新町2
江戸日本橋から75里(京から51里)の一里塚 |
 |
⑦伊奈村立場茶屋 加藤家跡
・・愛知県豊川市伊奈町茶屋
東海道吉田宿と御油宿の中間にあたり、立場茶屋が設けられた。茶屋のうち格式高い加藤家(初代は大林平右衛門)では、「良香散」という腹薬が有名であった。芭蕉とも親交のあった俳人の鳥巣(うそう)はこの加藤家の生まれである。 |
 |
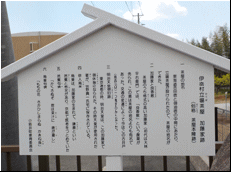 |
⑧菟足神社・・豊川市小坂井町宮脇2
7世紀後半頃に創建されたといわれる足神社は上足尼命(うなかみすくねのみこと)が祀られている。
稲の豊作を願った「田まつり」、風に対する信仰を寄せた「風まつり」が行われる。
風まつりの際に販売される「風車」は郷土玩具として多くの人が買い求める。
また弁慶の書と伝えられている「大般若経」585巻は国の重要文化財に,梵鐘(ぼんしょう)は県の有形文化財に指定されている。 |
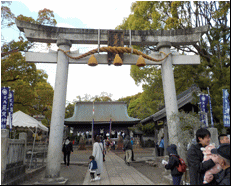 |
 |
 |
「御田植神事」
と「風(かざ)まつり」
菟足神社では当日運良く「御田植神事」が行われていた。また市指定無形民俗文化財の「風まつり」が開催されており、準備中の山車が見られた。 |
 |
 |
⑨瓜郷遺跡・・豊橋市瓜郷町寄道地内
この遺跡は低湿地に囲まれた自然堤防の上に立地する弥生時代中期から古墳時代前期(2000年~1700年前)にかけての集落の跡である。
昭和22年から昭和27年の間に発掘調査が実施され土器・石器・骨角器・木製の農具等が出土した。
ここでは農耕(主に稲作)の他に漁撈や狩猟等が行われていたことがわかった。
瓜郷遺跡は唐古遺跡(奈良県)・登呂遺跡(静岡県)等とともに弥生時代の低地にある遺跡の一つとして貴重なものである。 |
 |
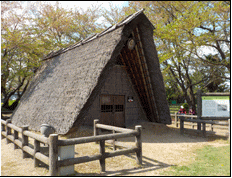 |
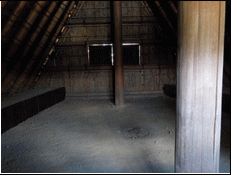 |
⑩下地一里塚跡
・・愛知県豊橋市下地町四丁目
江戸日本橋から74里の一里塚 |
 |
⑪聖眼寺・・・愛知県豊橋市下地町3-3
平安時代に創建され、鎌倉時代に下地に移転したと伝わる現在真宗高田派の寺院。山門前の標石には「寺内に芭蕉塚有、宝暦四甲戌年二月十二日東都花傘宜来」とある。境内の松葉塚には古碑松葉塚、明和六年(1769)の再建松葉塚、宝暦四年(1754)建立の古碑松葉塚標石の三基があり、文学史研究上資料的価値が高いものである。
古碑松葉塚には松尾芭蕉が愛弟子社国に詠んだ句が刻まれ、「松葉塚」の名称の由来を示している。”松葉を焚いて手拭あふる寒さ哉” |
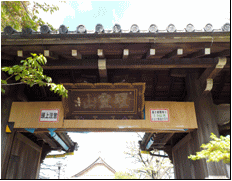 |
 |
 |
⑫豊川稲荷遥拝所
・・・愛知県豊橋市下地町2丁目
遥拝所とは「遠く離れた所から神仏などを拝むために設けられた場所」。横には石柱部分が道標になっている常夜燈が立っている。道標は安政二年(1855)の年号で「左吉田町、右後油道」と刻まれている。 |
 |
⑬吉田大橋(豊橋)・・愛知県豊橋市下地町~船町
豊橋(江戸時代の呼称は吉田大橋)は幕府直轄の五大橋の一つとされ現在の位置の73m下流に架けられていた。矢作橋、瀬田唐橋と共に東海道の三大大橋と言われた。当時は東袂には吉田藩の御船蔵が置かれ藩候専用の波止場があった。 |
 |
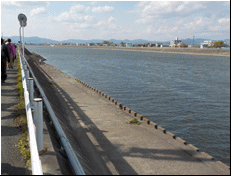 |
⑭高札場跡・・・愛知県豊橋市船町
寛永13年(1636)幕府の命により吉田大橋の南袂に高札場が設けられた。河川の取締り、橋の保護等の極めて重要な取り決めが掲げられていた。 |
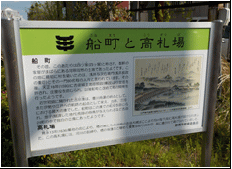 |
⑮吉田城西惣門跡
・・・愛知県豊橋市湊町157
吉田城の西惣門があった場所。往時は惣門の左手に番所があり、12畳の上番所、8畳の下番所、4坪の勝手があり、駒寄せの空地17坪があった。 |
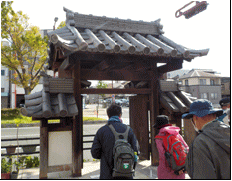 |
吉田宿
吉田宿は現在の豊橋市市街にあった。江戸日本橋から三十四宿目、京都三条大橋から二十宿目の宿場。
規模は宿場の町並み長さ23町30間(2564m)、人口5277人、家数1293軒、本陣2軒、脇本陣1軒、旅籠65軒であった。 |
 |
⑯きく宗
・・・愛知県豊橋市新本町40
創業は文政年間で以来200年以上に渡り吉田宿にて「菜めし田楽」一筋で変わらぬ味を守ってきた。
豆腐に秘伝の味噌を塗った「田楽」と細かく刻んだ大根の葉を混ぜ合わせた「菜めし」が賞味できる。 |
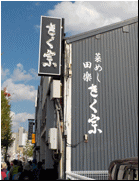 |
⑰吉田宿本陣跡
・・愛知県豊橋市札木町50
清須本陣の跡には現在うなぎ懐石の老舗「丸よ」が店を構える。往時はこの一帯が吉田宿の中心で最も賑わっていた。 |
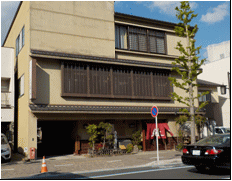 |
| 豊橋市内の旧東海道 |
 |
⑱曲尺手(かねんて)門史跡
・・・愛知県豊橋市曲尺手町
曲尺とは城の出入口や宿場内の街道を鍵の手のように曲がりくねらせて敵の侵入を妨げたもので、曲尺手町として現在も地名に残っている。 |
 |
⑲吉田城東惣門跡
・・愛知県豊橋市八町通5丁目
東惣門は鍛冶町の東側に位置する下モ町の吉田城惣堀西で東海道 にまたがって南向きに建てられていた。 門の傍らには12畳の上番所、8畳の下番所、勝手があり門外の西側に駒寄せ場11間があった。
惣門は朝六ツ(午前六時)から夜四ツ(午後十時)まで開けられており、これ以外の時間は一般の通行は禁止されていた。 |
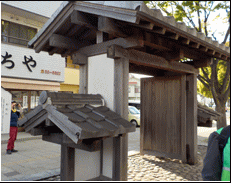 |
⑳秋葉常夜燈
・・・愛知県豊橋市旭本町71
文化2年(1805年)に東海道と本坂通の分岐点に建立された常夜灯であり吉田宿の名残を感じる遺構のひとつ。東惣門の斜め向かいに立っている。 |
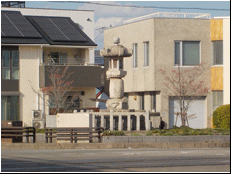 |
本日のゴール(西新町公園) ・・愛知県豊橋市舟原町119
次回はここからスタート予定
'18.4.8 16:25 |
|
|