|
|
| 吉田宿(第34番) ~ 白須加宿(第32番) |
'18.5.21 9:30
①今回はここからスタート(西新町公園)
・・愛知県豊橋市舟原町119 |
 |
| ②吉田宿から二川宿へ繋がる旧東海道の前半は現在の1号線 |
 |
③飯村一里塚跡
・・・愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺
江戸から73里、京から53里の一里塚跡 |
 |
④旧東海道のくろまつ跡
・・豊橋市岩屋町字岩屋下
江戸時代に街道の両側に植えられた松は昭和40年代にはこの地域でも100本以上が残っていたが、その後松くい虫や道路拡張のために減少し、ここにあった最後の松も平成19年に松くい虫の被害に遭い伐採された。 |
 |
⑤岩屋八丁道標
・・・愛知県豊橋市大岩町南元屋敷
「是より岩屋観音へ八丁」の道標
(二川駅前広場にある) |
 |
 |
<二川宿>
二川宿は当初、東西に12町(約1.3km)ほど離れた二川村と大岩村で一宿分の役目をはたしていた。しかし、両村は離れていたため不都合で、参勤交代などで交通量が増えると経済的に行き詰ってしまった。そこで、寛永二十年(1643)に吉田藩領から幕府領に移され、翌正保元年(1644)に両村は現在地に移転し、二川と加宿大岩からなる一続きの宿場町となった。
二川宿は、東海道五十三次の中では比較的小規模な宿場町で、町並長さは加宿を含めて12町16間(1340m)、人口1468人、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠38軒という規模であり、2箇所に街道を屈曲させた枡型が設けられていた。
歌川広重の絵「東海道五十三次之内二川猿ヶ馬場」には「名物かしハ餅」の看板を掲げた茶屋が描かれている。現在も勝和餅(柏餅)がこの地の名物となっている。 |
⑥二川宿内の旧東海道
|
 |
⑦大岩神明宮・・愛知県豊橋市大岩町東郷内14
二川宿の西の外れにある神社。
文武天皇2年(698年)、岩屋山の南山麓に創建されたのがはじまりと伝えられている。江戸時代には黒印地二石を受け、格式は高いものだった。現在では大岩地区の氏神となっている。古くから武将の崇敬を受け、織田信長も三河出陣の際、戦勝を祈願したと言われている。 |
 |
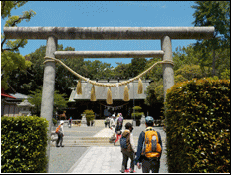 |
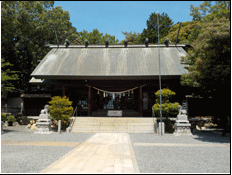 |
| 宿場町の特徴で各建物は間口が非常に狭く、奥行きが長いものとなっていた。今もその名残が残っている。 |
 |
⑧西問屋場跡・・・愛知県豊橋市大岩町東郷内
問屋場は、宿駅本来の業務である人馬の継ぎ立てを差配したところで、宿駅の中核的施設として、公用貨客を次の宿まで運ぶ伝馬と、人足を用意していた。二川宿には西問屋場、東問屋場があったが現在はいずれも道標が立っているのみ。 |
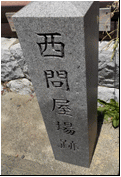 |
⑨二川宿本陣跡・・・愛知県豊橋市二川町中町中町65
二川には現在でも江戸時代の町割りがほぼそのままの状態で残り、東海道筋では滋賀県草津市の草津宿本陣田中家(国指定史跡)とここだけに現存する本陣の遺構がある。 本陣職は後藤家、紅林家、馬場家と引き継がれ、馬場家の本陣が本陣遺構の永久保存と活用を願って豊橋市に寄付された。市では、これをうけて昭和62年に二川宿本陣を市史跡に指定して二川宿ならびに近世の交通に関する資料を展示する資料館を建設し、二川宿本陣資料館として平成3年8月1日に開館した。 |
| |
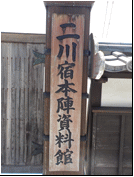 |
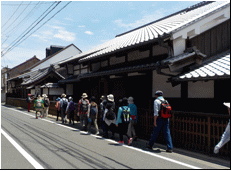 |
⑩清明屋・・・愛知県豊橋市二川町中町中町
旅籠屋「清明屋」は、江戸時代後期から明治時代まで二川宿で営まれた旅籠屋で、当主は代々八郎兵衛を名乗っていた。本陣の東隣に位置することから、大名行列が本陣に宿泊する際には家老などの上級武士の宿泊所としても利用された。
看板は東向きが「せいめいや」、西向きが「清明屋」と書かれ、これは東海道に共通した書き方で、旅人が江戸側、京側を間違わないようにとの工夫である。 |
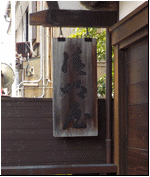 |
 |
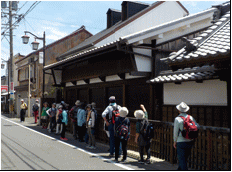 |
⑪東問屋場跡・・・愛知県豊橋市二川町中町
|
 |
⑫豊橋カレーうどん
昼食にB級グルメの「豊橋カレーうどん」を食べた。
丼の中は下から、ご飯、とろろ、カレー、うどんの順でトッピングにはウズラの玉子が載るのが豊橋カレーうどんと名乗る必須条件とか。 |
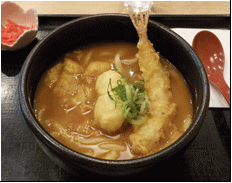 |
⑫東の枡形・・・愛知県豊橋市二川町新橋町
二川宿には2箇所(西の枡形、東の枡形)の枡形の道路があった。当時は直角に曲がっていたが車社会になって斜めの枡形に変更された。この曲がりは大名行列同士がかち合わないようにする役割もあった。
(かち合った場合は格下の大名が籠を止め、頭を下げるしきたりになっていた。そのため部下に偵察させ、格上の大名が来た場合はかち合う前に脇道にそれる等の対応をとっており、枡形の道は便利であった) |
 |
⑬駒屋・・・愛知県豊橋市二川町新橋町
商家「駒屋」は、主屋・土蔵など8棟の建物からなり、二川宿で商家を営むかたわら、問屋役や名主などを勤めた田村家の遺構である。豊橋市内に数少ない江戸時代の建造物で、当時の商家の一般的な形式を良く残していることから、平成15年5月に豊橋市指定有形文化財となった。 |
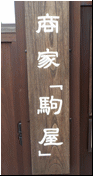 |
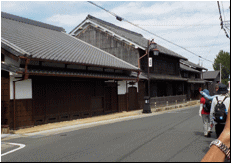 |
 |
⑭妙泉寺・・・豊橋市二川町字東町101-1
妙泉寺は日蓮宗の寺院で、前身は貞和年間(1345~50)に日台上人が建てた小庵だった。その後寛永から明暦(1624~58)の頃、観心院の日意上人が再興し、信龍山妙泉寺と改称。更に万治3年(1660)に現在地に移転して山号を延龍山に改められた。 |
 |
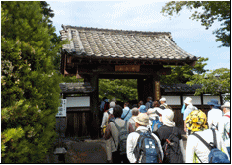 |
 |
⑮二川一里塚跡・・・愛知県豊橋市二川町東町114
江戸から72里、京から54里の一里塚。
|
 |
⑯東細谷一里塚跡・・・豊橋市東細谷町一里山
江戸から71里、京から55里の一里塚。
当時の面影を残すこんもりとした小山が残る。 |
 |
<白須加宿>
白須賀宿は、遠江国の西端の宿場町。東海道五十三次の32番目の宿。
元来、白須賀宿は、潮見坂下の現在の元町にあったが、宝永4年(1707年)の地震・津波により大半の家が流されてしまったため、翌年坂上に所替えをした。
天保14年(1843年)の東海道宿村大概帳によれば、白須賀宿は、江戸日本橋から70里22町(約275キロメートル)の距離で、町並みの長さは東西 で14町19間(約1.5キロメートル)、宿内の人数及び家数は、加宿境宿村を含めて2,704人、613軒だった。本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠屋が27 軒あり、宿場としては中くらいの規模だった。
現在でも、格子戸のある古い民家や、間口の狭い家並みなど、江戸時代の面影を残している。 |
⑰白須加宿の火防・・・ 静岡県湖西市白須賀
東海道白須賀の宿は、津波の難を恐れ、宝永五年(1708年)潮見坂の下から、坂上へ宿替えをした。それまでの坂下の白須賀を、元宿と呼ぶのはこのためである。
宿場の移転以来、津波の心配は無くなったが、今度は冬期に西風が強く、たびたび火災が発生し、しかも大火となることが多かった。これは当時、殆どの家の屋根が、わら葺きであったことにもよる。
そこでこの火事をくい止めるために、生活の知恵として工夫せられたのが火防で、人々は「火除け」とか「火除け地」とか呼んで大切にしていた。
火防の広さは、間口二間(3.6m)奥行四間半(8.2m)で、常緑樹で火に強い槙が十本くらい植えられ、元は宿内に三地点・六場所の火防があった。 |
| |
 |
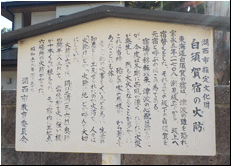 |
⑱夏目甕麿邸址・加納諸平生誕地
・・・静岡県湖西市白須賀3751
夏目甕麿(なつめみかまろ)は、白須賀で酒造業を営む名主の家に生まれた江戸時代後期の国学者。内山真龍に学び、後に本居宣長の門下に入り、国学の普及に努めた。著書には『古野の若菜』のほか歌集数編がある。
加納諸平は甕麿の長男。和歌山の藩医『加納家』の養子となり、『鰒玉集(ふくぎょくしゅう)』をはじめとする数多くの著作を残している。晩年には紀州国学者の総裁となっている。 |
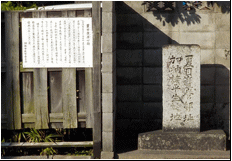 |
⑲白須加本陣跡・脇本陣跡
・・・静岡県湖西市白須賀
当時の白須加本陣は「大村庄左衛門」本陣であり、建坪183坪、畳敷231畳、板敷51畳の規模であった。 |
 |
 |
⑳白須加宿の東海道
|
 |
21. 潮見坂上公園跡・・・静岡県湖西市白須賀
潮見坂上は、かつて織田信長が武田勝頼を滅ぼして尾張に帰るとき、徳川家康が茶亭を新築して信長をもてなしたところと伝わる。
東海道を京側から歩く際に初めて海が見えるのがここ潮見坂上である。 |
 |
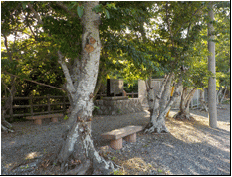 |
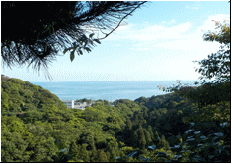 |
22. おんやど白須加
・・・静岡県湖西市白須賀900
(本日のゴール、次回はここから)
'18.5.21 16:55
|
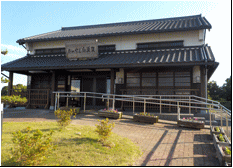 |
|
|