|
|
| 白須加宿(第32番) ~ 舞坂宿(第30番) |
'18.6.17 9:50
今回はここからスタート(おんやど白須加)
・・・静岡県湖西市白須賀900 |
 |
①潮見坂・・・静岡県湖西市白須賀
西国から東海道を歩くと初めて海が見える景勝地として、また急で長い坂であることから箱根と並んで東海道の難所としても有名だった。 |
 |
②白須賀一里塚跡
・・・静岡県湖西市白須賀
江戸から70里、京から56里の一里塚
③高札建場跡
・・・静岡県湖西市白須賀
白須加宿には2ヶ所、また加宿である境宿村にも1ヶ所の高札建場があった。 |
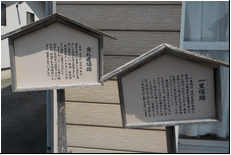 |
近辺の旧街道・・・静岡県湖西市白須賀 |
 |
④立場跡
・・・静岡県湖西市新居町浜名2108−2
旅人や人足、駕籠かき等が休息する茶屋である立場。この立場は新居宿と白須賀宿の間に位置し、代々加藤家が務めていた。 |
 |
⑤風炉の井・・・静岡県湖西市新居町浜名
この石積井戸は建久元年(1190)に源頼朝が上洛の折、橋本宿に宿泊した際にこの井戸水を茶の湯に用いたと伝わる。 |
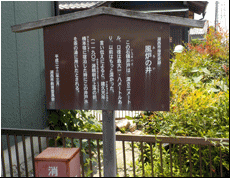 |
 |
<新居宿>
江戸日本橋から31宿目、京都三条大橋から23宿目の新居宿。古くは「荒井」とも書かれた。東側の舞坂宿へは今切の渡しによる渡船で浜名湖を渡り、新居側の渡船場に新居関所を置いて通行人を取り締まった。関所は江戸初期から中期にかけて度重なる高潮や津波の被害にあって2度移転しており、その度に今切渡しの距離が延びている。
天保14年(1843)当時、町並長さは東西2町37間(285m)、南北6町55間(755m)で加宿は7町50間(855m)だった。人口、家数は加宿を含めて3474人、797軒。本陣は疋田弥五郎家、飯田武兵衛家、疋田八郎兵衛家の3軒、脇本陣無し、旅籠26軒だった。
名物は鰻蒲焼、浜名納豆、鰹塩辛等。 |
⑥棒鼻跡・・・静岡県湖西市新居町新居1694−1
街道を一度に大勢の人が通行できないように土塁が突き出て枡形をなしていた。 棒鼻とは、駕篭の棒先の意味があるが、大名行列が宿場へ入るときに仕切り直して恰好良く入場するために、この場所で先頭(棒先)を整えたので、棒鼻と呼ぶようになったともいわれてる。 |
 |
⑦新居一里塚跡
・・・静岡県湖西市新居町新居
江戸から69里、京から57里の一里塚
塚には東に榎、西に松が植えられていた。
|
 |
⑧寄馬跡・・・静岡県湖西市新居町新居
江戸時代の宿場には公用荷物や公用旅行者のために人馬を提供する義務があり、東海道の宿場では常に100人の人足と100匹の馬を用意していた。しかし、交通量が多い時には助郷制度といって、近在の村々から人馬を寄せ集めて不足を補った。寄馬跡は、そのときに寄せ集められた人馬の溜り場になったところ。 |
 |
⑨疋田八郎兵衛本陣跡・・・静岡県湖西市新居町新居1311−1
新居宿に3軒あった本陣の1つ。天保年間の記録によると建坪193坪で、門と玄関を備えていた。八郎兵衛本陣は吉田藩のほか、徳川御三家など約120家が利用した。疋田家は、新居宿の庄屋や年寄役を務めた。 |
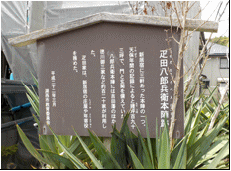 |
 |
⑩飯田武兵衛本陣跡
・・・静岡県湖西市新居町新居
飯田武兵衛本陣も新居宿にあった3つの本陣のうちの1つ。江戸時代に行われた参勤交代では約70家の大名が利用した。明治元年と明治11年の明治天皇の行幸の際には行在所として利用された。 |
 |
⑪新居関跡・・・静岡県湖西市新居町新居1227
新居関所(今切関所)は慶長5年(1600)徳川家康により創設された。幕府は江戸を守るため全国に53ヶ所の関所を設け、「入鉄砲と出女」に対し厳しく取り締まりをしたが、特に新居関所は約100年間、幕府直轄として最高の警備体制が敷かれていた。鉄砲など武器の通行ではもちろんのこと、当関所に限っては江戸へ向かう女性(入り女)にも「手形」が必要で、不備が見つかれば通ることはできなかった。
当関所は江戸時代中期に、自然災害で2度の移転を強いられ、現在に残る建物は、嘉永7年(1854)の地震でそれまでの建物が倒壊したあと、安政5年(1858)までに再建されたもの。当時の建物が日本で唯一そのまま残る関所としての歴史的価値が高い。 |
 |
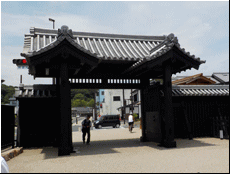 |
 |
 |
←渡船場跡
江戸時代、新居と舞坂の間は渡船による海路だった。この渡船場跡は宝永五年(1708)に今切関所がこの地に移転してからのものである。大正以降に埋め立てられて面影はの残っていないが、一部が復元整備されている。 |
| |
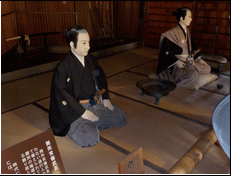 |
 |
⑫旅籠紀伊国屋
・・・静岡県湖西市新居町新居1280-1
紀伊国屋は新居宿にあった紀州(和歌山)藩の御用宿。江戸時代、関所を出た新居宿内の東海道沿いには20数件の旅籠が軒を連ねていた。
紀伊国屋の創業は明確ではないが、主が紀州の出身で江戸初期に新居に移り住み茶屋を営んだのが始まりといわれている。昭和戦後に廃業するまで約250年、旅館業を営んだ。江戸時代中期の元禄16年(1703)には徳川御三家紀州藩の御用宿となっており、その後「紀伊国屋」の屋号を掲げた。 |
 |
| 東海道の新居宿から舞坂宿の間は渡船による海路だったため今回はバスで橋を渡って移動した。 |
 |
<舞坂宿>
江戸から31番目の宿場であり、宿場西の坪井村と馬郡村を加宿としていた。天保14年(1843)当時の町並みは東西6町(655m)余り、加宿を加えて人口2475人、家数541軒、本陣2軒、脇本陣1軒、旅籠28軒であった。 |
⑬弁天神社
・・・静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2669
その昔、弁天島のこの辺りは砂洲が新居の橋本まで続き、白州青松「天の橋立」のような風景が広がっていた。舞阪と新居の間は渡船で行き来するようになった江戸時代の宝永六年(1709)今切渡の安全祈願のため、この島に弁天神社が建てられた。 |
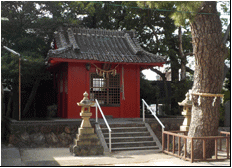 |
⑭渡船場跡北雁木・・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2120-12
今切の渡しの東側の船着場。雁木とは階段状になっている船着場のことであり、地元では「がんげ」と呼ばれていた。
舞坂宿には3カ所の雁木があり、
一番南には荷物を積みおろしをした「渡荷場」、真ん中には旅人が多く利用した「本雁木」があり、この北雁木は、主に大名や幕府役人が利用していた。
写真の石垣は左半分は江戸時代に作られたもの、右半分は後世に修復されたもの。右は石の繋ぎにコンクリートを使っているが使っていない左との対比が興味深い。 |
| |
 |
 |
⑮本雁木跡・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪
東海道を旅する人が一番多く利用した本雁木跡で東西15間、南北20間の石畳が往還より海面まで坂になって敷かれていた。またここより新居へ向かう船は季節により多少変わるが、関所との関係で朝の一番方は午前4時、夕方の最終船は午後4時であった。
現在は遺構は残っていない。 |
 |
⑯西町常夜灯・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2103
舞阪の往還道路沿いの三つの常夜灯の一つ。
舞坂宿では文化6年(1809年)西町より出火、宿の大半を焼く大きな火事があり復興に大変難儀をした。当時火防せ(ひぶせ)の山、秋葉信仰の高まりとともに人々の願いにより文化10年(1813年)にこの常夜灯が建立された。 |
 |
⑰舞坂宿脇本陣・・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2091
舞坂宿で一軒の脇本陣で茗荷屋堀江清兵衛が担った。建物は主屋・繋ぎ棟・書院棟で構成されていた。
現在は書院棟が残されており旧東海道の中で唯一の脇本陣遺構として貴重な建物である。 |
 |
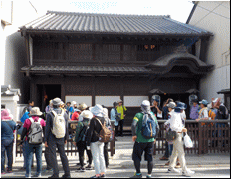 |
⑱舞坂宿本陣跡
・・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2092
舞坂宿には宮崎伝左衛門の本陣と源馬徳右衛門の相本陣があった。 |
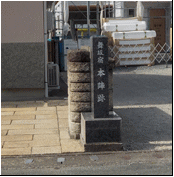 |
| 舞坂宿近辺の現在の町並み |
 |
⑲仲町常夜灯
・・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪
前述の西町常夜灯と同じく、文化6年(1809年)の大火事をうけて人々の願いにより文化10年(1813年)に建立されたもの。 |
 |
⑳新町常夜灯
・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2664
前述の西町常夜灯、仲町常夜灯と同じく、文化6年(1809年)の大火事をうけて人々の願いにより文化12年(1815年)に建立されたもの。 |
 |
21. 舞坂一里塚跡
・・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2664
江戸日本橋から68里、京都三条大橋から58里の一里塚。塚には松が植えられていた。 |
 |
22. 舞坂宿近辺の松並木
・・・静岡県浜松市西区舞阪町浜田
正徳2年(1712年)には、舞坂宿の東のはずれ見付石垣から馬郡境までの約920メートル間に、1,420本の松があったといわれている。昭和13年の国道付けかえ工事の際、堤を崩して両側に歩道がつけられ現在の姿になっ |
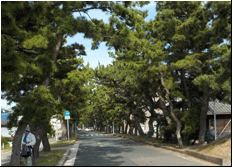 |
23. 坪井村高札場跡
・・・静岡県浜松市西区坪井町
高札には親孝行・忠孝の奨励や賭博の禁止など生活の規範に関するものとキリシタンや徒党の禁止などがあった。近くの元庄屋にはキリシタン札等の高札が永年保存されていた。 |
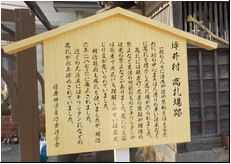 |
24. 篠原一里塚跡
・・・静岡県浜松市西区篠原町
江戸日本橋から67里、京都三条大橋から59里の一里塚。
|
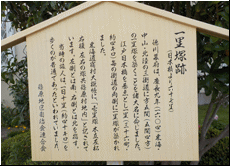 |
本日のゴール
静岡県浜松市西区篠原町21632
2018.6.17 17:30 |
 |
|
|