|
|
| 舞阪宿(第30番) ~ 浜松宿(第29番) |
'18.9.22 10:30
今回のスタート地点
・・・静岡県浜松市西区篠原町 |
 |
近辺の旧街道(現在の257号線)
・・・静岡県浜松市南区高塚町 |
 |
①麦飯長者跡 ・・・静岡県浜松市南区高塚町
昔、高塚に小野田五郎兵衛という長者がおり、明治維新の頃まで、だれかれの区別なく街道を行きかう人々に湯茶を接待し、空腹時には麦飯を食べさせていた。いつとなく「麦飯長者」と言われるようになった。五郎兵衛の善行が城下にも知られ、小野田の姓が許されて村役人、庄屋を務めた。そのため小野田家は代々五郎兵衛を名乗ってその歴史を今に伝えている。
|
 |
②高札場跡と秋葉燈籠跡
・・・静岡県浜松市南区高塚町
当時この地に高札場と秋葉常夜燈籠があった。江戸時代にはどこの村にも高札場があり、木板の札を村の中心で人目につくところに立て、切支丹禁制、火災防止、徒党の禁止、犯罪人の罪状などを書いて村人に布告、徹底させた。 |
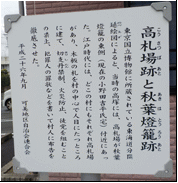 |
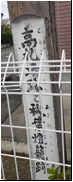 |
③堀江領境界石
・・・静岡県浜松市南区高塚町
江戸時代、宝永二年(1705)に高塚村は旧北庄内村堀江舘山寺に城を構えていた堀江領主大沢右衛門督基隆の領地となり、明治維新まで堀江領だった。そこで浜松藩との境界の高塚の東海道の南側東端に住んでいた高橋長兵衛家の前庭に境界標示の礎石が建てられていた。 |
 |
④浜松領地境界の標柱
・・・静岡県浜松市南区増楽町
宝永二年(1702)に高塚村は堀江領になったが増楽村以東は浜松領であったので領地の境を示すために建てられた標柱である。 |
 |
⑤二つ御堂 ・・・静岡県浜松市南区東若林町1155
奥州平泉の藤原秀衛公とその愛妾によって天治年間(1125年頃)創建されたと伝えられている。
京に出向いている秀衛公が大病であると聞いた愛妾は京へ上る途中、ここで飛脚より秀衛公死去の知らせ(誤報)を聞き、その菩提を弔うために北のお堂(阿弥陀如来)を建てた。一方京の秀衛公は病気が回復し帰国の途中、ここでその話を聞き愛妾への感謝の気持ちをこめて南のお堂(薬師如来)を建てたと言う。
現在の北堂、南堂とも昭和時代に改築、新築されたものである。 |
 |
 |
⑥若林一里塚跡
・・・静岡県浜松市南区東若林町
江戸から66里目、京から60里目の一里塚 |
 |
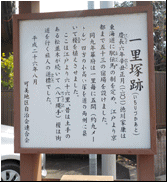 |
⑦鎧橋 ・・・静岡県浜松市南区東若林町
平安時代末期、戒壇設置のことで比叡山の僧兵が鴨江寺(静岡県浜松市)を攻めた際、鴨江寺側の軍兵は一帯の水田に水を張り、鎧を着てこの橋を守りを固めて戦ったので、鎧橋(よろいばし)と称したという。
その戦いの双方の戦死者およそ千人を鎧橋の北側に葬り、千塚(または血塚)と呼んだと伝えられている。 |
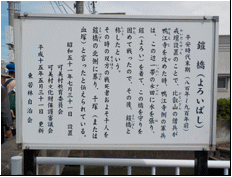 |
⑧子育地蔵尊・・静岡県浜松市中区菅原町
地蔵の台座に享保八年(1723)と彫られていることから徳川吉宗の時代より300年近く祭られていると思われる。
子宝に恵まれた親が石仏を寄進し、子供の病が治癒したお礼仏といった風習もあったのではないかと思われる。(案内板より) |
 |
<浜松宿>
浜松宿は江戸から数えて29番目、京から数えて25番目の宿場である。
浜松城の城下町として天保年間には人口5964人、家数1622軒、本陣6軒、脇本陣無し、旅籠が94件もあったとされ、遠江国、駿河国を通じて最大の宿場であった。
名物は鯉鮒料理、自然薯、濱納豆等であった。
なお浜松は第2次大戦で空襲により壊滅的な被害を受けたためか残っている江戸時代の遺構が大変少ないのが残念である。 |
⑨川口本陣跡
・・・静岡県浜松市中区伝馬町
浜松宿で最も新しい本陣で川口次郎兵衛が営んでいた。建坪163坪であった。 |
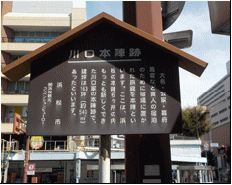 |
⑩杉浦本陣跡
・・・静岡県浜松市中区伝馬町
浜松宿で最も古い本陣。建坪272坪であった。 |
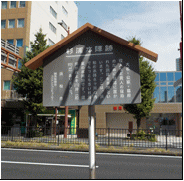 |
 |
⑪諏訪神社 ・・・静岡県浜松市中区利町302
延暦10年(791)、坂上田村麻呂が東征の際、敷智郡上中島村に奉斎と伝えられる。弘治2年(1556)に曳馬城下、大手前に遷座された。
秀忠公誕生に当り、五社神社と同じく産土神として崇敬され、天正7年(1579)徳川家康公が社殿を造営した。
元和元年(1615)、秀忠公、社地を杉山に改め、更に寛永11年(1634)、家光公が現在地に遷した。 |
 |
 |
 |
⑫高札場跡
・・・静岡県浜松市中区連尺町
人々に法令等を周知させるための高札を掲げた高札場の跡 |
 |
 |
⑬連尺交差点
・・・静岡県浜松市中区連尺町
東海道はここで右に曲がり、左に曲がると浜名湖の北を迂回して吉田宿や御油宿に至る姫街道が始まる。つまり東海道と姫街道の分岐点である。 |
 |
⑭浜松城 ・・・静岡県浜松市中区元城町
浜松城の前身は15世紀頃に築城された曳馬城であり、16世紀前半には今川氏支配下の飯尾氏が城主を務めていた。
徳川家康が元亀元年(1570)に曳馬城に入城して浜松城へと改称し、城域の拡張や改修を行い、城下町の形成を進めた。家康は29歳から45歳までの17年間をここ浜松城で過ごした。
また歴代城主の多くが幕府の重役に出世したことから「出世城」と呼ばれた。 |
 |
⑮浜松城大手門跡
・・・静岡県浜松市中区連尺町
現在の連尺交差点辺りに浜松城の大手門があった。南面する間口8間(約14.6m)、奥行4間(約7.3m)の瓦葺の建物で常に武器を備え、出入りが厳しく取り締まられていた。 |
 |
 |
⑯夢告地蔵尊
・・・静岡県浜松市中区中央3丁目
安政五年(1858)に大流行したコレラで亡くなった人々を供養するため建立されたもので、延命地蔵尊と呼ばれ、遺族達の香華が絶えなかった。明治になって廃仏毀釈で土中に埋められたが町民の夢に現れて「世上に出たい」と告げられ、夢告地蔵として名が知られるようになった。 |
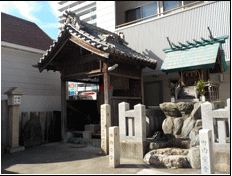 |
⑰見返り松・鳥居松 ・・・静岡県浜松市中区中央2丁目
見返り松は浜松宿の東出口であるこの地に植わっていた大きな松で、家康が駿府へ移るとき、馬込橋の上で名残を惜しんで見返したところから名付けられたと言われている。
また、同じ場所に鳥居松という枝ぶりの良い松が道をまたぐように植わっていた。この松は東海道膝栗毛にも「それよりかやんば(萱場)、薬師新田をうちすぎ鳥居松近くになりたる頃、浜松のやど引き 出引ひて」と紹介されている。どちらの松も大正時代に枯れたり焼失してしまった。 |
 |
⑱馬込一里塚
・・・静岡県浜松市中区相生町
馬込川の東にあった一里塚で、江戸から65里目、京から61里目の一里塚
|
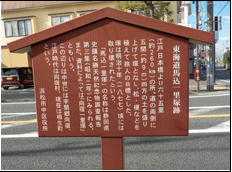 |
このあたりの旧街道
・・・静岡県浜松市東区天竜川町
|
 |
⑲立場跡跡
・・・静岡県浜松市東区薬師町
旅人や駕籠かき等の休息所である立場。
ここは藤棚があって旅人を楽しませたと伝わる。 |
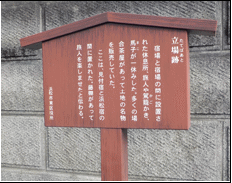 |
⑳安間一里塚跡
・・・静岡県浜松市東区安間町
本坂街道の安間起点にあたり、姫街道の一里塚も兼ねていた。
江戸から64里目、京から62里目の一里塚
|
 |
21. かやんば高札場跡
・・・静岡県浜松市東区中野町
萱場村にある臨済宗方広寺派の松林禅寺の向いに設けられた高札場跡。
|
 |
22. 舟橋木橋跡・・静岡県浜松市東区中野町
江戸時代の天竜川には江戸防衛の理由から橋が無く、東海道の往来はこの上流にある「池田の渡し」の渡船で行われていた。
明治7年には本流の舟橋と中州の木橋からなる最初の橋がこの場所に完成し、街道の往来は格段に便利になった。しかし舟橋は洪水により度々流されたので同9年に完全な木橋に架け替えられた。この「天竜橋」は昭和8年に現在の鉄橋ができるまで使用された。 |
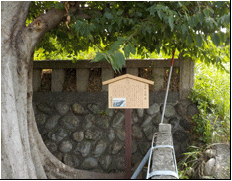 |
23. 六所神社
・・・静岡県浜松市東区中野町
天竜川の渡しの安全を願って建立された。三柱の海神と三柱の航海の守り神の六柱の神様が祭神として祭られている。
<祭神>底表津綿津見神、底筒之男命、中表津綿津見神、中筒之男命、表津綿津見神、表筒之男命 |
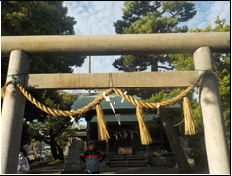 |
 |
| 今回のゴール!! '18.9.22 16:40 |
|
|