|
|
| 浜松宿(第29番) ~ 見附宿(第28番) |
2018.9.2 10:30
・・・静岡県浜松市東区国吉町
今回はここからスタート
天竜川の西岸。江戸時代、東海道は天竜川を渡舟で渡った。西岸には冨田・一色の渡船場、東岸には池田の渡船場が設けられ、渡舟は池田の渡しと呼ばれた。 |
 |
<中野町>
ここ浜松市の中野町は東海道のちょうど真中であることからその名前がついたと伝えられている。
十返舎一九の東海道中膝栗毛にも「舟より上がりて建場の町にいたる。此処は江戸へも六十里、京都へも六十里にて、ふりわけの所なれば中の町といへるよし」と記されている。
この辺りは川越しの旅人や商いをする人、天竜川をなりわいの場とする人々で活気があふれていた。 |
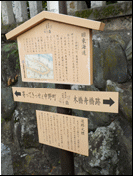 |
| 今回は天竜川を渡舟ではなく国道1号線を通って渡った。 |
 |
①長森立場・長森かうやく ・・静岡県磐田市長森
旅人・人足・駕籠かき等の休憩所である立場が設けられ、人々はお茶を飲んだり名物の餅などを食べて休息した。 |
| この地で売られていた「長森かうやく」は江戸時代の前期から山田与左衛門家で作り始められた家伝薬で、冬期にできる「アカギレ」や「切り傷」などに抜群の効能があるとして近隣の村人はもとより、参勤交代の大名行列の一行や東海道を上下する旅人達の土産品として大変な人気を博した。 |
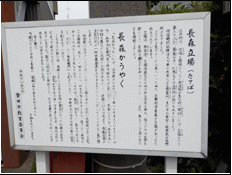 |
②宮之一色秋葉山常夜燈
・・・静岡県磐田市宮之一色
文政11年(1828)に建てられたものであり、竜の彫り物があるので「竜燈」とも呼ばれ数ある灯籠の中でも大変貴重なもの。風除けに灯籠の周りを板で囲み上部は明かりが漏れるよう格子になっている。 |
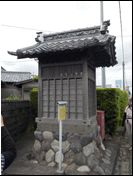 |
③宮之一色一里塚
・・・静岡県磐田市宮之一色
江戸から63里(京からも63里)の一里塚
東海道の真中である |
 |
④大乗院坂
・・・静岡県磐田市中泉
旧東海道のこの坂を「大乗院坂」という。この坂の途中に山伏の寺「大乗院」があった。そこに祀られていた地蔵菩薩像・阿弥陀如来像とも現存する。 |
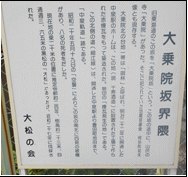 |
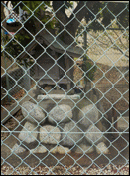 |
⑤旧中泉御殿裏門(西願寺山門) ・・・静岡県磐田市中泉字御殿
西願寺の山門は旧中泉御殿の裏門を移築したものである。旧中泉御殿は徳川家康が浜松城主であった天正12年(1584)に現岩田駅南の地域に別荘として建てられて以降約30年間使用され、寛文年間に廃止された。この間に家康が鷹狩りを兼ねて休養に訪れたと伝わる。 |
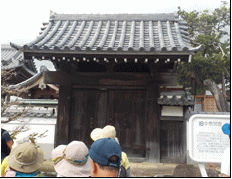 |
 |
⑥遠江国分寺跡 ・・・静岡県 磐田市見付
天平年間(729から749)聖武天皇発願によって国内60数ヶ所に建立された国分寺のひとつの遺跡。発掘調査によると金堂、講堂、七重塔、南大門、中門などの伽藍跡がみつかり、西側には築地塀の痕跡が土塁として残っている。昭和45年、伽藍の規模と位置を示す基壇を復元し、植樹など史跡公園としての整備を行い公開してる。 |
 |
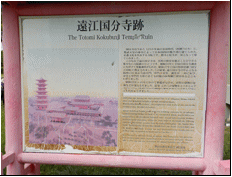 |
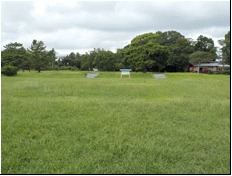 |
⑦府八幡宮 ・・・静岡県 磐田市中泉112
府八幡宮は、天平年間(729~748年)に遠江国司(現在の知事にあたる)であった天武天皇の曽孫の桜井王が、遠江国府の守護として赴任した時、遠江国内がよく治まるようにと府内に奉られたのが始まり。
宮内の建物は江戸時代初期に再建されたものが多い。 |
 |
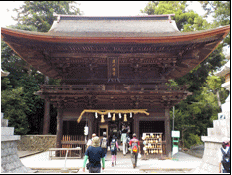 |
⑧旧中泉御殿表門(西光寺表門)
・・・静岡県磐田市見付3353-1
徳川家康が別荘として中泉村に築かせた中泉御殿の表門を移築したもので、薬医門と呼ばれる総欅造りである。 |
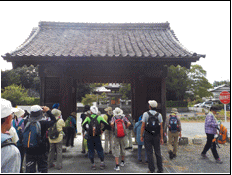 |
<見付宿>
江戸日本橋から28番目、京都三条大橋から26番目の宿場。京側からの旅人が初めて富士山を望めた(見付けた)というのが地名の由来と言われる。宿場の規模は江戸後期の記録では本陣は神谷三郎右衛門家(南本陣)と鈴木孫衛家(北本陣)の2軒、脇本陣は大三河屋新左衛門家1軒、旅籠56軒、人口3935人。
歌川広重は「東海道五十三次之内見附 天竜川図」の題で池田の渡しの様子を描いている。 |
⑨見付宿の西側の木戸跡 ・・・静岡県磐田市見付
木戸とは町を防御するために町境に設けられたもの。 |
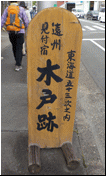 |
⑩姫街道追分見付起点 ・・・静岡県磐田市見付
姫街道の起点。御油宿と見付宿を結ぶ東海道の脇街道で浜名湖北側の本坂峠を越える道として本坂道、本坂通り、本坂街道とも呼ばれた。 |
 |
⑪西坂の梅塚・・・静岡県磐田市見付
見付東坂町・西坂町にそれぞれ一本の梅の木があり、「東坂の梅の木」「西坂の梅の木」と呼ばれており、これを梅塚という。
この梅塚は昔陰暦八月始めに、一筋の白羽の矢が町家の棟高く突き刺され、この家を年番と申し、娘を怪物の犠牲に備えた家の前にそのしるしとして植えたものだと言い伝えてられている。「西坂の梅塚」はその最後のものであったという。 |
 |
見付宿内の東海道
現在も電柱が無くすっきりした町並みとなっている |
 |
⑫旧見付宿脇本陣大三河屋門
・・・静岡県磐田市見付
大三河屋は、はじめ旅籠屋だったが、文化2年(1805)に脇本陣になった。この門は2本の本柱に冠木(かぶき)を渡し、その上に梁と切妻屋根を載せている。武家や商家の屋敷の門には棟門(むなもん=本柱2本で控柱がなく、切妻造り・平入りの門)が使われるが、脇本陣の玄関を飾るため小さいながら薬医門の形をした門である。 |
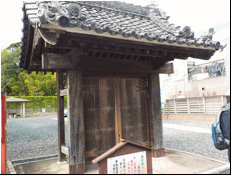 |
⑬史跡旧見付学校 ・・・静岡県磐田市見付
旧見付学校は明治5年の学制発布を受け、翌年8月に宣光寺、省光寺などを仮校舎として開校した。
現存する日本最古の木造擬洋風小学校校舎で、国の史跡に指定されている。
5階建ての洋館風の館内は教育資料の展示や授業風景を再現している。 |
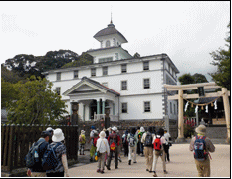 |
⑭総社 淡海國玉(おうみくにたま)神社 ・・・静岡県磐田市見付2451
遠江国総社として崇敬され、式内社・淡海國玉神社に比定されている古社。
総社とは国司が神社を巡拝するのに便宜を図り、総社をお参りすれば国内(ここでは遠江国)の全ての神社をお参りしたのと同様とされたもの。 |
 |
 |
⑮見付宿 本陣跡
・・・静岡県磐田市見付2575−4
見付宿の2軒の本陣の内、鈴木孫兵衛家の北本陣の跡 |
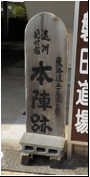 |
⑯問屋場跡 ・・静岡県磐田市見付2531
人馬・駕籠などを用意して、旅人の便宜をはかった問屋場の跡 |
 |
⑰宣光寺 ・・静岡県 磐田市 見付1340-1
宣光寺は寺伝によると慶長元年(1596)の開創。開山は妙厳寺(豊川市)の二十五世大淵龍堂和尚によって開山された曹洞宗の寺。
敷地内には戦国時代に戦死した多くの武将のために、徳川家康が信仰の厚かった延命地蔵菩薩にその冥福を祈って寄進した釣鐘がある。 |
 |
 |
 |
⑱矢奈比賣神社(見附天神)
・・静岡県磐田市見付1114-2
矢奈比賣神社は矢奈比賣命・菅原道真を祭神として祀る。創立年月は明らかではないが延喜式内社に列し、記録によれば「続日本後記」に「承和7年(840年)6月奉授、遠江国磐田郡無位矢奈比賣天神従五位下」とある。 |
 |
⑲愛宕山(阿多古山) 一里塚
・・磐田市見付 1164-2
江戸から62里(京からも64里)の一里塚
北塚は現在は民家の敷地内(奥の高いところに僅かに見える)、南塚は愛宕山神社裏手に現存する。
|
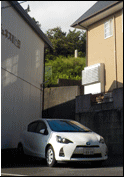 |
⑳大日堂 ・・静岡県磐田市三ヶ野1226-1
大日如来を本尊とし、養老元年(717年)に創建された。
元亀3年(1572)、遠江に侵攻する武田勢とそれを迎え撃つ徳川勢が戦った木原畷の戦いの際、家康方の本多平八郎が太田川から遠く袋井まで一望できるこの場所で敵情を視察したと伝わる。
敷地内に徳川家康が駿府にお手植えした蜜柑の木の子孫とされる木が植わっている。 |
 |
 |
 |
21. 木原畷古戦場跡・許禰(こね)神社 ・・静岡県袋井市木原611−2
元亀 3年(1572)、甲斐の武田信玄が大軍を率いて遠江に侵攻し、犬居城、飯田城を落として久野城へと向かったが城主の久野宗能の激しい抵抗にあったため、無理をせず東海道を西へと軍勢を進め、木原・西島に布陣した。この知らせを受けて浜松城を出陣した家康公の軍勢と小競り合いを繰り返し、その後武田軍は二俣城を攻略し、12月22日、三方ヶ原合戦で家康公率いる徳川軍を破った。現在、かつての古戦場には、長閑な田園風景が広がっている。
尚、家康公は、慶長 5年(1600)、東海道を関ヶ原へと向かう途中、旧東海道に面している、かつては木原権現社と称された許禰(こね)神社を参拝し、合戦の勝利を祈願したといわれる。その際に家康公が腰掛けたと伝わる「徳川家康公腰掛石」が神社前の古戦場碑の隣に残されている。 |
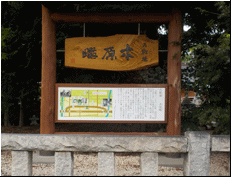 |
 |
 |
22. 木原一里塚 ・・静岡県袋井市木原
江戸日本橋から61里(京から65里)の一里塚
現在の塚は多くの一里塚に習い直径5間(9m)、高さ1間半(2.6m)で復元されたもの。 |
 |
今回のゴール
・・・静岡県袋井市川井
次回はここからスタート
2018.9.2 17:45 |
 |
|
|