|
|
| 見付宿(第28番) ~ 掛川宿(第26番) |
2018.10.13 10:05
・・・静岡県袋井市川井
今回はここからスタート |
 |
①澤野医院記念館
・・・静岡県袋井市川井444-1
江戸中期から代々医業を営んできた澤野家の医院兼住居の建物。明治末期に廃業し、建物が袋井市に寄贈された。 |
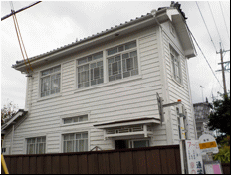 |
<袋井宿>
江戸日本橋から27宿目、京都三条大橋からも27宿目。つまり五十三次の丁度真中にあたる宿場。元和2年(1616)、見付宿と掛川宿の間の距離が長くて不便なため中間にあった茶屋をもとに作られた。
宿内の町並みは東西5町15間(573m)と53宿の中で最も短い宿場だった。江戸後期の人口843人、家数195軒、本陣3軒、脇本陣無し、旅籠50軒であった。
近くに遠州三山と呼ばれる「法多山尊永寺」、「医王山油山寺」、「萬松山可睡斎」があり、その門前町として、また秋葉信仰の参詣の人々で賑わった。 |
②高札場跡 ・・・静岡県袋井市袋井
幕府が人々を治めるため、法令や禁令を掲示した高札場の跡。 |
 |
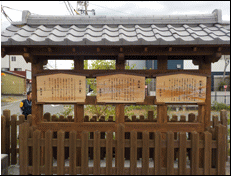 |
 |
③袋井宿本陣跡
西本陣跡・・静岡県袋井市袋井61
中本陣跡・・静岡県袋井市袋井51
東本陣跡・・静岡県袋井市袋井39
袋井宿には三軒の本陣があり、西本陣は大田八蔵家、中本陣は大田八兵衛家、東本陣は田代八郎左衛門家が営んでいた。東本陣は敷地坪数1068坪、間口13間半、奥行31間で、三軒の中で最も格式が高かった。
|

西本陣跡 |
東本陣跡  |
 |
中本陣跡  |
④問屋場跡 ・・・静岡県袋井市袋井
人馬の継立などを行う問屋場があった。 |
 |
⑤秋葉山常夜灯
・・・静岡県袋井市新屋2丁目
珍しい瓦屋根を載せた木造の「屋形」常夜灯 |
 |
⑥九津部一里塚跡
・・・静岡県袋井市広岡
江戸日本橋から60里目、京都三条大橋から66里目の一里塚 |
 |
 |
⑦妙日寺
・・・静岡県袋井市広岡2340
日蓮宗の古刹で、江戸時代初期の形を残した五輪塔や遠州七不思議のひとつ「方葉の葦」がある。また境内に日蓮聖人の先祖貫名氏供養塔がある。 |
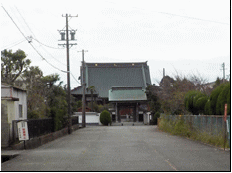 |
 |
⑧松並木 ・・静岡県袋井市広岡
旅人を強い日差しから守っていた松並木が名栗から久津部の間に残されている |
 |
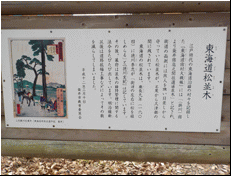 |
⑨富士浅間宮鳥居・・・静岡県袋井市国本
赤鳥居と呼ばれ親しまれているこの鳥居は、東海道分間延絵図にもその姿が描かれ、重要文化財で木花開耶姫命を祀る冨士浅間宮本殿までの参道の入口に立っている。
現在は鳥居と社殿の間に一般国道1号や東名高速道路が通り、周辺には多くの工場が立ち並んでいるために、鳥居だけが取り残されたようにみえるが、江戸時代には東海道から木々の間に社殿を見通すことができたという。 |
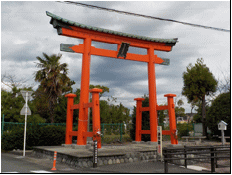 |
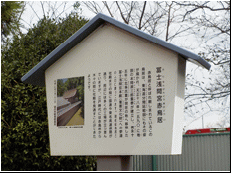 |
⑩大池一里塚・・・静岡県掛川市長谷
蓮祐寺の門前に大池一里塚の道標がある。北塚は大池村内、南塚は長谷村地内に存在した。
江戸日本橋から59里目、京都三条大橋から67里目の一里塚 |
 |
<掛川宿>
江戸時代の掛川宿は慶長初期に山内一豊が形成した城下町から発展、形成された。天保14年(1843年)の記録によると、本陣2軒、脇本陣なし、旅籠屋30軒等、960軒の家があり、3443人が住んでいた。宿の東寄りの天然寺と西端の円満寺は朝鮮通信使が来聘した折には宿所として使用された。
1691年に東海道を旅したケンペルの「江戸参府旅行日記」には、「この町の両側(東西)には郭外の町があり、門と番所があります。北側には城があり、櫓のない簡単な石垣で囲まれ、中には高くそびえた白壁の天守閣があり、大きな城に美しさを添えていた」と記され、1776年のツュンベリーの「江戸参府随行記」には「防備された大きな町、掛川」と表現されている。 |
⑪十九首塚(じゅうくしょづか) ・・・静岡県掛川市大池
天慶3年(940年)、藤原秀郷が平将門一門19名を討伐してその首を弔った塚と伝えられており、昔は19基あったものが時代と共に減ってゆき、将門のものと思われる大きな1基だけが残されたと伝わる。その後、将門の首塚を取り囲むようにして18基の首塚が新しく作り直された。地元では首塚を町の守り神として、彼岸と命日にあたる8月15日に供養祭が行われている。 |
 |
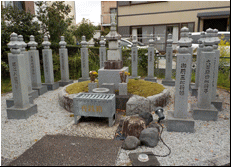 |
⑫掛川城蕗の門
・・・静岡県掛川市掛川468
この門は、掛川城 の内堀(蓮池)のほとりに建てられていた四脚門である。大手門や仁藤門などから本丸、二之丸などの城の要所にいたる道筋にあり、小さいが重要な門であった。
廃城後の明治5年に円満寺が買い受けて、現在地に移築した。 |
 |
⑬掛川城・・・静岡県掛川市掛川1138
室町時代、駿河の守護大名今川氏が遠江進出を狙い、家臣の朝比奈氏に命じて築城させたのが掛川城のはじまり。戦国時代には、山内一豊が城主として10年間在城した。働き盛りの一豊は大規模な城郭修築を行い、天守閣、大手門を建設するとともに、城下町の整備や大井川の治水工事などに力を注いだ。掛川は、一豊の人生にとって大きな意味をもつ土地であり、高知城は掛川城を模して作られたとも伝えられている。 |
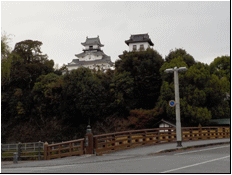 |
⑭沢野本陣跡 ・・・静岡県掛川市連雀2
掛川宿には中町に浅羽本陣、連雀町に沢野本陣の2軒の本陣があった。
現在、連雀町の沢野本陣は「掛川本陣通り」屋台村となり、活気ある地元の名所となっている。 |
 |
⑮掛川城大手門
・・・静岡県掛川市城下27番地
大手門は天守閣に続いて平成7年(1995年)に復元されたもので、大きさは間口7間(約12.7メートル)、奥行3間(約5.4メートル)の二階建。掛川城の表玄関にふさわしい楼門造りの本格的な櫓門は、木造日本瓦葺き入母屋づくりになっている。白壁で板ひさしが配され、棟の上にはシャチ瓦が飾られた勇壮な構えである。実際は現在地より50メートルほど南にあった。 |
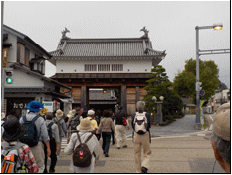 |
⑯ゲイスベルト・ヘンミィの墓
・・・静岡県掛川市仁藤町5-5
寛政年間、長崎出島のオランダ商館では4年に一度江戸城で将軍に拝謁して献上品を贈り、貿易通商の御礼言上をしていた。ゲイスベルト・ヘンミィもその使節団の一員だったが、寛政10年(1798)に将軍家斉に謁見して長崎に帰る途中、掛川連雀の本陣でかねてからの病気が悪化して死亡し、天然寺に葬られた。 |
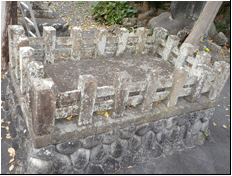 |
⑰七曲り ・・静岡県掛川市掛川
葛川と新町の境の掘割に架かる橋を渡ると門があり、この門から西側が掛川宿で掛川城下だった。ここの先旧東海道は南に折れ、道が鉤の手にいくつも折れ曲がる道、新町七曲りに入る。
七曲りは容易に敵を進入を防ぐ為に造られた。七曲りの終点には城下に入ってくる人物や物を取り締まるための木戸と番所があった。 |
 |
 |
⑱塩の道
その昔、まだ国という概念が明確でなかった頃、沿岸部から内陸部に向かって塩を運んだ道が全国に沢山あった。
その代表的な塩の道のひとつに、静岡県牧之原市相良から掛川市を抜けて、新潟県糸魚川市へと続く道があり、その一部は「秋葉街道」とも呼ばれ、秋葉神社への信仰の道としても栄えていた。 |
 |
⑲葛川一里塚跡・・・静岡県掛川市葛川
掛川市内には大池、葛川、伊達、佐夜鹿の4ヶ所の一里塚があった。その内、この葛川一里塚は江戸日本橋から58里目、京都三条大橋から68里目の一里塚であった。 |
 |
⑳伊達一里塚跡跡
・・・静岡県掛川市伊達方
江戸日本橋から57里目、京都三条大橋から69里目の一里塚。当時の塚の大きさは直径7間、高さ3間の小山で、明治33年頃に取り壊されたという。 |
 |
本日のゴール ・・静岡県掛川市八坂
'18.10.13 17:25 |
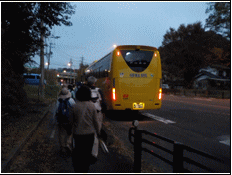 |
|
|