|
|
| 掛川宿(第26番) ~ 金谷宿(第24番) |
2018.11.11 10:15
・・静岡県掛川市八坂
今回はここからスタート |
 |
①事任(ことのまま)八幡宮
・・・静岡県掛川市八坂642
成務天皇の時代(西暦百数十年頃)に創建され、大同2年(807年)に阪上田村麻呂が勅命を奉じて再興したと伝わる。
康平5年(1062)、源頼義が京都より石清水八幡宮を当社に勧請、戦国の時代を経て、徳川家康が大檀那として本殿を造営した棟札がある。幕府は御朱印百石余を寄進して幕府の守り神であると祟めた。その後、徳川秀忠が中門を造営した記録がある。本殿の扉の金具には、菊の紋と葵の紋が刻まれているところから、将軍家が当社を信仰されていたことがわかる。 |
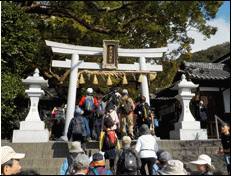 |
 |
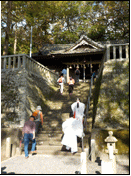 |
<日坂宿>
江戸日本橋から25宿目、京都三条大橋から29宿目の宿場。
古くは「新坂」や「西坂」とも書かれた日坂宿は難所の「小夜の中山」を控え、峠越えに備えて多くの旅人が足を休めた。町並み長さ6町半、人口750人、家数168軒、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠33軒の規模であった。名物は、わらび餅、飴の餅、子育飴など。 |
②下木戸跡 ・・静岡県掛川市日坂
江戸時代、宿場 の治安維持のため、東西の入り口には木戸が設けられていた。大規模な宿場では観音開きの大きな門だったが、小規模であった日坂宿では川が門の役割を果たしていた。
粗末な木橋で、一旦事が起こった時は、宿場の治安維持のために橋をはずしたとも伝えられる。 |
 |
③日坂宿高札場跡
・・・静岡県掛川市日坂
日坂宿の高札場は宿の西端にある相伝寺敷地内にあり、下木戸の高札場とも呼ばれていた。高札の内容は、この地が幕府直轄地であったことから公儀御法度(幕府法)が中心。現在掲げられている8枚は、『東海道宿村大概帳』の記録に基づき、天保年間(1830から1843年)のものが復元されたもの。 |
 |
④川坂屋 ・・・静岡県掛川市日坂149番地
慶長19年(1624)大阪の陣で深手を負い、その後日坂に居住した武士太田与七郎源重吉の子孫、斉藤次右衛門が始めたと伝えらている日坂宿の旅籠屋。
現存の建物は宿場の殆どが焼失した嘉永5年(1852)「日坂宿大火」後に再建されたもの。日坂宿で江戸時代の面影を遺す数少ない建物のひとつである。
江戸より招いた棟梁の手で、精巧な木組みと細やかな格子が造作されたと言われ、身分の高い武士や公家などが宿泊した格の高い脇本陣格であったことが伺える。旅籠屋としては、明治3年(1870年)まで存続していた |
 |
 |
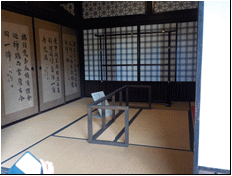 |
⑤萬屋 ・・・静岡県掛川市日坂35番地
江戸時代末期の旅籠屋。川坂屋と同様に嘉永5年(1852)「日坂宿大火」後に再建されたもの。筋向いの川坂屋が士分格が宿泊した大旅籠だったのに対して萬屋はもっぱら庶民の泊まる旅籠であった。 |
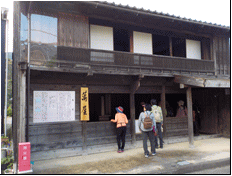 |
 |
⑥脇本陣黒田屋跡 ・・静岡県掛川市日坂
日坂宿の脇本陣は時代と共に移りかわり何軒かが務めた。 ここには幕末期に日坂宿最後の脇本陣を務めた「黒田屋(大澤富三郎家)」があった。黒田屋は文久2年(1862)の宿内軒並取調書上帳に間口8間、奥行き15間、畳101畳、坪数120坪と記されている。
|
 |
⑦問屋場跡 ・・・静岡県掛川市日坂
宿場では幕府などの貨客をリレー方式で次の宿場へと受け継いで送るため、一定の人馬の設置が義務づけられていた。その業務を取り扱う役職を『問屋』、役所を『問屋場』といい、宿場では最も重要な施設だった。
日坂宿の問屋場はこの場所にあり、問屋のほか補佐役である『年寄』、帳簿付けの事務担当『帳付(ちょうづけ)』など宿役の者が毎日交代で一人ずつ詰めていた。参勤交代など重要な通行がある時には全員で業務にたずわっていたようである。 |
 |
⑧本陣扇屋跡 ・・・静岡県掛川市日坂
日坂宿本陣の屋号は『扇屋』といい、代々片岡家が営んでいた。嘉永5年(1852年)の日坂宿大火で全焼したのち再建したが、明治3年(1870年)に店を閉じた。
その後、跡地は日坂小学校の敷地とされ、家屋は校舎として利用されたが現存していない。 |
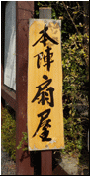 |
 |
⑨秋葉常夜燈 ・・静岡県掛川市日坂
日坂宿はしばしば大火に見舞われたため火伏せの秋葉信仰が盛んであった。秋葉常夜燈は秋葉神社に捧げる灯りをともすもので辻などの人目につきやすい場所に建てられた。
日坂宿にはここ本陣入口をはじめ、三基の常夜燈が建てられていた。 |
 |
静岡県掛川市日坂
日坂宿を離れると急に勾配のきつい登り坂になる。
|
 |
⑩夜泣石跡 ・・静岡県掛川市日坂
強盗に襲われて殺された妊婦の霊が乗り移り、夜毎に泣いたと言う夜泣石。高さ3尺、直径2尺の丸石で、刻まれた「南無阿弥陀仏」の文字は弘法大師が刻んだと伝わる。江戸末期まではこの地の東海道の真中にあったが明治時代に他の場所に移された。歌川広重の浮世絵にも描かれている。 |
 |
 |
⑪小夜の中山 ・・静岡県掛川市佐夜鹿
日坂宿と菊川村(中世の菊川宿)の間は「小夜の中山」と呼ばれ、左右を深い谷に挟まれた険しい坂道は小箱根とも呼ばれた。また箱根峠、鈴鹿峠と並んで東海道の三大難所として知られていた。「邪身鳥」や「夜泣石」等の神秘的な伝説が語り継がれている。 |
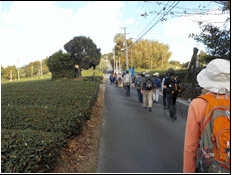 |
⑫鎧塚・・静岡県掛川市佐夜鹿
建武2年(1335年)、鎌倉幕府を再建しようと北条時行が挙兵し、世に言う『中先代(なかせんだい)の乱』をおこした。その折り、時行の一族である名越邦時が京へ上ろうとして、この地で足利一族の今川頼国と戦い、壮絶な討ち死にをした。鎧塚は頼国が邦時の武勇をたたえてつくり葬ったと言われる塚である。 |
 |
⑬佐夜鹿一里塚跡
・・・静岡県掛川市佐夜鹿
江戸日本橋から56里、京都三条大橋から70里の一里塚
|
 |
⑭扇屋の子育飴 ・・静岡県掛川市佐夜鹿
前述の夜泣石の伝説に出てきた殺された母の霊は石に乗り移り夜毎に泣いたが、生まれた男児は飴のおかげですくすく育ち、後に母の仇を討ったと伝わる。そして「子育飴」と呼ばれる飴が峠の名物として広く知られるようになった。
江戸時代にはこの周辺には20軒ほどの飴屋があったそうであるが現在残っているのは久延寺の隣の茶屋・扇屋だけ。扇屋は宝永(1704年~1710年)頃の開業といわれ、300年以上この峠を越える旅人のために茶店を営んできた老舗である。
広重の浮世絵にもその飴売りの女性が描かれている。 |
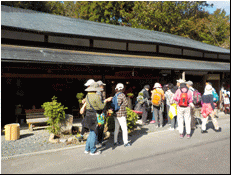 |
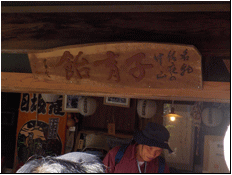 |
 |
⑮久延寺 ・・静岡県掛川市佐夜鹿291
小夜の中山峠の中腹に位置する古刹。山内一豊が関ヶ原合戦のきっかけとなる会津上杉攻めの軍を大坂より進めてきた家康をもてなした茶亭の跡地や、その礼に家康が植えたとされる五葉松の跡が残されている。また夜泣石伝説ゆかりのお寺としても有名。 |
 |
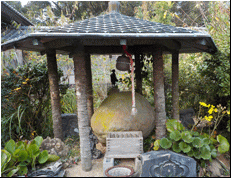 |
⑯間の宿 菊川 ・・・静岡県島田市菊川
菊川宿は金谷宿と日坂宿の間に位置する中世に栄えた古い宿。天正5年(1575)の武田vs徳川の諏訪原城の戦いで菊川の里は激戦地となり、人々が戦火を逃れて流亡。その後家康が天下を治め、慶長6年(1601)に東海道宿駅制が定められると、村人が戻って茶屋を営むようになり、間の宿として旅人で賑わうようになった。井原西鶴の「一目玉鉾」に「此処に矢の根鍛冶の名人有、また切飴の名物有」とあり、それらが菊川の名物として知られていた。 |
 |
⑰菊川坂 ・・静岡県島田市金谷
江戸時代、東海道の金谷宿から掛川市の日坂宿へ抜ける道は急斜面が続く道で、菊川坂・金谷坂は『青ねば』というすべりやすい土質のため、行き交う旅人を苦しめた。そのことから石畳が敷かれ、困難を救ったといわれている。
菊川坂の石畳は、諏訪原城址から小夜の中山に至る途中の菊川宿周辺の石畳。平成12年の発掘調査により、西側の上り口から161メートルは江戸時代後期のものと確認された。これに加えて平成13年には市民の手によって山石が敷かれ、611メートルの石畳が復元された。 |
 |
 |
⑱諏訪原城跡 ・・静岡県島田市菊川174
諏訪原城跡は戦国時代の東海道における戦略上の要地に位置し、はじめ武田信玄が砦を築き、その後天正元年(1573)、遠江侵攻の拠点・徳川氏に対する備えとして、信玄の子
武田勝頼が家臣 馬場美濃守信房に命じて、牧之原台地に築いた山城である。武田家の守護神諏訪大明神を祀ったことからこの名が付いたと言われている。
天正3年(1575)に徳川家康によって攻め落とされた後、「牧野城」と改名され、今川氏真や松平家忠らが城主となった。
やがて武田氏が滅亡するとこの城の必要性はなくなり、天正18年(1590)頃廃城となったと言われている。城跡から東側に目を向けると大井川、更に遠くには富士山を望むことが出来る風光明媚な立地でもある。 |
 |
 |
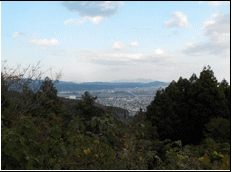 |
⑲金谷坂の石畳 ・・静岡県島田市金谷
牧ノ原から金谷に向かって続く460mの石畳。江戸時代には約850m続いていた石畳が時を経るごとに失われて昭和の時代には僅か30mになったが、平成3年に町民により430mが復元された。
写真は江戸時代から残った部分の石畳。 |
 |
 |
<金谷宿>
「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と言われた大河が控える金谷宿。江戸日本橋から24宿目、京都三条大橋から30宿目の宿場。
金谷本町と金谷河原町にわかれ、本町が伝馬役、河原町が大井川の川越しを取り仕切る川越役を担っていた。
全長16町24間(約1.8km)、人口4271人、家数1004軒、本陣3軒、脇本陣1軒、旅籠51軒の規模。名物は菜飯田楽であった。 |
⑳金谷一里塚跡
・・静岡県島田市金谷田町
江戸日本橋から55里目、京都三条大橋から71里目の一里塚。
南側には榎と松の木、北側には松と桜が植えられていた。 |
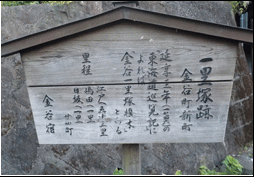 |
21. 定飛脚問屋(三度屋)跡
・・静岡県島田市金谷田町
田町の南側に「浅倉屋何右衛門」、北側に「黒田屋重兵衛(治助)」という定飛脚の問屋があった。定飛脚とは、「三都定飛脚」ともいい、江戸と上方の京・大坂を定期的に往復した民間の飛脚 で、月三度(2日・12日・22日)出したことから「三度飛脚」、取扱所を「三度屋」とも言い、この飛脚がかぶった笠を「三度笠」と呼んだ。 |
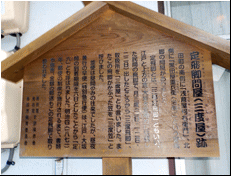 |
22. 本陣跡 ・・静岡県島田市金谷本町
金谷宿には本陣が3軒あり、それぞれ一番本陣、二番本陣、三番本陣と呼ばれた。
<柏屋本陣(一番本陣)跡>
柏屋は代々河村八郎左衛門を名乗り「金谷六人衆」と呼ばれた名家の一つで、代々本陣と名主を務めていた。先祖の河村弥七郎 が徳川家康 に忠節を尽くしたことで信州に知行地を与えられ、金谷宿・島田宿にも屋敷を与えられていた。
<佐塚本陣(二番本陣)跡>
寛永12年(1635)参勤交代精度とともに各宿に本陣が開設された当初より佐塚家は金谷宿本陣を務めていた。
<山田家本陣(三番本陣)跡>
江戸時代初期、金谷宿の本陣は柏屋本陣と佐塚本陣の2軒で、山田家は脇本陣だった。徳川家の本陣は当初柏屋だったが貞亨元年(1684)、大井川満水を浜松まで飛脚を遣わして注進すべきところを怠ったため、宿泊所が山田家に変更された。それ以降、山田家が三番本陣として格上げされたと思われる。 |
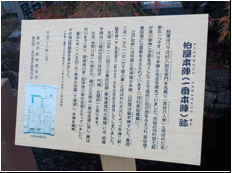 |
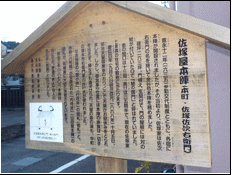 |
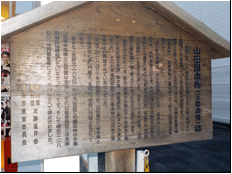 |
23. 川越し場跡 ・・・静岡県島田市金谷東2丁目
東海道最大の難所だったといわれる大井川は軍事上の理由から架橋は許されなかった。また両岸の金谷宿と島田宿の川越人足の既得権益を守るために渡船すら禁止されていた。そのため旅人は川越人足による肩車や連台に乗って川を越すしかなかった。川越賃銭は当日の水量によって決められ、大水ともなれば数日も足止めとなった。 |
 |
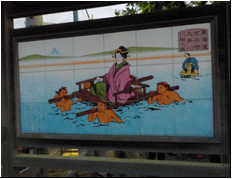 |
本日のゴール(大井川西岸)
・・・静岡県島田市金谷東2丁目
'18.11.11 17:10 |
 |
|
|