|
|
| 金谷宿(第24番) ~ 藤枝宿(第22番) |
2018.12.16 9:55
今回のスタート地点
・・・静岡県島田市金谷東2丁目
大井川西岸からスタート |
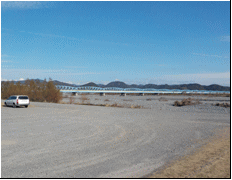 |
①大井川・・・静岡県島田市
大井川は江戸時代には橋がなく、渡船も禁止されていたため旅人は川越人足の肩や梯子状の連台に乗って渡るしかなかった。
川幅は1000m程あり現在橋を歩いても15分ほどかかる。 |
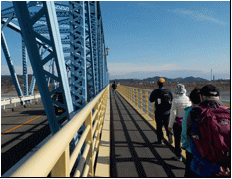 |
<島田宿>
江戸から23番目、京から31番目の宿場。
町並長さは9町40間(1053m)、人口6727人、家数1461軒、本陣3軒、脇本陣なし、旅籠屋48軒の規模だった。名物は小饅頭。 |
②島田大堤 ・・静岡県島田市河原1丁目
天正の瀬替え以降、島田宿 の大井川沿いに築かれていた川除堤が、慶長の大洪水(1604~1605)で決壊し、建設まもない島田宿のすべてが押しながされた。その後、大堤完成までの確かな記録は不明であるが正保元年(1644)までには完全な大堤が完成していたと思われる。大堤の規模は高さ2間(約3.6m)で向谷水門下から道悦島村境までの長さ3150間(5733m)と記録されている。
|
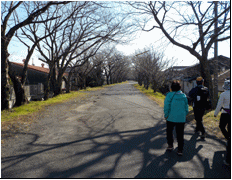 |
③朝顔の松
・・・静岡県島田市河原1丁目15
浄瑠璃「朝顔日記」の盲人朝顔が光を取り戻し、初めて目に映ったのが一本の松であった。「朝顔の松」と呼ばれていたこの松は昭和10年に枯れた後、お堂の中で木碑として安置されている。 |
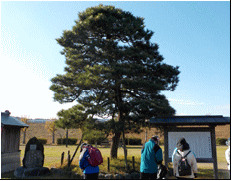 |
④せぎ跡 ・・・静岡県島田市河原1丁目15
石積みの堤防が築かれ、大井川が増水した際に水防の役目を果たした。道で分断された部分には増水時に板を設置できるように溝がつけられている。 |
 |
 |
 |
⑤川会所 ・・・静岡県島田市河原1丁目13−10
元禄9年(1696)にできた川越制度の管理を担う川庄屋の拠点が川会所であった。川会所には年行事、待川越、川越小頭等の役職をおき、大名から庶民まで全ての通行人に対する渡渉の割り振りや荷物の輸送配分等の運営を行う仕事が行われていた。人足を雇うために必要な川札はこの会所で売られていた。
川越の手段は一般庶民向けの人足の肩にまたがる肩車(川札1枚)、平連台、半高欄連台、中高欄連台、お殿様等が利用した大高欄連台(川札52枚)まで様々な方法があった。またその川札はその日の水位によって48文から94文まで5段階の値段が設定されていた。 |
 |
 |
 |
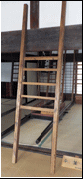 |
←平連台 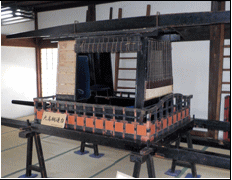 ←大高欄連台 ←大高欄連台 |
⑥札場 ・・静岡県島田市河原2丁目
川越で働いた人足が受取った川札を換金するところで、昔の位置に保存されている |
 |
⑦三番宿 ・・静岡県島田市河原2丁目
川越人足が集合する番宿で、三番宿は沢山あった番宿の一つ。 |
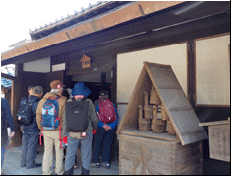 |
川越遺跡近辺の旧東海道
・・静岡県島田市河原2丁目
昔の風情が残されている。 |
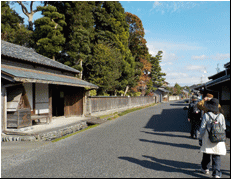 |
⑧大善寺の梵鐘・・・静岡県島田市向島町2919
この寺の鐘は、天明4年(1784)「時の鐘」として備え付けられ、宿民に刻を知らせた。明け六ツ(日の出時刻)と、暮れ六ツ(日の入り時刻)の鐘の音は、大井川川越の始まりと終わりの合図となっていた。 |
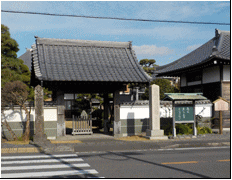 |
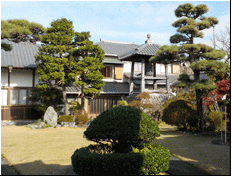 |
⑨大井神社 ・・静岡県島田市大井町2316番地
創建時期は不詳であるが貞観7年(865)には大井神社が従五位下を授かったとの記録がある。その後大井川の氾濫が度々位置が変わり、元禄二年(1689)に現在の御社地に遷された。
御祭神は水の神「弥都波能売神」、土の神「波邇夜須比売神」、日の神「天照皇大神」で三柱共に女神であるため、昔から安産の神、女性の守護神として信仰されていた。
3年に一度行われ、日本三大奇祭のひとつである島田大祭帯祭が有名。 |
 |
 |
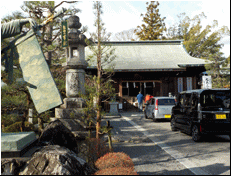 |
 |
←大井神社参道の石垣
江戸時代に川越稼業の人たちが毎日河原から石をひとつ持ち帰り、それを蓄積してこの石垣を築いたと伝わる。 |
現在の島田市内の旧東海道
・・・静岡県島田市本通2丁目付近
電柱が見えないスッキリした街並みである |
 |
⑩本陣跡 ・・静岡県島田市本通3丁目5−5
島田宿には上本陣、中本陣、下本陣の3軒の本陣があった。
現在はいずれも遺構としては残っていない。 |
 |
⑪塚本如舟屋敷跡
・・静岡県島田市本通3丁目6
塚本家は代々孫兵衛を名乗り、元禄九年(1696)、初代の川庄屋を代官から任命された。その他にも組頭、名主、問屋場の年寄、六代目からは問屋を努めるなど、代々宿役人の要職を務めた。 |
 |
⑫島田一里塚跡
・・・静岡県島田市本通7丁目
江戸日本橋から52里目、京三条大橋から74里目の一里塚跡 |
 |
⑬上青島松並木
・・静岡県藤枝市上青島
この付近は昔ながらの街道沿いの松並木の風景が残されている |
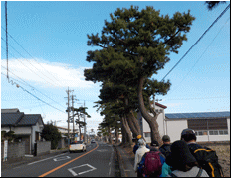 |
⑭上青島一里塚 ・・静岡県藤枝市上青島
江戸日本橋から51里目、京三条大橋から75里目の一里塚跡 |
 |
⑮千貫堤 ・・静岡県藤枝市下青島1006
千貫堤は、江戸時代の寛永12年(1635)に田中城主の水野監物忠善が、大井川の洪水から領内を守るために築いた堤防。建設には千貫の費用がかかったことから、千貫堤と呼ばれている。
瀬戸山から本宮山(現・正泉寺山)までの全長500m以上、幅32m、高さ3.6mの規模の堤防だった。現在は一部が残されている。 |
 |
 |
⑯染飯茶屋跡 ・・静岡県藤枝市下青島
瀬戸の染飯は東海道が瀬戸山の尾根づたいに通っていた頃から、尾根の茶店で売り始めたと言われ、天正十年(1582)の「信長公記」にその名が記されている。東海道が平地を通るようになっても現在の茶店跡で江戸時代の終わり頃まで売られていた。染飯とは強飯(こわめし)をくちなしで染め、薄く小判型にしたものであったという。くちなしは足腰が強くなるというので旅人には好評だった。
現在も近くの瀬戸染飯伝承館ではくちなしを栽培して伝統を守っている。 |
 |
 |
⑰東海道追分 ・・・静岡県藤枝市下青島
東海道がこれより東で瀬戸山裾を通るルートはその昔、池や湿地が多い所だったので中世の古東海道は瀬戸山を越えるルートだった。その後開拓が進んでから山裾を通るルート(旧東海道)が使われるようになった。
ここはその二つのルートの分かれ道であり、「追分」と呼ばれていた。 |
 |
⑱田中藩領牓示石蹟
瀬戸新屋村は田中藩領と掛川藩領が入り組む特異な村で藩境に境界を示す牓示石を立てた。牓示石は一丈余り(約3m)の石柱で「従是東田中領」と書かれていた。これと対になるのが「従是西田中領」で美濃国岩村藩領横内村との境界に立てられていた。 |
 |
⑲志太一里塚跡
・・静岡県藤枝市志太三丁目
江戸日本橋から50里目、京三条大橋から76里目の一里塚跡 |
 |
本日のゴール
・・静岡県藤枝市志太3丁目
明日はここからスタートする。
2018.12.16 15:45 |
 |
|
|