|
|
| 藤枝宿(第22番) ~ 丸子宿(第20番) |
2018.12.17 8:55
本日のスタート地点
・・・静岡県藤枝市志太3丁目
昨日のゴールだった瀬戸川東岸からスタート |
 |
<藤枝宿>
東入口の左車町木戸から西入口の川原町まで19町12間(約2km)の長さで、総家数1061軒、人口4425人と県下の宿場の中でも有数の規模であり、本陣2軒、脇本陣なし、旅籠47軒に加え、旅人や近在の人々を相手にした商店、刀鍛冶など武士相手の店などが軒を並べ宿場町として大層な賑わいをみせていた。
藤枝宿は他の宿場のように一つの町や村が宿場になったものではなく、志太郡、益津郡の街道沿いの八つの村の街道に面した一部の町がそれぞれの親村に属しながら宿駅の役割を担った。その中心となったのが上伝馬町・下伝馬町で、上伝馬では下りを、下伝馬町では上りをと伝馬業務を分担していた。 |
①上伝馬問屋場跡
・・静岡県藤枝市藤枝3丁目1
旅人や荷物を次の宿場まで運ぶ継立と通信業務のために人馬や飛脚をそろえ問屋場。ここを上伝馬、田中城大手口の問屋場を下伝馬と呼んで区別していた。
ここは歌川広重の「東海道五十三次藤枝人馬継立」に描かれた場所である。 |
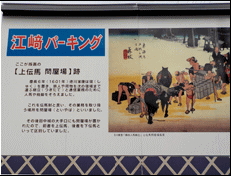 |
②藤枝宿 本陣跡
・・静岡県藤枝市藤枝3丁目
藤枝宿の2軒の本陣は上本陣、下本陣と呼ばれ隣接していた。現在は舗道にレリーフが埋め込まれているのみである。 |
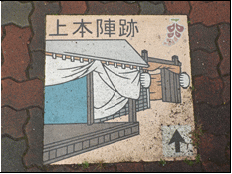 |
 |
③大慶寺 ・・藤枝市藤枝4丁目2-7
大慶寺は田中城の祈願寺とされ、田中城主太田資直の墓があり、田中藩家老の大半が檀家となっていたため「さむらい寺」とも呼ばれていた。
境内には、日蓮上人ゆかりの「久遠の松」が立派な枝ぶりを見せてくれる。大慶寺をひらいた道円・妙円夫婦が日蓮聖人の説法教化を受け、本尊と毘沙門天を授与されたときに植えられたと伝わる。客殿は徳川幕府家老・田沼意次の居城「相良城」の御殿を移築したものである。 |
 |
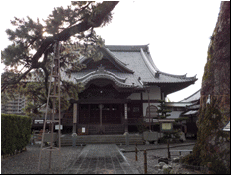 |
 |
④白子由来碑 ・・藤枝市本町2丁目6-1
本能寺の変の後、明智光秀に追われた徳川家康が伊勢白子に逃げた際、白子の住人小川孫三が匿って助けた。家康はその褒賞としてこの地を新白子と命名し孫三が住むことを許可した。 |
 |
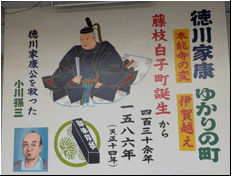 |
⑤須賀神社 ・・静岡県藤枝市水守17
創立年月日は不詳であるが、慶長10年(1605)に再建されたとの記録がある。
境内には御神木として大切に守られてきた樹齢約500年の楠の大木がある。 |
 |
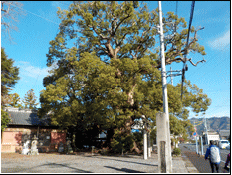 |
⑥鬼島一里塚跡
・・静岡県藤枝市鬼島
江戸日本橋から49里目、京三条大橋から77里目の一里塚 |
 |
⑦田中藩領牓示石蹟
・・静岡県藤枝市横内
田中藩が美濃国岩村藩領横内村との境界に立てた牓示石の跡。「従是西田中領」と書かれていた。
前述の「従是東田中領」の牓示石と対になるもの。 |
 |
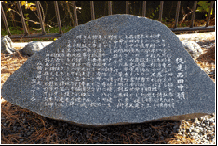 |
近辺の東海道
・・静岡県藤枝市仮宿
国道で分断されているが左の松並木が旧東海道 |
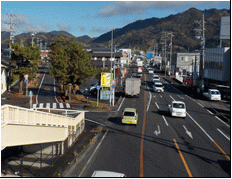 |
⑧岩村藩領傍示杭跡
・・静岡県藤枝市横内
江戸時代享保20年(1735)より明治維新までの135年間横内村が岩村藩領であったことを標示した杭を復元したもの。
岩村藩は、美濃国岩村城(岐阜県恵那郡岩村町)を居城として、松平能登守が三万石の領地を持っていた。駿河国に十五ヶ村、五千石分の飛領地があり横内村に陣屋を置いて治政を行っていた。
|
 |
<岡部宿>
岡部宿は江戸日本橋から21番目、京三条大橋から33番目の宿場。
東海道の難所の一つ宇津ノ谷峠を控える山間の宿場で今も静かな町並みが残っている。
横町、本町、川原町の3町から成り、南隣の内谷村新町を加宿とした。
町並み長さは13町50間(約1.5km)、人口は加宿を含めて2322人、家数487軒、本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠27軒の規模であった。
名物は宇津ノ谷峠付近で売られていた十団子。 |
⑨岡部宿の松並木
・・静岡県藤枝市岡部町内谷
現在約500mに渡って松並木が保存されている。
|
 |
近辺の東海道
・・静岡県藤枝市岡部町内谷
電柱の無いすっきりした町並みである |
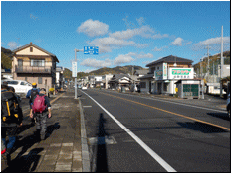 |
⑩五智如来像
・・静岡県藤枝市岡部町岡部
岡部宿内の誓願寺の境内で街道に面して安置されていたが、寺の移転のため現在の場所に移された。
地元産の三輪石で作られ、石造の五智如来像としては大きなもの。一組は宝永2年(1705)に陸奥棚倉城から駿河田中城に移った内藤豊前守弌信の家老脇田次郎左衛門正明 が娘に関する祈願が成就した御礼に寄進したもの。 |
 |
⑪岡部宿問屋場跡
・・静岡県藤枝市岡部町岡部
岡部宿には2軒の問屋場があった |
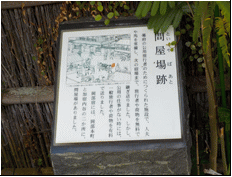 |
⑫岡部宿高札場跡
・・静岡県藤枝市岡部町岡部
幕府や領主の基本的な法令を書いた高札(木の札)を掲示した高札場の跡 |
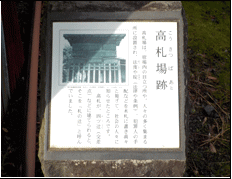 |
⑬小野小町姿見の橋
・・静岡県藤枝市岡部町岡部
長旅と病弱のためやつれた晩年の小野小町が旅の途中で岡部宿に泊まった。この宿場の橋の上で立ちどまり野山の景色の美しさに見とれていたが、ふと水に写ったやつれ果てた自分の姿を見て嘆き悲しんだとの話から姿見の橋と呼ばれるようになった。 |
 |
⑭岡部宿本陣跡 ・・静岡県藤枝市岡部町岡部
内野九兵衛本陣の跡。
間口15間、奥行き29間余、建坪174坪、総畳数129畳半であった。
徳川家茂が参拝し社号を与えたと言われる将軍稲荷が残っている。
岡部宿には他に仁藤本陣があった。 |
 |
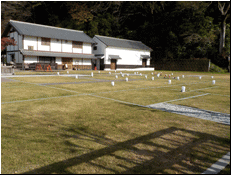 |
⑮柏屋(かしばや) ・・静岡県藤枝市岡部町岡部817
柏屋は天保7年(1836)に建てられた大旅籠であり、山内家が営んでいた。敷地面積2384坪、母屋の延べ面積は約100坪であった。
現在は歴史資料館となっており、国の登録有形文化財。 |
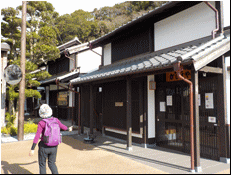 |
 |
⑯宇津ノ谷峠 ・・静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷
宇津の山を越えるルートは鎌倉時代以前には蔦の細道があったが鎌倉幕府は部隊の行進ができないこの道を廃止し、新たに宇津ノ谷峠道を作った。上り下り八丁(約870m)の険路であった。 |
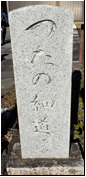 |
 |
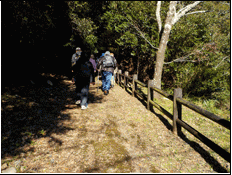 |
 |
 |
⑰地蔵堂跡
・・静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷
ここには旅人の道中の安全を祈願した地蔵堂があった。
現在は建物は消失し土台であった石垣だけが残っている。 |
 |
⑱御羽織屋
・・静岡県 静岡市 駿河区宇津ノ谷171
宇津ノ谷峠の手前、旧東海道の面影を色濃く残す宇津ノ谷集落にある、かつての立場茶屋。豊臣秀吉が小田原城侵攻の途中に立ち寄った際に主人が馬用のわらじを差し出した機転を喜んだ秀吉が戦勝の帰りに立ち寄り、着ていた陣羽織を褒美として与えた。この陣羽織は今も所蔵されており一般公開している。 |
 |
⑲名残の松
・・静岡県静岡市駿河区丸子
江戸時代から現在に至るまで多くの旅人を見てきた丸子地区に残る3本の松の中の1本である。 |
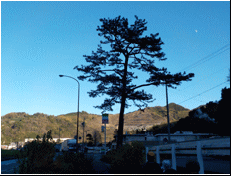 |
<丸子宿>
丸子宿は江戸日本橋から20番目、京三条大橋から34番目の宿場。かつての鞠子から丸子に変わったが読みは「まりこ」で変わらず。
町並み長さ7町(764m)、人口795人、家数211軒、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠屋24軒の山裾の小さい宿場であった。
名物は付近の山で採れる山芋の「とろろ汁」。 |
⑳丸子宿高札場跡
・・静岡県静岡市駿河区丸子
丸子宿の西口にあたる丸子橋横に高札場が復元されている。 |
 |
21. 丁子屋
・・静岡県静岡市駿河区丸子7
創業は慶長元年(1597年)。宿場町として栄えた丸子で400年以上もとろろ汁を提供する老舗。松尾芭蕉は「梅若葉丸子の宿のとろろ汁」という句を詠み、歌川広重は「東海道五十三次・丸子」で丁子屋を描くほどこの店は有名である。 |
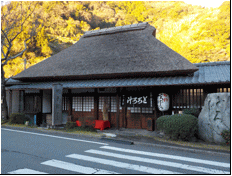 |
22. 七里役所跡 ・・静岡県静岡市駿河区丸子
七里役所とは徳川御三家の一つ、紀州家が重要書類の送信のために、七里(約28km)ごとに置いた飛脚 の継立所(飛脚小屋)のこと。
この飛脚は幕府の継飛脚、民間の定飛脚(町飛脚)に対して、「大名飛脚」・七里飛脚」とも呼ばれていた。 |
 |
23. 丸子宿脇本陣跡
・・静岡県静岡市駿河区丸子7丁目
丸子宿には2軒の脇本陣があった |
 |
 |
24. 丸子宿本陣跡
・・静岡県静岡市駿河区丸子7丁目
丸子宿の本陣は横田家が務めたこの1軒のみであった。 |
 |
25. 丸子宿江戸方見付跡
・・静岡県静岡市駿河区丸子6丁目
丸子宿の江戸からの入口に位置し、見付は街道の見張場の役目をしていた。 |
 |
26. 丸子一里塚跡
・・静岡県静岡市駿河区丸子6丁目
江戸日本橋から47里目、京三条大橋から79里目の一里塚跡 |
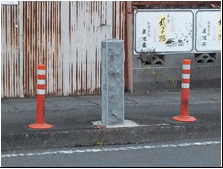 |
本日のゴール
・・静岡県静岡市駿河区丸子6丁目
2018.12.17 15:55 |
 |
|
|