|
|
| 大津宿(第53番) ~ 草津宿(第52番) |
'18.2.3 10:10
①大津駅前公園・・ 滋賀県大津市京町3丁目1
先回の終点。今回はここからスタート。 |
 |
②大津駅近辺の旧東海道 |
 |
③義仲寺
・・・滋賀県大津市馬場1-5-12
義仲寺の名は、平家討伐の兵を挙げて都に入り、帰りに源頼朝軍に追われて粟津の地で壮烈な最期を遂げた木曽義仲(1154-84)をここに葬ったことに由来している。近江守護であった佐々木六角が、室町時代末期に建立したといわれている。 |
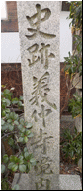 |
 |
④膳所城北総門跡・・・滋賀県大津市西の庄5
膳所城北総門のあった場所に、その印として小さな標柱が建っている。門の遺構は見られないものの、旧東海道にあたるその道は、門があったことを思わせるように直角に曲がっている。ここから南が膳所城下であった。 |
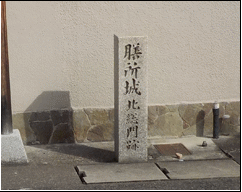 |
⑤紅殻格子
京町家の外観をしつらえる大切な要素の一つ。細かな木を縦と横に組み合わせ、中からはよく見えるが外からは容易に見えないようにする防犯上の機能ももっている。
着色は防腐や魔除けの意味を兼ねており、紅殻が使われるところから紅殻(べんがら)格子と呼ばれる。 |
 |
⑥石坐神社・・大津市大津市西の庄15-16
祭神は彦坐王(ひこいますおう)と、天智天皇、伊賀釆女宅子媛命(いがうねめやかこひめのみこと)とその子大友皇子(おおとものおうじ)(弘文天皇)、豊玉比古命、海津見神。
前四柱の神像は平安および鎌倉時代の作で、重要文化財に指定されている。創建年代等は不詳。 |
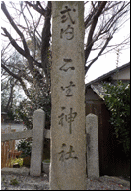 |
 |
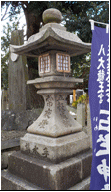 |
⑦和田神社・・・滋賀県大津市木下町7-13
斉明天皇、天智天皇、天武天皇のいずれの御世かとされる白鳳4年に、創祀されたと伝えられている。 その後、八大龍王社や正霊天王社、などと時代の移り変わりとともに呼び名も代わり、明治維新のころに膳所藩主の令達により、現在の名前、 和田神社になったと言われている。 |
 |
 |
 |
⑧膳所城跡公園・・・滋賀県大津市本丸町7
近江大橋西詰のすぐ南側に突き出た地にあった膳所城は徳川家康が関ヶ原の合戦の後、築城の名手といわれた藤堂高虎に最初に造らせたもの。城構えは湖水を利用して西側に天然の堀を巡らせた典型的な水城で、白亜の天守閣や石垣、白壁の塀・櫓が美しく湖面に浮かぶ姿は、実に素晴らしかったと伝わる。この美観は、「瀬田の唐橋、唐金擬宝珠(からかねぎぼし)、水に映るは膳所の城」と里謡にも謡われている。
戸田・本多・菅沼・石川と城主が変わった後、本多6万石代々の居城として長く偉容を誇ったが明治維新で廃城になり楼閣は取り壊された。 |
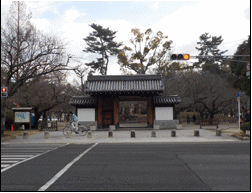 |
 |
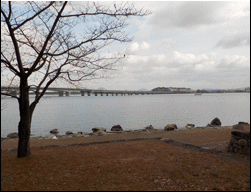 |
⑨旧膳所城下の旧東海道 |
 |
⑩篠津神社・・・滋賀県大津市中庄1-14-24
古くは大梵天王と号し天王社と称されていたが、のち天王宮さらに牛頭天王社と改称された。膳所中庄の産土神である。創祀年代は不詳であるが、康正二年の棟札が現存しているところからみても、室町時代にはすでに鎮座されていたと考えられる。また大津円満院門跡常尊法親王や覚淳法親王、有栖川家の崇敬厚く、鳥居額等種々寄進され、社参の記録もある。さらに膳所城主や戸田、菅沼、石川諸氏ならびに本多家の崇敬が長く続き、社領二十二石の他、社殿の修復も本多家でしばしば行なわれた。現在の本殿は膳所城主本多俊次公の万治四年に造営されたものである。 |
 |
⑪若宮八幡神社・・・大津市杉浦町20-20
白鳳4年(664)の創始と伝わる古社で膳所の旧東海道筋に鎮座する。天智天皇がこの地へ行幸の際、紫雲がたなびき、金の鳩が付近の大木に止まるのを見て、この地へ社を建立することとしたのが始まりとされる。江戸期には膳所の多くの神社同様膳所藩の庇護を受け、現在の表門は膳所城の犬走門を移築したもの。 |
 |
| |
⑫膳所城勢多口総門跡・・・滋賀県大津市御殿浜20-37
膳所城下の南の入り口にあたる勢多口総門のあった地点を記す標柱。門の遺構はないものの、前には粟津の番所跡建物が現存し、また道も門の存在を今に伝えるかのように直角に曲がっている(写真右)。 |
 |
 |
⑬瀬田の唐橋・・・滋賀県大津市唐橋町
日本三名橋の一つで近江八景「瀬田の夕照」で名高い名橋。古くは、瀬田橋・瀬田の長橋とも呼ばれ、日本書紀にも登場する。現在の状態は、織田信長により現在の状況(大橋・小橋)に整備された。
「唐橋を制するものは天下を制す」とまでいわれるほど、京都へ通じる軍事・交通の要衝であることから幾度となく戦乱の舞台となった。現在の橋は昭和54年に架け替えられたが、緩やかな反りや旧橋の擬宝珠など往時の姿をとどめている。
「いそがばまわれ」の語源となったことでも有名。
<急がば回れ>の語源
宗長(室町時代の連歌師)の歌「もののふの矢橋の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」が語源である。
東海道五十三次草津宿(滋賀県草津市矢橋港)と大津宿(大津市石場港)の間には湖上水運「矢橋の渡し」があり、瀬田の唐橋(長橋)経由の陸路よりも近くて速いのだが比叡山から吹き下ろされる突風(比叡おろし)により危険な航路だったため急ぎの場合は遠回りではあるが確実な陸路を選んだほうが良いという意味。 |
 |
 |
 |
⑭建部大社・・・滋賀県大津市神領1-16-1
瀬田の唐橋の東約500m。この社は、近江一の宮といわれ、長い歴史と由緒を持つ全国屈指の古社。祭神は、日本武尊(やまとたけるのみこと)。奈良時代に神崎郡建部郷(かんざきぐんたてべごう)から瀬田大野山(所在不明)山頂に遷され、その後、建部氏によって現在地に遷座された。 古くから歴代朝廷の尊信が驚く、また武将たちの崇敬も深く集めた。特に平安時代末、源頼朝が平家に捕らえられて伊豆に流される途中、建部大社に立ち寄って源氏再興の祈願をし、見事にその願が叶って以来は、武運来運の神として信仰を集めた。 社殿は、日本武尊を祀る正殿と大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る権殿が並び立ち、拝殿左右に未社が並んでいる。
(当日は節分のイベントで賑わっていた) |
 |
 |
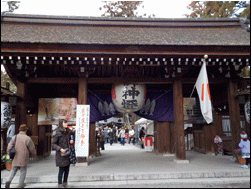 |
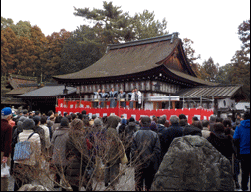 |
⑮月輪一里塚跡
・・滋賀県大津市一里山2-18
江戸日本橋から120里の一里塚跡 |
 |
 |
⑯月輪立場跡・・滋賀県大津市月輪2丁目-3-18
江戸時代以前、月輪辺りは原野だったが、開墾が進められて延宝4年(1676年)に大萱新田となり、東海道沿道には立場が置かれた。明治7年(1874年)当地にある月輪池を名の由来として月輪村と改称された。
右の写真は月輪を行く旧東海道。 |
 |
 |
 |
⑰萩の玉川
・・・滋賀県草津市野路4丁目-3-26
玉のような清水が湧き出たという故事来歴を有する名所で、諸国六玉川の一つに数えられた。浮世絵や名所図会等で諸国の人々に知られるようになった |
 |
 |
⑱平清宗塚・・・滋賀県草津市野路5丁目-2-2
平安後期の公卿、平宗盛の長男、母は兵部権大輔平時宗の娘。後白河上皇の寵愛をうけ、三才で元服して寿永二年には正三位侍従右衛門督であった。源平の合戦により、一門と都落ち、文治元年壇ノ浦の戦いで父宗盛と共に生虜となる。 「吾妻鏡」に「至野路口以堀弥太郎景光。梟前右金吾清宗」とあり、遠藤権兵衛家が代々胴塚として保存供養している。 |
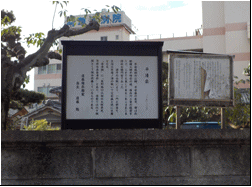 |
⑲野路一里塚・・・滋賀県草津市野路6丁目-5-13
江戸日本橋から119番目の一里塚 |
 |
 |
⑳瓢泉堂・・滋賀県草津市矢倉2丁目2-1
江戸時代より、酒や水を入れる容器として使われてきた瓢箪。当時宿場町である草津も数軒の瓢箪屋があり、その一つ。
安藤広重の描いた「東海道五十三次」の草津宿(うばがもちや)は現在の当店に位置する。 |
 |
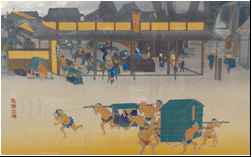 |
21.立木神社・・・滋賀県草津市草津4丁目1番3号
立木神社の創建は古く、縁起によると今から約1200余年前の称徳天皇神護景雲元年(767年)のこと、御祭神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)が常陸国の鹿島神宮を白鹿に乗り旅に出られ、諸国を経てこの地に到着された。そして、手に持たれた柿の鞭を社殿近くに刺され「この木が生え付くならば吾永く大和国(やまとのくに)(奈良県)三笠の山(今の春日大社)に鎮まらん」と言われた。すると、その後不思議にも柿の木は生え付き枝葉が茂り出した。里人は御神徳を畏み、この木を崇め神殿を建て社名を立木神社と称したのが始まりと伝えられている。
今回はここが終点。
(2月3日の節分に重なり、大行列だったため参拝は断念)
'18.2.3 16:35 |
 |
|
|