|
|
| 草津宿(第52番) ~ 石部宿(第51番) |
2017.3.20 10:00
①立木神社・・草津市草津4丁目
東海道に面し、古くから交通安全厄除けの神社として信仰を集めている。
本日はここからウォーキングスタート!
|
 |
②太田酒造_道灌蔵・・草津市草津3丁目
江戸城を築城した武将太田道灌を先祖に持つ太田家が海道の守りのために草津に移り、この地域の良質な近江米を使って酒造りを始め、先祖の名にちなんで「道灌」と名づけた。
|
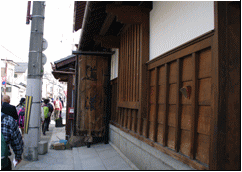 |
③常善寺・・草津市草津3丁目
735年に建立され、当時は奈良の東大寺と並ぶほどの規模だったとのことで関が原で勝った徳川家康が上洛途中で泊まった。
重要文化財「本尊阿弥陀如来坐像」が安置されている。 |
 |
④草津宿本陣・・草津市草津1丁目
当時は大名などが宿泊した本陣。現存する本陣では最大級とのこと。
浅野内匠頭、吉良上野介、土方歳三、篤姫・・等が宿泊、または休憩で立ち寄った。 |
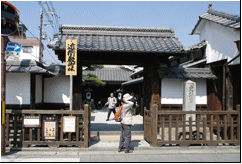 |
⑤うばがもち
古くは広重や北斎の浮世絵にも「うばがもちや」として描かれている草津名物
街道を行く旅人に人気があったよう。 |
 |
⑥追分道標・・草津市草津1丁目
東海道と中山道の分岐点。
「右東海道いせみち」「左中仙道美のぢ」と書かれている。土手は天井川の名残り。
中山道は直進、東海道は右折。 |
 |
⑦老牛馬養生所跡・・・栗東市小柿
老馬を殺して皮を剥ぐ残酷さに驚いた庄屋岸岡長右衛門が老牛馬が静かに余生を過ごせるよう天保12年に養生所を設立した。 |
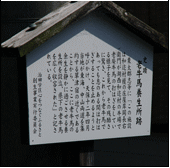 |
 |
⑧膳所城大手門
膳所城は関が原の戦いの直後に徳川家康が大阪方への備えとして藤堂高虎に命じて築城したもの。 |
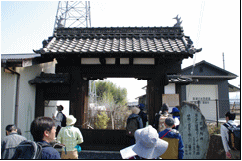 |
⑨田楽茶屋・・草津市
東海道各所に旅人の休憩所として立場が設けられた。ここ目川立場には地元の食材を使った菜飯と田楽が供され名物となった。
田楽茶屋として「元伊勢屋」「京伊勢屋」「古志ま屋」の三軒があった。
|
 |
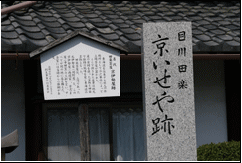 |
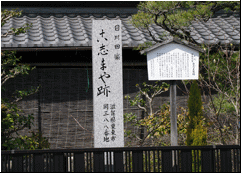 |
⑩善性寺・・・栗東市川辺
植物学者シーボルトが江戸からの帰路に立ち寄り、珍しい植物を見物したとの記録がある |
 |
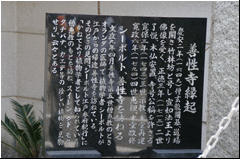 |
⑪鈎(まがり)の陣跡・・・栗東市上鈎
室町時代、近江守護六角氏が幕府に対し反抗的な態度を取るようになり、幕府の権力回復をめざして九代将軍足利義尚が長享元年(1487)六角氏を討伐するため近江に出陣した。
その際の陣所跡。 |
 |
⑫六地蔵一里塚跡
・・栗東市六地蔵
江戸から117里の一里塚 |
 |
 |
⑬旧和中散本舗・・・栗東市六地蔵
腹痛や暑気あたりに効くと評判だった和中散の製造・販売を行っていた和中散本舗。
また宿の間の休憩所としても利用されていたとのこと。 |
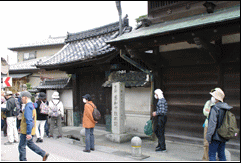 |
⑭福正寺(法界寺)・・・栗東市六地蔵
重要文化財の木造地蔵菩薩立像が本尊として安置されている。
作られたのは平安時代。 |
 |
⑮高架は名神高速道路
手前は栗東市、向こう側は湖南市 |
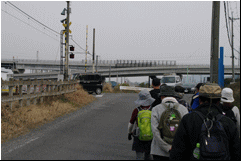 |
⑯石部宿 西の見附跡・・・湖南市石部西
見附とは通行人を見張る城門で石部宿には東西2ヶ所に見附があった |
 |
⑰吉御子神社・・・湖南市石部西
奈良時代に創建された神社で現在の本殿は幕末の頃、京都上賀茂神社の本殿を移築したもの。
重要文化財になっている。 |
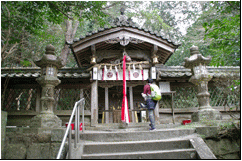 |
⑱石部宿 小島本陣跡・・湖南市石部中央
明治天皇も宿泊された本陣。建物は残っていない。 |
 |
 |
2017.3.20 16:20
⑲石部宿 高札場跡・・湖南市石部中央
高札とは幕府が決めた法度や掟を板札に書いて掲示したもの。
本日のゴール!!
次回はここから歩く。 |
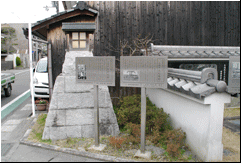 |
|
|