|
|
| 石部宿(第51番) ~ 水口宿(第50番) |
2017.4.17 10:20
①石部宿 高札場跡・・湖南市石部中央
先回はここが終点
今回はここがスタート地点
|
 |
②吉姫神社・・・湖南市石部東8丁目4−1
木花開耶姫を祀り、上鹿葺津姫、吉比女大神を配祀する。同じく湖南市の吉御子神社とは対の関係にあり、5月1日の例祭では両社から神輿が出る。境内の木造の狛犬は南北朝時代に作られたと言われている。 |
 |
③東の見附跡・・・湖南市石部東6-8-25
東の見附は幅約3m、高さ約2mの台場であり、石部宿場の両入口にあった。枡形城門の俗称で番兵が通行人を見張るところから見附と言われた。 |
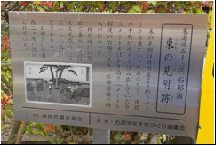 |
④高木陣屋跡・・・湖南市平松
元禄十一年(1698)道中奉行に任命された高木伊勢守が元禄十二年に平松を領するようになった。その後、文化年間に宏壮な二階建ての陣屋を建てた。 |
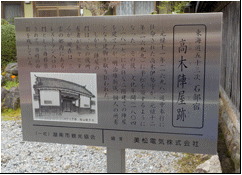 |
⑤北島酒造・・・湖南市針756
文化二年(1805)に創業し淀藩配下の酒造取締役に任ぜられた。 |
 |
⑥由良谷川隧道・・・湖南市夏見1447
湖南市を流れていた3つの天井川の一つ「由良谷川」に作られた隧道 |
 |
⑦夏見一里塚・・・湖南市夏見1498
江戸日本橋から115里の一里塚 |
 |
⑧夏見の里・・・湖南市吉永
この辺りが夏見の里と言われ何軒かの茶店があり立て場の役割を果たしていた。名物トコロテンや名酒桜川が茶碗酒として計り売りされていた。
「いなりや」という茶店があり歌川広重が描く藤の棚の店として紹介されていた。 |
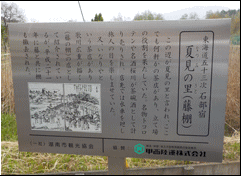 |
⑨大沙川隧道・・・湖南市吉永292
|
 |
| |
|
⑩弘法杉・・・湖南市吉永
大沙川の堤の上にそびえる大杉で幹の周囲6m、高さ26m、樹齢750年と言われる。
弘法大師が通りかかった際に眺めの良いここで昼食をとり、その時に使った杉箸を堤にさし、それが成長して大杉になったと伝えられ「弘法杉」と名づけられた。 |
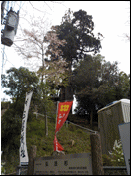 |
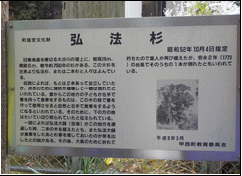 |
⑪立志神社・・・湖南市三雲1353
欽明天皇の御代に五穀が実らず、庶民の多くが餓死寸前に追いやられた。そこで天皇は全国十二ヶ所の神社に祈願の勅使を遣わされ、この神社もその祈願所の一つであると伝わる。 |
 |
⑫横田常夜燈(三雲側)・・・湖南市三雲448
東海道十三の渡しの難所の一つに数えられる横田の渡し場、湖南市側に建立されている。
安永八年(1774)に東講中によって建てられた火袋付の常夜燈である。 |
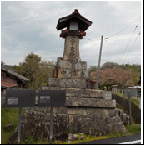 |
⑬天保義民碑・・・湖南市三雲
天保十三年(1842)十月、現在の野洲市の三上地区で近江天保一揆が発生した。野洲、栗田、甲賀3郡の農民約4万人が幕府による検地の中止を要求して決起し、三上村に集まり幕府が派遣した役人から十万日の日延べを勝ち取った。しかし多くの犠牲者を伴ったため義民として永久に伝えるために碑が建立された。 |
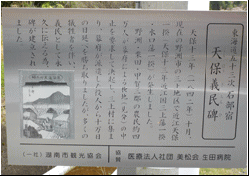 |
⑭横田渡常夜燈(甲賀市側)・・甲賀市水口町泉351
横田川(現在の野洲川)の「横田の渡し」は江戸時代には参勤交代などで通行量が多く、夜も通行が絶えなかった。
対岸の渡し場の目印として文政5年(1822)に建設されたもので東海道随一の規模。 |
 |
⑮北脇縄手と松並木・・・甲賀市水口町北脇944
東海道が一直線に伸びるこの辺りは江戸時代「北脇縄手」と呼ばれた。縄手とは田の中の道のことで東海道の整備に伴い曲がりくねっていた旧伊勢大路を廃し見通しの良い道路としたことにちなんでる。江戸時代、東海道の両側には松並木があり、旅人は松の木陰に涼をとり旅の疲れを休めたと言われている。 |
 |
⑯百間長屋跡・・・甲賀市水口町城内6
百間長屋はお城の郭内の武家地にあった百間(180m)の棟割長屋で下級武士達が隣り合って住んでいた。郭内側に玄関があり敵の攻撃から防御するため東海道側に出入口は無かった。東海道側には小さい高窓(与力窓)があり、買物はここから紐をつけたザルを吊るして行った。 |
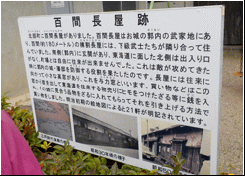 |
⑰今回はあいにくの雨。
合羽を着てのウォークだった。 |
 |
2017.4.17 16:10
⑱本日の水口宿の終点
次回はここからスタート
|
 |
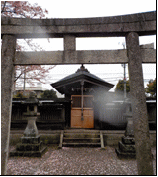 |
|
|