|
|
| 水口宿(第50番) ~ 土山宿(第49番) |
2017.5.22 9:57
①藤榮神社
・・・滋賀県甲賀市水口町梅が丘
先回はここが終点
今回はここからスタート
|
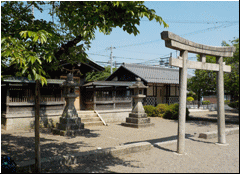 |
②三筋の道・・ 滋賀県甲賀市水口町本町
水口岡山城を守るための迷路の役目を果たすため道が3本に別れていた(この左にもう1本道がある) |
 |
③水口宿
天下を握った家康は慶長6年東海道を整備し五十三の駅をおいて公用の輸送を確立。この時水口も宿駅となった。宿場は町数27、家数718と発展。庶民の旅が盛んとなった江戸後期には40余りの旅宿と本陣・脇本陣で賑わった |
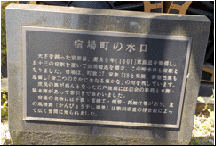 |
④問屋場跡・・・滋賀県甲賀市水口町京町
問屋場は、宿駅本来の業務である人馬の継ぎ立てを差配したところで、宿駅の中核的施設として、公用貨客を次の宿まで運ぶ伝馬と、人足を用意した。
水口宿では、江戸中期以来ここ大池町南側にその場所が定まり、宿内の有力者が宿役人となり、運営にあたった |
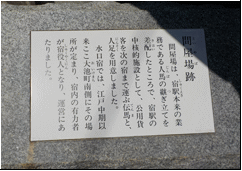 |
⑤高札場跡・・・滋賀県甲賀市水口町元町
高札場とは、幕府の法度や掟書を書き記した板札を立てた場所のこと。水口宿では1711年に宿場東部に設けられていた。 |
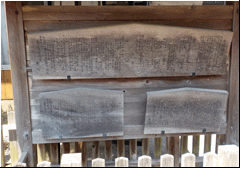 |
⑥水口本陣跡・・・滋賀県甲賀市水口町元町
水口本陣は古い家柄で苗字帯刀を許された鵜飼伝左ヱ門が営んでいた。表門は貴人宿泊の格式を表し、瓦葺か冠木門で屋舎は平屋だった。本陣の特色として庭はあるが絶対に石は入れず、必ず裏手に立ち退き口があり、非常の際の脱出口になった。現在の本陣跡は明治天皇行在所の石碑が建っているだけでその面影はない |
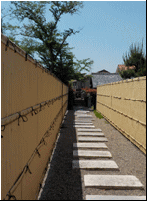 |
⑦東見附跡・・滋賀県甲賀市水口町秋葉
江戸時代に東海道水口宿の東端にあった見附跡。見附とは土居と木戸で囲まれた場所のことで、宿の防御と管理のために宿場の東端と西端に置かれていた。 |
 |
 |
⑧岩神社・・滋賀県甲賀市水口町新城
岩神社は本来東海道側に面してあり、子供の成長の神様として、また街道名所の一つとして知られていた。社は無く岩を祭るとあり、村人は子供が生まれるとこの岩の前に抱いて立ち、旅人に頼んで名前を決めてもらう習慣があった。
一帯は奇岩に富み、また眼下には野洲川の清流が流れる景勝の地であったとこから、街道に面した茶店などで行き交う旅人は疲れを癒した |
 |
 |
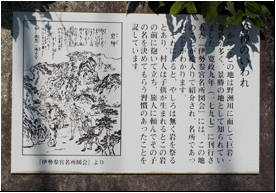 |
⑨今在家一里塚・・滋賀県甲賀市水口町今郷
江戸から112里の一里塚。
今在家集落の半ば浄土寺の手前で街道は左に屈曲し同寺の背後から再び東に進む。ちょうどその付近に一里塚が道を挟んで二基あったが、明治に入って撤去された。 |
 |
⑩明治天皇聖蹟(旅籠小幡屋跡)
・・・滋賀県甲賀市土山町徳原 |
 |
 |
⑪従是東淀領碑・・滋賀県甲賀市土山町徳原
従是東淀領と書かれていて淀藩の領地(飛び地)であることを示す |
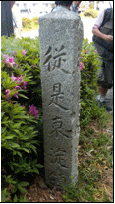 |
⑫大野市場一里塚・・滋賀県甲賀市土山町市場
江戸から111里 |
 |
⑬ 垂水頓宮建立跡地・・滋賀県甲賀市土山町頓宮
垂水の頓宮建立跡地は、平安時代の初期から鎌倉時代の中頃まで、約三百八十年間、三十一人の斎王が伊勢参行の途上に宿泊された頓宮が建立された所である。
斎王とは、天皇が即位される度毎に、天皇のご名代として、皇祖である天照大神の御神霊の御杖代をつとめられる皇女・女王の方で、平安時代に新しく伊勢参道がつくられると、この道を斎王群行の形でご通行されることとなった。京都から伊勢の斎宮まで、当時は五泊六日もかかり、その間、近江の国では勢多・甲賀・垂水の三ヶ所、伊勢の国では鈴鹿・一志の二ヶ所で、それぞれ一泊されて斎宮まで行かれたのである。その宿泊された仮の宮を頓宮といい、現在明確に検証されている頓宮跡地は、五ヶ所のうち、ただこの垂水頓宮だけである。 |
 |
⑭瀧樹神社
・・滋賀県甲賀市土山町前野
古くより川田神社として地主神を奉斎し、垂仁天皇四年倭姫命は、天照大神を奉じて近江国甲賀郡垂井日雲宮に至り、ここに座する事四年、この間川田神社にて調膳を司った関係で、大神に神縁深い滝原宮より仁和元年速秋津日子神、速秋津比賣命の二柱の分霊を勧請し之を地主神の城内に合祀し社号を川田神社滝大明神とし岩室郷頓宮牧の産土神と崇め奉り郷中の総社とし、祭礼儀式は特に鄭重を極めた。応永年中地頭岩室主馬頭橘家後が樹の文字を加へ奉り滝樹大明神と改号した。 |
 |
 |
⑮土山宿
土山宿は平安時代に伊勢参宮道が鈴鹿峠を越える旧東海道筋を通るようになって以来、難所を控える宿駅として発達してきた。
源頼朝が幕府を鎌倉に開くと従来の京都中心の交通路は京都と鎌倉を結ぶ東西交通路線が重視されるようになり武士のみならず庶民の通行も盛んになった。特に江戸幕府は伝馬制度を整備し宿駅を全国規模で設け、土山宿は東海道五十三次の49番目の宿駅に指定されてから宿場町として真に隆盛し始めた。 |
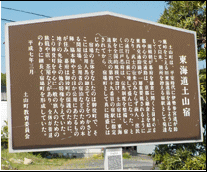 |
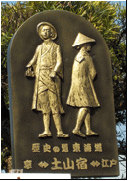 |
⑯土山宿陣屋跡
・・滋賀県甲賀市土山町北土山
土山宿の陣屋は天和三年(1683)当時の代官であった猪飼次郎兵衛のときに建造され瀬古川の東崖にあり東西二十五間、南北三十間の広さがあったと言われている。寛政十二年(1800)の大火災で類焼し以後再建されず百二十年の歴史を閉じた |
 |
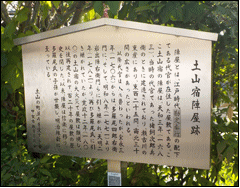 |
⑰大黒屋本陣跡
・・滋賀県甲賀市土山町北土山
土山本陣は寛永十一年(1634)三代将軍家光が上洛の際に設けたが参勤交代制施行以来諸大名の休泊が増加し、土山本陣のみでは収容しきれなくなり土山宿の豪商大黒屋立岡氏に控本陣が指定された。古地図によると当本陣は土山本陣のように門玄関、大広間、上段間をはじめ多数の間を具備し宿場に壮観を与えるほどの広大な建築であったことが想像できる |
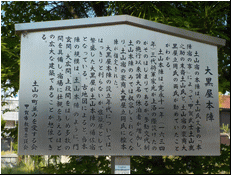 |
 |
⑱土山家本陣跡・・滋賀県甲賀市土山町北土山
土山本陣は寛永十一年(1634)三代将軍家光上洛の際に設けられた。土山家初代は甲賀武士土山鹿之助であり、三代目喜左衛門の時に本陣職を務めた。当家には当時の道具や宿帳等、貴重なものが多数保存されている。
幕末から明治にかけては宮家が東西の往来の途次に休泊されることもあり中でも明治元年九月の明治天皇行幸の際んはこの本陣で満十六歳の誕生日を迎えられ近代日本として天長節が祝われた。この時には土山宿の住民にお神酒とスルメが下賜され、今なお土山の誇りとして語り継がれている。明治三年(1870)に本陣制度が廃止されたため土山家本陣も役目を終えた |
 |
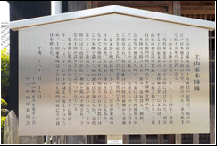 |
 |
⑲土山宿の東海道
土山宿の東海道は現在はカラー舗装されていた |
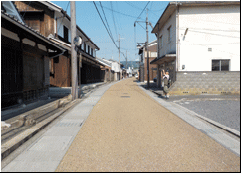 |
⑳問屋場跡
・・滋賀県甲賀市土山町北土山
問屋場は公用通行の客や荷物の人馬継立、宿泊施設の世話、助郷役の手配等の宿に関わる業務を行う場所で宿の管理を司る問屋とそれを補佐する年寄り、業務の記録を行う帳付、人馬に人や荷物を振り分ける馬指、人足指らの役人が詰めていた。
土山宿の問屋場は中町と吉川町にあったとされるが問屋宅に設けられていたこともあり時代とともに場所も移り変わっていった。明治時代の宿駅制度廃止に伴い問屋場も廃止されたが、その施設は成道学校として利用された。 |
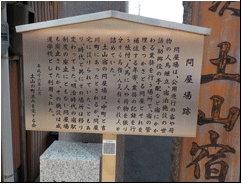 |
 |
21.堤家(二階屋)本陣跡
・・滋賀県甲賀市土山町南土山
土山宿には北土山村側の土山家本陣と南土山村側の堤家本陣の二軒があった。堤家本陣はその屋号から二階屋本陣とも呼ばれ代々忠左衛門を名乗った。史料上の初見は延宝八年(1680)で以後本陣職を務めた。
堤家本陣は幕末に衰微し、これより約250m西の吉川町の北土山村側にあった大旅籠の大黒屋がその代替として利用された。 |
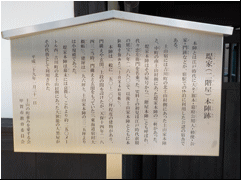 |
 |
22.平野屋跡・・滋賀県甲賀市土山町北土山
井筒屋跡・・滋賀県甲賀市土山町南土山
文豪森鴎外の祖父白仙は、文久元年(1861)11月7日、土山の井筒屋で没した。鴎外が明治33年に記した「小倉日記」で明らかなように、森家は代々津和野藩亀井家の典医として仕えた家柄である。白仙は長崎と江戸で漢学・蘭医学を修めた篤学家であった。参勤交代に従って江戸の藩邸より旅を続けるうち、この井筒屋で病のため息をひきとったのである。のちに白仙の妻清子、一女峰子の遺灰も、白仙の眠る常明寺に葬られた。
そして森鴎外が祖父白仙の墓参のために明治三十三年に土山を訪れ、宿泊したのが平野屋である。 |
 |
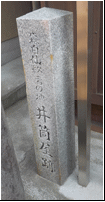 |
2017.5.22 16:03
23.道の駅あいの土山・・滋賀県甲賀市土山町北土山
本日のゴール
次回はここからスタートする |
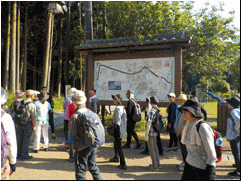 |
|
|