|
|
| 土山宿(第49番) ~ 関宿(第47番) |
2017.6.19 9:58
①土山宿(道の駅あいの土山)
先回はここが終点
今回はここからスタート
|
 |
②田村神社・・滋賀県甲賀市土山町北土山
創建は弘仁3(812)年
この地は近江国(滋賀県)と伊勢国(三重県)の国境にあり、古来には都より伊勢へと参宮する交通の要衝だったが、鈴鹿峠に悪鬼が出没して旅人を悩ましており、嵯峨天皇は坂上田村麻呂公に勅命を出してこれを平定させた。交通の障害を取り除いて土地を安定させた遺徳を仰ぎ、
嵯峨天皇は勅令を出して坂上田村麻呂公をこの土山の地に祀られることになったもの |
 |
③海道橋(田村川橋)・・滋賀県甲賀市土山町南土山
江戸時代の安永4年(1775年)に架けられた田村永代板橋を復元した橋。
往時の橋は、巾二間一尺五寸(約4.1m)、長さ二十間三尺(約37.3m)。高さ0.3mの低い欄干が付いた当時としては画期的な橋であった。
安藤広重の「土山宿・春の雨」は、この橋を渡る大名行列の様子を東側から描いたもの。
この田村川橋ができるまでは、約六百メートル程下流に川の渡り場があったが、大水が出るたびに溺れ死ぬ旅人が多く、その対応に土山宿の役人達をはじめ、宿の住民の苦労は大変なものだった。また、川止めも再三あり、旅人を困らせていました。
そこで幕府の許可を得て、土山宿の人達が中心になりお金を集め、今までの東海道の道筋を変えて新しい道を造り、田村川木橋を架けることになった。
役人や生活に必要な住人の通行は無料だったが、一般の住民や旅人は一人三文の渡り賃が必要だった。高札には「永遠に続く」と書かれていたが現在は無料。
|
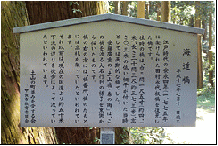 |
 |
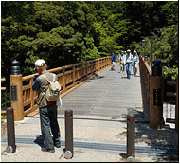 |
④蟹坂古戦場跡
天文11年(1542年)9月、伊勢の国司北畠具教は、甲賀に侵入しようとして武将神戸丹後守および飯高三河守に命じ、鈴鹿の間道を越えて山中城を攻めさせた。当時の山中城主の山中丹後守秀国は直ちに防戦体制を整え、北畠軍はひとまず後退したが直ちに軍政を盛りかえし、さらに北伊勢の軍政を加えて再度侵入し、一挙に山中城を攻略しようとした
このため秀国は守護六角定頼の許へ援軍を乞い、六角氏は早速高島越中守高賢に命じて、軍政五千を率いさせ山中城に援軍を送った。一方、北畠軍も兵一万二千を率い、蟹坂周辺で秀国と合戦した。この戦いは、秀国勢が勝利を収め、北畠勢の甲賀への侵入を阻止することができた。 |
| |
 |
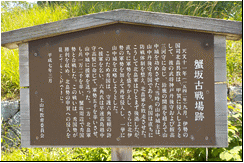 |
⑤猪鼻村立場・・滋賀県甲賀市土山町猪鼻
猪鼻村は鈴鹿山脈の西方に位置し中世は鈴鹿山警固役であった山中氏の支配を受け、近世は幕府領や諸藩領になり幕末に至る。村中を東海道が東西に五町三十六間余、商いを営むものも多く、往時五十戸を超え街道を賑わしていた。
立場(休憩所)があり、草餅や強飯が名物だった。 |
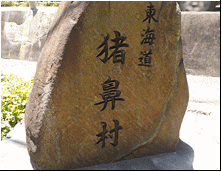 |
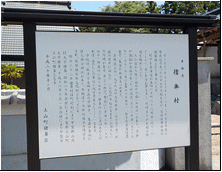 |
赤穂浪士の一人で俳人の大高源吾(俳号は子葉)が旅の途中で詠んだ
「いの花や早稲のもまるゝ山おろし」
の句碑がある |
 |
⑥鈴鹿峠の登り
土山宿側からは勾配の緩い登りが続く(1号線沿い)。
昔はどうだったか・・は?
前方に見えるのは新名神高速道路 |
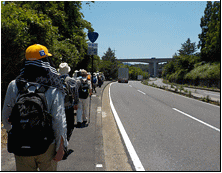 |
 |
⑦櫟野観音道道標・・滋賀県甲賀市土山町山中
東海道と櫟野村を結ぶ生活道路と東海道の分岐点に建てられていたもので道路整備により現在は一里塚公園に移転されている。
「いちゐのくわんおん道」と刻まれている。 |
 |
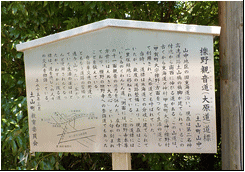 |
⑧鈴鹿峠最後の登り
峠の最後の登りは少し勾配のきつい部分があった |
 |
⑨万人講常夜燈・・滋賀県甲賀市土山町山中
万人講常夜燈は、江戸時代に金比羅参りの講中が道中の安全を祈願して建立したものである。重さ38t、高さ5.44mの自然石の常夜燈で、地元山中村をはじめ、坂下宿や甲賀谷の人々の奉仕によって出来上がったと伝えられている。もともとは東海道沿いに立っていたが、鈴鹿トンネルの工事のために現在の位置に移設された。
東海道の難所であった鈴鹿峠に立つ常夜燈は、近江国側の目印として旅人たちの心を慰めたことであろう。 |
 |
⑩県境
右 滋賀県 近江の国
左 三重県 伊勢の国
是より京まで十七里
と書かれている |
 |
 |
⑪鈴鹿峠(坂下宿側への下り)
林の中の非舗装路。15分程で通り抜けられる |
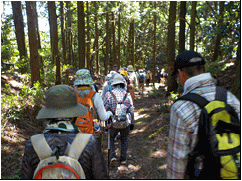 |
ヤマビル(山蛭)対策
下りの山道(非舗装路)はこの季節はヤマビルがいるとのことだったので靴には虫除け剤をたっぷり塗ったシューズカバー、上部は塩漬けしたタオルを巻いてゴムバンドを。
ただし2週間以上雨が降っていなかったので、ヤマビルには全くお目にかかれませんでした(^0^) |
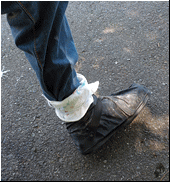 |
⑫坂下宿・・三重県亀山市関町坂下
東海道を近江から鈴鹿峠を越えて伊勢に入った最初の宿場。
少なくとも室町時代には宿として機能していた。
慶安三年(1650年)に大洪水で壊滅し、翌年現在地に移転し復興された。江戸時代には五十三次の四十八番目の宿場として賑わい、難所鈴鹿峠を控えて参勤交代の大名家の宿泊も多かった。江戸後期には本陣3軒、脇本陣1軒、旅籠48軒の有数の宿場町だったが明治23年に関西鉄道が開通し通行者が激減し、役割を終えた。 |
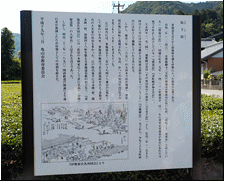 |
⑬坂下宿本陣跡
・・三重県亀山市関町坂下
坂下宿の三軒の本陣 |
 |
 |
 |
⑭坂下市瀬一里塚・・三重県亀山市関町市瀬
江戸から百七里の一里塚 |
 |
⑮筆捨山・・三重県亀山市関町市瀬
東海道からは鈴鹿川を挟んだ対岸に位置する標高289mの山。
江戸時代から名勝として知られ、東海道を往来する人々は対岸の筆捨集落にある茶屋から四季折々の景色を楽しんだ。
歌川広重「東海道五十三次阪ノ下筆捨山」をはじめ浮世絵の坂下宿のほとんどに筆捨山が描かれている。 |
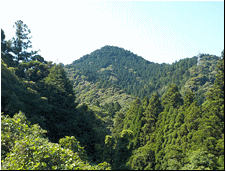 |
⑯関宿 西の追分・・三重県亀山市関町新所
慶長6年(1601年)に徳川幕府が宿駅制度を定めた際、関宿は四十七番目宿場となり、問屋場や陣屋などが整えられた。天保14年(1843年)には本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠屋42軒があったとされ鈴鹿峠を控えた重要な宿駅として、また伊勢別街道や大和街道の分岐点として反映した。
この西の追分は大和街道との分岐点にあたる。
今回はここがゴール! |

|
 |
 |
|
|