|
|
| 関宿(第47番) ~ 庄野宿(第45番) |
2017.9.18 9:40
①関宿 西の追分・・・三重県亀山市新所
先回はここが終点
今回はここからスタート
|
 |
②関宿の町並
関宿は東海道の中でも珍しく江戸~明治時代に建てられた町屋が200軒以上残っており、また現在も街道側には電柱が無く、往時の姿を色濃く残している |
 |
③会津屋・・・三重県亀山市関町新所1771-1
関宿を代表する旅籠の一つである会津屋。現在も食事処として営業されている。
二階の屋号の表示は江戸側が漢字、京都側がかなで書かれている。旅人が方向を間違わないようにとの配慮とのこと。 |
 |
 |
 |
④地蔵院・・・三重県亀山市関町新所1173-2
「関の地蔵さんに振袖きせて奈良の大仏婿に取る」の俗謡で名高い関地蔵院。天平13(741)年、奈良東大寺で知られる行基菩薩が、諸国に流行した天然痘から人々を救うため、この関の地に地蔵菩薩を安置したと伝えられている。この本尊は日本最古の地蔵菩薩で、関に暮らす人々に加え、東海道を旅する人々の信仰も集め、全国の数あるお地蔵様の中でも最も敬愛されていると言われている。境内の本堂、鐘楼、愛染堂の3棟の建物は国の重要文化財。 |
|
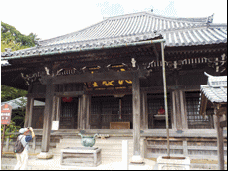 |
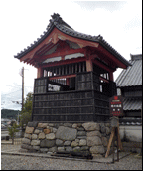 |
⑤福蔵寺・・・三重県亀山市関町木崎417
織田信長の三男・信孝は本能寺の変で斃れた信長の菩提を弔うために、旧家臣大塚長政に命じて福蔵寺の建立に着手した。しかし信孝は羽柴秀吉との後継争いに敗れ、1583年知多半島の野間大坊で自害した。
大塚長政は信孝の首を福蔵寺に持ち帰り、首塚を設けて福蔵寺を信孝の菩提寺として開創した。
現在は、新しい供養塔が建立されている。 |
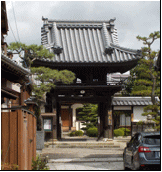 |
 |
⑥関宿高札場・・・三重県亀山市関町中町428-6
関宿高札場は街道に面した間口十一間余の中央に枡形状の土塀に囲まれてあり、高札の付け替え等は亀山藩が行っていた。
ここには8枚の高札が掲げられており、その内容は生活に関わる様々な規範、キリシタン禁令や徒党・強訴の禁止といった幕府の禁令、隣接宿場までの人馬駄賃の既定などであった。 |
| |
 |
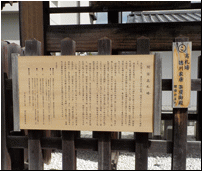 |
⑦銘菓関の戸(深川屋)・・・三重県亀山市関町中町387
寛永年間より伝わる伝統の銘菓「関の戸」は舌触りの良い赤小豆のこし餡をぎゅうひ餅で包み、阿波特産の和三盆をまぶした一口大の餅菓子。
関宿の背後にそびえる鈴鹿の嶺に降り積もる白雪になぞらえて創られたと言われている。 |
| |
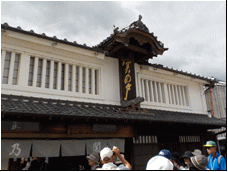 |
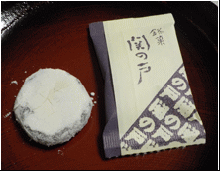 |
⑧旅籠玉屋・・・亀山市関町中町444-1
旅籠とは江戸時代に公用以外の武士や一般庶民が利用した旅の宿。玉屋は「関で泊まるなら鶴屋か玉屋、まだも泊まるなら会津屋か」と謡われたほどの、関宿を代表する大旅籠のひとつだった。現在は江戸時代の貴重な旅籠建築として修復され、亀山市文化財に指定されている。 |
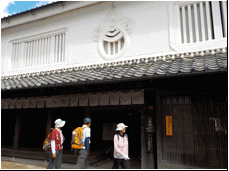 |
 |
⑨伊藤本陣・川北本陣・・・亀山市関町中町
関宿にはこの二件の本陣があった。両家とも広大な敷地に千坪ほどの家屋を持っており、東海道関宿の本陣として栄えた。 |
 |
 |
⑩関宿の町並
当時のままか・・と思わせるような町並 |
 |
⑪鶴屋脇本陣・・・三重県亀山市関町中町470−1
鶴屋(波多野家)。 脇本陣は、本陣に準じる宿として、主に身分の高い人達の宿泊の用を勤めたが、平素は一般庶民も泊まることができた。 鶴屋は西尾吉兵衛を名乗っていたので西尾脇本陣ともいった。玄関前についた千鳥破風がその格式を示す |
| |
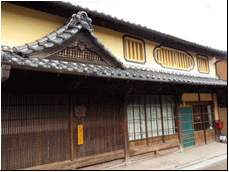 |
 |
⑫御馳走場跡
・・・三重県亀山市関町中町564
宿場の役人が、関宿に出入りした身分の高い武家や公家に対し、衣服を改め宿場両端の御馳走場まで出迎えや見送りを行った場所。 |
 |
 |
⑬東の追分・・・三重県亀山市関町木崎
東の追分は関宿の東の入口にあたり、東海道と伊勢別街道の分岐点。今も残る大鳥居は伊勢神宮を遙拝するためのもので、20年に一度の伊勢神宮式年遷宮の際に内宮宇治橋南詰の古い鳥居を移設するのが慣わし。鳥居の近くには、「これよりいせへ」「外宮(伊勢神宮)まで15里(60km)」と刻まれた石の道標がある。おかげ参りや参勤交代で人々が行き交う関宿の道に明かりを灯した常夜灯なども、当時のまま残されており、現代の旅人の心に楽しみを灯してくれる。
|
| |
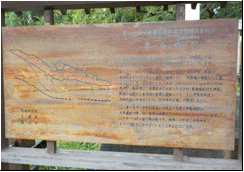 |
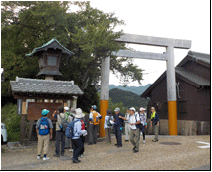 |
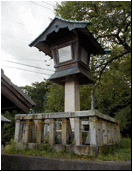 |
⑭関の小萬のもたれ松・・・三重県亀山市関町小野
江戸中期、九州久留米藩士牧等左衛門(まきとうざえもん)の妻は夫の仇を討とうと志し、旅を続けて関宿山田屋に止宿、一女小萬を生んだ後病没した。小萬は母の遺言により、成長して三年程亀山城下で武術を修行し、天明3年(1783)見事仇敵軍太夫を討つことができた。 この場所には、当時亀山通いの小萬が若者のたわむれを避けるために、姿をかくしてもたれたと伝えられる松があったところから「小萬のもたれ松」とよばれるようになった。 |
| |
 |
 |
⑮野村一里塚
・・・三重県亀山市野村3丁目
三重県には旧東海道に沿って12ヶ所に一里塚が設置されていたが、当時のまま現存するのはこの野村一里塚のみ。
元々は道の両側にあったが現在は北側だけが残っている状態で、昭和9年1月に国の指定文化財となった。塚の上には、歴史を見守り続けてきた樹齢400年の椋(むく)の巨木がそびえ立っている。 |
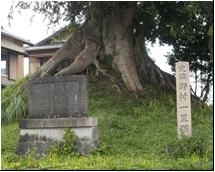 |
 |
⑯京口門跡・・・三重県亀山市西町702−2
亀山宿の西端、西町と野村の境を流れる竜川左岸の崖上に築かれた門である。『九々五集』によれば、亀山藩主板倉重常によって寛文12年(1672)に完成したとされる。翌延宝元年(1673)に東町に築かれた江戸口門とともに亀山城総構の城門として位置づけられ、両門の建設によって東海道が貫通する城下の東西が画された。京口門は石垣に冠木門・棟門・白壁の番所を構え、通行人の監視にあたっていた。また、門へ通じる坂道は左右に屈曲し、道の両脇にはカラタチが植えられ不意の侵入を防いだとされる。 |
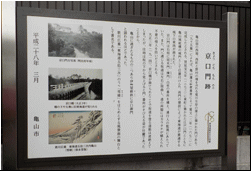 |
⑰亀山城西の丸と外堀・・・三重県亀山市本丸町
西の丸は亀山城の西南にあり家中屋敷と表記されることもあり仕事場や重臣の屋敷地の他、藩校もおかれた。復元された外堀の一部は深さ1.8m程度の水掘で、水深は60cm程度。この深さでは城の防衛に適さないように見えるが堀の傾斜は急勾配で城の内側には土居(土手)があるため堀底から3m以上の高低差があり、更に土居上に土塀が設けられていたので十分な防御機能を有していたと思われる。 |
|
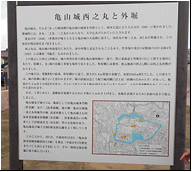 |
 |
⑱西町問屋場跡・・・三重県亀山市西町
問屋場とは、江戸時代の各宿において、主に公用の荷物などを運ぶ伝馬人足の継ぎ立てのほか、一般の商品物資などの継ぎ立て業務をおこなう施設で、町の重役である宿役人がこれを受け持った。
東町と西町からなる亀山宿 では、代々宿役人であった東町の樋口家(本陣の家)と西町の若林家(家業は米問屋)が、十日あるいは20日程の期間で定期的の交替しながら宿継ぎの問屋業務を担当していた。 |
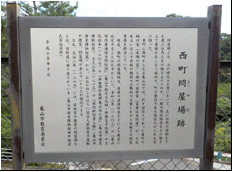 |
⑲亀山城多聞櫓(やぐら)・・・三重県亀山市本丸町
伊勢亀山城は、文永2年(1265年)に伊勢平氏の流れをくむ関実忠によって伊勢国鈴鹿郡若山に築城された。江戸時代においては、亀山城は伊勢亀山藩の藩主の居城となった。江戸時代初頭には丹波亀山城の天守を解体するよう命じられた堀尾忠晴の間違いによって、天守を取り壊されている。寛永13年(1636年)、城主となった本多俊次の手で大改修が行われ、天守を失った天守台に多聞櫓が築造された。 |
 |
左奥に見えるのが亀山城多聞櫓
右に分岐したカラー舗装の道が旧東海道 |
⑳遍照寺
・・・三重県亀山市西町524
街道から鐘楼門をくぐると急な坂で、坂の下に本堂があるため「頭で鐘撞く遍照寺」といわれた古刹。本堂は、亀山藩主在国中の居館であるとともに、亀山藩政務を執る政庁でもあった旧亀山城二之丸御殿の玄関と式台の一部を移築してできたもの。 |
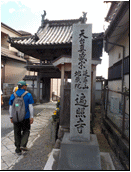 |
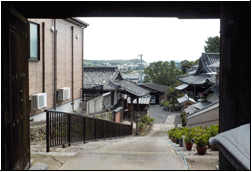 |
21.江戸口門跡・・・三重県亀山市本町2丁目1
延宝元年(1673)、亀山城主板倉重常によって築かれた。西側の区画には番所がおかれ、通行人の監視や警固にあたっていた。江戸口門は東海道の番所としてではなく、城下西端の京口門とともに、亀山城惣構の城門と位置づけることができよう。現在は往時の状況を示す遺構は存在しないが、地形や地割、ほぼ直角に屈曲した街路にその名残をとどめている |
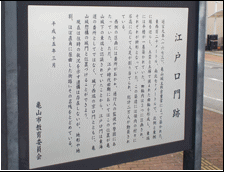 |
22. 能褒野(のぼの)神社・能褒野王塚古墳・・・三重県亀山市田村町1409
古墳は全長90m、後円の径54m、高さ9m。
東征の帰路に日本武尊(やまとたける)が伊勢能褒野で亡くなったという記紀の記述に基づき明治12年に内務省によって日本武尊能褒野御墓と定められた。現在も日本武尊の墓として宮内庁が管理している。 |
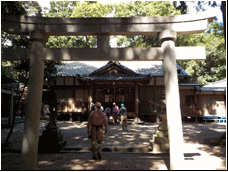 |
 |
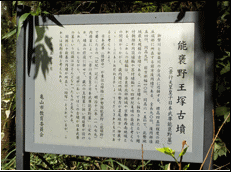 |
23. 和田一里塚・・・三重県亀山市和田町1488-154
慶長9年(1604)に幕府の命により亀山城主の関一政が築造した。江戸から104里(京都から21里) |
 |
24. 中冨田一里塚
・・・三重県鈴鹿市庄野町1622
和田一里塚と同じく慶長9年(1604)に築造された。江戸から103里(京都から22里) |
 |
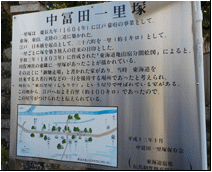 |
25. 女人堤防碑
・・・鈴鹿市汲川原町254
この辺りは鈴鹿川と交流安楽川の合流点で、たびたび氾濫して被害が大きく、文政12年頃、神戸藩に何度も修築を申し出たが許されず、女性たちが禁を犯し打ち首を覚悟で堤防を補強した。
女性たちは一旦は処刑場に送られましたが赦免の早馬で救われたといわれる。 |
 |
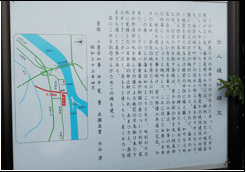 |
2017.9.18.16:30
今回はその後庄野宿のちょっと手前(1号線とのクロス点)でウォーキング終了。
次回はここからスタート。
|
|
|