|
|
| 庄野宿(第45番) ~ 四日市宿(第43番) |
2017.10.14 9:45
①三重県鈴鹿市庄野町
先回はここが終点
今回はここからスタート
|
 |
②庄野宿入口
庄野宿は江戸から102里余り、東海道四十五次にあたり、幕府の直轄領だった。他宿に比べて宿立ては遅く、寛永元年(1623年)と言われている。
この宿は「草分け三十六戸、宿立て七十戸」と言われ、鈴鹿川東の古庄野から移った人たちを合わせ七十戸で宿立てをし、南北八丁で宿入口の加茂町中町上町からなる。 |
 |
 |
③川俣神社・・・三重県鈴鹿市庄野町12
亀山宿から庄野宿の間に三社ある川俣神社の一つ。
もと貴船社と称し、元禄16年に川東の門田より川西古屋敷(現在の字田中)に移つた。
明治40年11月、庄野村の川俣神社他七社、汲川原村の三社を庄野村大国神社へ合祀し、村社川俣神社と単称した。
境内には幹周り5m、樹高11mのスタジイの神木があり県指定天然記念物になっている。 |
 |
 |
 |
④高札場跡・・・三重県鈴鹿市庄野町19
幕府の御法度、掟をはじめ、人馬賃銭の規定、人倫の奨励等を記載、掲示していた。
写真右は近くの庄野宿資料館にある江戸初期から使われていた高札 |
 |
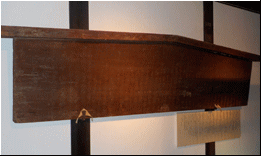 |
⑤庄野宿本陣跡・・・三重県鈴鹿市庄野町19
本陣は代々沢田家が勤めた。間口14間1尺、奥行21間1尺、面積229坪7合、畳数197畳半、板間44畳半だったと伝わっている。 |
 |
⑥庄野宿資料館・・・三重県鈴鹿市庄野町21-8
江戸時代は油屋であった旧小林家の建物。庄野宿に残る宿場町関連資料の活用を図り、併せて旧小林家の保存を進めるため主屋の一部を創建当時の姿に復元し、平成10年に開館。
前述の江戸初期の高札もここに展示されている。
歌川広重の東海道五十三次の浮世絵"庄野「白雨」"はここ庄野宿を描いたもの。ただし庄野宿近辺の東海道はほとんどが平地であり急な坂はほとんど無いため、この絵はかなり誇張されたもの、または想像で描かれたものでは・・との説も |
 |
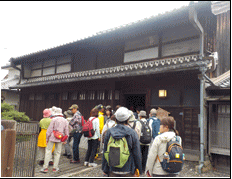 |
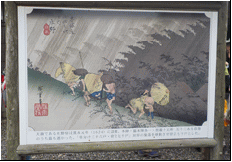 |
⑦石薬師宿西の入口・・・三重県鈴鹿市上野町367
石薬師宿は、四日市と亀山の間が長すぎるために設けられた宿場である。そのため、宿場の設置は遅く、元和2年(1616年)であった。 |
 |
⑧石薬師の一里塚
・・・三重県鈴鹿市上野町367
江戸日本橋から102里の一里塚 |
 |
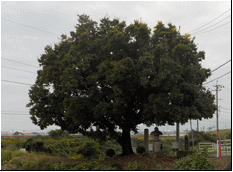 |
⑨御曹子社
・・・三重県鈴鹿市石薬師町40
源頼朝の弟で蒲の冠者といわれた源範頼を祀った神社。範頼は武道、学問に優れていたので、それらの願望成就の神様と言われ、昔は弓矢を奉納し、文武の向上を祈願する慣わしがあった。
境内には範頼所縁の「石薬師の蒲桜」がある。 |
 |
 |
⑩石薬師の蒲桜・・・三重県鈴鹿市石薬師町40(御曹子社境内)
寿永(1182~1184)の頃、蒲冠者源範頼が平家追討のために西に向かう途中、石薬師寺に戦勝を祈り、鞭にしていた桜の枝を地面に逆さに挿したのが芽を出してこの桜になったと言われている。 |
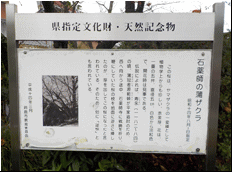 |
 |
 |
⑪石薬師寺・・・三重県鈴鹿市石薬師町1番地
弘仁3年(812年)空海(弘法大師)が、巨石に薬師如来を刻み開眼法要を行い、人々の信仰を集めたことにより、嵯峨天皇(在位809年 – 823年)は勅願寺とし、荘厳な寺院を建立し、名を高富山西福寺瑠璃光院と称していた。
元和 (日本)2年(1616年)に、東海道五十三次の宿場 石薬師宿にちなみ、高富山瑠璃光院石薬師寺と改称し、今日に至っている。
写真右下は歌川広重の東海道五十三次の浮世絵「石薬師」。
木立の合間に見えるのは石薬師寺。背景に山々は鈴鹿山脈だと思われる。 |
 |
 |
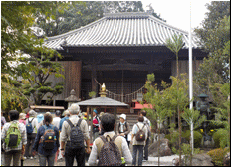 |
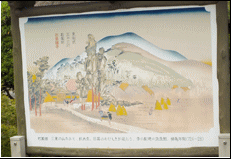 |
⑫小沢本陣跡・・・鈴鹿市石薬師町1614
代々小沢家が本陣を勤めた。
浅野内匠頭、岡越前守、徳川家光等々、宿帳には馴染みの名前が登場する。千姫(家康の孫)が姫路城に行く際に宿泊したこともある。 |
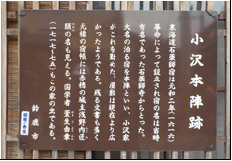 |
⑬大木神社
・・・三重県鈴鹿市石薬師町2139
この神社は式内社という由緒ある神社。式内社とは延喜年間(901~922年)の時代に既に存在していた神社のことであり正式には「延喜式内社」という。
大木神社には天照大神ほか九柱の神様が祀りされている。 |
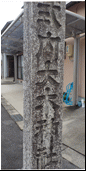 |
 |
⑭采女一里塚跡
・・・三重県四日市市釆女町
江戸日本橋から101里の一里塚 |
 |
⑮杖衝坂(つえつきざか)と血塚社(ちづかしゃ)
三重県四日市市釆女町3464
杖衝坂は東海道の中でも急な坂で杖突坂とも書く。日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の帰途、疲れきった身体でこの急な坂を杖をつきながら登った。この時「吾が足は三重の勾がりの如くして、はなはだ疲れたり(私の足は三重に折れ曲がったようになって、非常に疲れた)」と言ったという。
後に「杖衝坂」と呼ばれ、旧東海道でも有名な急坂として知られるようになった。そしてこの近辺は日本武尊の言葉から「三重郡」と呼ばれることとなり、現在の三重県の由来となった。
また坂の上には日本武尊の足の出血を封じたといわれる血塚の祠がある。
|
 |
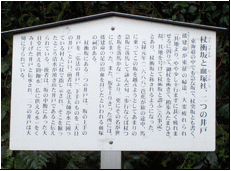 |
 |
 |
⑯小許曽(おごそ)神社・・・三重県四日市市小古曽 2-28-2
平安時代、後醍醐天皇の延喜5年(905)に編纂された神名帳にも小許曽神社の名が記載されている。このように小許曽神社は格式のある延喜式内社として千百有余年の歴史を有しており古くから地元民に崇拝されている。
|
 |
 |
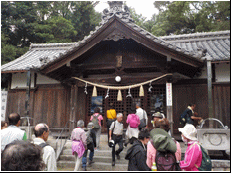 |
⑰日永追分・・・三重県四日市市追分3丁目1
東海道から伊勢道が分岐する追分。近辺には旅籠や茶屋が並び、古くから伊勢参りの旅人が往来し、賑わった。今も伊勢神宮の遥拝鳥居が立ち、寛永2年(1849)建立の追分道標が残る。
またここに設けられた手水所にこんこんと落ちる水は「追分鳥居の水」と呼ばれて多くの人がその水を求めて訪れる。 |
 |
 |
 |
⑱東海道名残りの一本松・・・三重県四日市市日永5丁目10−4
昔この辺りから泊の集落までは、東海道 の両側に低い土手が築かれ、その上に、大きな松の木が並んで植えられていた。
その間には、家は一軒もなく、縄手と呼んでいた。この松は、その縄手に植えられていたものが残った貴重なものであり、往時の東海道や日永の歴史の一端を今に伝えている。
縄手の道幅は、土手も入れて約五間(9メートル)であった。松の木が無くなった現在の道幅とほぼ一致する。因みに、旧東海道の道幅は三間(約5.5メートル)で、現在も変わっていない。 |
 |
⑲日永一里塚跡
・・・三重県四日市市日永5丁目3−1
江戸日本橋からちょうど百里の一里塚 |
 |
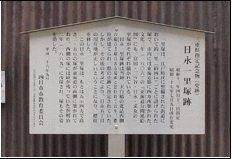 |
⑳日永神社
・・・三重県四日市市日永4丁目5
日永神社は伊勢の神宮で祀られる天照大御神を祀っている。古くは南神明社と呼ばれていた。江戸時代には神戸藩主本多家からの崇敬も篤く、また東海道に面して多くの人々に参拝された。 |
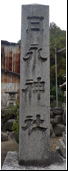 |
 |
追分道標
日永神社の境内にある道標。元は追分の神宮遥拝鳥居の場所にあったもので、明暦2年(1656)に僧侶によって立てられた東海道最古の道標である。 |
 |
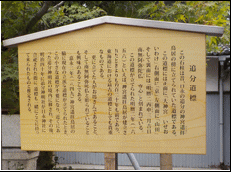 |
21. 興正寺
・・三重県四日市市日永2-9-6
当山は浄土真宗高田派で、創建は貞観6年(864)と言われている。もとは天台宗だったが文暦元年(1234)親鸞聖人が立ち寄られた時に浄土真宗に改宗した。 |
 |
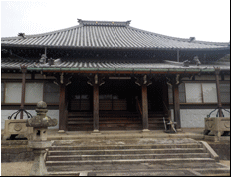 |
22. 大宮神明社
・・・三重県四日市市日永1丁目12
永宮さんとも呼ばれ主祭神として天照大御神を祀る。垂仁天皇の時代に倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大御神を伊勢の地にお遷しする際にこのお社に一時お留まりになったという伝えもある。 |
 |
 |
23. 諏訪神社
三重県四日市市諏訪栄町22-38
鎌倉時代初期の建仁2年(1202)に、信州の諏訪大社の御分霊をこの地に勧請し創祀されたと伝わっている。
17:00
今回のウォークはここまで。
次回はここからスタート。 |
 |
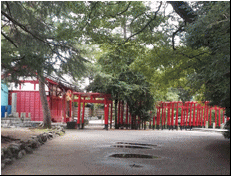 |
|
|