|
|
| 四日市宿(第43番) ~ 桑名宿(第42番) |
2017.11.11 8:50
①諏訪神社 ・・・三重県四日市市諏訪栄町22-38
鎌倉時代初期の建仁2年(1202)に、信州の諏訪大社の御分霊をこの地に勧請し創祀されたと伝わっている。建御名方命(タケミナカタノミコト)と八重事代主命(ヤエコトシロヌシノミコト)が主祭神。
今回はここからスタート |
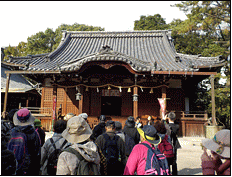
|
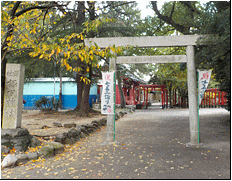 |
②四日市道標
文化七年(1810)建立の道標。
「すぐ江戸道」のすぐは「もうすぐ」ではなく「まっすぐ」の意
|
 |
③笹井屋
三重県四日市市北町5-13
天文19年(1550)頃から続くお菓子処。初代彦兵衛氏がここ勢州日永の里に因んで創った銘菓「なが餅」はさらりとした小豆餡を白い搗き餅でくるんで平たく長くのばし、両面を焼香ばしく焼き上げたもの。永い年月の間、多くの人々に愛された素朴な味わい。 |
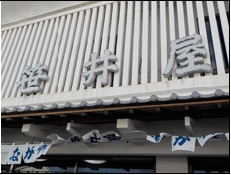 |
④三滝橋
・・・三重県四日市市川原町
四日市市街の中央部を東流する三滝川にかかる橋。江戸時代には東海道を往来する人馬で賑わう土橋だった。
歌川広重が四日市宿を描いたのがこの三滝橋。 |
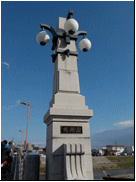 |
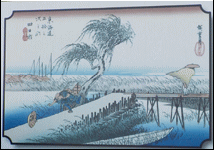 |
⑤四日市宿の旧東海道 |
 |
⑥三ツ谷一里塚跡・・・三重県四日市市三ツ谷町
江戸日本橋から99番目の一里塚 |
 |
⑦志氐(シデ)神社・・・三重県四日市市大宮町14-6
当社は垂仁天皇の御代の鎮座にて高野御前と称へ奉られ「志氐」の名は天武天皇が皇子であられた頃壬申の乱を避け吉野から鈴鹿を経て桑名への途次跡太川の辺で伊勢の神宮を望拝されたことに起因しています。シデとは御幣のことで天皇が四方に幣を班ち祓いの神気吹戸主神をお祀りし禊ぎ祓いをなされた御跡を斎い奉れる神社であります
(神社の社頭掲示板より・・解釈が難しい) |
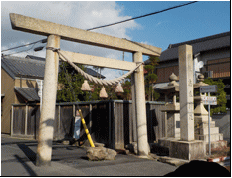 |
⑧かわらずの松
この松は、樹齢約二百年で江戸時代より東海道 を行き交う旅人を見守ってきた。
戦前は、この付近の東海道沿いには多くの松が植えられていて、松並木の風景が見られたが、戦後経済の発展に伴い道路の拡幅と松くい虫の被害を受けて東海道の松並木が姿を消した。現在四日市市では往時の松が残っているのは、ここ羽津地区と日永地区の二本だけになった。
昔からこの付近の町名が川原須(かわらず)と言われていたので、ここ羽津地区の松を昔の町名から「かわらずの松」とした。 |
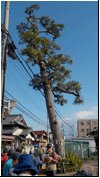 |
 |
⑨富田一里塚跡・・・四日市市富田西町
江戸日本橋から98番目の一里塚 |
 |
⑩長明寺 ・・・三重県四日市市蒔田2-13-29
朝明山長明寺は東海道沿いにある浄土真宗本願寺派のお寺。
中世には蒔田城がここにあった。文治年間(1185-1190)の伊勢平氏残党の反乱の時、蒔田相模守宗勝が居住していた。寺の周りには現在も城の堀が残っている。 |
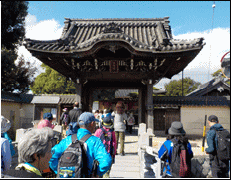 |
 |
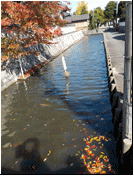 |
⑪松寺の立場跡
立場とは宿場と宿場の間にあって、旅人が休憩する茶店などが集まっている所であり、四日市宿と桑名宿の間には5箇所の立場があった。 |
 |
⑫朝明橋・・・三重県三重郡川越町高松
「朝明」の名は『和名抄』伊勢国の項に「朝明郡」として見える。東征中の日本武尊が当地で夜明けを迎え、朝明川の水で口をすすいだことから川の名が付いた、とする伝承もある。 |
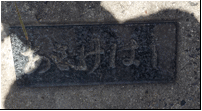 |
 |
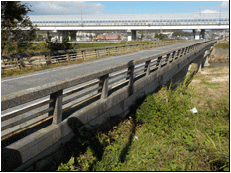 |
⑬多賀大社常夜燈・・・三重郡朝日町柿
朝明川堤にある常夜灯は弘化3(1846)年に建立されたもの。台座には多賀大社と刻まれている。
東海道より多賀大社へ参詣するための間道に入る目標となった。 |
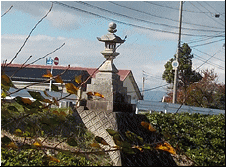 |
⑭浄泉坊
・・・三重郡朝日町大字小向955
浄土真宗本願寺派。山号を小向山という。慶長八年(1603)に伊勢慶昭が小向にあった正治寺を再興し、小向山浄泉坊と改称したことにはじまる。寛永十五年(1638)に西本願寺より寺号の交渉を許された。参勤交代の大名は駕籠を降りて黙礼したと伝わる寺。 |
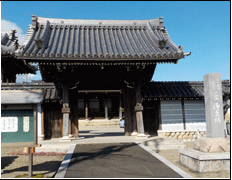 |
 |
⑮縄生一里塚・・・三重県三重郡朝日町縄生
江戸日本橋から97番目の一里塚 |
 |
⑯伊勢両宮常夜燈・・・桑名市安永452番地1
文政元年(1818)に東海道 のみちしるべとして、また伊勢神宮 への祈願を兼ねて桑名・岐阜の材木商によって寄進されたものである。石工は桑名の根来(根来〉市蔵(いちぞう)とある。
安永は、町屋川(員弁川)の舟運や東海道筋の通行客を相手とする茶店などで賑わった場所であり、この常夜燈はその頃をしのばせる遺物である。 |
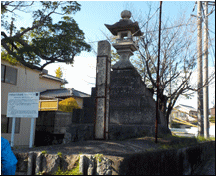 |
⑰矢田立場跡・・・桑名市矢田
江戸時代の矢田町は、東海道の立場だった。『久波奈名所図会』には、「此立場は、食物自由にして、河海の魚鱗・山野の蔬菜四時無きなし」とある。福江町へ曲がる角には火の見櫓があった(現在の火の見櫓は平成三年に再建したもの)。西矢田町には現在でも、馬を繋ぎとめた鉄環のある家や連子格子のある家も見られる。 |
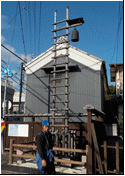 |
⑱天武天皇社
・・・桑名市東鍋屋町89番地
壬申の乱(672年)に大海人皇子(のちの天武天皇)が桑名郡家に駐泊されたことにちなみ、のちに創建された。元は新屋敷付近にあったが、江戸時代に鍋屋町に移った。 |
 |
 |
⑲十念寺 ・・・桑名市伝馬町53番地
ここには桑名藩士森陳明の墓所がある。
森陳明(つらあき)は、松平定敬侯京都所司代に在職中、公用人として 公を助け、勤王佐幕のことに心を砕き、戊辰戦争当時は、公に従って函館に立て籠ったが、敗れてのち、朝廷は桑名藩より反逆の主謀者を出だせと命じた時、陳明進んで全藩に代わって出頭し、明治2年11月13日東京深川藩邸で死に就いた。 |
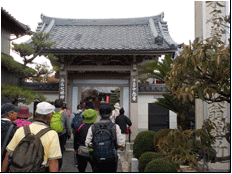 |
 |
⑳桑名宿の旧東海道 |
 |
21.桑名城城壁・・・桑名市三之丸
川口町揖斐川に面する川口樋門より南大手橋に至る堀川東岸(三之丸地内)の城壁延約500m、桑名城跡は県史跡地ではあるが、これに含まれていた揖斐川右岸の城壁は伊勢湾台風後の復旧工事(別にこの城壁は少しの被害もなかったのであるが)で凡てなくなり、残る城壁はこの500mとなり上述の史跡区域には含まれていないので将来のために指定保存となった。
積み石の状態は乱積で野面はぎ、打込はぎの二方法によっている。 |
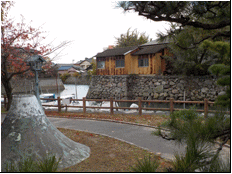 |
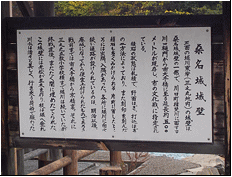 |
22.春日神社の青銅の鳥居・・・桑名市本町46番地
鳥居が建立されたのは、慶長7年(1602)12月13日、時の城主 本多忠勝公の寄進であるが、木造であって、これは51年後(承応2年6月5日)の大風で倒壊してしまった。
その後13年たって、藩主松平定重侯が日本随一の青銅鳥居の創建を企画し、神社修理料の積立金を基本に(慶長金250両と云う)鋳物師辻内善右衛門尉藤原種次に命じた。種次はこの大事業に精根を注ぎ、家産を傾けて見事に成就せしめたのがこの鳥居である。寛文7年(1667)完成。 |
 |
23.七里の渡し跡・・・桑名市東船馬町
元和2年(1616年)、東海道における唯一の海上路で「七里の渡し」が始まった。七里の渡しは、満潮時に陸地沿い航路が約7里(27㎞)で、干潮時に沖廻り航路が約10里(39㎞)であった。渡し船によって移動し、所要時間は約4時間であった。
ここは伊勢国東の入口にあたるため天明年間に「一の鳥居」が建てられた。
渡しの西側には舟番所、高札場、脇本陣駿河屋、大塚本陣が、南側には舟会所、人馬問屋や丹波本陣があり東海道を行き交う人々で賑わい、桑名宿の中心として栄えた。 |
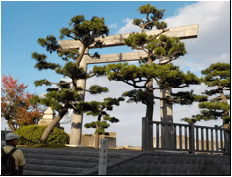 |
 |
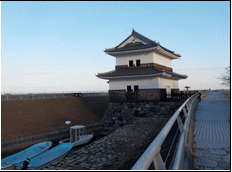 |
'17.11.11 15:50
今回はここまで。ここからは海路のため次回のウォークは向岸の宮の渡し跡からのスタートとなる。 |
|
|