|
|
| 季節によせて vol.238 平成28年3月25日 |
| 涅槃会や燭消える時煙あげ 晶 |
| お釈迦様はむかしむかし、沙羅双樹の間で右脇を下にして、両足を上下に重ね、北枕に横になって入滅されたそうだ。そして、その周りには天界から馳せ参じた生母摩耶夫人や弟子や諸菩薩、在俗の人々や鳥獣が取り囲み嘆き悲しんだそうで、その様子が事細かく描かれている画像が涅槃図。法隆寺や金剛峰寺が有名だが身近なお寺でも陰暦2月15日(今では3月15日)涅槃会(または常楽会)で拝見できる。 |
 |
| 季節によせて vol.237 平成28年3月18日 |
| 茎立ちや時無しになる寺の鐘 晶 |
| 時代劇などで、明け六つ(明けの鐘)、暮れ六つ(日暮れの鐘)という言葉を聞くように、江戸時代は寺の鐘が時報であったため、各戸から鐘役銭を取り鐘を撞く「時の鐘役」という役もあったようだ。現代では、むやみに撞かれては迷惑と撞木を取り外しているという話もあるが、四国のある遍路寺では鐘を撞く作法が鐘撞き堂に張ってあって誰でもご自由にとあった。 |
 |
| 季節によせて vol.236 平成28年3月11日 |
| すべすべの毛並に日ざし猫柳 晶 |
| 日本にある柳は凡そ90種ほど。その中の水辺に群生する「川柳(かわやなぎ)」または、「えのころ柳」が猫柳の正式な名前。高さ2メートルほどで、街路樹などにもよく見られる。雌雄異株で早春、冬芽の鱗片が取れると銀色の花芽が広がる。この花穂が猫のしっぽのようであることから猫柳という名がつく。奈良時代に中国から入ってきた渡来植物。 |
 |
| 季節によせて vol.235 平成28年3月4日 |
| 摘草やひしめくものを踏みしめて 晶 |
| 何年か前、上海の子を土筆(つくし)摘みに連れて行ったとき、日本人は草を食べるのかと大いに驚かれた。外国には野草を食べる習慣がないのかとこちらも新鮮な驚きだったが、春の野草の苦みは体の毒素を排出する効果があるとも聞くし、蕗の薹(ふきのとう)に始まる芹(せり)、土筆、蓬(よもぎ)を摘みに出ることは私の毎年の楽しみでもある。まだ冷たさの残る土手の風の中、でかかった頭を踏まないように歩を運びながら土筆を探す。 |
 |
| 季節によせて vol.234 平成28年2月22日 |
| 燃えさしを集めて燃やし二月尽 晶 |
| まだ庭や畑で物を燃やしても条例違反ではなかった頃、農家の人たちは畑のものは勿論、燃やせるものは畑へ持ち込んで燃やしていたように思う。木の株や太い枝など燃えにくいような物も何度か火を潜っているうちに燃えて灰になる。早春、少し焦げあとの見える土が耕される時を待ち構えているようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.233 平成28年2月15日 |
| 兄弟子と連れ立ち二月礼者かな 晶 |
二月礼者(にがつれいじゃ)とは正月に年始回りをできなかった人が、二月一日に回礼に歩くことで、正月多忙な人がこの日を回礼にあてたと言われている。
正月に多忙と言えば芝居や歌舞音曲に携(たずさ)わる人か。昼夜二部の公演のあいまに稽古も欠かせない弟弟子にとっては年始回りどころではないだろう。今日は休みという日に兄弟子に伴われて御贔屓筋(ごひいきすじ)にあいさつ回りをするのも修行の一つなのだろう。 |
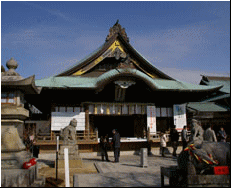 |
| 季節によせて vol.232 平成28年2月8日 |
| 羽の触れあはぬやう詰め鶯餅 晶 |
「街の雨鶯餅(うぐいすもち)がもう出たか 富安風生」 和菓子屋の窓ガラスに鶯餅ありますという張り紙を見るたび、この句を思い出す。和菓子には一年中あるものもあるが、ふさわしい季節にならなければ店頭に並ばない季節限定のものがある。
今年も鶯餅の季節になったかと時の移ろいを感じたり、和菓子職人さんの新しい趣向や見立てに思いを巡らすのも楽しい。鶯餅は、餡(あん)をくるんだ餅の両端をとがらせて青黄粉をまぶし、鶯を思わせる早春らしい和菓子。 |
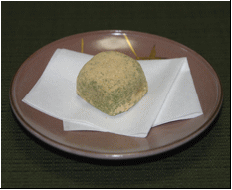 |
| 季節によせて vol.231 平成28年2月1日 |
| 端すこし浮き上がらせて残る雪 晶 |
今年は暖かい冬と喜んでいたのに、このところの寒気団の南下で、当地も久々の雪景色。スノーブーツを穿いて雪掻きをするつもりで庭に出たのに、いつのまにか雪達磨作りになって、枯芝や土まみれながら、大きな雪達磨を四つも作ってしまった。
バーベキュー用の堅炭で顔を作り、バケツの帽子を被せて、なかなかの面構えにしあがったと喜んでいたのだが、日差しには勝てなかったようで、夕方を待たずに堅炭の目は垂れ、空を仰ぐように雪達磨たちは傾いていた。 |
 |
| 季節によせて vol.230 平成28年1月25日 |
| 日に力戻りはじめて冬木の芽 晶 |
| 暖冬の影響で、我が家の椿は春を待たずに咲いてしまったが、夏から秋にかけて作られた芽は鱗片葉や密生した毛で寒気や雪などから守られて春に芽吹く。このような芽を冬芽(ふゆめ・とうが)、冬木の芽と呼ぶ。もちろん常緑樹にもあるが葉を落しきった枯木状の落葉樹の方が目を引く。先の尖ったものや丸いもの、中には顔のように見える芽もあるので観察すると面白い。 |
 |
| 季節によせて vol.229 平成28年1月18日 |
| 蠟梅や蝶のかたちの飴細工 晶 |
| 葉を落した枝の小さな蕾が次第に膨らみ、正月を迎える頃には蘭に似た良い香りを放つようになる。江戸時代初め、後水尾帝の時代に朝鮮より渡ってきた中国原産の花で、南京梅、唐梅ともいうが、梅の仲間ではない。蝋細工のような光沢のある半透明の花で芯まで黄色い種類を素心蠟梅(そしんろうばい)という。 |
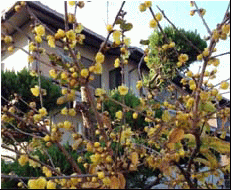 |
| 季節によせて vol.228 平成28年1月11日 |
| 日の入りも日の出も牡蠣の筏より 晶 |
| 今年の牡蠣は例年に比べて小ぶりで出荷数も少ないらしい。そういえば、牡蠣の好きな知り合いが今年は何軒電話しても牡蠣食べ放題コースがないと嘆いていた。養殖なのだからどこでも同じだろうと言う向きもあるようだが、やはり自然豊かな山に源を発する川が流れ込んでいる海で育つ牡蠣の方が味が良いようだ。養殖業者さんによると牡蠣の生育年数によって必要な栄養が違うので、湾の中で筏を移動させて育てるのだそうだ。 |
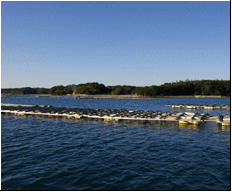 |
| 季節によせて vol.227 平成28年1月4日 |
| 手鏡のくもりぬぐひて三日かな 晶 |
| 早々と冬用タイヤに履き替えていた夫には物足りないかもしれないが、年末年始の暖かさは何ともありがたかった。おかげで大掃除も、正月の準備も例年より仕事が捗った気がする。三が日が過ぎ、インターへ続く家の前の道路が込み始めた。勤めていた頃は明日から仕事と思うと少し憂鬱にもなったが、新しい一年をまた頑張ろうという気持ちも湧いてきた。鞄やポーチに忍ばせて、ささっと身だしなみを確認する手鏡。くもりを拭って心も晴れやかに出勤したいものだ。ちなみに鏡は古くは銅や鉄などを磨いて作ったが、現在はガラス板の裏面に水銀を塗って作られるようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.226 平成27年12月25日 |
| 返り花咲けば心のよりどころ 晶 |
帰り花とも書く。暖かな日差しに誘われるように春に咲く草木が季節外れの花をつけることをいう。主に桜だがたんぽぽやつつじ、雪柳なども小さな花をつける。ただでさえ、花の少ない季節、葉が落ちた枝に小さな花を見つけた時は「おっ!」と思わず声が出る。「狂咲き」という傍題もあるが、それではせっかく咲いてくれた花に申し訳ない。自然からの贈り物と思うと今日一日が楽しくなる。
芭蕉「凩に匂ひやつけし帰花」
虚子「日に消えて又現れぬ帰り花」
狩行「人の世に花を絶やさず返り花」 |
 |
| 季節によせて vol.225 平成27年12月21日 |
| 思はざる出方や鳰も賽の目も 晶 |
「鳰」、この字を(かいつぶり)(にお)と読むと知ったのは俳句を始めてから。池や湖などでよく見かけるが、あまり人のそばには来ない。見事に逆立ちして水に潜り、たいていはこちらの予想とは大きく外れた場所に顔を出す。小さい鳥なのに胸いっぱい空気を吸い込むのか息が長い。浮いてくるまで息を止めていようと目を白黒させて待っていても、なかなか浮いて来ないこともある。かと思うと、とっくにあらぬ方に浮き出ていることもある。何にしても予想の付かないことは面白い。
*賽(サイ)の目 |
 |
| 季節によせて vol.224 平成27年12月14日 |
| はやばやと討ち入りの日の暮れはじむ 晶 |
| 元禄15年12月14日と言えば、元赤穂藩家老大石良雄をはじめ47志が江戸本所の吉良邸に討ちいった日。毎年、どこかのテレビ局でお芝居や解説があるので、何となくこれを見なければ歳末の気分にならないと言う人さえいる。義士の墓所である泉岳寺や旧赤穂城内の大石神社では14日から15日にかけて様々な行事があるそうだが、愛知県吉良町では今も上野介は名君と慕う人もいると聞く。 |
 |
| 季節によせて vol.223 平成27年12月7日 |
| 市松に敷いて鮮やか畳替 晶 |
| 帰省した際、玄関を開けると新しい畳の匂いがした。法事で兄弟が集まるからと兄嫁が気を使ってそれぞれの部屋の畳を替えてくれたのだ。二階にある和室の畳を一日に一部屋ずつ三日かかったそうだ。以前は畳屋さん一人で運んでいたそうだが、歳を取られてご夫婦での作業だったらしい。和室を作る家も減っているなか、畳屋さんの跡継ぎはあるのかと少々気になる。最近の家は、洋間の一隅に縁のない畳を市松に敷いて畳コーナーを作るというのも人気らしい。 |
 |
| 季節によせて vol.222 平成27年11月30日 |
| 踏ん張つて抜き差しならぬ蓮根掘り 晶 |
| 蓮根(はすね)と読むが、蓮根(れんこん)のこと。夏には美しい花を咲かせる蓮は泥田深くに長々と根を伸ばす。泥田に板を敷き、その上を通って蓮根を掘りに行く人を見た。板でも敷いておかないと、歩くだけで掘るまでに疲れてしまうんだそうだ。昨今は、水圧で泥を緩めたり、機械で掘ったりしているようだが、いずれにしても水や泥に浸かりながらの大変な作業。虚子「泥水の流れ込みつつ蓮根掘る」 狩行「蓮根掘モーゼの杖を摑み出す」 |
 |
| 季節によせて vol.221 平成27年11月22日 |
| 海よりも山の明るき初しぐれ 晶 |
| 珍しく良い天気が続くと思っていたら、明日から一気に寒くなるという予報だ。日差しがあれば日中は汗ばむ陽気だったが、ようやく、この時期らしい気温になるということか。時雨は冬のはじめに降る通り雨のことで、初時雨は、その年の冬の最初に降る時雨のこと。山はまだ紅葉が真っ盛りだが、時雨に出合えばやはり冬の到来を思わずにはいられない。芭蕉「初しぐれ猿も小蓑をほしげ也」 虚子「初時雨これより心定まりぬ」 |
 |
| 季節によせて vol.220 平成27年11月15日 |
| 落ち鮎の水の濁りとなりにけり 晶 |
| 聞いた話だから定かではないが、月のない夜や雨降りの続いたあとなどに、たくさん鮎は落ちるそうだ。自らの力で海をめざすのもなくはないだろうが、多くは暗闇や濁った流れに紛れながら何キロも先の海を目指すという。簗番という人たちは今にも落ちてきそうな濁りとなった川で「今日あたりは」などと言いながら更けるのを待つのであろう。 |
 |
| 季節によせて vol.219 平成27年11月8日 |
| 使はざる部屋にも予鈴夜学校 晶 |
| 中学はやや遠くにあったが、小学校と高校は走れば五分とかからないところに住んでいた。昔のことだから、校内放送と言っても運動場にも拡声器があって近隣の民家にも放送内容が丸聞こえであった。今なら必要な教室にだけ放送が流れるようにと気を使っていると思われるが、当時は日曜や祝日でもチャイムが鳴るという長閑さであった。 |
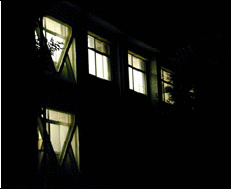 |
| 季節によせて vol.218 平成27年11月3日 |
| 玉突きの玉のごとくに小鳥来て 晶 |
| 春先、日本に渡ってくる鳥は繁殖のための相手を探したり縄張り宣言するための囀りが美しいと詠まれるが、秋に渡ってくる鳥は姿が美しいことを詠まれてきた。実際庭先に来る鶲類の羽の紋様などに目を奪われることも少なくない。写真の鳥は鳴門海峡を波すれすれに渡る小鳥の群れ。高く飛べばよいものを敢えて波しぶきのかかるようなところを飛ぶのはサシバやハヤブサに襲われない知恵である。 |
 |
| 季節によせて vol.217 平成27年10月24日 |
| 吸口の香も愛でて土瓶蒸し 晶 |
| 本来は魚や鶏肉、野菜や松茸を土瓶に入れて吸い物汁を加えて蒸したり煮たりするのが土瓶蒸しだが、国産の高価な松茸がおいそれと手に入るわけもない。そこで、我が家では長らくしめじで代用していたが、最近ではしめじより歯応えのあるエリンギも時折使っている。松茸の入らぬ少々寂しい土瓶蒸しだからこそ、吸口の香はかかせない。結び三つ葉や松葉にした柚子、酢橘をたっぷり絞って深まる秋を味わっている。 |
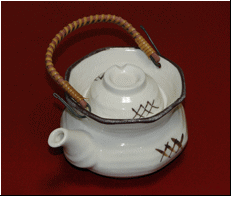 |
| 季節によせて vol.216 平成27年10月17日 |
| ほどほどの緩みもたせて萩括る 晶 |
| 草冠に秋と書いて「萩(はぎ)」。秋の七草の筆頭にあげられる萩は「万葉集」では、最も多く詠まれている花の王者であったようだ。現代でも、寺や神社、個人のお宅で見事に仕立てられた萩があるが、どれも大木というより立派な大株。春先、根元から新しい芽が出て、枝がある高さまで伸びると先端がほどよく枝垂れる。薄紫や白の花が風に吹かれているさまはなんとも優美である。 |
 |
| 季節によせて vol.215 平成27年10月10日 |
| 揺れだしてをさまりつかずゑのころ草 晶 |
| 狗尾草(ゑのころぐさ)は花穂が子犬の尾を思わせるところからつけられた名前だが、この花穂で猫をじゃれさせて遊ぶことから、猫じゃらしとも呼ばれている。日当たりのよい荒れ地や道端で風に吹かれて機嫌よく揺れているさまは狗尾草(ゑのころぐさ)自体がじゃれ合っているようでもある。どこでも見かける秋の植物なので日本古来のものかと思いきや、縄文時代前半以後、アワ作とともにアワの雑草として日本に入ってきたもののようだ。 |
 |
|
|