|
|
| 季節によせて vol.214 平成25年9月7日 |
| 翅よりも透きとほる声かなかなかな 晶 |
庭にまいた打ち水がかえって蒸し暑さを招くような暑さからもようやく解放され、朝夕どこからともなく蜩(ひぐらし)の声が聞こえてくるようになった。ほぼ空洞の腹部をふくらませオスは切ないまでによく通る声で鳴く。日を暮れさせるように夕方に鳴くのでいうので蜩と呼ばれるようになったそうだ。日ごとに早まる秋の夕暮れも蜩のせいかもしれない。
*翅:はね |
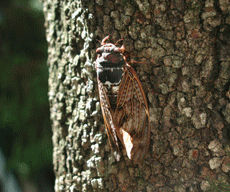 |
| 季節によせて vol.213 平成25年8月31日 |
| 蘂の先までも染まりて酔芙蓉 晶 |
| 漢文にはまったく興味がなかったのに、なぜか、楊貴妃の顔が芙蓉の花のようで、眉が柳のようだという(白居易の長恨歌)くだりは記憶にある。7月から9月にかけて、中国原産のこの花は大人の手のひらよりも大きな一日花を咲かせる。園芸種も多く、八重の白花で午後から酔ったような桃色になるものが酔芙蓉といわれている。なるほど、楊貴妃が例えられるような艶な花のようだ。
*蘂:しべ |
 |
| 季節によせて vol.212 平成25年8月24日 |
| ふるさとの空の深さよ盆の月 晶 |
| 日中はうだるような暑さが続いているが、さすがに日が落ちる頃になると、ほてりが残る草叢からも虫の声が聞こえるようになった。人間よりも昆虫の方が敏感に季節の移り変わりを捉えているようだ。盆の月とは、旧暦7月15日の盂蘭盆の夜の月ことで、今年は一晩中きれいな月を見ることができた。来年は母の新盆、できれば今年のような月を見上げたい。 |
 |
| 季節によせて vol.211 平成25年6月22日 |
| 亀の子の手足残して首すくめ 晶 |
| ハリエットという亀が心臓発作で175歳で死亡したという記事を読んだことがあるが、やはり亀は長生きする動物のようだ。夜店で売られているミドリガメも初めは五百円玉ほどの大きさだが三十年も生きると甲羅もそれ相当の大きさになるそうだ。買っていく人がいるのだから長生きの亀の話題がもっとあって良いと思うのだが、なつかないのかかわいくないのかそれ以来亀のニュースを聞かない。 |
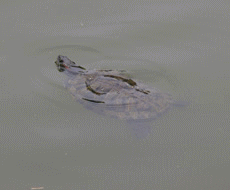 |
| 季節によせて vol.210 平成25年6月15日 |
| 時の日や抱へてあまる写真集 晶 |
| 母が言いだしてアルバムの整理をした。長く勤めていたので家族の写真の他に仕事を通しての写真も多く、残すものを選ぶのに随分迷ったようだが、父と出会った独身時代、父と母の結婚、子供の誕生、家族旅行‥‥、母の八十五年が一冊のアルバムにおさまってしまった。一枚一枚の写真につながる思い出をしっかり聞いておこうと思う。 |
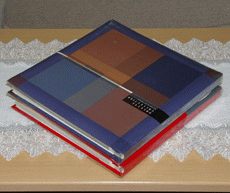 |
| 季節によせて vol.209 平成25年6月8日 |
| 羽繕ふこともつぱらに通し鴨 晶 |
| 鴨の仲間の大部分は渡りをし、春先に群れをつくって北へ帰っていくが、夏鴨と言われるカルガモにはその習性がなく水辺の草地に棲みつき、初夏、巣をつくり子育てをする。何羽ものかわいい雛を連れて道路など横切っているのもこの鴨。通し鴨はそういした鴨ではなく、夏になっても北へ帰らないで残っている真鴨のこと。群れるでもなくどこかひそやかな印象さえ受ける。 |
 |
| 季節によせて vol.208 平成25年6月1日 |
| 卯の花やまだ糸切らぬ絞り染め 晶 |
| 卯の花の匂う垣根にという歌に登場する卯の花。初夏、粟粒のような蕾を付けたかと思うと五弁の真っ白い花を重なり合うように咲かせる。幹が中空なため空木(うつぎ)とも呼ばれている。ところで、大豆のしぼりかすが卯の花の色に似ていることから、おからのことを「卯の花」とも言う。酢でしめた魚や野菜の細切りなどを煎って調味したおからで和える卯の花和えもひと手間かけた家庭料理といえよう。 |
 |
| 季節によせて vol.207 平成25年5月25日 |
| 蔓薔薇の付け放題の蕾かな 晶 |
| 蔓薔薇は剪定次第で花付きが全く違う。棘に痛い思いをしながらも、冬場にきちんと剪定し枝を誘引し直しておくと、春には立派な花芽が付き蕾がどんどん上がってくる。この楽しみな時期に要注意なのがチュウレンバチとバラゾウムシ。新芽や蕾の陰に潜んで樹液を吸い萎れさせてしまう。日に何度か目を凝らすようにして虫を探すのだが、食害を防げずにいる。運よく、虫にとっては運悪くだが、見つけた時には容赦なく冥土へ送ることにしている。 |
 |
| 季節によせて vol.206 平成25年5月18日 |
| 麦秋や八丁味噌の樽干さる 晶 |
| お城から八丁のところに店を構えているから八丁味噌というのだと味噌屋の栞にあったが、天保年間の樽が残る味噌屋の敷地の中には味噌が付いたままの空の樽がごろごろ転がしてある。素人目には洗ってから干せばと思うのだが、樽の保存のためにはこの方がよいのだそうだ。近くの川から持ってきたと言う形の良い磧石を三角錐に積み上げ昔ながらの製法で三年寝かせて味噌の熟成を待つという。 |
 |
| 季節によせて vol.205 平成25年5月11日 |
| 夏近し影深くなるプラタナス 晶 |
| 四月の桜が咲く頃まではどこかゆったりのどかだった春も、桜蘂が降る頃になるといっきにページを捲ったように季節がすすむ。散歩で見かけるつつじや牡丹、溢れんばかりに咲き出した草花に足を止めて見とれているうちに、街路樹の欅やプラタナスも、いつしか柔らかな若葉におおわれていた。ついこのあいだまでは日向を探して歩いていたのに気が付けば影を選んで歩く季節になっている。 |
 |
| 季節によせて vol.204 平成25年5月4日 |
| 大株となりたる都忘れかな 晶 |
| 終の棲家をどこにするかと考えてか、花の好きな友人がご実家へ越していかれた。そのときトラックに載らない植物をみんなで記念に頂いた。我が家に来たのは鉢植えのジャカランダとギボウシと都忘れ。ジャカランダは申し訳ないことに枯れてしまったが、ギボウシと都忘れは株分けをするほどに大きくなった。土が変わると花の色が変わるという都忘れだが、友人の庭で咲いていた時と同じ色で今年も咲き始めた。 |
 |
| 季節によせて vol.203 平成25年4月27日 |
| 脈絡の元からなくて蜷の道 晶 |
| 蜷(にな)は細長い巻貝。淡水だけでなく海や磯、全国どこにでもいるが、俳句で詠まれるの川蜷が多いようだ。蛍の幼虫の餌といえば見たことが無くても名前を耳にしたことがある方もいらっしゃるのでは。しかし、春は川蜷の産卵期でもあるため動きが活発なため、田圃や川底の泥にくねくね這いまわった跡があればそれをたどると簡単に見つけることができる。這った跡がくっきりと道のように見えることから「蜷の道」と言う言葉が生まれたようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.202 平成25年4月20日 |
| のどけしや縄束ねるに輪を重ね 晶 |
| 物を測る道具がまだ十分ではなかった頃、人々は指や手の長さを基準にして物を作ったり仕事をしてきた。たとえば握(あく)とか束(つか)はこぶしを握った四つの指の幅のことで、この長さは約4寸、草履づくりに利用されていたようだ。また両手を左右にのばして広げた時の両手の端から端までを一尋(ひろ)、一尋の二割五分に相当する腕の約半分を肘(ひじ)といい、農家では縄の長さを測る基準にされていたらしい。体格も違うだろうに何とも大まかで長閑な図り方ではないか。 |
 |
| 季節によせて vol.201 平成25年4月13日 |
| 春愁や半透明に粥の膜 晶 |
| 健康だけが取り柄と思っていたら、最近は人並に胃もたれをするようになった。朝からきりきり痛む胃のためにお粥ならよいかもしれないと、何年ぶりかで行平(ゆきひら)に白米と多めの水を入れとろ火にかけた。一食か二食抜けばと思わないでもなかったがこんな時こそ胃を空っぽにしない方がよいのではと勝手に思い粥を炊いた。何年かぶりの湯気まで甘い粥を口にして束の間ではあるが胃の痛みも薄れたような気がした。 |
 |
|
|