|
|
| 季節によせて vol.333 平成30年3月31日 |
| 色褪せしドライフラワー万愚節 晶 |
| 草花を薬品などを使って乾燥させたものがドライフラワー。英語ではever lasting flower(乾燥花・永久花)と呼ばれる。ヨーロッパ北部で冬の室内装飾用として作られたのが始まりという。信州に住む義姉は毎年ラベンダーのドライフラワーを作って分けてくれる。贅沢に籠に入れて御手洗に置いてあるが一年もたつと色も香りも褪せてくる。永久花と言えど退色は免れないようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.332 平成30年3月24日 |
| 朝寝して若かりし父母に会ふ 晶 |
| あまり夢を見る方ではないので、亡くなった両親の夢を見ることはほとんどない。おまけに、叱るなら夢に出て来なくていいよなどと罰当たりなことを心の中で呟いたからなおさら夢に出て来てはくれない。昼間妹と子供の頃の話をしたからだろうか、掲句のような夢を見た。もちろん私も妹もまだ子供で、みんなでどこかに出かけるところだったようなのだが定かではない。起きるには早いと二度寝したため、一家がそろっている夢が見られた。ほんのつかの間のこと。 |
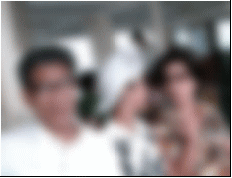 |
| 季節によせて vol.331 平成30年3月17日 |
| 青竹に潮の手応へ魞をさす 晶 |
| 魞(えり)は河川、湖沼などで用いられる定置漁具の一つ。魚の通りみちに竹簀を廻らしその先端の魞壺に魚を誘導する仕掛けで、「魞挿す」は魞を水中に設置すること。岸に近いところから順に青竹を挿し竹や葦の簀を張り付けていく。浜名湖は潮入り湖ゆえ潮が引いた時の作業。春浅い風の中、なかなかの力仕事と見た。大がかりなものは琵琶湖で見ることが出来る。 |
 |
| 季節によせて vol.330 平成30年3月10日 |
| 揚雲雀声にひかりをちりばめて 晶 |
| 雲雀(ひばり)は野山や畑、河原などに巣を作り地上を歩き回って餌を探す。羽の色は黄褐色で斑があり、頭には冠毛が見られる。繁殖期には縄張りを宣言するために雄はピーチュルピーチュルと囀りながら空高く舞い上がる。これを揚げ雲雀と呼ぶ。天心にも届くかと上りつめると鳴き止め一転して一直線に落下する。これが落雲雀。万葉時代の歌人大伴家持も「うらうらに照れる春日にひばりあがり心かなしもひとりし思へば」と雲雀の囀りの明るさを歌っている。 |
 |
| 季節によせて vol.329 平成30年3月3日 |
| 波うくるたびに寄り添ひ流し雛 晶 |
| 雛を川や海に流して穢れを祓う行事。三月三日のひな祭の夕方、祓に使った形代を流す風習の名残りともいわれる。例えば、鳥取の流し雛は藁で編んだ桟俵のなかに紙雛をのせる。所によっては白木の舟に本物のお雛様を乗せて流すこともあるようだ。舟に身を寄せ合うように乗せられたお雛様、波を受けるたび揺られてお互いを支え合っているようにも見える。 |
 |
| 季節によせて vol.328 平成30年2月24日 |
| くれなひの波紋広ごる落椿 晶 |
| 椿は北海道を除く日本全土と中国、朝鮮半島に分布する常緑高木。日本に自生するのは海岸地方に自生するヤブツバキ。500種類にも及ぶ園芸種があるが、野生種の花は紅色で半開。山茶花はひとひらひとひらばらばらになって散るが、椿は一花崩れることなくぽとりと落ちる。「落」の字を伴って散った花を詠むのは桜(「落花」)と椿(「落椿」)ぐらいか。花の王様と言われる牡丹でも「落牡丹」とは言わず「牡丹散る」だ。平らだった水面が紅色の椿が落ちたことで紅の波紋が広がったように見えた。 |
 |
| 季節によせて vol.327 平成30年2月17日 |
| 流れきしものをとどめて薄氷 晶 |
| 薄氷と書いて「うすらい」と読む。もちろん「うすごおり」とも。春先になって、ごく薄く張る氷や解け残った薄い氷のことで、冬の氷とは違って薄く消えやすい儚さが特徴。外の睡蓮鉢で目高を飼っているが冬は指で押してもびくともしなかった氷が、しだいに薄くなりまぶしく光る。「春になればすがこも溶けて、どじょっこだのふなっこだの、てんじょこぬけたとおもうべな」 |
 |
| 季節によせて vol.326 平成30年2月10日 |
| 冴返る神より仏きらびやか 晶 |
| 古事記に出て来られる神様たちのお住まいは白木でたいそう慎ましやかなのに対し、外国からいらっしゃった仏様たちはご自身もお住まいも派手だなあとふと思ってしまいました。建物や須弥壇に装飾をこらし、金箔をふんだんに使ってお釈迦様のいらっしゃる極楽浄土を再現しているかのようにさえ思われます。そういえば、伊勢神宮で行われているような式年遷宮のように何年かに一度お住まいを移られるようなことはあまり聞いたことがないような。それはともかくとして、我が家も神棚より仏壇の方がいささかきらびやかでした。 |
 |
| 季節によせて vol.325 平成30年2月2日 |
| 切れ味といふは水にも寒造 晶 |
| 昨年、米作り・酒造り体験(田植、草取り、稲刈り、稲架掛け)に参加し、100平米の田んぼを任された。半年かけて山の水で育て天日で乾かしたお米は期待以上の美味しさ。そのお米を使って贅沢にも地元の酒蔵で日本酒も作った。こちらは蒸した米を冷ましてタンクに入れるという工程だけの体験だったが、酒蔵見学を始め非常に貴重な体験をさせてもらった。そこで聞いたお酒の甘口と辛口について。米を固めに蒸すと辛口、柔らかめだと甘口だとか。先日届いた私達のお酒は濃厚辛口でこれも期待以上の出来だった。 |
 |
| 季節によせて vol.324 平成30年1月20日 |
| 被せ藁にふくらみもたせ寒牡丹 晶 |
| 12月から1月にかけて咲く牡丹を「冬牡丹・寒牡丹」という。春先に蕾を摘み取って花期を遅らせるため花は小さめである。寒さをしのぐため敷藁をしたり藁苞をほどこし保護しなければならないが真冬の花の無い庭園を華やかにする。花びらを傷めない様に風で飛ばされないようにと藁苞を調整するそうだが、ご機嫌をうかがうかのように膝をついての作業。園丁たちこのような心遣いがあってこその美しさと思う。 |
 |
| 季節によせて vol.323 平成30年1月13日 |
| 舞ひ終へてにはかに小さき傀儡かな 晶 |
| 「傀儡(かいらい)師」とは人形を廻し今様を歌って旅をした芸能民のこと。首から人形の箱を吊るし、手を使って人形を操る。記憶にある門付けの傀儡師(くぐつ師)たちも人形を生きているかのように操り、子供心にはめでたいと言うより不気味にさえ感じ、「おいべっさんが来た」と隠れたものだった。色の褪せた木偶人形の「おいべっさん」は実は「夷さん」だったと歳時記をよむようになってようやく気付いた。 |
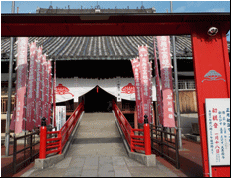 |
| 季節によせて vol.322 平成30年1月5日 |
| 大過なく過ごして厚き古日記 晶 |
| 無事、大過なし、という言葉がだんだん身に沁みてありがたいと思えるようになった。新しい日記はプレスしたズボンのように型崩れしてないが、1年、あるいは10年と書き込んだ日記は文字だけでなく使い込まれた分だけ分厚くなる。ぱらぱらとめくるページの間から挟んだことさえ忘れていたチケットの半券が落ちて来たり。楽しいことばかりではなかったが、まずまずの一年だったと思える古日記の重さだ。 |
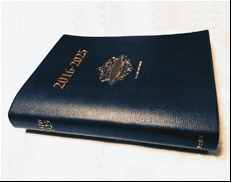 |
| 季節によせて vol.321 平成29年12月22日 |
| 完売の箱をつぶして年の市 晶 |
年末に正月用の注連飾りや縁起物、盆栽や雑貨などを売るために立つ市のことで、神社や寺の門前などで開かれる。軽トラックの前に品物を並べ景気よく売りさばく。
まさに何でも有る青空スーパー。品出しのすんだ段ボールや空き箱は軽トラの後ろに積み上げられ、これまた手際よく潰されたり畳まれたり。店主も客も馴染みになると値引き交渉も巧み。しかし、忙しい暮れのこととて適当なところでお互い手を打つのがよさそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.320 平成29年12月16日 |
| 島のどこよりも平らか牡蠣筏 晶 |
| 牡蠣の美味しい季節。レモンを絞って啜る生牡蠣は想像するだけで口の中が潤う。なんといっても宮城県、広島県の牡蠣は名前が通っているが、昨今では全国いろんなところで養殖され隠れた名産地があるようだ。入り組んだ入り江で波の穏やかなところが適するのだろう。ところで、牡蠣の貝殻は形が不規則とはいえ、海中の岩石や杭等に付着するときは決まって左殻だそうだ。二枚くらべて、やや小さく膨らみの弱い方が蓋になる右殻と覚えておけば美味しいエキスを零さず焼くことができるかも。 |
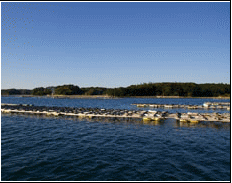 |
| 季節によせて vol.319 平成29年12月9日 |
| 綿虫やさだかならざる物の影 晶 |
| 晩秋から初冬にかけて、青白く光りながら浮遊する昆虫が綿虫。白い綿のようなものを丸く膨らませても体長二ミリほどなので捕まえようとしても、指の間をすり抜け一瞬にして見失う。明るく晴れた昼間より、曇りがちな日や夕方近くに目にすることが多い。「大綿・雪蛍・雪婆・白粉婆・雪虫」という傍題がありどちらかといえば陰のある詠み方をされる季語。井上靖の小説「しろばんば」も綿虫の傍題「雪虫」のこと。 |
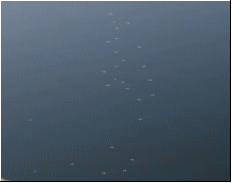 |
| 季節によせて vol.318 平成29年12月2日 |
| 大根の抜け出しさうな日和かな 晶 |
| 大根の美味しい季節になった。おろし、膾、煮物、切干、沢庵などなど。献立に迷うときでも何かの一品になるので、欠かすことができないありがたい食材だ。団地のリタイア組が借りている畑にも必ず大根や白菜があり、中にはプロに引けを取らないほど立派な野菜を作る人もいる。今年は秋の長雨の被害や菜虫の食害もあったそうだが、ここへきてお天気もようやく安定してきたようだ。このところの暖かい日差しに誘われたかのように、大根が土から肩をだしている。 |
 |
| 季節によせて vol.317 平成29年11月25日 |
| 散りざまは人には見せず返り花 晶 |
| 小春日和に誘われて春の草木が季節外れに咲かせた花が帰り花。本来は桜であるため、他の花の場合は例えば、躑躅(つつじ)の帰り花などと固有名詞をいれなければならない。春の花は蕾の頃から今か今かと待たれるが、帰り花は何輪か咲いてようやく気がつくくらい。ましてや、花が散ったことなどは誰も気にも留めない。しかし、思いがけず目にした時は、春先の初花とは別のがある。よろこびがある。どこかで、精一杯花を咲かせているいる一輪の返り花を探してみてください |
 |
| 季節によせて vol.316 平成29年11月18日 |
| しぐるるや笊に青菜の水を切り 晶 |
北陸に、弁当忘れても傘忘れるなという諺(ことわざ)があるそうだが、変わりやすい天気に油断するなということなのだろう。降ったかと思えばすぐ止み、止んで日が差し始めたかと思えばまた降りだす時雨。もともと、京都の北山など山がちなところで見られる現象を「時雨」と呼んでいたそうだが、今では冬の通り雨のことも「時雨」と呼ぶようになった。物寂しい季節につかの間の華やぎを見出す雨と言えようか。晩秋の「秋時雨」、その冬初めての「初時雨」、「時雨」、「春時雨」、この四つの季語を詠み分けられたらと思う。
*笊:ざる |
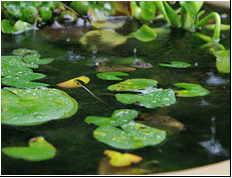 |
| 季節によせて vol.315 平成29年11月11日 |
| 一粒の種をかかへて穂絮飛ぶ 晶 |
| 絮(わた)でまず思い浮かぶのは、蒲公英(たんぽぽ)の丸い絮毛だろうか。しかし、蒲公英の絮は春の季語。草の絮と言えるのは、秋の雑草から出た穂絮に限られる。イネ科やカヤツリグサ科などの草は秋に花穂をつけ、やがてそれが絮となり実をつけて飛ぶ。蒲公英の絮のように目立つことはないが、川原や道端で風にそよいでいるのを見かける。イネ科の植物は一万種もあって、海岸から高山帯、熱帯から極地、砂漠でも見られるそうだ。頼りなげな草の絮だが、一粒の種を抱いて風に乗り、人や動物についていろんなところへ種を広めていくのだろう。 |
 |
| 季節によせて vol.314 平成29年11月4日 |
| 鶺鴒や石なめらかに瀬を分かち 晶 |
| 日本の固有種の背黒鶺鴒をはじめとして、黄鶺鴒、白鶺鴒など五種類の鶺鴒(せきれい)が日本に生息するそうだ。北海道や東北地方で繁殖し秋に南下してくるので秋の季語とされているが、私の町ではたしか「市の鳥」。人家近くや水辺で長い尾をしきりに打ち付けている姿をよく見かける。ツツツツとしばらく歩いては波のような飛び方をするのも他の鳥とは違うところ。トントンと石を叩くのは、驚いて石の下から出てきた虫を捕食するための行為なのかもしれない。 |
 |
| 季節によせて vol.313 平成29年10月28日 |
| 年代の根の隆隆と万年青の実 晶 |
| 結婚前の父と母を引き合せて下さった方の代表作の一つが「万年青(おもと)」。実物と見紛うばかりの陶芸で、今も実家の玄関にある。赤と緑の万年青の実が隆隆とした葉の間にうまく配され、季節によって向きを変えれば年中飾れっておけるのがよい。そんなご縁もあってか、庭にも本物の万年青がなん株かあった。そよりともしないぶ厚い葉、気付かぬ間に咲いて散る花、子供にはまるで良さがわからなかったが、今は留守宅で逞しく枯れずに頑張っているのをみるとなんだかいとおしくさえ思える。 |
 |
| 季節によせて vol.312 平成29年10月21日 |
| 蓮の実が飛ぶ校則のまた緩み 晶 |
| 蓮の花が散ると中央の花托がはっきりとみえてきます。その花托の蜂の巣状の穴の中で種子が一粒ずつ育ちます。楕円形で薄緑色だった種子が黒く熟し花托も緩んで来ると、風に揺れた拍子に蜂の巣上の穴からこぼれてまるで飛び出たように見えるのを「蓮の実飛ぶ」といいます。日本ではあまりなじみはありませんが、東南アジアや中国台湾ではお菓子の材料や食用としても一般的だそうです。そういえば、蓮の実の砂糖漬けという中国のお土産、更年期にもいいからといただいたことがあります。 |
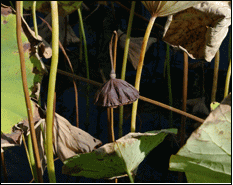 |
| 季節によせて vol.311 平成29年10月14日 |
| 決めかねる籠の正面虫の秋 晶 |
| 昼間も汗ばむほどではなくなり、まさに秋本番、昼間でも草叢からにぎやかな虫の声が聞こえる。夕方、小一時間ほどの散歩の間も、まるでついてきてるのかと思うほど切れ間なく虫の声がして虫籠の中に千戸の団地があるような不思議な感覚だ。虫籠と言えば、江戸時代初期に、主として武士の手仕事として始まり、岡崎藩から全国にその技法が伝えられたそうだ。大和虫籠は殿様や豪商、御殿虫籠は京都の公家、一般では飾りのない竹で作られたものが人気だったとか。 |
 |
| 季節によせて vol.310 平成29年10月7日 |
| 火袋の日から月から小鳥来る 晶 |
| 電気がなかった時代、石灯籠は大切な灯を守るものだった。それゆえ、灯を入れる火袋と呼ばれる部分には、風雨から灯を守るため格子を入れたり、石に彫りを加えたりさまざまな工夫が見られる。私が見た灯籠は公園の奥に据えられていたもので火袋には三日月型と円型の窓が施されていたので、てっきり太陽と月だと思ったのだが、いやいや、夜に使うものだから円型は太陽ではなく満月だろうという人もいる。本当のところはわからないが、火の入らなくなった火袋には鳥の古巣があった。 |
 |
| 季節によせて vol.309 平成29年9月30日 |
| 円崩すことなく車田の刈られ 晶 |
車輪の形に稲を植えることから車田と呼ばれ、神事に関した農作業ではないかとか、伊勢神宮にお供えする米を作っていたという説がある。現存するものとしては、渦巻き状に植える佐渡の車田と、七本のラインが車軸のように見える高山松之木町の車田がある。飛騨の里で見た車田は松之木町の形を再現したものだそうで、車田保存会が、毎年五月下旬に「たかやまもち」という稲の田植えを行っているようである。
秋には2アールの田に約1,5俵の収穫があるそうでお米は、飛騨の里の鏡餅や花餅飾りに使われるそうである。 |
 |
| 季節によせて vol.308 平成29年9月23日 |
| ざりがにの逃げそびれたる落し水 晶 |
| お米を作って日本酒を作ろうと言う体験講座に参加している。田植も草取りも初体験で衣装や道具を揃え、恰好だけはそれらしく参加したものの農作業の苦労が身に沁みた。今月末、稲刈と収穫祭をして、念願の日本酒造りの工程へという運びだ。たった数回しか関わらない農作業体験なのに、近所の田んぼの稲の育ち具合や水の張り具合に目が行く自分が可笑しい。指導員の方が稲は足音を聞いて育つと言われたが、目を配り手間をかけた分だけ美味しいお米になると言うことなのだろう。農薬を使わない田んぼはいろんな水生昆虫が棲みつき、それを狙う鳥が畦に羽を休めていた。 |
 |
| 季節によせて vol.307 平成29年9月16日 |
| 待宵の蕾がちなる壺の花 晶 |
| 改正月令博物筌によると、「月を見ること、四時隔てなし。しかれども、春は朧(おぼろ)に霞み、夏は蒸雲月を蔽(おお)い、冬は繁霜人を侵して、ともに月を翫(もてあそ)ぶに害あり。秋は夏に遅れ、冬に先立ち、その時の宜しきを得、秋の金気を得て、月いよいよ明らけし。」とある。月を眺めるのに最適な季節、満月だけでは惜しいではないか。満ち欠けの様子も存分に楽しもうと言うことで月齢に応じた呼び方がある。待宵は十五夜の月を待つ心ということで望月に少し満たない十四日の夜のこと。その夜の月は待宵の月、小望月、十四夜月(じゅうしやづき)。 |
 |
| 季節によせて vol.306 平成29年9月9日 |
| 水瓶のあふれむばかり星月夜 晶 |
| 今年の夏は土星を観測するには最適だったと聞く。この時期だと日没頃から南の空、蠍座(さそり座)のアンタレス(オレンジ色っぽい星)のやや右辺りに見えるクリーム色をした星が土星。天体望遠鏡があれば土星の環が帽子の鍔のようにきれいに見えるそうだ。星月夜とは、月のない夜空が星明りで月夜のように明るいことを言う。現代社会では滅多に経験できないが、見事な星空を追いかけてのツアーが横浜港発着五泊六日のスターパーティークルーズがあると聞いた。夜はデッキのチェアに寝ころんで星のソムリエによる案内で夜空を満喫できるそうだ。こういう旅も悪くない。 |
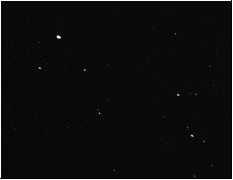 |
| 季節によせて vol.305 平成29年9月2日 |
| 犇いてをらねば倒れ貝割菜 晶 |
貝割れと言えば、水耕栽培による貝割れ大根のパックが頭に浮かぶが、その歴史は意外と古く、平安時代の「和名類聚鈔」にノダイコンの若芽としてカイワレの記載があるそうだ。「さわやけ」とも呼ばれ、「宇津保物語」では「さわやけ汁」としても登場している。現在も、発芽直後の胚軸と子葉を食用とするスプラウト食品として大根や、ブロッコリー、豆苗など手ごろな食材として人気を博しているちなみに9月18日は貝割れ大根の日だそうだ。
*犇いて:ひしめいて |
 |
| 季節によせて vol.304 平成29年8月26日 |
| 新涼や退りて仰ぐ五重塔 晶 |
| 先日、会津若松の栄螺堂へ行った。栄螺堂とは、江戸時代後期の東北から関東に見られた堂内に螺旋構造の廻廊を持つ特異な建築様式の仏堂で、螺旋のスロープに沿って行けば、上りと下りの参拝者がすれ違うことなく、三十三観音詣りができる構造になっている。会津若松のそれは寛政8年(1796年)に建立された六角三層の御堂で国の重要文化財。東北地震にも持ちこたえたのだから先人の知恵と技術は素晴らしいものとだと、御堂を参拝した後、あらためてじっくりと眺めた。もちろん、全体像が臨めるところまで離れて。 |
 |
| 季節によせて vol.303 平成29年8月17日 |
| 青き穂の風にそよげる秋初め 晶 |
| 暦の上では秋と言うが、その暦を見直してほしいぐらいの暑さが続いている。熱帯夜につぐ熱帯夜、真夏日につぐ真夏日で、暑さがどんどん蓄積されているような気がする。太陽も雨も風も随分と粗暴になったものだ。せめて朝晩だけでも秋の気配を感じさせてくれたらと思うが、植物はけなげにも実りの秋に向けて稲は白い花をつけ、蘆や芒も穂を伸ばし、猫じゃらしはさかんに風に尾を振る。間もなく終戦記念日。こんな名前の記念日は二度といらない。 |
 |
| 季節によせて vol.302 平成29年8月3日 |
| 水道の水生ぬるき朝曇 晶 |
| 世界で水道水が飲める国は意外と少なく15か国ほどだそうだ。もちろん日本の水道水も飲めるが、飲料水や調理用にとミネラル水や浄水を買うと言う人が多い。マンションであれ、一戸建てであれ、貯水タンクや水道管の錆なども気になる要因だろうし、カルキ臭にも抵抗があるのだろう。私もできれば生ぬるい生水より湯冷ましかお茶が飲みたい方だ。季語の「朝曇」は真夏の朝の靄がかかったような曇りのこと。日中の厳しい暑さが思いやられる朝の始まりだ。 |
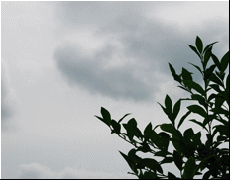 |
| 季節によせて vol.301 平成29年7月29日 |
| 吊橋の奈落は見せず夏の霧 晶 |
| 髙いところから下を見るのは怖いと言う人がいるが、私にはむしろ何も見えない方が不気味だ。周りの景色を楽しみながら渡った吊橋を帰りには霧で真下はおろか、対岸さえも見えない状況を想像すると足が竦む。今は知らないが、以前行った祖谷のかずら橋は長さ45メートル、幅1.5メートルで猿梨の蔓を編んで川に渡してあり、その端は両岸の樹木に止めてあるだけだった。渡してある木の隙間から川底が見えるところを通るのも勇気がいったが、何も見えない中を蔓を頼りに渡ると言うのも不安なものだ。 |
 |
| 季節によせて vol.300 平成29年7月22日 |
| 歩むたび馬上に揺れて夏帽子 晶 |
| 二人の姪とポニー牧場へ行った時のこと。上の子は乗馬条件をクリアーしたが、下の子は身長が足りず木馬で我慢させられ大泣きをした。晴れてポニーに乗ることができた姉の方も、生まれて初めての体験。促されるままに踏み台からポニーにまたがったものの緊張しているのがみてとれる。そんなお客には慣れっこなのだろう、ポニーは首を小さく振ってゆっくりと歩き始め無事一まわり。二十年ほど前の話だが、今でも忘れられない光景。 |
 |
| 季節によせて vol.299 平成29年7月15日 |
| 噴水にゆるがぬ丈のありにけり 晶 |
| 最近の噴水は音楽に合わせて水を噴き上げたり止まったり、カラフルな照明を浴びたりと演出が凝っていて、見ていて楽しいものが多いが、決められた高さにひたすら水を噴き上げる昔ながらの噴水もなかなか捨てたものでもない。勢いよく噴きあがる天辺の水の拳や、風に吹かれて折れ曲がる水の柱や水しぶきに虹が生まれるのを眺めるのも楽しい。今も昔も、噴水のある広場は夏の待ち合せ場所の一つ。 |
 |
| 季節によせて vol.298 平成29年7月8日 |
| 干し網に立つまくなぎの太柱 晶 |
| 夏の夕方など、顔の周りなどにまとわりついてくる小さな虫がいるが、これが「まくなぎ」である。漢字では、虫偏に軽蔑の蔑がつく「蠛」と、虫偏に暗いとか愚かという意味を持つ蒙がつく「蠓」をあてる。たしかに鬱陶しい虫ではあるが、こんな漢字を宛がわれていてはいささか気の毒な気もする。網を干してある庭先で、そんな小さなまくなぎ(蠛蠓)が柱のように群れてまるで干してある網を支えているかのように見えた。傍題は「めまとい、めまわり、めたたき、糠蚊など」 |
 |
| 季節によせて vol.297 平成29年7月1日 |
| 犇いて粒不揃ひの青葡萄 晶 |
昨年、びっくりするほど大きな箱のお中元が届いた。何かと思えば青い実をつけたデラウェアの葡萄の鉢。一番大きな粒で小指の爪ほど、小さなものは待針の頭ほど、そんな可愛い粒が連なった房が五つ、葉に隠れるように枝についている。はてさて、どこに置いたものやらと、日の当たるところ、反日影と持ち運んでいるうちに、一枚の葉の軸に五センチほどの揚羽の幼虫がいることに気づいた。まさかとは思うが、この揚羽の幼虫も蝶に育てよということだったのだろうか。
*犇いて:ひしめいて |
 |
| 季節によせて vol.296 平成29年6月24日 |
| こぼれ種咲きつぎ小判草長者 晶 |
| 小判草はヨーロッパ原産のイネ科植物。日本へは明治初めに渡来したそうだ。葉の先に緑色の小判型の穂をつけ、熟すと黄金色に変わるところから小判草、または俵麦と呼ばれている。十数年前、鎌倉へ行った折り、大きなお屋敷の小判草が溢れんばかりで、まさに小判草長者のお屋敷。どんな花が咲くのかは見たことがないが、細長い茎に黄金色で光沢のある俵型の穂がつくこの帰化植物に、小判草という和名を与えた明治の人に感心する。 |
 |
| 季節によせて vol.295 平成29年6月17日 |
| 五月雨や揺れ小止みなき舫ひ舟 晶 |
五月雨は旧暦五月に降る長雨のこと。稲作中心の日本の農家にとっては田植えを控えてまことに大切な雨である。春先、川の水が引き込まれ、田起しされた土が黒々とした色に変わっていくさまは田植えの季節になったことを知らせてくれる。五月雨はそうした田の隅々まで水をいきわたらせ、木々の緑を深めていくような雨。「五月雨を集めて早し最上川(芭蕉)」「五月雨の降り残してや光堂(芭蕉)」「五月雨や大河を前に家二軒(蕪村)」「五月雨や上野の山も見あきたり(子規)」。「空も地もひとつになりぬ五月雨(杉風)」。傍題に「さつき雨、さみだる、五月雨雲」
|
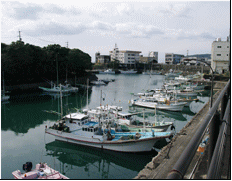 |
| 季節によせて vol.294 平成29年6月10日 |
| 紫陽花をあまた剪りたる刃のくもり 晶 |
挿木で育てた額紫陽花、柏葉紫陽花、カメレオン、墨田の花火、アニバーサリー、名前はわからないがピンクの紫陽花、友人に分けてもらった山あぢさゐなど、狭い庭だが紫陽花が次々咲いて雨の日を楽しませてくれる。鋏を鳴らしながらどの花を剪ろうかとしばし迷うのも楽しいひと時。大輪の紫陽花も良いが、最近では山あぢさいや甘茶などのように小振りで少々控えめな花の方が美しいと思えてきた。紫陽花の傍題には、あずさい・かたしろぐさ・四葩(よひら)の花・七変化・刺繍花・瓊花(たまばな)。
|
 |
| 季節によせて vol.293 平成29年6月4日 |
| 笹舟の堰越えられず螢川 晶 |
| 家の周りに蛍が飛ぶと知人が招いてくれた。夕方、まだ日があるうちに川べりを散策すると、思いのほか川の水があり流れも速い。人家近くのこのような川に本当に蛍が出るのだろうかと思いながら、暗くなるまで笹舟を作ったり草矢を打ち合って蛍を待った。堰も飛沫も暗闇に包まれたころ、岸辺の草むらに一つ、二つとみどりの火が点り、ふわっと舞い上がり、向こう岸辺りからも呼応するかのように光が点りだす。川の音がする中、どこから湧いて出たのか蛍が肩にふれんばかりに飛び出した。 |
 |
| 季節によせて vol.292 平成29年5月26日 |
| 鹿の子の跳ねて日の斑をこぼしけり 晶 |
鹿はウシ目(偶蹄類)シカ科のニホンジカ。体長1.5メートルほどだが、北に住むものほど体が大きい。牡は40センチほどの角を持ち毎年生え変わる。春日大社では10月中の土曜、日曜に事故防止のため発情期の前に角を切り落とす。
鹿の子は鹿の子斑があり、茂みなどに逃げ込むとまだら模様のおかげで敵から身を守ることができる。子供の角は二年目に生えるそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.291 平成29年5月20日 |
| 折鶴に息吹きこみて愛鳥日 晶 |
母が「鶴ってどう折るんだった?」と私に聞いた。父は自分で折ったことがないと言う。それならばと、テーブルを囲んで二人に鶴を折ってもらうことにした。何度か折り間違えたものの、母のすらりと伸びた指は鶴を思い出したようで、角まできれいに折りあげた。父も頑張って折ったが鵞鳥のような鶴が折り上がり大笑いした。
節高で爪も丸い私の手、ぶきっちょなところまで父にそっくりだ。二人とも他界したが、鶴を一緒に折った楽しい時間を残してくれた。 |
 |
| 季節によせて vol.290 平成29年5月13日 |
| 葉脈のかく頼もしき柏餅 晶 |
| 長い間、私の柏餅の葉は丸だった。ひらぺったくつるんとした二枚の葉で餅を挟んだのがいわゆる柏餅で、それを疑うこともなかった。が、ある日、それはサルトリイバラという葉で、本物の柏の葉にくるまれた柏餅を出された時には驚くとともにいささか落ち込んだ。見たこともない形の葉で、しかも大きすぎて餅が見えない。葉脈は一本太い筋が通って、畳むと筋が折れるほどしっかりしている。男の兄弟がいないので兜飾りも見たことがなかったが、男の子のお節句というのはお餅の葉っぱまで違うと妙な感心をしたものだった。 |
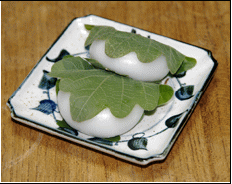 |
| 季節によせて vol.289 平成29年5月6日 |
| 流木に靴をあづけて磯あそび 晶 |
| 祖母の家から子供の足でも五分も歩けば海だった。遠浅のような砂浜でも荒磯のように波が荒くもなく、遊ぶには手ごろな浜。潮が引いた砂地では蟹が這い出し、貝が潮を吐く。潮だまりでは取り残された小さな魚が汐が満ちてくるまで息を潜めてている。石をひっくり返して海の生き物を探しているうちに汐が満ちてきて汐だまりの魚も蟹もさっと姿を消す。潮が満ちる速さは意外に早く、思わぬ深みに足を取られてスカートの裾を濡らしてしまうことも。流木の上に靴を置いておいたからと言って安心できない。 |
 |
| 季節によせて vol.288 平成29年4月27日 |
| 若鮎の瀬頭よりも跳ね上がる 晶 |
| 秋、孵化した稚鮎は海に下り冬の間海ですごす。4、5センチに成長した子鮎(若鮎)は再び川に戻ってくるのだが、堰や水門に阻まれ上流を目指すのも容易ではない。遡上する魚のために設けられた魚道を目の前にして稚魚がまっくろな群れをなしているのも春先の光景。やがて、覚悟を決めたものから、押し流されながら懸命に魚道や魚梯をのぼっていく。川を上りきったものだけが次の命を繋ぐことができる。 |
 |
| 季節によせて vol.287 平成29年4月21日 |
| うつとりと蘂かかへこみ熊ん蜂 晶 |
「春はええなあ~」とでも言っていそうに蜜を吸ったり、花の蘂をかかえて蜜を吸ってうっとりしている熊ん蜂。熊ん蜂と言ってもスズメバチではなくコシブトハナバチ。ハナバチは体が丸っこく、口には折り畳み式の長い舌を持ち、長い毛がふさふさしているので花粉が付きやすくなっているらしい。蜜の出る場所を花の奥にしたのは花粉を運ばせようと言う花の作戦かもしれませんね。中にはハナバチにしか蜜がすえない構造の花もあるとか。蜂と花にも相性があるんですね。
*蘂:しべ |
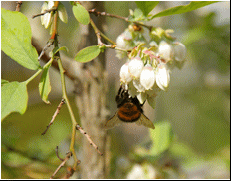 |
| 季節によせて vol.286 平成29年4月15日 |
| 葉に隠れがちになりゆく巣箱かな 晶 |
| 日に日に日差しが強くなり弱々しかった若葉も葉を重ね合うようになった。それでも、芽吹きの遅れている高い梢には小枝を差し渡した去年の巣が丸見えだ。大きな鳥は狙われる心配が少ないので人目に付くようなところにでも巣をかける。巣箱は、できるだけ目立たないように巣作りしなければならない小さな鳥にとっては最高のプレゼントだろう。小さな丸い穴を出入りして住み心地が気に入ればカップル成立。林が鳥の声で賑やかになる日が待たれる。 |
 |
| 季節によせて vol.285 平成29年4月8日 |
| ほほゑみがほどの日の差し仏生会 晶 |
お釈迦様の誕生日とされる4月8日を祝う法会が仏生会。灌仏会、花祭などとも。
摩耶夫人の右脇からお釈迦様が生れた時、竜王は産湯にと甘露の雨を降らせ、蓮の花が足を支えたと言われている。生まれたばかりのお釈迦様は、すぐ7歩歩いて天地を指し「天上天下唯我独尊」と唱えたことにちなみ、右手を上げて蓮の上に立つ誕生仏を花御堂に安置し、参詣者が甘茶を注ぐようになったと伝わる。日本書紀の記録では推古14年(606年)に元興寺で行われたのが始まりとしるされている。 |
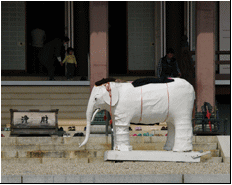 |
| 季節によせて vol.284 平成29年4月1日 |
| 花びらの反りてあでやか紫木蓮 晶 |
| 戒名は真砂女でよろし紫木蓮(真砂女) 紫木蓮の句でまず思い浮かぶのが真砂女さんのこの句である。4月ごろ、大ぶりの白木蓮(はくもくれん)に少し遅れて、外側が紫または紅紫色の木蓮が咲き始める。大きな蕾は柔らかな毛におおわれているが、蕾が大きく膨らみ、花びらが反るにつれて内側の白っぽい赤紫色が半襟のように見えて、よりあでやかだ。恋多き女性であったと言う真砂女さんには印象鮮明で相応しい花なのであろう。 |
 |
|
|