|
|
| 季節によせて Vol.379 平成31年3月30日 |
| 芽を出せば列の乱れてチューリップ 晶 |
「咲いた、咲いた、チューリップの花が。並んだ、並んだ、赤白黄色。どの花見てもきれいだな」この歌を歌ったことがない日本人はいないだろうと思うぐらい有名な歌。
昭和五年に世田谷の近藤宮子さんと言うご婦人が作詞された歌だそうだ。戦争の足音がする時代、どんな思いで作られた歌か。並んで咲く赤も白も黄色もどれもきれいだ。一色じゃなくいろんな色があったほうがきれいという意味だろうか。一列に植えたつもりのチューリップ。土の中で傾いたのか思い思いの方向へ芽を出した。 |
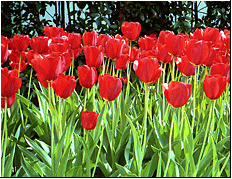 |
| 季節によせて Vol.378 平成31年3月16日 |
| 植替への縄かけられしまま芽吹く 晶 |
| 最近はホームセンターなどで年中植木を買うことができるが、以前は立春過ぎの市や春祭りで苗や植木が売られていた。丸く掘り上げた土付きの根を荒縄で縛り、枝がからまらない程度の間隔で並べて売っていた。日当たりの良い畑で育った苗などは、幼木ながら花をつけているものもあったし、花芽がかなりふくらんでいるものなどもあった。桃栗三年柿八年、やっぱり果樹には花芽はないなあなど、植えるところも、買うあてがなくても植木市を見て回るのは今でも楽しみの一つ。 |
 |
| 季節によせて Vol.377 平成31年3月9日 |
| ひと騒ぎありて子猫の名が決まる 晶 |
| 「岩合光昭の世界ネコ歩き」という番組。動物写真家の岩合さんが映しだす猫の動きや表情が実に自然ですばらしく、猫好きではなかった私がいつのまにか番組のファンになっている。もちろん猫の習性を熟知しているからこそなのだろうが、猫の行動を予測して、岩合さんの狙うアングルにぴたりとおさまって、どの猫も本当に主演ニャン優賞。飼い猫の場合は、ちゃんと名前を呼んで、かっこいいねえ、すてきだねえと必ず声を掛けて撮影。猫だって一生付き合う名前だ。名前は真剣に決めてやらねば。 |
 |
| 季節によせて Vol.376 平成31年3月2日 |
| 土雛も飾る毛氈敷きたして 晶 |
| 町おこしの一環か、飾られなくなった古い雛人形や土雛を古民家や蔵などで見せるところが多くなった。私の生まれた頃は御殿飾りが主流だったようだが、大正、明治、江戸と時代を遡るほどにお顔立ちも衣装もどことなく雅に。雛祭の起源は形代に穢れ(けがれ)を移し川に流す祓(はらい)の行事だったそうだが、江戸中期頃から流す雛、抱いて遊ぶ雛、鑑賞する雛に分かれてきたようだ。愛知県は陶磁器産業が盛んだったためか戦前まで庶民の雛人形として土雛が広く親しまれていたようで子供が生まれるとさまざまな土人形を送る習慣があったと聞く。素朴な風合の土雛が豪華な雛飾りとともに大切に残されている。(毛氈:もうせん) |
 |
| 季節によせて Vol.375 平成31年2月23日 |
| 薄墨の春めく色とおもひけり 晶 |
| 「墨に五彩あり」という言葉がある。硯に水を注いで摺墨で摺っても墨汁の色はその時々で異なる。隷書、楷書、行書、かな等、文字によって墨の色合も微妙に異なるが、究極の墨づかいは、濃淡や暈し(ぼかし)を用いて墨の無限の色をひきだす水墨画だろう。「松煙墨(しょうえんぼく)」といって、松を燃やしてできた煤を集めたものが墨を代表するもの。その中の青みを強く帯びたものが特に「青墨(あおずみ)」と呼ばれ珍重されている。薄墨の流れるような草書や仮名文字には躍動的な春の訪れを予感させるものがある。 |
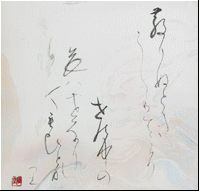 |
| 季節によせて Vol.374 平成31年2月16日 |
| 眩しさの加はる水辺猫柳 晶 |
猫柳(ねこやなぎ)は枝が水に浸かれば、そこからでも根を下ろして株を増やすため、水があるところなら、北海道から九州までどこの河川でも見られる植物である。早春、他の柳類より早く葉に先立ち、銀白色の短い毛を密集した長楕円形の花を咲かせる。特徴的で、「ねこやなぎ」の名前は猫の尻尾に見立てられたことによるそうだ。ところで、猫柳の樹液は甘いらしく、カブトムシやクワガタムシ、カナブン、スズメバチなどの好物らしい。
|
 |
| 季節によせて Vol.373 平成31年2月7日 |
| 薄氷掬ふみどりご抱くやうに 晶 |
| 薄氷(うすごおり・うすらい)とは、春先、薄々と張る氷や、薄く解け残った氷のことをいう。「春の氷」「残る氷」ともいい、冬から春へ向かう季節の移ろいを感じさせてくれる季語。二月四日、立春を過ぎたとはいえまだ朝は寒い。メダカを飼っている鉢は朝ごと見事に氷が張っているが日ごとに緩む時間が早くなってきたように思う。日脚が伸び日中の日差が眩しいとそれだけで心が弾む。 |
 |
| 季節によせて Vol.372 平成31年2月2日 |
| 風なきに闇のざはめき鬼やらひ 晶 |
| 追儺(ついな)、なやらい、ともいう。もともとは大晦日の夜に悪鬼を追い払うための宮中の年中行事だったものが、社寺や民間にも広まり、今では二月の節分に行われている。家庭では節分の夜に「鬼は外、福は内」などと豆を撒くのが一般的だが、社寺の行事としては、年男が裃姿で豆を撒いたり、古式にのっとって鬼を負ったりする二つのタイプに分かれるようだ。 |
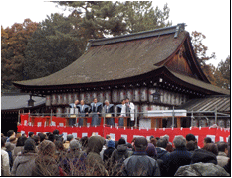 |
| 季節によせて Vol.371 平成31年1月25日 |
| 提げ帰るうちにも折れて九条葱 晶 |
| 九条葱(くじょうねぎ)は、青(葉)ねぎの一種。もともとは難波に自生していたものが後に京都に伝わり改良されたもので、京都市南区九条が主産地であったことから九条葱と呼ばれるようになったそうだ。葉身部が直径2センチ、長さが1メートルほどで、旬の真冬の時期になると「ぬめり」がでて甘みも加わる。耐寒性があって周年育つので鍋物の季節にはありがたい野菜。昔から「風邪に葱」と言われるように、疲労回復、解熱、咳や痰を鎮める等、民間療法としても用いられている。 |
 |
| 季節によせて Vol.370 平成31年1月16日 |
| 雨雲をはらふ日の差し弓始 晶 |
| 弓始(ゆみはじめ)とは、新年になって初めて弓を引くこと。厳かな神事や儀式としての「初弓・的始・射初め」。いろいろな神社で執り行われているが、愛知県の熱田神宮では「歩射神事(ほしゃしんじ)」と言って、五穀豊穣と除災を祈る神事が行われる。直径6尺(約1.8m)の大きな的に向かって6人の神職がそれぞれ2本づつ3回に分けて36本奉射するという新春の宮中にならったもの。最後の矢が射られると参拝者は先を争うように大的をめがけて殺到し、厄除けにご利益のあるといわれる大的の千木を奪い合うのだそうだ。 |
 |
| 季節によせて Vol.369 平成31年1月7日 |
| 日だまりの土ふつくらと初雀 晶 |
最近少なくなったと言われるものの、一番人の近くで愛らしい姿を見せてくれるのはやはり雀。そんな見慣れた雀でさえ、姿や声を見聞きして嬉しい気持ちになるのも元旦なればこそ。俳句では親しみを込め、正月の雀を「初雀」とよんでいる。
欣喜雀躍(きんきじゃくやく::雀が踊り跳ねるように大喜びすること。)という言葉があるように、喜びを象徴するものとして「初雀」と新年の季語とされたのだろう。
ちなみに、春は「孕み雀・雀の子」、秋は「稲雀」、冬は「寒雀・ふくら雀」が季語。 |
 |
| 季節によせて Vol.368 平成30年12月22日 |
| 星が勝手に動き出し聖夜劇 晶 |
| キリスト教系の幼稚園や学校でなくても、昨今はクリスマスには劇や発表会をして祝う。正月やお祭のように行事の一つになっているのだろう。星をつけたわっかを頭にかぶり立っているだけの役なのに小さい子たちはじっとしていられない。もぞもぞごそごそ。一人が流れ星のようにどこかに消えた。主役級の子はそんなことにはおかまいなし、大きな声で台詞を言ってどうどうと役になりきっている。たいしたものだと感心する。流れ星のように舞台から消えていた子が先生に連れ戻され全員でクリスマスの歌を歌って一幕が無事終了。 |
 |
| 季節によせて Vol.367 平成30年12月15日 |
| 曰く言ひがたき火加減玉子酒 晶 |
| 「曰く言い難し」とは言葉では何とも説明しにくいというような意味。玉子酒は日本酒に砂糖を少し加え、溶き卵を入れて温めた飲みもの。その火加減がなかなか難しく強すぎると掻き玉汁の卵のようになるし、弱すぎると濁ってしまうのだ。風邪気味のときに飲むとよいとされるが、温めるからアルコール分が飛ぶとはいえ、本当に子供が飲んでもよかったのだろうか。いささか気にはなりながら風邪気味と言って自分で適当に作って飲んでいた。 |
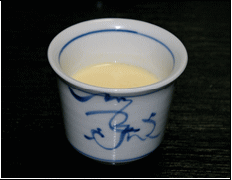 |
| 季節によせて Vol.366 平成30年12月8日 |
| 鍋蓋を湯気が押し上げ開戦日 晶 |
| 何の番組だったか、テレビの街角インタビューで、日本が第二次世界大戦でどこの国と戦ったか答えられない若者が多いことに愕然とした。となると、十二月八日が太平洋戦争開戦の日などと知っている若い人はほとんどいないだろう。かくいう私も歳時記で知った。二度と戦争を引き起こさないためにも、1941年(昭和16年)開戦当時の世相を知る人に直接聞いておかないといけないことがたくさんあるような気がする。 |
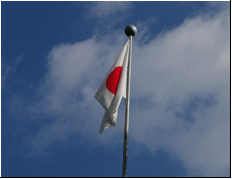 |
| 季節によせて Vol.365 平成30年12月1日 |
| 石高にあまる城址の実万両 晶 |
| 万両、千両、百両(カラタチバナ)、十両(ヤブコウジ)、冬枯れの中で赤い実をつける植物は目を楽しませてくれる。そんな赤い実に実の数や実の着き方でこのような名前をつけるとは。葉の上に明るい赤い実をつけるのが千両。それよりも大きな実が万両。万両は葉の下に実をつけるため鳥に食べられにくく冬を越しても実が減らないので、財産を減らさない縁起の良い植物として江戸時代に広まったと言われている。 |
 |
| 季節によせて Vol.364 平成30年11月24日 |
| 日だまりの日ごと広がり石蕗の花 晶 |
日当たりの良い所を好む石蕗(ツワブキまたはツワ)だが、明るい日影や半日影でも花を咲かせるので、日本庭園には重宝な花。
わが家でも10月末あたりから、落葉樹の根元の石蕗に日が当たり始め、長い花茎を伸ばし、花を咲かせている。例年のこととはいえ、石蕗が咲くと今年も冬が来たことを実感する。今年はことさら、新聞やテレビで平成最後の冬と報じている。来年の五月からはどんな元号になるのだろうか。 |
 |
| 季節によせて Vol.363 平成30年11月17日 |
| 手折りたる音にも芙蓉枯れしこと 晶 |
芙蓉は直径8~10センチの五弁花。朝開いて夕方にはしぼみ花殻を落とす大きな一日花。八月半ばごろから咲き始め当地では11月の声を聞く頃まで咲き続ける。
そんな芙蓉も冬になると一枚残らず葉を落とし、花殻の後には黄色っぽい毛に覆われた球形の実をつける。細い枝の先は枯れやすく折れやすい。種を採ろうと引き寄せた枝が乾いた音をたてて折れ、近づく冬を実感した。 |
 |
| 季節によせて Vol.362 平成30年11月10日 |
| 湯疲れの柚子にもありて仕舞ひ風呂 晶 |
| 今年も30個ほどの柚子が黄色く色づいてきた。毎年楽しみに待っていて下さる方へなるべく綺麗なものをと思うのだが、形がいびつだったり柚子の棘で傷ついたりしてこれはと思うような柚子にはめったに出会えない。よって、ぜいたくな話だが、湯船には戦力外の柚子が冬至の前から浮かぶ。この芳しい香りと体を温める薬効があるというので江戸時代から銭湯で柚子湯の風習が広まっていたようだ。 |
 |
| 季節によせて Vol.361 平成30年11月3日 |
| 熟れ柿のいまにも蔕の抜けさうな 晶 |
| 家を建て替える時に借りた一軒家の庭には柿の木があった。自由にとっても良いと言う許可を得ていたので、11月の家賃を届ける時に少し捥いでお届けしたところ、あれは富有柿だからまだまだ収穫は先だと笑われた。美味しそうな色に見えたのだが富有柿は木で十分熟した方が美味しいと言う。私は熟柿よりやや柔らかくなり始めた頃の方が好みなんだけどなあと思いながら次にお届けするか木を目で取り置いておいた。
*蔕:ヘタ |
 |
| 季節によせて Vol.360 平成30年10月30日 |
| 小鳥来る朝の日差しを待ちきれず 晶 |
| 種類にもよるのでしょうが、野鳥の写真を撮る人の話によると、夜行性の鳥を除いて野鳥は日の出20分前ぐらいから活動を初めて午前9時ぐらいまでが最も活動的で観察に向く時間帯なのだそうです。そういえば、我が家のブルーベリーを収穫するのにいつも鵯(ヒヨ)に先を越されて悔しい思いをしていましたが、日の出前から動いているのでは、始から勝負にならないことだった。ブルーベリーに網を掛ければよいと言う人もいるが、そこまでする気もなく、風見鶏をおいてささやかな抵抗をしている。 |
 |
| 季節によせて Vol.359 平成30年10月21日 |
| 粉を吹いて甘さ極まる黒葡萄 晶 |
| 葡萄の美味しい季節になった。大粒の巨峰や長野パープル、シャインマスカット、子供も食べやすいサイズのデラウェア、品種改良が進み種なしや皮ごと食べられる葡萄がふえたことが嬉しい。ところで、ながらく葡萄の皮につく白い粉は農薬だと思ってせっせと洗っていたのだが、実は「ブルーム」といって果実に含まれる脂質から作られたろうが表面に出て来たものだそうだ。しかも、この粉は葡萄の病気を防いだり鮮度を保つすぐれものでもあるらしい。葡萄農家さんたちはこの白い粉を新鮮な証しとしてできるだけ落さないように気を使いながら出荷しているのだそうだ。 |
 |
| 季節によせて Vol.358 平成30年10月14日 |
| 合併に町の名消えて桐一葉 晶 |
| 淮南子(えなんじ)の「一葉落つるを見て、歳のまさに暮れなんとするを知る(わずかな前兆を見てやがてやって来るだろうことをいち早く察知すると言う意味)」に由来すると言われ、この一葉は梧桐、桐をさすと言われている。桐の大きな葉がゆらりと落ちるさまは一枚でも十分に存在感がある。平成の大合併で多くの市町村が合併し歴史的な地名が消えたり、縁もゆかりもない新しい名前に変ってしまった町もある。開発で地形が変わり土地の名前まで変ってしまえば、後世にその土地の歴史が伝わりにくいように思うのだが。 |
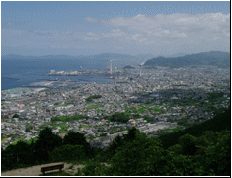 |
| 季節によせて Vol.357 平成30年10月6日 |
| 艶やかにしだれ紫式部の実 晶 |
| 6~7月ごろ葉の付け根ごとに薄紫色の小さな花を咲かせるが、紫の実の美しさから才媛紫式部の名に因んで「紫式部」と名付けられた。「実紫、紫式部の実」ともいわれる。また、白い実のものは白式部とも言われこちらも乳白色の艶やかな実をつける。では、才媛紫式部が現れる前はこの植物は何と呼ばれていたかというと、「むらさきしきみ」だそうだ。「しきみ」とは重なる実=実がたくさんなると言う意味らしいが、やはり才媛の名の「紫式部」のほうがふさわしい気がする。 |
 |
| 季節によせて Vol.356 平成30年9月29日 |
| 尾を振つていふこときかずゑのこ草 晶 |
| イネ科の一年草で道端や野原などいたるところで見かける草。夏から秋にかけてつける花穂が、犬の尾に似ていることから「狗尾草(えのころぐさ)」と言われるが、花穂を振ると猫が飛びついてじゃれるので「猫じゃらし」とも。どこにでもありながら秋の七草には入れてもらえなかったのはやはり花穂が落ち着きなく地味だったからか。「七草にもれて尾をふる猫じゃらし 富安風生」 |
 |
| 季節によせて Vol.355 平成30年9月22日 |
| ころあひの土の湿り気茸生ふ 晶 |
| 松茸や舞茸の生えているところは見たことがないが、初茸、栗茸、しめじ、なめこ、椎茸は実際に山で採らせてもらったことがある。日当たりの悪い雑木林は降り積もった落葉や腐葉土で湿り気を帯びているため滑りそうになることも。〈この辺りにあるはず〉という木の株元には、茸、茸、茸。掬うように一株、また一株、面白いように採れる。もちろん、食べられるだけ。採れたてのぬめりのある茸の土や汚れを洗うのは水より湯が良いとも教えてもらった。次は松茸山の湿りも嗅いでみたい。 |
 |
| 季節によせて Vol.354 平成30年9月15日 |
| みそはぎの川も暗渠になりにけり 晶 |
| 千屈菜・鼠尾草と書いてどちらも「みそはぎ」と読む。みそはぎは湿地や水辺に生える多年草で高さ1メートル前後になるものもあり、花は盆花として精霊棚に水を掛けて使うことから「禊萩(みそぎはぎ)」とも。丈夫な花だが、みそはぎが自生していた場所も埋め立てられたり暗渠となってかつての群落が消えたところもある。旧盆の頃に咲くので、精霊花という別名を持つみそはぎ、お盆の行事とともに盆花としてなくしてはならない花だ。 |
 |
| 季節によせて Vol.353 平成30年9月8日 |
| 風よりも日に口を割り石榴の実 晶 |
| 旧約聖書にも登場する石榴(ざくろ)、5千年以上前から栽培されていたと言われるが日本へは平安時代に渡来したそうだ。完熟すれば硬い皮に罅が入りその裂け目に沿って手で割ればルビーのような実がぎっしり詰まっている。あまり美味しいとも思わず石榴は見る物と思っていた。ある時、外国の女性が大粒の実を一粒ずつ口に運ぶのを見て、小鳥が啄む様だと思ったことがある。石榴と言うと、先ずその時の彼女の白い歯と石榴の赤い実が思い浮かぶ。やはり私にとっての石榴は食べるより鑑賞する果物のようだ。 |
 |
| 季節によせて Vol.352 平成30年9月1日 |
| 朝顔や眠りたりたること声に 晶 |
| 目覚めた時にはいつも咲いている朝顔。一体何時頃咲くのだろうと調べてみると、意外にも日の出より日没の時刻に関係しているらしい。朝顔は日没から8~10時間で開花するそうで、たとえば7月1日の日没は19時1分、朝顔の翌日の開花目安は5時1分。8月1日の日没は18時46分、開花目安は4時46分。日没が早まると開花時刻も早まると言うことのようだ。勿論、気温にも関係があるようで、今年のように高温が続くと開花が遅れる傾向であることもわかっているそうだ。朝顔にとっても熱帯夜はこたえるのだろうか。 |
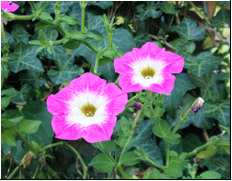 |
| 季節によせて Vol.351 平成30年8月25日 |
| 墓移す話に及ぶ墓参り 晶 |
| 住む人がいなくなり、自治体としての機能を果たせなくなっている集落を「限界集落」という。空家のまま放置された家や田畑、草ぼうぼうの墓などを見るといつから誰も来てないんだろうと悲しくなってしまう。しかし、見方を変えると、先祖代々の墓と刻まれた立派なお墓も都会に住む子孫にはもしかすると重荷なのかもしれない。私の知り合いも自分たちが住む関東へ墓を移す話を進めているそうだ。先祖を敬う気持ちに変りはないが、今の暮らしに見合った墓のありかたを考える時期なのかもしれない。 |
 |
| 季節によせて Vol.350 平成30年8月18日 |
| 湧水にふくらむ水面涼新た 晶 |
| 「新涼」「涼新た」は秋はじめて感じる涼しさをいう季語。立秋を過ぎても、連日35度近くの暑い日が続くとまだまだ夏の盛りのようにも思うが、夕方や夜明けに蜩(ヒグラシ)を聞いたり、赤蜻蛉が田んぼまで下りて来ているのを見かけると季節の移ろいを肌で感じることができる。湧水は地表、または河川、湖沼、海などに自然状態で湧き出す地下水のこと。 |
 |
| 季節によせて Vol.349 平成30年8月4日 |
| 陸の灯のしだひに低く納涼舟 晶 |
| 納涼(すずみ)とは、夏の暑さを逃れて、屋外や水の近くなどに涼を求めること。夕方、縁台に座って将棋を指したり花火をした昭和の光景が懐かしく思い出される。今ほど過酷な暑さでもなかったため、水を打ったり、風鈴を吊るすなど工夫して涼しさを演出する楽しみもあったように思う。「納涼舟」は川や海に出て涼しさを得ようとするもの。昨今では昔ながらの屋形船の他、○○湾星空クルーズなどと称して夜の海へ出て夜景を楽しむというツアーもあるようだ。 |
 |
| 季節によせて Vol.348 平成30年7月31日 |
| 波の裏よりサーファーの立ちあがる 晶 |
| 以前、ハワイへ行ったとき、せっかくだからとサーフィンのメッカのノースショアへサーフィンを見に行った。私には結構な波と思ったが、ビッグウェーブとよぶような波は冬にしか現れないそうだ。地形や風などいろんな自然条件が整ってサーファーたちの待ち望むビッグウェーブが生まれるのだろう。足のつかないところは危険だと思っている私には砂浜のビーチパラソルからの眺めがもっともよい。 |
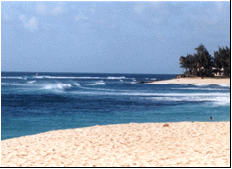 |
| 季節によせて Vol.347 平成30年7月21日 |
| あとがきのやうなひととき夕端居 晶 |
| 夏の夕方、家の中の暑さを避けて涼を求めて縁側や窓辺近くに出て寛ぐことを端居(はしい)という。冷房などがない頃、夕方には庭に打水をして蚊遣りを焚いて団扇を使いながら縁側で涼んでいるのが日常だった。最高気温が連日35度を超すような時代の若い人にはそんな涼み方など想像もつかないことだろう。今年も5月の長期予報で早々と猛暑が予想されている。夏本番の暑さはまだまだこれからも続く。 |
 |
| 季節によせて Vol.346 平成30年7月13日 |
| 露天湯につかり万緑あふれしむ 晶 |
| 昨今の秘湯ブームで地元の人しか知らないような温泉地も都会から訪れる若者たちで混み合っていると聞く。川に湧き出す湯を石で堰き止めたりしてなかなか野趣あふれるものらしい。そこまでこだわらなくて、温泉地の露天湯などでも鳥の声を聞いたり風に吹かれながら緑豊かな自然を堪能できる。アルカリ泉、炭酸泉など温泉ごとの効能もあるだろうが、ゆったりとお湯に浸ることで身も心も開放できるのが温泉の一番の利点かもしれない。 |
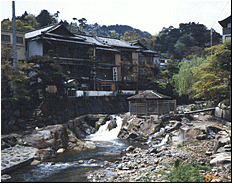 |
| 季節によせて Vol.345 平成30年7月7日 |
| 藺の花や一重まぶたのものもらひ 晶 |
| 藺草(いぐさ)は湿地に生える多年草だが、畳表の材料として水田でも栽培される。稲には葉があるが藺草の葉は退化して茎の下の方に鞘状のものがあるだけで、1メートルほどの細い茎を立てる。5,6月ごろ茎の上部に緑褐色の小花をつける。和室で畳の需要が多かった時代には炎天下に青々とした藺草を刈取り作業はさぞかし重労働だっただろう。藺の花の咲く頃は埃っぽくて目の病が多かった。 |
 |
| 季節によせて Vol.344 平成30年6月30日 |
| もう覚めていさうな気配籐寝椅子 晶 |
| 籐の茎や皮を細く剝いで編んで作ったものが籐椅子。ひやりとした肌触りで見た目にも涼しげなので夏の調度として風の通るところに置かれていたりする。何のドラマだったか、機嫌を損ねて籐寝椅子に横になっている父に娘が声を掛けるシーンがあった。画面には父親の背中しか映らないのだが、籐寝椅子のわずかな軋みで父親の心情まで伝わってきたのを覚えている。蒸し暑い日本の夏には見た目の涼しさも欠かせない。 |
 |
| 季節によせて Vol.343 平成30年6月16日 |
| 紋様の水より淡き薄ごろも 晶 |
| 真夏用に薄絹の絽(ろ)や紗(しゃ)で作った単衣を羅(うすもの)という。蝉の羽のように薄くて透き通っていることから「蝉の羽衣」とも呼ばれる。現代では着る機会も少なく日常着としては高価なため、茶会など何かの催し物でしか見かけない。汗ひとつ見せずに、羅を涼しげに着こなしているご婦人を見かけると不思議と一瞬でも暑さを忘れる。翅のように透けて見えるという視覚効果もあるのだろう。 |
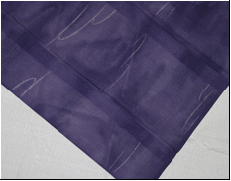 |
| 季節によせて Vol.342 平成30年6月9日 |
| 抽斗を小箱で仕切り梅雨ごもり 晶 |
| 包み紙でも小箱でも、最近は捨てるには惜しいと思われる製品が多い。かといって何でもとっておけるほどの収納場所もないので、仕切として使えそうなものだけ取り置くことにしている。しかしながら、美しい小箱で仕切って物がきちんと収まっているのは初めだけで、引きだしの中はすぐにごちゃごちゃになってしまう。私の場合は思うに使い勝手よりも箱でいかに仕切るかを優先していることが問題のようだ。
(抽斗:ひきだし) |
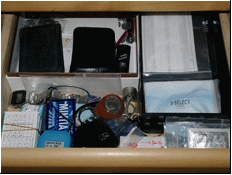 |
| 季節によせて Vol.341 平成30年6月2日 |
| 星涼し水ある星の暮らしかな 晶 |
| 2015年7月、NASAは地球から1400光年離れたところに液体の水が存在する可能性がある惑星「ケプラー452b」を発見したと発表し、天文ファンばかりか一般人にも宇宙への夢を抱かせた。当たり前のように使っている水が実は生命誕生には欠かせないもの、この先「地球のいとこ」と呼ばれるこの星に水が発見されたら、次は何らかの生命体の存在が発見されるかもしれないと次々興味がわいてくる。星を見上げて空想を膨らませてみるのも楽しい。 |
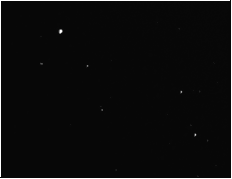 |
| 季節によせて Vol.340 平成30年5月25日 |
| 草木もて染める絹糸風薫る 晶 |
近道路を挟んであった幼稚園が山の方へ引っ越したときのこと。花芽を付けた桜や藤、椿がばさばさ伐られて山積みにされている。もう少しすればきれいに咲くのにと思うと何とも胸の痛む光景だったのが忘れられない。友人が以前、梅の樹皮で染めたという着物の話をしていたのを思い出し、伐採作業の人に桜の枝をもらって持ち帰った。樹皮を煮だし、布を染め、色を定着させるために媒染液に浸す。
同じ桜の樹皮で染めても媒染液を変えると違う色に染め上がった。幼稚園の跡地には住宅が立ち並び景色も一変したが、毎年楽しませてくれていた桜は私の帯揚げになって今でも身近にある。 |
 |
| 季節によせて Vol.339 平成30年5月19日 |
| 刈時を雨にじらされ麦の秋 晶 |
近くに大きな車の会社がある町だが、それでもまだまだのどかに麦畑が広がる。
麦畑の上空で声を降らしていた雲雀もどこかへ行ってしまったようで刈り取りを間近にした麦畑を掠めるように、燕が飛び交う。道を隔てた水田の泥を狙っているのだろう。生産調整がされているのか、以前ほど麦の後は米作りという二毛作は少ないが雨の季節の前に麦を刈り取りたいらしく、兼業農家のお父さんたちは会社を休んでコンバインを操作している。AIの技術が発達して天候の予測はできても作物の成長は人間の思い通りにはいかない。 |
 |
| 季節によせて Vol.338 平成30年5月12日 |
| 雲厚くなりし憲法記念の日 晶 |
| 憲法記念日は現行の日本国憲法が施行された昭和22年5月3日を記念する国民の祝日である。国民主権、民主主義、平和主義に基づく国のあり方について思いを馳せる日でもあるだろう。国際情勢が変わっているのだからとか、アメリカに押しつけられた憲法だからとか、憲法改正を唱える向きも多くなっているようだが戦争に加担するようなことは絶対避けなければならないと思う。悲惨な戦争体験を語ってくださる方が年々減っていくが、貴重な話は受け継がなければならない。 |
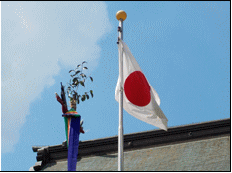 |
| 季節によせて Vol.337 平成30年4月28日 |
| 着陸の体勢芽吹き山かすめ 晶 |
空港近くに住む人の中には飛行機の離発着時の騒音を耐えがたいと感じている人も多いのではなかろうか。以前、仲間と植物園を吟行していた際、思いがけない轟音がして真上を飛行機が通過していった。植物園の真上が飛行コースだったとは思いもよらなかったのでびっくり。まさに山をかすめるように飛ぶ飛行機の音とその大きさに目を丸めた。
市街地の空港は便利だけれども騒音や危険と隣り合わせ。沖縄や基地のある町の人々の心痛が頭をよぎった。 |
 |
| 季節によせて Vol.336 平成30年4月21日 |
| 房よりも木洩れ日揺れて藤の昼 晶 |
| 藤は山野に自生する蔓性の落葉木で、他の木や岩などに巻きついて高く這い上る。公園などでは棚を作り一メートルに余る長い花房を垂らす見事な藤棚もある。蔓は適当に巻いているのかと思いきや,左巻きの山藤系と右巻きの野田藤系に大別されるらしい。左巻きや右巻きはがんじがらめのところもありわかりにくいかもしれないが、花房の長さでいうと10~20センチと短い方が山藤だそうだ。 |
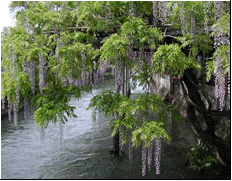 |
| 季節によせて Vol.335 平成30年4月14日 |
| 一斉といふ贅尽くし花吹雪 晶 |
| 「落花」は桜の花にかぎっての季語。ひとひらずつ静かに散るのもよいが風にいっせいに散る様も美しい。「散る桜、花吹雪、桜吹雪、飛花、花散る、花屑、花の塵、花埃、散る花、花の滝」など散りざまのありようを表現する傍題も数多い。「初桜」「初花」「彼岸桜」「枝垂桜」「桜」「花」「山桜」「八重桜」「遅桜」「落花」「花筏」「残花」「桜蘂降る」、咲き始めから散るまでこんなにも季語の多い花は桜をおいてほかにはない。 |
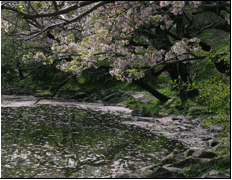 |
| 季節によせて Vol.334 平成30年4月7日 |
| 囀りや嘴のかたちの注ぎ口 晶 |
| 春になると小鳥たちは繁殖期を迎える。その頃の鳴き声を囀りと言い、求愛や縄張りをを知らせるものだと聞く。早春の鶯に始まって雲雀、頬白と鳴き出す。地鳴きだけだったものが急に姿を現し高い梢などで美しい声で鳴き出すのを聞いているとこちらまで浮き浮きした心持だ。急須の注ぎ口まで鳥のくちばしのように見えてきた。 |
 |
|
|