|
|
| 季節によせて vol.283 平成29年3月25日 |
| 逃げ水の逃げ足速き滑走路 晶 |
| 晴れた日、降ってもないのに路面が濡れて見えたり、水たまりがあるように見えることがある。そして、水だと思って近づくと逃げるように遠ざかっていくような現象を逃げ水、または偽水面、地鏡という。逃げ水を追いかけて速く走れば速く遠のき、後ろを振り返れば後ろに現れ近づくのを待っているようでもある。空気の温度差による物理的な現象といえばそれまでだが、感情移入したくなる季語である。 |
 |
| 季節によせて vol.282 平成29年3月18日 |
| 鳴く前に売れてしまひぬ鶯餅 晶 |
| 和菓子は季節感を何より大切にする。寒さにかまけて家の中ばかりに居たため、鶯の初音を聞きそびれ、鶯餅も食べそこねた。その「鶯餅」だが、諸説ある名前の由来の一つが、大和郡山の城主であった豊臣秀長が秀吉を招いた茶会で粒餡を餅で包み黄な粉をまぶした菓子を献上したところ、大いに気に入った秀吉が「以来、この餅を鶯餅と名付けよ」と言ったという話。天正年間(1580年代)のことだそうだが、やはり鶯の季節であったのだろう。現在、店頭に並ぶのは1月末から2月上旬。 |
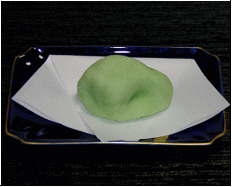 |
| 季節によせて vol.281 平成29年3月12日 |
| 外海の波の輝き卒業歌 晶 |
| 穏やかな海を見て育った者には、外海の波の荒さは脅威だった。浜に寄せて来る波に足を掬われ引っくり返ってしまったほど。隆起した崖、それを侵食するように打ち寄せる波とその飛沫。内海のひねもすのたりのたりの波とどうしたらこうも違うのか。島影など一つも見えず、沖合は潮の色さえ異なり、その遥か彼方には水平線が光る。果てしない海原に、どこまでも行けそうな期待と頼るものがない不安を覚える。未知への旅立ちは心のエンジンを全開にして。 |
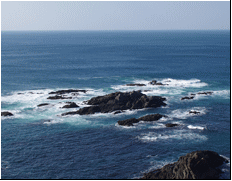 |
| 季節によせて vol.280 平成29年3月4日 |
| 啓蟄や穴一列のハーモニカ 晶 |
小学一年の音楽の時間に先生の手ぶりに合わせて、吹く(ド)吹く(ド)吸う(レ)吸う(レ)吹く(ミ)吹く(ミ)吸う(レ)と練習したことを思い出す。(ドミソ)は吹いて、(レファラシ)は吸って音を出すため、曲によっては頭がくらくらしそうになることも。近年はブルース用、ジャズ用、クラシック用など、演奏しやすく改良が施されているそうだが、内蔵される金属のリードを息で振るわせて鳴らすという構造は同じ。
啓蟄(けいちつ)の「蟄」は隠れるとか、閉じこもるの意味。二十四節季の啓蟄は冬籠りをしている虫たちも這い出るという意味で、太陽暦では3月5日ごろに当たる。 |
 |
| 季節によせて vol.279 平成29年2月26日 |
| 上澄みに紛れてしまひ薄氷 晶 |
| こんな鉢に張る氷でも厚いときには猫が載っても割れなかったほどだが、さすがに2月も末になると凍らない日も珍しくない。そんな日は、じっと身を潜めていた金魚や目高が水中の日だまりへ出てきて緩やかに尾鰭を動かして春が近いことを感じさせてくれる。枯れたように見える水草にも粟粒ほどの芽らしきものが育っているようだ。あー心底、本物の春が待ち遠しい。 |
 |
| 季節によせて vol.278 平成29年2月18日 |
| 海苔篊を挿すや手探り足探り 晶 |
| 海苔の養殖は日本特有の技術で、江戸時代に東京湾ではじめられたそうだ。秋、海水温度が20度前後のころ、海苔篊を設置して海中に浮遊する胞子を付着させる。胞子は発芽、成長して幼海苔になり、さらに胞子を発生しながら寒くなるにつれ葉状に成長する。これを収穫。栄養塩類を多く含み潮の干満の差が少ない静穏な浅海が適所と百科事典マイペディアにある。浅い海とはいえ、一本一本竹を挿していくのはさぞかし大変な作業だろう。艶々の海苔を遠火に炙りながらご苦労を思う。 |
 |
| 季節によせて vol.277 平成29年2月11日 |
| 水飲んでこめかみ疼く寒戻り 晶 |
| 暦の上とはいえ、もう春なのにと思うからいっそう、この寒さが堪えるのかもしれない。日増しに日差しは眩しくなり日脚は伸びているのに、頬や耳に触れる空気はあいかわらず刺すようで痛みさえ覚える。おしゃべりな口だって寒さで舌が思うように回らない。寒中の水は冷たく清らかなので、神秘的な効力があるとされ昔から薬にもなるといわれているが、こう寒いのでは、白湯にでもしなければ体の芯まで冷えてしまいそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.276 平成29年2月4日 |
| 旧正や焼玉弾む舟溜り 晶 |
| 海がまだ近かった頃、ポンポンポンと言う舟の音が夜明けの町に響き、浜は地物の魚の水揚げで活気があった。祭や行事も旧暦で行われたり、歳を聞けば当然のように数え年で答えてくれる年配の人も少なくなかった。たかだか半世紀ほどの間に、沿岸の海はどれほど埋立が進んだのだろうか。漁師さんたちはどんな仕事に変わられたのだろうかと思いながら、車を走らせていると思いがけず昔ながらの漁港に出会うことができた。 |
 |
| 季節によせて vol.275 平成29年1月28日 |
| 煮凝や母の知らざる子の時間 晶 |
| 煮魚を一晩おいておくと魚ごと煮汁が固まるが、これを煮凝という。鯛、鰈などを煮て流し箱に入れて固めたりもするが、寒中の鮒は特に美味と聞く。ゼラチン質のそれが舌にとける味わいは格別で、お酒が飲めて幸せと思うひとときだ。昔の家は寒く、冷蔵庫などに入れなくても、夜の片づけ物が終わり床に就くころには鍋の中で容易に煮凝になっていたような気がする。親たちが先に寝た後、勉強はそっちのけでオールナイトニッポンや短波放送を聞いていた。 |
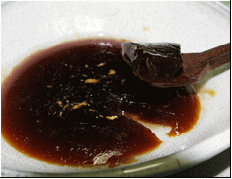 |
| 季節によせて vol.274 平成29年1月21日 |
| 寒泳や近づけぬほど火を焚きて 晶 |
| 寒泳とは、川や海で一定の形式の下に距離泳ぎを行ったり、古式泳法にのっとった泳法を披露したりすることで、心身の鍛練と水泳の技術を示す寒中の行事である。当地でも、お城の下の川で成人を迎える若者を先頭に水泳教室の子供たちがが泳いだり、古式泳法が披露されたりする。河原では、士気を鼓舞するかに和太鼓が演奏され、焚火が行われる。泳ぐ者は勿論だが、見ている方も吹きっさらしの河原ではじっとしていられないほど寒い。燃え上がる火を遠巻きにしながら子供たちの元気を分けてもらう。 |
 |
| 季節によせて vol.273 平成29年1月7日 |
| 子に広く父には深き初御空 晶 |
思いきり伸びをして空を広いと思った。入道雲や飛行機を見て空は高いと感じた。そして、満天の星空を見て底なしに見える空を少し怖いと思った。同じものを見てもその時々で見方や感じ方は異なってくる。新しい年、60をいくつか越したが、五感をフルにはたらかせて気持ちだけは若々しくいよう。
「初御空(はつみそら)」は、元日の空のこと。しだいに明けていく空にはいかにも清新な気が満ちている。今年もいい年になりますように。 |
 |
| 季節によせて vol.272 平成28年12月24日 |
| 寺々の音を違へて除夜の鐘 晶 |
| 除夜(大晦日の夜)の夜半、正子(ね)の刻に諸方の寺々で百八煩悩を除去する意味で108回撞く鐘。では、百八煩悩とは何か。眼、耳、鼻、舌、身、意の六根におのおの好・悪・平の三を数え、この十八類に浄・洗の二つがあり、さらにこの三十六類を三世に配当して百八とするという説と、一年の十二月・二十四節季・七十二候の数の和という説がある。よくわからぬが、鐘を撞いて煩悩を打ち消そうと言う風習は日本だけのものらしい。いずれにせよ、心静かに新しい年を迎えるにふさわしい音のように思われる。 |
 |
| 季節によせて vol.271 平成28年12月18日 |
| 湯気もまた脂じみたる薬喰 晶 |
今ほど、肉食が当たり前ではなかった頃、寒さに備える体力をつけるために滋養のある鳥獣の肉を薬と称して食べていた。確かに薬喰といえば聞こえも良く罪悪感も軽減したのであろう。
以前、句会の仲間と評判の店へ猪鍋を食べに行ったことがある。猪垣を廻らせた山を見た後、くだんの店へ。何でも知りたがりの客と思ったのか、店主自ら、目の前の山で今朝捕れた猪です、血を抜く池ですと親切に説明してくれた。いささか食欲は失せたものの、独特の臭みもなく、美味しくいただいた。「いただきます」の挨拶が「命をいただきます」につながることに思いをいたしながら。 |
 |
| 季節によせて vol.270 平成28年12月12日 |
| 紙漉きの水かたときも休ませず 晶 |
| 私たちが日頃使っている紙の多くは製紙会社でパルプや古紙を原料に作られているもので、たとえば2014年のデータでは日本の国民一人あたりの紙・板紙消費量は215.1kg(世界平均は56.8kg)にもなるそうだ。この句のような紙梳きの和紙は原料の楮(こうぞ)の刈取りに始まり、蒸し,皮はぎ、乾燥、晒し、塵とり、こうかい(叩き)、ざぶり(とろろを加え掻き混ぜる)などいくつもの手順を踏んでようやく紙を漉くという実に手間暇のかかる仕事。洋紙、和紙どちらも山の木が原料、大切に使いたい。 |
 |
| 季節によせて vol.269 平成28年12月2日 |
| 綿虫の綿逆立てて飛びたてり 晶 |
| 晩秋から初冬にかけて、曇りがちの日や夕方に青白い綿を持って飛んでいる虫を見かけることがある。それが綿虫。初雪のころに現れるので北国では雪虫とか雪婆(ゆきばんば)と呼ぶことも。眼の高さあたりをふわふわと飛ぶので容易にとらえることができる。子供のころ、湿気を帯びれば綿が萎んで飛べなくなるかと掴まえた綿虫に息をかけたことがあるが、何の問題もなかったように綿を膨らませて掌から飛び立った。一部は雌もいるが翅のあるのはおおかた雄。 |
 |
| 季節によせて vol.268 平成28年11月26日 |
| 初霜の星追ふやうに消えにけり 晶 |
| その冬、初めて降りる霜が初霜。冬が早い北海道などでは10月上旬にはすでに観測されることもあるようだが、本州半ばの当地では12月初めごろか。早朝、庭の落葉や草の葉に霜が降りているのを目にするが、日が昇り始めると朝露であったかのように消えてしまう。寝坊などしていては出会えないのが「初霜」である。ちなみに、百人一首に、初霜が置きまどうような白菊を詠んだ歌がある。「心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花 躬恒」 |
 |
| 季節によせて vol.267 平成28年11月20日 |
| 水を出て鳥の歩める小春かな 晶 |
鴨や雁、鴛鴦(おしどり)が渡ってくると川などの水辺が急に賑やかになる気がする。彼らは燕のように卵を孵(かえ)したり子育てをすることもないので、日本各地本の越冬地で餌を食べ、ゆったり浮寝を楽しんでいるように見える。(実際には違うのかもしれないが)
ところで、水鳥の脚の蹼は、泳ぐときには水を掻く用をはたすものの、陸上を歩くにはペタペタとなんともぎこちなく歩きにくそうに見える。 |
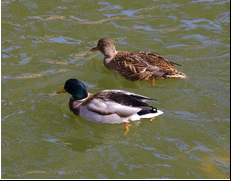 |
| 季節によせて vol.266 平成28年11月14日 |
| 咲き残るものみな小ぶり冬隣 晶 |
| 11月は「晩秋」と「初冬」の二季が入り混じる月。木枯らしが吹きぐっと冷え込む日があるかと思えば、縁側が焦げそうな暖かい日差しの日もある。我が家でも、庭の千両が色付き始める足元で石蕗(ツワブキ)の花が黄色く咲き、その隣で盛りを過ぎた杜鵑草(ホトトギス)や秋海棠(シュウカイドウ)がまだ花をつけている。とはいっても、ピンクの秋明菊はえんじ色になってきたし、アサギマダラがしばらく来ていた藤袴は絮(ワタ)になりはじめた。ゆっくりとではあるが、確実に冬の足音が大きくなりつつある。 今年の立冬は11月7日、22日ははや小雪である。 |
 |
| 季節によせて vol.265 平成28年11月8日 |
| 釜の底よりかきまぜて茸飯 晶 |
| 今年は雨が多かったので松茸が豊作だという話は聞いていたが、思いがけずわが家も御裾分けに預かった。香りが強いうちにと、先日見たテレビ番組のレシピを参考に炊きこみご飯と酒蒸しにして今夜早速いただくことに。レシピというほどでもないが、炊きこみご飯:裂いた松茸を沸かした醤油だしで20秒煮て取り出す。その醤油だしでご飯を炊き、炊き上がったら20秒煮た松茸を入れて混ぜる。酒蒸し:大きめに裂いた松茸に霧吹きで酒を吹きつけ軽く塩を振ってアルミホイルで包み3分蒸す。酢橘を絞ればさらに美味。行く秋を惜しむにはやはり日本酒を用意せねばなるまい。 |
 |
| 季節によせて vol.264 平成28年11月1日 |
| 寝ころびてひやりと銀杏落葉かな 晶 |
鴨脚樹、銀杏、公孫樹と書いてどれも「いちょう」と読む。中国原産の落葉高木で、葉が鴨の脚に似ることから「鴨脚」と呼ばれたと語源にはあるが、ドイツの詩人、ゲーテは銀杏の葉が二枚に裂けた形をしていることに興味を持ち、その葉は「一枚の葉が二枚になったのか、二枚の葉が相手を見つけて一枚になったのか」 とうたったそうだ。さすが凡人には及ばぬ発想!
日本には仏教伝来のころに渡来し、成長が早く火災にも強いので神社や寺に植えられたそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.263 平成28年10月24日 |
| 糸底の土のざらりと今朝の冬 晶 |
| 朝はさすがに寒く感じる日が増え、朝一番の熱いお茶が美味しい。そこで、今まで使っていた磁器の湯飲から陶器の湯飲みに替えた。磁器のようにすぐには熱くならないので、じんわりと温もりが手に伝わるし、また冷めにくいので、これからの季節は釉薬がかかった土ものの器がわが家では活躍する。糸底とは、陶磁器の底の、輪状に突き出た部分のこと。轆轤(ろくろ)から切り離すのに糸を使うことから、糸切りまたは糸じりともいう。 |
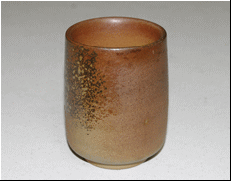 |
| 季節によせて vol.262 平成28年10月15日 |
| 船の名を四股名に島の草相撲 晶 |
| ブリタニカによると、「丸」は、日本の船名の後に付けられる語で、使われた上限は12世紀末期まで遡るとされる。一般に普及したのは室町時代以後で、小船を除いてほとんどの船が船名の後にこの丸をつけたそうだ。その由来については、諸説あるものの、目下のところでは、刀や楽器などに丸を付けたのと同様に船主が自分の所有する船に対する愛称として用いたのではないかと考えられているようだ。船の名前を見れば、持ち主がわかるというもの。 *四股名:しこな |
 |
| 季節によせて vol.261 平成28年10月8日 |
| 松手入遺愛の鋏受け継ぎて 晶 |
| 母の一周忌を済ませて半年後、父が急逝した。手入れする人がいない庭は日増しに草が生え枝は伸び放題となる。父が丹精した庭が荒れるのが忍びなくできるだけ草取りに行くのだが、とても追いつかない。作業のたびに剪定鋏や草刈り鎌を研いだのであろう、磨り減った砥石が乾ききって流しの下にあった。少し錆の浮いてしまった鋏とこの砥石も大事な父の遺品である。 |
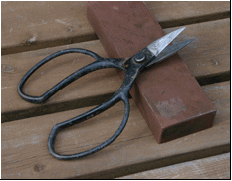 |
| 季節によせて vol.260 平成28年10月1日 |
| 母の帯締めて口上風炉名残り 晶 |
早いもので母が亡くなって丸三年が過ぎた。何事にも几帳面だったので、家事に関することや、お付き合いのことなど、聞きたいと思うことはだいたいノートに書き残しておいてくれた。
そんな母を窮屈に思ったこともあったが、妹や家人は、私の口ぶりや恰好が年ごとに母に似てきていると言う。そんなはずはないと思ってはみたものの、ふくよかだった母の着物がいつのまにか私の身に添うようになってきたし、鏡に映る姿に自分自身驚くこともある。しかし、大雑把なところだけは変りようがないようである。 |
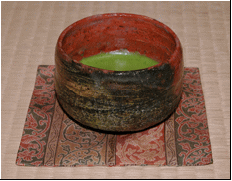 |
| 季節によせて vol.259 平成28年9月23日 |
| 咲くやうに雲のふくらむ花野かな 晶 |
| 花野とは、秋の草花がさまざまに咲き乱れた野原のこと。身近でそのような広々とした景に出会うことは少なくなったが、芒(すすき)や萩ならばまだ河川敷や公園で見られる。もともと、秋に咲く草花は小ぶりで淡い色あいの花が多いため、かたまって咲いていてもさして目立たず、蜜を求めて盛んに虫が飛び回ると言うほどでもない。夏の強烈な日差しに耐えて、楚々と花を咲かせる秋の草ぐさには心を安らかにする何かがあるようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.258 平成28年9月17日 |
| 馬跳びの先に広がり鰯雲 晶 |
馬跳びは、前かがみになった人の背中に手をついてぽんと跳び越える遊び。何人かいれば馬を連ねたり、代わる代わる馬になって遊ぶこともでき、休み時間や放課後などよくやったものだ。遊具も少なかったし、ゲームなどもなかった時代。
みんなでルールを考えながら新しい遊びがどんどんでき、多少の擦り傷やけんかも一晩たつと忘れた。還暦を過ぎても○○ちゃんと呼び合える顔が浮かぶのは嬉しいことだ。 |
 |
| 季節によせて vol.257 平成28年9月10日 |
| 絹扇切り出しにくきこと一つ 晶 |
| 誰しもなかなか言い出せない事の一つや二つはあるのではなかろうか。顔や態度に出やすい私などはすぐに様子がおかしいと気付かれて、言いだす前に白状させられてしまう。世間話をするように自然にきっかけを作り、波風をたてず穏便にスムーズに事が運び、いつのまにか話がまとまっているというのが理想だが、そんなにうまくいくはずもない。汗を拭き拭き、扇子を開いたり閉じたりしながら、話を切り出すタイミングをはかるのである。 |
 |
| 季節によせて vol.256 平成28年9月3日 |
| 新涼や一度で決まる帯の位置 晶 |
| 涼しいうちにと思って、朝早くから着物を着始めても、真夏ばかりは着終る頃には汗が流れる。絽など薄手の着物は滑りが良すぎるし、羅や、絽の帯は締め加減が難しくなかなかしっくりこない。もともとは母の寸法で仕立てたものを譲り受けて着ているのだからぜいたくは言えないのだが、本音を言うと夏の着物は大変だ。実際は暑いのだけれど、見た目は涼しげでなければと思うと、支度するときから気合が要るのである。 |
 |
| 季節によせて vol.255 平成28年8月27日 |
| 向日葵の頭に水をあびせかく 晶 |
| 向日葵はキク科の大型の一年草。北アメリカ原産で日本には300年ほど前に伝えられた。茎は直立して2メートル以上にもなり花の直径は20から40センチもある大型のもの。近頃は矮性化された園芸品種の向日葵も見かけるようになったが、やはり夏を代表する花だ。この丈夫そうに見える花も、炎天に立ち尽くしているのを見ると、頭から水をかけて暑さを忘れさせてやりたくなる。ちなみに、太陽に向かって回ると言われているが、これは蕾の時だけの習性らしい。朝は東向き、夕方は一斉に西向きの向日葵もまだ見たことはない。 |
 |
| 季節によせて vol.254 平成28年8月17日 |
| 湖に影を浸して夏木立 晶 |
| 夏木立とは夏になって枝枝を伸ばし青葉を茂らせた木々のことで、一本の木をさすのではない。この句の夏木立も湖畔に生えている白樺や岳樺が湖に映っている様子がかにも涼しげに見えた時の句である。ところで、季語としては夏木立と冬木立はあるが、春木立、秋木立という言い方はない。春は芽吹き、秋は紅葉、落葉と木の立ち姿以外の見どころがあるからかとも思うが。冬木立には冬枯れの潔さが、夏木立には生命力にあふれた活力を木から感じる。 |
 |
| 季節によせて vol.253 平成28年8月4日 |
| 棒切れを立てて鍬形虫の墓 晶 |
| 自然に接する機会が少なかったからか、甥は三十歳をすぎた今でも虫が大嫌い。その妹たちも、もちろんその母も虫が触れない。私はと言うと、脚がないのや多いのは苦手だが、昆虫の類は見るのも採るのも抵抗がなく、蝶や蝉はよく採ったし、虫籠に蜜や葉っぱを入れて飼いもしたが、大方は翌日かその翌日ぐらいには死んでしまった。ただでさえ短い一生なのにと、今から思えば、気の毒な事をした。 *鍬形虫:くわがたむし |
 |
| 季節によせて vol.252 平成28年7月30日 |
| 舟に手をかけて息継ぐ鮑採り 晶 |
| 海人漁は男性より皮下脂肪の多い女性の方が向いているとされるが、海に潜っての作業は二時間が限界の重労働。焼石や焚火で体を温めながら天草や貝を採るのである。海女には浅い海に潜る磯(桶)海女と、夫婦一組の「ととかか舟」に乗り、少し沖合に出る沖海女がいる。沖海女は、分銅を用いて沈み、腰の命綱を用いて浮上する。海に浮かべた桶に凭れて息を整える磯海女、舟縁に手をかけて息を整える沖海女、どちらも海底知識や経験がものをいう命がけの仕事だ。 |
 |
| 季節によせて vol.251 平成28年7月23日 |
| 峯雲や杓一杯の力水 晶 |
雲の峰、または入道雲ともいうが、この雲の中では1秒間に十数メートルの上昇気流が吹いており、雲の中を水滴や凍った霰の粒がたえず移動しているのだそうだ。それらがぶつかりあって放電が始まると雷鳴や落雷になると言う。
力水は力士が身を清めるのに使う水で、前の取り組みの勝ち力士が土俵上の力士に柄杓で水をすくってさしだす水のこと。縁起を担ぐ勝負の世界、一口の水を口に含むだけでも、むくむくと気力が漲ってくることだろう。 |
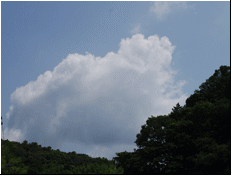 |
| 季節によせて vol.250 平成28年7月14日 |
| 来世には魚になりたき暑さかな 晶 |
| 近頃のお天気の手荒なこと。雨でも降るとなれば手加減なく底抜けに降るし、暑さも天井知らずかと思うほど。いつぞやテレビの海外番組で、インドではアスファルトが融けて履物が道路に張り付き歩くのに難儀をしているさまが映し出されていた。さすがに日本ではそこまでではないが、熱中症で救急搬送されたというニュースを聞かない日はない。水もお茶もそうは飲めないし、いっそのこと水にどっぷり浸かっているのも悪くないと思った次第。動物にも植物にも容赦ない暑さがしばらく続く。 |
 |
| 季節によせて vol.249 平成28年7月7日 |
| 一山の水しぼりこむ滝の口 晶 |
滝壺のあたりで落ちてくる滝しぶきを浴びていると、涼気満点でしばらくは暑さを忘れていられる。今では夏の季語として疑いもない「滝」だが、、芭蕉のころは夏の季語としては認められていなかったようで、「奥や滝雲に涼しき谷の声 其角」 「暫時は滝にこもるや夏の初 芭蕉」のように、他の季語が必要だった。近代になって夏の季語と定められてから、
「神にませばまこと美はし那智の滝 高浜虚子」
「滝落ちて群青世界とどろけり 水原秋桜子」
「滝の上に水現れて落ちにけり 後藤夜半」
など滝の名句が詠まれるようになった。 |
 |
| 季節によせて vol.248 平成28年6月30日 |
| 物干しは非武装地帯水鉄砲 晶 |
| 二階に張りだした物干し台。学校から帰ったいがぐり頭のわんぱく坊主が追っかけあいながら物干し台へ駆け上がり、水鉄砲に興じている。洗濯物を楯に打ち合っているうちに、おおかた乾いていた手拭や敷布がずぶ濡れ。騒ぎに気付いた母親が「ここで遊んではだめ、水鉄砲禁止!」と叱る。半世紀前には確かにあった光景が、今では、テレビのドラマでしか見られない。 |
 |
| 季節によせて vol.247 平成28年6月21日 |
| 木製の鳥のノッカー夏館 晶 |
| ノッカー(knocker)は訪問者が来訪を知らせる敲き金のことで、普通、玄関の戸についているもの。先日、防犯設備の整ったマンションを訪れた際のことである。教えられたとおり、ロビーにいるコンシェルジュに訪問先を告げ、先方に確認したうえでようやくエレベーターホールへ案内された。当然、訪問先の玄関にもテレビモニターがあり、来訪を告げる。その間およそ15分。これを煩雑と思うか否かは人によるだろうが、都会に暮らす人たちの安全に対する意識を思い知らされた。 |
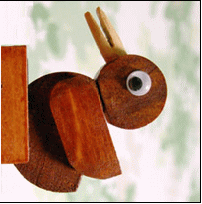 |
| 季節によせて vol.246 平成28年6月14日 |
| 葉桜の近寄りがたき枝垂れかな 晶 |
| 梅は花が散って葉が出るまでしばらく間があるが、桜は花の終る頃には葉が出はじめ六月にはすでにうっそうとしてくる。花があれば、木々の多い山中で目につくが、葉桜になってしまえば再びほかの木々にたち交じって遠くからでは見分けがつない。持統天皇お手植えという言い伝えの枝垂れ桜が近くにあり、花の頃は渋滞になるほど賑わうが、花がすんでしまえば人通りも絶え静かな山里に戻る。 |
 |
| 季節によせて vol.245 平成28年6月7日 |
| 風呂敷に包む四隅をすずやかに 晶 |
| お茶道具を扱うお店の方に風呂敷の扱いを教えていただいたことがある。大事な道具だから、まずは安全に包むのはもちろんのことだが、見た目も美しくなくてはならないと言うのである。なるほどと、じっくり手許を見ていると四隅の布を内側に折りこみきっちりと角を作り出していく。余分なふくらみもなくきちんと包まれ見た目にも美しいとなれば実践しない方はない。おかげで自慢できる数少ない特技になった。 |
 |
| 季節によせて vol.244 平成28年5月31日 |
| 明易し水道といふ海の路地 晶 |
| 「短夜」「明易し」ともに短い夏の夜を言うものであるが、明るくなり始めたことに軸足をおいた方が「明易し」と聞いた。この句の水道は海または湖などの、接近した陸地によって挟まれた狭い部分を言う。たとえば尾道水道は本州の尾道市と向島に挟まれた200から300メートルほどのまさに路地のような所。そこでは生活に直結した渡し舟や漁船が夜が明けきらぬうちから動き出すのである。 |
 |
| 季節によせて vol.243 平成28年5月24日 |
| 爪先の汚れやすくて麦の秋 晶 |
| 日本語教室で形容詞を勉強すると、留学生たちは必ずと言っていいほど「日本の空気は新鮮です」「空気はおいしいです」という。表現に違和感がないでもないが、空気がいいと言ってもらえるのはやはり嬉しく、身近に豊かな自然があるありがたさを実感する。このところの汗ばむような陽気に、黄金色になっていく麦畑。発芽率の高い麦にはカラカラ天気はのぞましいが、人にはいささか埃っぽい季節でもある。 |
 |
| 季節によせて vol.242 平成28年5月16日 |
| 宥めるがごとくに均す代田かな 晶 |
山裾の林を造成した団地から少し外れたところに小さな集落がある。地元の人の話では、長男が家や田畑を継ぎ、他の者はその土地を出て、代々、戸数を変えずに集落を守ってきたそうだ。区画整理されずに地形のなりの田は見る者には美しく懐かしく見えたが、やはり効率は悪かったらしい。大方の田は四角く形を整えられ、次の代の若い人が耕耘機で効率よく代田を掻いていた。
(宥める:なだめる、均す:ならす) |
 |
| 季節によせて vol.241 平成28年5月9日 |
| 組みかへて混じるうたかた花筏 晶 |
| 平地の桜はとっくに葉桜になったが、標高の高いところや東北、北海道の桜は連休あたりが見頃だっただろうか。開花予報に胸をときめかせ、桜前線を待ちこがれる。瑞々しい初花から花吹雪となって散るまでのほんの一週間か十日のあいだを幸せな気持ちで過ごす。水面を重なって流れる花びらを筏に見立てたのを「花筏」。うたかたは水の上に浮かぶ泡のこと。 |
 |
| 季節によせて vol.240 平成28年5月2日 |
| 蒸しパンの湯気の甘さも桜どき 晶 |
| 蒸しパンは小麦粉に重曹やベーキングパウダー、砂糖などを混ぜ、捏ねてからカップなどに入れ蒸し器で蒸したもの。食糧不足だったころには小麦の代わりに玄米、砂糖の代わりにサツマイモや栗を混ぜて代用食としていたようだが、今ではホットケーキミックスなど便利なものもあるし、電子レンジを使えば子供でも簡単に作ることができる。しかし、昔ながらの蒸籠で蒸したパンは芯まで柔らかく立ち上る湯気までが食欲をそそる。 |
 |
| 季節によせて vol.239 平成28年4月2日 |
| 黄梅や日差し一足飛びにまし 晶 |
| 冬の初めが暖かかったせいか、今年は1月の終わりには黄梅が見頃を過ぎていた。通称、ジャスミンと言われる6弁の黄色い花は枝が四方に伸び垂れるので、満開の頃には辺りがひときわ明るく感じる。花の少ない時期だけに春を呼ぶ花と呼ばれるのも納得がいく。そういえば、金縷梅(まんさく)、蠟梅(ろうばい)など、いち早く咲く花はどれもあざやかな黄色をしている。 |
 |
|
|