|
|
| 季節によせて vol.148 平成24年3月31日 |
| 城壁の石に刻印鳥ぐもり 晶 |
| ピラミッドにしろ万里の長城にしろ、今に残る石組みの技術は舌を巻くばかりだが、人手に頼るしかなかった時代、駆り出された人たちはさぞかし大変な思いをしたことであろう。名古屋城の一角に巨石に乗って石曳を指揮する加藤清正の像があるが、諸国の大名が築城にあたったのだろう。○に十の字のあきらかに島津藩とわかる印が刻まれた石もあったが、長い年月のうちに風化して○や□にしかみえないような印の石も目をひいた。 |
 |
| 季節によせて vol.147 平成24年3月24日 |
| 水底に光ひしめき水草生ふ 晶 |
| 水の底まで差し込む光が水に溶けだすというわけでもないのに、春は流れる水の音まで軽やかに聞こえる。冬の間、水に閉じ込められていたようにじっとしていた魚たちは水の眠りを覚ますかのように鰭を使い泳ぎだす。腹鰭や尾鰭が枯れてしまったかのような水草を揺らすと中に角ぐむものがかすかにのぞく。ところどころにあがる泥けむりや泡、きらめきと影、水の中がいっきに賑やかになり始めた。 |
 |
| 季節によせて vol.146 平成24年3月17日 |
| 掻くたびに大きく揺れて浅蜊舟 晶 |
| この時期の貝は身が大きくコクがあって本当においしい。ちょっと年上の海辺育ちの私の友達はまだ毎年潮干狩りを楽しんでいて、少し冷たいぐらいの潮風が最高に心地よいという。もくもくと貝を掘り、時折背中を伸ばした時のまぶしい海に何とも言えぬ春の訪れを実感するのだそうだ。生業にする漁師さんたちは大粒の貝を選別するために目の粗い篩にかけるようだが、私がいただくおすそ分けは大小実にさまざまである。 |
 |
| 季節によせて vol.145 平成24年3月10日 |
| 三椏の咲きて節目といふ別れ 晶 |
| 犬の散歩コースの途中に高校の通用門がある。鉄製の門扉で一応、鍵らしきものはあるのだが閉まっていたためしがない。私が通っていた頃には門の近くに大きな楠があったと思うのだが、整地されたときに切られたのだろう。グランドも校舎も丸見えで、たまに授業中にもかかわらず退屈そうに外を見ている子を見かけることも。今日は卒業式。賑やかな正門に比べ通用門は普段通りだなと思っていたら、珍しく花束を手に別れを惜しんでいる女の子たちに出合った。 |
 |
| 季節によせて vol.144 平成24年3月3日 |
| 桃の日の艶やかなりし鳥の声 晶 |
| 何でもよく知っている人に先日、三月は辰の月だと教えてもらった。その辰に縁の深い巳の日に災厄を祓う祓を行ったのが「上巳(じょうし)」の由来だそうだ。上巳にあたる三月三日にやはり災厄を払うとされる桃の花を飾り女の子の健やかな成長を願ったというのがひな祭りの始まりらしい。何回目かの年女、辰年生まれの母は今年は父にお雛様を飾ってもらったと上機嫌だった。よい厄払いができて今年も元気ですごしてもらいたい。 |
 |
| 季節によせて vol.143 平成24年2月25日 |
| 北窓を開く雀に促され 晶 |
| うんざりするほど雪が残っている雪国でも空の明るさと日差しは春が近づいていることを感じさせる。「北窓開く」という季語は冬の間、寒気や風を塞ぐために閉めきってあった北側の窓を、春の気配が感じられるのを待って開け放つという意味がある。窓を開けて風の通り道を作ると、冷たい空気がさあっと家の中に入ってくる。一瞬ぶるっとはするが、冬の間のよどんだ空気が一掃されるようで体や心までしゃきっとする。 |
 |
| 季節によせて vol.142 平成24年2月18日 |
| おはじきのごとき島影瀬戸の春 晶 |
| 今年の大河ドラマは「平清盛」。今までのドラマになかった清盛の描き方に毎回どんな展開になるのかと楽しみになってきた。12日(日)の放送は瀬戸内海に跋扈する海賊を討伐するという話だったが、瀬戸内海がすでに国内だけではなく、外国との文化や物流の大切な航路となっていたことがわかりおもしろかった。大小3000と言われる島が点在する瀬戸内海。海賊や水軍の根城や舟隠しになりそうな島がいたるところにありそうだ。当時、航海した人々にとってはこののどかな風景も気を抜けない恐ろしい所だったのかもしれない。 |
 |
| 季節によせて vol.141 平成24年2月11日 |
| 初午の匂ふばかりの幟かな 晶 |
| 「向こう横丁のお稲荷さんに一銭上げて、ざっと拝んで」云々、という唄をご存知の方もいるだろう。途中の歌詞は忘れたが、「とうとうトンビにさらわれた」で終わる唄だ。油揚げをお供えするお稲荷さんの二月最初の祭礼が初午。京都の伏見稲荷大社の鎮座の日にちなむと言われている。商売繁盛や開運を願って朱色の鳥居や幟も数多く奉納されており、立ち並ぶ艶やかな色に目を奪われる。五行思想で「火」にあたる「赤」の幟が焔のようになびく様を見ているだけで活気を感じ、運気上昇間違いないという気分になる。やはりお稲荷さんは庶民の神様のようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.140 平成24年2月4日 |
| 葉牡丹の芯せり上がる日和かな 晶 |
| 青汁ケールの仲間である葉牡丹をあのように品種改良したのは、やはり凝り性の日本人だった。江戸時代に渡来したころの原種はどんなものであったか知らないが、葉だけ鑑賞する植物を、赤紫色系と白色系、波状に襞のある葉が縮れる縮緬系、葉の縁に襞のない丸葉系と切葉系、花壇用、切り花用と次々に改良したのだからたいしたものだ。花の少ない時期、種類や形状の違いを利用した植栽のデザインに目を奪われることも。しかし、キャベツの仲間の悲しさ、やがて日ごとに暖かくなる日差しに芯がゆるみ大株が傾き始めると苦心のデッサンも乱れてくるのである。 |
 |
| 季節によせて vol.139 平成24年1月28日 |
| 波畳よりもたひらか牡蠣筏 晶 |
| 山や森がないとよい漁場は育たないと、近頃は漁業に携わる人たちが里山の植林に乗り出しているらしい。養分を含んだ水が海に入りプランクトンを育て美味しい海産物を育てるのだろう。今日の新聞に、震災後に入れた牡蠣が震災前の三分の二まで生産が回復しそうだという東北地方の漁師さんの話があった。親父を奪った海だけど海は銀行、預ければ金になる。立ち止まってなんかいられないという言葉が印象的だった。 |
 |
| 季節によせて vol.138 平成24年1月21日 |
| パイプオルガンさながらに滝氷柱 晶 |
| 瀬を落ちる水はしぶきを、目もくらむような高さを落ちる水は水煙をあげる。声をかき消さんばかりの大音響で落ちていた滝の水も、岩さえ凍るような寒さにすっかり凍りつき鳴りをひそめている。まるで礼拝堂で静かに控えているパイプオルガンのようだ。氷柱と化した滝が水の音を封じ込めてたパイプのようで、解けた時の水量豊かな滝の音まで聞こえるようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.137 平成24年1月14日 |
| ぬかるみの筵踏みしめ初詣 晶 |
| ロープウェイに乗って四国霊場雲辺寺へ行った時のこと。寒いとはいえ、下では雪などなかったのに山頂は雪でつるつるに凍っていてまともに歩けたものでなかった。正月早々転んでは縁起でもないと、腰を落としながら歩いていくと、雪でぬかるんだ参道に筵(むしろ)が敷きつめてあった。雪を被っている羅漢さんをみると山の上はかなり降ったようだが、そんななかでの参拝者への心遣いをありがたく思った。 |
 |
| 季節によせて vol.136 平成24年1月7日 |
| 新暦良きこと三百六十五 晶 |
| 真新しいものは普段使いのものであっても気持ちが良い。とりわけ、何でも書き込む私には暮にいただく書き込み式のカレンダーはこの上なくありがたい物。表紙を切り取りたい気持ちを抑えて行儀よく並ぶ日にちを見ていると、なんだかどの日も良いことが待っていそうな気がする。捲るとインクのにおいがするカレンダー、今年もみんなが健康で、楽しいことで埋められる年になりますように。 |
 |
| 季節によせて vol.135 平成23年12月31日 |
| 国宝の音を惜しまず除夜の鐘 晶 |
| 夫の父が健在だったころ、年が明けて一番初めに行くところは菩提寺だった。私たち家族だけなのに住職がお経をあげてお話をしてくださった。お経の本が全員に渡され、何ページと言われるところを一緒に唱える。いつだったか、お参りの後で住職が、この頃は除夜の鐘を撞くのに数がわからなくなるので金平糖を並べることにしましたとおっしゃり、子供たちにその金平糖を分けて下さった。父が亡くなって伺わなくなったが、まだ金平糖で数を数えていらっしゃるのだろうか。 |
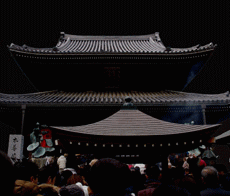 |
| 季節によせて vol.134 平成23年12月24日 |
| 天辺に月の待ちゐる冬至の日 晶 |
| 冬至は北半球では昼の長さが最も短い日。たださえ用の多い師走、すぐに暗くなる日がうらめしくよけい気忙しい思いがする。緯度の高い北欧では、新しい太陽の誕生日として冬至を祝うそうだが、喜びもひとしおだろう。民族や宗教が違っても、冬至に太陽の復活を祝う祭は今も盛んにおこなわれているようで、家の入口には冬でも生命力を感じさせる青々とした葉を飾るということだ。 |
 |
| 季節によせて vol.133 平成23年12月17日 |
| 米蔵も金蔵もなく実千両 晶 |
| 枯れがすすむ季節の赤い実はとりわけ目をひく。正月用の切り花として有名な「せんりょう」は「仙蓼」 より「千両」と書くほうが馴染みがある。夏、見落としそうな黄緑色の花をつけ時雨の季節に真っ赤な実を結ぶ。茎の上にあるのが千両、重そうな少し黒みがかった実が葉の下にあるのが万両。では、藪柑子はと聞くと、百両、十両、はては一両と言う人も。我が家の千両は場所が悪いのか、まだ一両も実をつけてくれない。 |
 |
| 季節によせて vol.132 平成23年12月10日 |
| 軽々と日を押し上げて枯木山 晶 |
| 青葉台、桜台‥、里山は開発されると、昔からの地名は消えて何となくしゃれた名前の団地になってしまう。私の住む所もそんな町の一つ。こんもりとした山があると思えば寺領か小さな社がひっそりとあったりする。里人が手を入れて薪を拾ったり茸を取りに入った美しい里山がなくなってしまったら、獣や鳥たちがすみかを失うばかりでなく私たちにも住みにくい所になってしまうだろう。枯木立となった雑木山にはたっぷりの光が差し込む。ふかふかの落葉は大切な山の肥やしだ。 |
 |
| 季節によせて vol.131 平成23年12月3日 |
| 山茶花や料紙にかなをちらしがき 晶 |
| 今春、父と叔母が書と刺繍の二人展をひらいた。叔母が誘ってくれた時にはまったくその気がなかったようだったが、積極的な叔母と面白がりの子供たちに乗せられ、どんどん話が進み、ついには今まで書き溜めた作品集を作る話にまで発展。軸装したり、額に入っているのを広げたり外したりしながら写真に撮り、なかなか立派な冊子に仕上がった。勢いのあるのが父の書体と思っていたのに、思いがけず優しい仮名文字にも出合って新鮮な驚きだった。 |
 |
| 季節によせて vol.130 平成23年11月26日 |
| スピーチを文字に起こして憂国忌 晶 |
| なんの会議だったか録音したテープを文字に起こすのを手伝ったことがある。何度もテープを止めながら再生するが、雑音が大きかったり、イントネーションの違いで聞き間違えたりと、大変な思いをした。国会中継などでも必ず速記者が映るが、何分かごとに交代している。緊張はそんなに続かないということだろう。ところで、答弁の議員さんはというと、事前に用意された答弁書を顔も上げずに読んでいる光景をよく見かける。 |
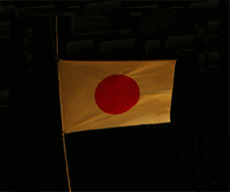 |
| 季節によせて vol.129 平成23年11月19日 |
| 秤よりはがす鮃の尾鰭持ち 晶 |
| 帰省の楽しみの一つはおいしい魚を食べること。魚屋さんから、生きのいいのが入ってるよなどと言われると、こちらが一本釣りされてしまう。おかげで子供たちまで鰈は煮つけ、鮃はえんがわのところが美味しいなどと一人前の口をきくしまつ。たしかに鮮度のよい魚は刺身はもちろんだが、煮ても焼いても身が反り返り、身離れが格段に違う。ねっとりと秤に張り付くほど新鮮な鮃の刺身が早く食べたい。 |
 |
| 季節によせて vol.128 平成23年11月12日 |
| 堰の水まつすぐ落ちて冬に入る 晶 |
| 国の天然記念物の高野槇を甘泉寺へ見に行った。台風で折れた姿は痛々しかったが、残った枝がたくましく枝を茂らせていた。台風の被害は思いのほか大きく、不通となった道路を迂回して住民は倍の時間をかけて隣町へ用足しに出るのだそうだ。濁流が押し流した爪痕は深いが、流れにはもはや堰から躍り出るような勢いはない。帰りに友人の住職夫人から、折れた高野槇で作った念珠のブレスレットをいただいた。数珠を繰るたびに高野槇の何とも良い匂いがする。 |
 |
| 季節によせて vol.127 平成23年11月5日 |
| 黄金の国ジパングの銀杏散る 晶 |
日本における金箔の一大生産地は石川県金沢市。
漆器や仏壇の生産地が近いということもあるのかもしれないが、日本の総生産量の98%を占めるそうだ。おもに仏像や工芸品に使用される金箔も、近頃は日本酒や和菓子、洋菓子などの食品分野や栄養クリームやエステなど美容分野にも用いられているようだ。金粉のふりかけまであることを知ったらマルコポーロは何というだろう。 |
 |
| 季節によせて vol.126 平成23年10月29日 |
| まなざしの先にひろがり秋の雲 晶 |
| 秋の雲の代表的なものとして、鰯雲、鯖雲があるが、一刷毛の薄い絹のような筋雲が流れるように過ぎるのも秋ならではの光景。早朝、高原にかかっていた霧も日が昇るにつれて消え、遠くまでくっきりと見渡せるようになる。上空には速い風があるのか、雲がどんどん形を変えながら流れていく。仰向けになって見ていると舟にでも乗って海原を漂っているような気がする。 |
 |
| 季節によせて vol.125 平成23年10月22日 |
| 熟考のさなか胡桃を握りしめ 晶 |
NHKで向田邦子さんの「胡桃の部屋」を見た。リメイクされた今回の作品の母親役は竹下恵子さんだったが、生々しい母親役には先回の加藤春子さんのイメージの方があっていたような気がする。「胡桃割る胡桃の中に使はぬ部屋 (狩行)」
無駄と思えるようなものも、その意味に気付かないだけで、必要なものなのかもしれない。何でも一途に考え込まないで、うまく気分転換しなくてはなるまい。 |
 |
| 季節によせて vol.124 平成23年10月15日 |
| 引幕を開くかに初鴨の水脈 晶 |
| いよいよ水辺に鳥たちが戻ってきた。近くの人造湖に今までも鵜や鷺がいるにはいたが、やはり水脈を引いてすいすい泳ぐ鳥が水辺には好ましい。鴨は早いものでは8月の終わりごろから来ているものもあるらしい。先発隊なのであろう。意気揚々とやってきて、まるで、水鳥の季節の到来を告げるかのように池や湖に今年一番のまっすぐな水脈を引く。 |
 |
| 季節によせて vol.123 平成23年10月8日 |
| 汲み置きの水張りつめし十三夜 晶 |
| 十三夜は陰暦九月十三日の夜、その夜の月を「後の月」といい、満月に二日早い少し欠けた月を賞した。新芋を供える中秋の名月を「芋名月」というのに対し、枝豆や栗を供える「後の月」は「豆名月、栗名月」、また「名残の月」とも呼ばれる。なんでも、昔は中秋の名月を見て後の月を見ないのは「片見月」と言って忌み、「二夜の月」を楽しんでいたようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.122 平成23年10月1日 |
| どんぐりこ山の学校一クラス 晶 |
| 台風が明日にも来ようかという日、地区の防災訓練があった。事前の連絡では土嚢を作る係になっていたので、雨風の中で実践さながらの訓練になるのかと、いくらか気が重いまま指定された学校へ向かった。通学路にはまだ青いどんぐりをつけた枝が折れて散乱していた。子供が減ってだだっ広く感じる校庭では雨の中、すでに炊き出し訓練の煙が上がっていたが、土嚢作りは免除され担架設営訓練に回された。 |
 |
| 季節によせて vol.121 平成23年9月24日 |
| 側溝の蓋を鳴らして秋出水 晶 |
| 近頃の雨は、一日で一カ月分の降水量に匹敵するほどのどしゃ降りになることも。各家の雨樋を伝い雨水マスや側溝から下水や川に大量の水が流れ込むので、小さい河川ならあっという間に増水する。それに伴う浸水の被害を防ごうというのか、市が助成金を出して雨水タンクの設置を呼び掛けているのを知った。助成金などの補助は市によってまちまちだろうが、タンクに蓄えた雨水で我が家のような小さな菜園なら十分賄える。興味のある方にはぜひお勧めしたい。 |
 |
| 季節によせて vol.120 平成23年9月17日 |
| 家毀つ埃を鎮め秋の雨 晶 |
地震に強い住宅を意識し始めてか、我家の近くも建替えラッシュ。一軒終わったかと思えば、実は来月から‥という具合で、現在はお隣、お向かいの工事が同時進行中である。建替えで、案外ネックになるのはその間に住まう家だ。ことに動物を飼っている場合、なかなか快く貸してくれる家は少なく、猫を二匹飼っているお隣さんによると、犬はいいけど猫はねえ‥とさらにハードルが高かったようだ。騒音や埃はお互い様。みんな元気で早く帰ってきてほしい。
*毀つ:こぼつ(壊すの意) |
 |
| 季節によせて vol.119 平成23年9月10日 |
| 鰯雲投げては広げピザの生地 晶 |
| 田んぼの真ん中にピザとパスタの店ができた。なんでもイタリアで修行してきたという触れ込みと、すべて手作りというのが人気を呼び、たまに行っても待たされることもしばしば。ガラス越しにピザを作っているところが見えるようになっているため、待っている間も食欲がそそられる。おなかが鳴りそうになるのをぐっとこらえて待っていると、ご注文は決まりましたかとばかりににこっと笑うピザ職人と目があった。 |
 |
| 季節によせて vol.118 平成23年9月3日 |
| 白桃の皮剥く肩の力抜き 晶 |
| 皮がむきにくく、甘さも香りも足りない桃に当たった時は悲しくなってしまうが、改良が進んだのか、近頃はめったにハズレの桃にであわない。親指と人差し指で、少しめくった皮をつまみ、薄紙をはぐようにすうっと剥いていくと、甘い汁がしたたり、良い香りが鼻をくすぐる。独り占めしたい気持ちをぐっと押さえて夫と半分こ。食べ終えて、お皿やフォークを洗ったあとの手にまだ桃の良い香りが残っている。 |
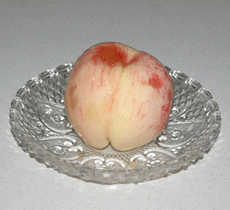 |
| 季節によせて vol.117 平成23年8月27日 |
| 赤とんぼ昔なじみの散り散りに 晶 |
| ふだんは忘れているのに、何かのきっかけでふっと懐かしく思い出されるのが、昔なじみ。学生時代の友達、仕事の同僚、趣味の仲間など、ずっと一緒にいられればそれに越したことはないが、就職や結婚、引っ越しなどいろんな事情で散り散りになることも少なくない。それでも、ある時間を共に過ごした記憶が、一瞬にして長い空白を埋めてくれる。 |
 |
| 季節によせて vol.116 平成23年8月20日 |
| 乗換のホーム込み合ふ残暑かな 晶 |
| 慣れている駅での乗換も込んでいれば大変なのに、不案内な駅ともなるとなおのこと。自称、方向音痴で一人旅が苦手という人と東京駅ではぐれてしまった。今のように携帯電話もない時分で、さぞかし心細いことだろうと、当てもなくホームや構内を探し回ったが結局会えずに帰宅したところ、とりあえず西へ向かう新幹線に乗って先に家についたと連絡があった。ほっとしたと同時にどっと疲れが出た懐かしい思い出。 |
 |
| 季節によせて vol.115 平成23年8月13日 |
| 蓮の香に雲のうすれてきたるかな 晶 |
| 蓮は、お釈迦様の国インドが原産地。その大きな葉を利用した、荷飲(はすのみ)というのがあるそうだ。なんでも、蓮の葉を盃にしてお酒を入れ、その茎に穴をあけて吸うと聞くが、どんな味がするものなのか一度試してみたい。さて、「ハス」を表す漢字だが、延喜2年に記された「手挑灯」によると、「荷」が葉を、「藕」は根を、「蓮」が花を表すのだそうだ。一つの植物でこんなに漢字の使い分けがあるとは知らなかったが、一般には「蓮の葉」「蓮根」「蓮の実」と「蓮」が使われている。 |
 |
| 季節によせて vol.114 平成23年8月6日 |
| 借景の山の麓の端居かな 晶 |
| いつから棲みついているのか、時折、蛙が姿を現す。水やりの水がかかるのか、驚いたように、紫陽花の下から飛び出して、目高の池(実際は、睡蓮を植えている大ぶりの鉢)の中に乱入することも。鉢の縁に座ったり、暑さをしのぐように水の上にちょこんと顔だけ出しているさまは何とも愛らしい。蜩を聞きながら、蚊取り線香の渦が小さくなるまで夕涼みをする。 |
 |
| 季節によせて vol.113 平成23年7月30日 |
| かはほりや木場にうするる木の匂ひ 晶 |
| この頃では、五時からの庭の水やりが終わる頃には少し薄暗くなってきた。ひと月前には西日が眩しいくらいだったのに、季節の進む早さに驚く。運動がてらに夕方川沿いを散歩するが、街灯の明かりが届かない川は生い茂る草の匂いや水の音だけで、流れを見ることはできない。薄暗くなった空を影よりも暗く蝙蝠が飛び交い始める。一見鳥のようだが、蝙蝠は初夏に子供を生み育てるれっきとした哺乳類。 |
 |
| 季節によせて vol.112 平成23年7月23日 |
| 夜濯ぎの水切って星ふやしけり 晶 |
| 初期の洗濯機の脱水はハンドルを回すと、二つのローラーの間から熨斗烏賊のようになった洗濯物がぺらっと出てくるようなものだった。母が勤めていたので、よく手伝わされたが面倒で一度にたくさんローラーにかけてにっちもさっちもいかなくなったこともある。現在、家を改築中の両親は、夜だけ隣にある旧宅に寝ているそうで、不便さも狭さも懐かしく思い出しているようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.111 平成23年7月16日 |
| おのが水脈曲げてヨットの急転舵 晶 |
| 人というのは外見だけではわからない。いつも会うときはきちんと髪を結い、夏でも着物を涼やかに着こなしている人が、ある時、話の弾みで、船舶免許を持ちヨットを操る活発な女性であることを知った。なるほど、そういえば、決断が早く、ここ一番というときの度胸は並々ならぬものがある。彼女と何年も付き合っていながら、気が付かなかったとは。ヨットの運転は無理だが、今度会うときには日焼け対策など教えていただこう。 |
 |
| 季節によせて vol.110 平成23年7月9日 |
| くわくこうや籠にワインとクラッカー 晶 |
| 郭公(カッコー)を旧仮名で記すと、「くわくこう」。なんだかいっぺんにぶかっこうな鳥になったようで申し訳ない表記をしてしまった。実際に声を聞いたことがなくても郭公時計や音楽で親しみのある鳥だが、モズやホオジロ、オオヨシキリなどの巣に托卵し、早く孵化する郭公の雛だけが仮親の世話を受けて成長すると聞けば、その声ものどかで明るいとばかりは言えなくなる。そういえば夕方に聞く声は心なしか物寂しげで、「閑古鳥」という呼び名の方がふさわしいようでもある。 |
 |
| 季節によせて vol.109 平成23年7月2日 |
| 縁なき人とくぐりし茅の輪かな 晶 |
| 夏越(なごし)の祓えは6月晦日の行事。疫病が流行する季節を前に、茅萱で輪をつくり、それを潜ることによって半年間の罪や、穢れ(けがれ)を払おうというもの。私の故郷では輪を潜ることから、輪越しと呼んでいたが、大きな輪を潜るとき、押されて家族とはぐれてしまった思い出がある。母は今でも紙の人形(ひとがた)に私や妹の家族の全員の名前を書いて神社におさめてくれている。 |
 |
| 季節によせて vol.108 平成23年6月25日 |
| ふり向かれあらぬ方へと打つ草矢 晶 |
| 草矢は、青々とした茅草や芒、葦などの葉を矢の形に割いて、指で挟んで飛ばす子供の遊び。子供の頃は誰が遠くまで飛ばせるかなどと、日が暮れるまで投げ合ったものだ。先だって帰省した折、久しぶりにみんなで遊んだ辺りへ行ってみた。芒が生い茂っていた池は埋め立てられ、いつのまにか新しい家が建てられていた。鯉や鮒はどうなったんだろう。草矢にできるような芒も見つけることができなかった。 |
 |
| 季節によせて vol.107 平成23年6月18日 |
| 水路狭まればはげしく行々子 晶 |
| 舟で水郷巡りをした。大雨の後だから浮巣は流れたかもなあと、船頭さんは気の毒がりながら、葦原で狭まる水路に細い舳先を差し入れていく。突然、漕ぐ手を止め葦原の水際を指さし、小声で浮巣の在処を教えてくれた。さすが水郷を知り尽くしていると目を凝らしたが、私には芥の塊にしか見えなかった。小一時間ほどの水郷巡りの間中、時に話が聞き取りにくくなるほどギョギョシ、ギョギョシ、ケケと葭切が騒いでいた。 |
 |
| 季節によせて vol.106 平成23年6月11日 |
| 水たぐりよせては進み水馬 晶 |
| 水の上を駆け回るからではなかろうが、「水馬」と書いて、「あめんぼう」。飴のような匂いのすることから「飴ん坊」の字をあてることもあるそうだが、長めの中と後ろの足を×状に大きく広げて水面を進むところを見ればやはり水馬の方がふさわしいようにも思う。ピンポイントで水に触れている足や、一掻きに揺れる水輪の影が実物よりくっきりと水底に映っている。 |
 |
| 季節によせて vol.105 平成23年6月4日 |
| 短夜の日付変更線を越す 晶 |
| まだ地球が丸いものだと思わず、自分の国が世界の中心ぐらいに思っていた頃には、日付などというものは朝が来れば自然に変わるものというほどだったろう。実際、マゼランが世界一周の航海をしたときはじめて日付の矛盾に気づいたのだそうだ。ジュール・ヴェルヌの「80日間世界一周」の小説も、日付変更線を巧妙に利用した小説。現在は、最も早く日付が変わるのは、太平洋の中ほどにある多くの島々からなるキルギス共和国ということだ。 |
 |
| 季節によせて vol.104 平成23年5月28日 |
| 片付かぬ机辺卯の花腐しかな 晶 |
| 春先からの定まらない陽気に、風邪を引いたり体調を崩した人も多かったのではなかろうか。降れば何となく肌寒いので、我が家もなかなか季節のものの入れ替えがすすまない。旧暦四月の別名が「卯の花月」。その頃に降り続く長雨を卯の花腐し。雨でせっかくの白く清らかな花が腐ってしまうのではないかという思いが感じられる季語。明日は武蔵丸の一周忌。 |
 |
| 季節によせて vol.103 平成23年5月21日 |
| 撥ね上がる泥もめでたき御田祭 晶 |
| かつては集落ごとに行っていた田植えも、今では機械化により家ごとの作業になり、知らぬ間に隣の田植えが終わっているというのも珍しくない。以前に見た神事では、白い装束を着た人たちが運ぶ玉苗を手甲と脚絆で装った早乙女が田植え唄に合わせて植えていくというものだった。以前はどこでも見られた光景が今は神事という行事でしか見られなくなった |
 |
| 季節によせて vol.102 平成23年5月14日 |
| 蔓薔薇を這はせ出窓を開けられず 晶 |
| こと薔薇に関しては凝り性のわが友。力仕事など苦手そうに見えるのだが、薔薇のためなら泉のごとくパワーとアイデアが溢れでてくるようで、蔓(つる)薔薇を這わせるフェンスも、木を切りペンキを塗るところから自分でやって組み立てるのだからまったく頭が下がる。その甲斐あって、年々見事な庭に変身していく。今年もまもなく薔薇の季節。花に囲まれた部屋でのお茶会を今から楽しみにしている。 |
 |
| 季節によせて vol.101 平成23年5月7日 |
| 瀬のしぶき光あげつぐ端午かな 晶 |
| 端午の節句に欠かせない菖蒲は、古くから病や災いを払う香草とされてきた。江戸時代には、菖蒲を「尚武」にかけて武士階級の間で男児の武運を願う行事となり、この風習が町民にも広まったといわれる。春の花の時期を過ぎ、木々は生き返ったように芽を吹き新緑の季節を迎える。五月は早瀬にあがるしぶきも木々を吹き渡る風も光り輝くときである。 |
 |
| 季節によせて vol.100 平成23年4月30日 |
| 刈り込みの強くて芽吹きひしめける 晶 |
垣根と何本かの木の剪定は庭師さんに頼んでいる。込み合った枝を手際よく落し
形を整えてくれるので、春になると、整然と芽を吹く。それに対して、私が鋏を入れる木の芽吹きのなんと大胆なこと。秋の終わりに胸の高さあたりですっぱりと切る宗旦木槿などは、枝の切り口と言わず枝からも幹からも犇めくように芽を吹き収拾がつかないくらいだ。刈り込みのせいもあろうが、暑い盛りに毎日新しい花を咲かせるような樹は芽吹く時からすでに勢いが違うようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.99 平成23年4月23日 |
| なだらかに見えてでこぼこ青き踏む 晶 |
この間まで枯れ一色だったのに、見る間に若草で土手も芝山も生気に満ちてきた。
冬の間は轍があらわだった野原も、柔らかい草に覆われると見違えてしまうほど。
踏青は、春芽生えた青草を踏みながら、野山を散策すること。もとは中国の風習だったのが日本にも伝わったもの。 |
 |
| 季節によせて vol.98 平成23年4月16日 |
| どの石もひつくり返し磯遊び 晶 |
| 彼岸の大潮の頃は一年の中でも干満の差が大きく、遠浅の浜辺には大きな干潟が現れる。浅蜊などの貝を掘るのもおもしろいが、潮だまりの魚や蟹を探すのも楽しい。フナムシなどはどんなにそっと近づいても影や気配で一斉に逃げ出してしまう。ヤドカリ、イソギンチャク、砂の中、岩場の影、流木の隙間、春の磯にはいろんな生き物が犇めいている。 |
 |
| 季節によせて vol.97 平成23年4月9日 |
| 春雨や紺屋に糊を炊く匂ひ 晶 |
| 鯉幟を染めているところを見せてもらったことがある。白い布に描いた鯉の輪郭や鱗にぐいぐいと一定の幅で、勢いよく糊を置いていく。柿渋を塗ったかなり使い込んだ筒状の容器に糊を入れては絞り出す。染め上った後、白く残る線だ。鱗一枚一枚くっきりと仕上げようという意気込みが感じられた。以前はどこの染物屋も糯米を炊いて自家製の糊を作っていたそうだが、今ではあまり見られなくなったそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.96 平成23年4月2日 |
| 蠟燭の火を吹き消してより朧 晶 |
| 思いがけない大震災から半月余りが過ぎた。被災された地に明かりが増えるたび、画面を通して復興の息吹を感じる。どんな小さな明かりも、暗闇の中では希望であり勇気へとつながる。遠くに住む私たちも自分たちにできることから始めている。蝋燭の火を分かち合うように支援の輪を広げたい。 |
 |
|
|