|
|
| 季節によせて vol.200 平成25年3月30日 |
| 鳥小屋の水かへてやり卒業す 晶 |
| 人気グループの「いきものがかり」の名前の由来はグループの男性二人が小学一年生の時、金魚の餌をやる係だったからだとか。なるほどそんな係もあったのかと微笑ましく思ったものだ。病気になったり死ねば悲しい思いはするが、物言わぬ魚や鳥に餌をやり、水を替え、小屋や水槽を掃除したことはきっと長く心に残ることだろう。もうすぐ新学期、心に残るような新しい出会いが生まれる季節だ。 |
 |
| 季節によせて vol.199 平成25年3月23日 |
| 脈絡のなきは叩かれ野焼きの火 晶 |
| 小さな火種でも乾燥した草に放たれると生きもののように燃え広がり、あっという間に野や土手を焼き払う。土地を肥やし、害虫を駆除するために広い牧草地や山あいの田畑で昔から早春の行事として行われてきたが、火を操るのは並大抵のことではない。思いがけない方へ飛び火して大惨事を引き起こす事さえある。ゆえに、あらぬ方へと走ろうとする火は容赦なく踏まれ、叩かれるのである。 |
 |
| 季節によせて vol.198 平成25年3月16日 |
| 白魚を桶の真水に見失ふ 晶 |
| 英語ではice fish というように白魚は半透明な魚。早春に太平洋沿岸でみられる、やはり半透明なレプトケファルスと呼ばれる鰻や穴子などの稚魚とは違い、立派な成魚で、産卵のため河口に遡上してくるのだそうだ。黙阿弥の、「月もおぼろに白魚の、篝もかすむ春の宵‥」で有名な大川端(隅田川の吾妻橋より下流の右岸一帯)の白魚漁の篝火は江戸時代、春の到来を告げるものであったようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.197 平成25年3月9日 |
| 瀬頭のわけてもひかり猫柳 晶 |
| 「猫柳」は花穂の銀毛が猫を思わせるので、「猫柳」と呼ばれているが川柳(かわやなぎ)の季節的な愛称である。日当たりのよい小川や渓流沿いに自生し、葉よりも先にふわふわとした花穂を上向きにつける。銀色の毛がきらめくさまは、少々風は冷たくても春が来た喜びを実感させてくれる。産卵をひかえた魚が柳の根元の川べりに乗っこんでくるのももうまもなく。 |
 |
| 季節によせて vol.196 平成25年3月2日 |
| 雛の間に時を知らせるものあらず 晶 |
| 人々に時刻を知らせる時の鐘が一般的になったのは江戸時代だと言われる。寺院や町内に設けた鐘楼で、日の出時の明け六つ、正午の九つ、暮れ六つまで六回、それぞれの時刻の数だけ鐘が打たれたそうだ。ところで、現代につながるような雛飾りが町人の間で流行りはじめたのも江戸時代。いろいろな調度に趣向が凝らされた雛が飾られた部屋では雛菓子や白酒がふるまわれ、ゆったりとした豊かな時が流れていたことだろう。 |
 |
| 季節によせて vol.195 平成25年2月23日 |
| 紅梅は淵白梅は早瀬かな 晶 |
| 一月が寒い年の二月はなぜだか暖かいと天気予報の時間に聞いたとおり、たっぷりふりそそぐ二月の日差しに梅の開花も早まったようだ。清楚なイメージの白梅、艶やかでどちらかというと女性をイメージさせる紅梅。同じ植物でも色によって受ける印象やイメージがこれほど異なる花も多くはあるまいと思いながら、梅林を見下ろしているとふと掲句のように紅梅のあたりが淵のように見えたのである。 |
 |
| 季節によせて vol.194 平成25年2月16日 |
| 下波に押し戻さるる若布刈竿 晶 |
| 鳴門と言えば灰干し糸若布(いとわかめ)が有名だったのだが、最近は灰の成分が問題だとされ、昨今は塩蔵品が主流になっている。灰干し若布に慣れ親しんだ者にとってはやや物足りない気がしていたが、先だって、鳴門の鯛が食べたいという夫に付合い、漁師さんが開いているお店で鯛定食を頼んだところ、御膳についてきた味噌汁の若布の量とその柔らかさと美味しさに三度驚いた。 (若布刈竿:めかりざお) |
 |
| 季節によせて vol.193 平成25年2月9日 |
| 待春や艶の出るまでココア練り 晶 |
| 日ざしに明るさが増したとは言うものの本物の春が待ち遠しい。ココアはカカオ豆の脂肪分を抜いてお湯やミルクにも溶けやすくしたもので、オランダのヴァンホーテンがその技術をあみだした。それでも、急いで混ぜるとだまができやすいのでじっくりと練らなければならない。昔はスプーンが立つほど濃厚な飲み物だったと聞くが、私は熱々のミルクをたっぷり加える。たっぷりココアが入ったカップを両手に包み込むと寒さもしばし忘れてしまう。 |
 |
| 季節によせて vol.192 平成25年2月2日 |
| 板塀の板のささくれ虎落笛 晶 |
| 「虎落笛」と書いて「もがりぶえ」と読むが、楽器ではなく、寒く風の強い日に、立木や電線など様々なものに激しい風が吹きつけて鳴るヒューヒューという音と言えば誰しも聞き覚えのある冬の音だろう。暖かい部屋の中でさえその風の音を聞くとぶるっと身震いがするほど寒さが増してくるような気がする。間もなく立春だがこの時期の寒さが一番こたえる。 |
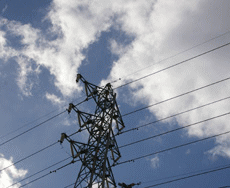 |
| 季節によせて vol.191 平成25年1月26日 |
| 寒鯉の息をひそめし水の張り 晶 |
| 鮒と鯉の一番の見分け方は口髭があるかどうか。鯉には端午の節句の鯉幟を見てもわかるように立派な2対の口髭がある。雑食性で何でも食べる大きな口には喉の奥に咽喉歯という歯があり貝でも砕いてしまうのだそうだ。そんな鯉も寒さ厳しい季節は流れのない深みに潜んでいるようでなかなか釣れないとのこと。滋養たっぷりの寒鯉を釣り上げるには相当の寒さ対策と忍耐が必要なようだ。 |
 |
| 季節によせて vol.190 平成25年1月19日 |
| 十字架に嘴をぬぐひて初鴉 晶 |
| 暮も正月もなく真っ黒黒づくめの鴉(カラス)、大胆にも、教会の十字架で丹念に嘴をぬぐっているではないか。どうせ、その辺のごみ箱をあさって肉か魚の切れ端を失敬してきたのだろうが、教会の木の十字架はそんな罪深い鴉にさえ止り木になって安息を与えている。さんざん十字架に嘴をなすりつけ満足したのか鴉は力強く十字架を足蹴にして、カアと鳴いて飛び去ってしまった。なんと、傍若無人な鴉!神様、来世は鴉にだけはしないでくださいと願った。 |
 |
| 季節によせて vol.189 平成25年1月12日 |
| をさなごの絵とも文字とも筆始め 晶 |
ここ数年、私と妹は家事手伝いと称して遠慮し、婿殿たちは互いに譲り合い、子供たちはそれぞれの用事で帰省できないこともあって、書初をするのはついに父だけになってしまった。暮からきれいに掃除をして、条幅が書けるように支度をしてくれているのに、やはり普段から筆をとらない者にとってはこの書初の時間はいささか苦痛でもある。
しかし、字を書くことが父の元気の源ならと、心を入れ替え今年は参加することにした。 |
 |
| 季節によせて vol.188 平成25年1月5日 |
| 餅搗いて臼に木の香のよみがへる 晶 |
| 現在流通している木製の臼の大部分は欅だそうだ。臼はただ硬くて丈夫なだけではだめだそうで、水に強く粘りのある木でないと罅が入ったり割れたりするのだそうだ。一本の欅で一つしか作れない根に近い部分の根臼はかなり高価なようだが、家庭用やレンタルでもそれなりに良いものが出回っているようだから、家庭や子供会などの行事で腕に覚えの杵をふるった方もいらっしゃるのではないだろうか。 |
 |
| 季節によせて vol.187 平成24年12月29日 |
| 欲りし時には見当たらず龍の玉 晶 |
| 犬走りの縁に竜の鬚が植えてある。家を建てた時、父が植えたのだが、何十年もたち株が盛り上がるまでに育っている。初夏には薄紫の小さな花をつけ、緑の小さな玉を結ぶ。そして、冬の日差しが低く届く頃には艶々とした濃紫色の実になる。葉をかき分けて美しい実を探したことも懐かしい思い出だが、今では足元がおぼつかない母が家の周りを散歩するには滑りそうでいささか邪魔な存在になってきた。 |
 |
| 季節によせて vol.186 平成24年12月22日 |
| 大輪と言はむ花咲蟹茹でて 晶 |
| 花咲蟹の殻を覆う棘を見るたび薔薇やサボテンを見る思いがする。ここまで武装しなくてもと思うが、ベーリング海など北の海には鋭い歯を持つ天敵も多いのだろう。タラバガニより足は短いが太いので食べごたえは十分だ。母などは手が汚れるからと蟹を嫌うが、やはり冬の味覚の一、二を争うものだろう。食べているとついつい口数が少なってしまうので気の置けない人と楽しみたい。 |
 |
| 季節によせて vol.185 平成24年12月15日 |
| 日の高きうちに戻りて浮き寝鳥 晶 |
| 探鳥会の人たちの鳥の観察はまことにこまやかだ。私などは大雑把なものだから「鴨が潜った、餌を採った」と言うと、「あれは逆立ちだ。」と仰る。潜るのは海鴨で小魚や貝などを採るだそうで、池などに入る淡水鴨は逆立ちして届く範囲で水草や藻を食べるのだそうだ。飛び立つときも水面を蹴って走りながら飛ぶのは海鴨、滑走せずその場から垂直に飛び立つのは淡水鴨と教わった。なるほど、そうして注意深く見ていると顔つきも尾羽の長さも違って見えてきた。 |
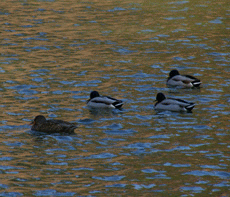 |
| 季節によせて vol.184 平成24年12月8日 |
| ぎこちなく揺れて蓮の枯れはじむ 晶 |
| 春に植えた蓮(蓮植ふ)は、夏には青々と葉を広げ美しい季節(蓮浮葉・蓮・蓮見)を迎える。お盆に花の蕾を仏様に供え、爽やかな風が蓮田の葉を吹き渡る秋には(蓮の飯・秋の蓮・蓮の実・敗蓮)が、そして田も畑も枯れる冬には(枯蓮・蓮根掘る)と季語を提供してくれる。蓮の一年は人の一生のようだというような句があるが言われてみればなるほど、私の頭も体も固くなってきたことよ。 |
 |
| 季節によせて vol.183 平成24年12月1日 |
| 蟷螂の鎌まつさきに枯れはじむ 晶 |
| 初冬に見る褐色の蟷螂(かまきり)、あれは冬になったから緑から茶に変色したものではない。もともと茶色の蟷螂なのだが、昔の人は草木が枯れるように生気が抜けて色褪せたと感じ「蟷螂枯る・枯蟷螂」という季語が生まれたそうだ。産卵期を迎えた初冬、餌の乏しくなった雌は交尾後、雄を喰い殺し卵を産んだのち自らの命も閉じるのだそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.182 平成24年11月24日 |
| 蜜蜂の巣箱出て飛ぶ小春かな 晶 |
今でも渡し舟があるというので目と鼻の先の対岸まで舟に乗せてもらった時のこと。
乗り場も舟着き場も板があるだけでさほど利用する人も入るまいと思われる草深い所。だからか、珍しく蜜蜂の巣箱がいくつか無造作とも思えるように置いてある。温暖な土地柄とはいえ、花の少なくなったこの時期どんな蜜を求めて蜂たちは飛ぶのだろう。 |
 |
| 季節によせて vol.181 平成24年11月17日 |
| 口能登の駅に乗換へ初時雨 晶 |
| 能登半島の付け根のあたりを口能登と言うのだそうだ。半島を巡る鉄道も昔はあったようだが今は列車とバスを乗り継いで行くほかはないと地元の人が説明してくれ、そのついでに弁当忘れても傘忘れるなという地元の言い伝えも教えてくれた。折りたたみ傘は準備していたもののこんなに良い天気なのにと高をくくっていたら、一駅もいかないうちに時雨れてきた。 |
 |
| 季節によせて vol.180 平成24年11月10日 |
| 藍甕の藍揺り起こし夜なべかな 晶 |
秋の夜長に昼間出来なかった仕事の続きをすることを「夜なべ」と言ったが、藁(わら)仕事や繕い物など実際に目にすることは少なくなった今では残業の色合いの濃い「夜業」の意味で使われることが多いようだ。家人が寝静まった中一人で起きているのは集中できるようでもなんとなく寂しいもので、私の場合、寝ている犬をつついてしまう。
*甕:かめ |
 |
| 季節によせて vol.179 平成24年11月3日 |
| 墳山に拾ふ木の実と鳥の羽根 晶 |
| 私が住む団地は丘陵地を開発して造成したところなので、6世紀頃の物と言われる古墳がいくつか遺構として残されているし、発掘作業が続いているところもあるらしい。家が建ち並び、道は整備されても古墳のあったところは公園となって伐りのこされた木々が枝を張り木の実をつけて今でも野鳥のよりどころとなっている。 |
 |
| 季節によせて vol.178 平成24年10月27日 |
| こころざし半ばに枯れて菊の志士 晶 |
| 菊人形には大河ドラマをテーマにしたものが多いように思う。いつだったか、幕末に活躍した志士たちが新選組と戦っている菊人形があった。見たところ浪士とは思えぬほど立派な菊の衣を着ているのだが志士の袖口が枯れ始めているではないか。人いきれや暑さで水切れを起こしたのかもしれないが、心なしか太刀筋は新選組の人形の方がよさそうに思えた。 |
 |
| 季節によせて vol.177 平成24年10月20日 |
| 宿木の玉から玉へ小鳥来る 晶 |
| 春、南の国から渡ってきて繁殖し、秋にまた南の国に渡って行くものを夏鳥と言い、その代表的なものに燕(つばめ)や大瑠璃(おおるり)、郭公(カッコー)がいる。「小鳥来る」の場合の小鳥とは、秋に北の繁殖地から渡ってきて冬を越し、春になると北の国へ渡っていくツグミ、レンジャク、ヒワなどと、山から平地に下りて来るカラ類の留鳥をいうようだ。燕のように高い空をすいすい飛ぶのではなく、目の前の枝をひょいひょいと移動して目を楽しませてくれる。 |
 |
| 季節によせて vol.176 平成24年10月13日 |
| ひと枝を引けばみな揺れ萩の花 晶 |
| 落葉低木でありながら秋の七草の筆頭にあげられるほど「萩」は昔から日本人にはなじみ深い植物。いつのまにか咲き、また散るのでいつが盛りなのかさえ定かではない。以前伺ったお宅に紅白の花が入り混じった株立ちのみごとな源平萩があったので、たわむれにひと枝引っ張ってみたところ、源平合い乱れるかのように枝が揺れた。 |
 |
| 季節によせて vol.175 平成24年10月6日 |
| 蟷螂の強き一辺倒の斧 晶 |
| 蟷螂(かまきり)には細長い前翅と扇形に広がる後翅があるが、多くの蟷螂は飛行が苦手で短距離を直線的に飛ぶのが精一杯なのだそうだ。してみると、扇状に翅を広げているのは、もっぱら相手を威嚇するためのものか。威嚇といえば、鎌と呼ばれる前脚を持ち上げて獲物を待ち伏せする姿をよく見る。その姿から日本では拝み虫とも呼ばれるが、ギリシャ語の学名では預言者という意味もあるらしい。そのかなりユニークな風貌がいろんな想像をかきたててくれる。 |
 |
| 季節によせて vol.174 平成24年9月29日 |
| 衰へぬ日差しを返し椿の実 晶 |
| 椿は花と実の季節に季語を持つ。椿の実が季語になったのは食料や燃料、整髪料と利用価値の高いものだったからだろうか。美しく有用な椿も実は競走馬や馬術競技の世界ではツバキの名前は人気がない。萼を残して首から落ちるところから落馬を連想させるようだ。実際、第36回日本ダービーで本命視されていたタカツバキという馬が落馬のアクシデントで競走中止になった。戦時中はゼロ戦の燃料としても使われたという椿油、環境に優しい油として平和利用したいものだ。 |
 |
| 季節によせて vol.173 平成24年9月22日 |
| まなぶたの薄きを閉ぢて虫の夜 晶 |
| 西洋では単なる音としてしか認知されない虫の音を、われわれ日本人は言語を司る左脳で聞いているため、「虫の声」として捉えるのだと以前聞いたことがある。それゆえ、昔から庭に放したり、美しい虫籠に飼ったり、声を競わせたりして秋の夜長の楽しみとなっていたのだろう。家人が寝静まった夜更け、眠りにつくまでのひとときを虫の声にじっと耳を傾けると闇に立体感が生まれてくるような気さえする。 |
 |
| 季節によせて vol.172 平成24年9月15日 |
| 打つ音を山に返してばつたんこ 晶 |
| ばったんこは"添水","ししおどし"とも言われ、竹筒に水を引き入れ、たまる水の重みで反転した竹筒が石などに当たって「コン」という音を立てるようにした装置で、田畑を荒らす鳥獣を威し追い払うためのものである。戦国時代、長篠城が武田勝頼に包囲されたとき夜陰に乗じて家康に援軍を請いに走った鳥居強右衛門終焉の地にもよく響くばったんこが鳴っていた。 |
 |
| 季節によせて vol.171 平成24年9月8日 |
| 生垣の影ののびくる秋簾 晶 |
| 庭師さんが体を壊したため、今年はいつもの年より庭木の剪定が遅れた。32年前にここへ移り住んだ時に植えた木はそれなりに大きく育ち、貝塚伊吹の生垣はいつしか夫の手に負えなくなってきた。日差しの届かない地面にはひとさし指の太さほどの蝉の穴があちらこちらに目につく。蝉の抜け殻のしがみついたアメリカ花水木の影が真夏より心もち長くなったようだ。
(簾:すだれ) |
 |
| 季節によせて vol.170 平成24年9月1日 |
| 吊屋根の上に大屋根震災日 晶 |
| このところ日本のあちらこちらで地震活動が活発で、言われ続けている東海地震も遠い話ではないような気がしてきた。懐中電灯、非常食、水と、思いつくままリュックに詰めて背負ってみたら案外重い。欲が深くて命を落としては何もならないと荷物を減らしていると、面白そうに見えたのだろうか、犬がリュックに入りたそうに寄ってきた。 |
 |
| 季節によせて vol.169 平成24年8月25日 |
| 息をつぐことも惜しみて法師蝉 晶 |
| 8月も終わりに近づくと、かしましく鳴いていた油蝉やクマゼミにまじり、つくつく法師が鳴き出す。点火した導火線のようにジュジュジュジュと鳴き出し、ホーシツクツクホーシ、ツクツクホーシと全身で鳴く。この鳴き声は一説によると、旅先で死んだ筑紫の姫が蝉となって筑紫恋しと鳴くという言い伝えから「筑紫恋し」と聞きなされてもいるそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.168 平成24年8月18日 |
| 草市やはかなきものの嵩張りて 晶 |
| 草市は、陰暦7月12日の夜から13日にかけて、魂祭に用いる蓮の葉や真菰筵、真菰の馬、溝萩、茄子、鬼灯、苧殻(おがら)などを売る市で、所によっては盆の市とも呼ばれている。神棚はあったが仏壇のない家で育ち、婚家にもそのような習慣がなかったので、実際、草市で求めてきたものをどのように祀るのかを知ったのは俳句を通してといってもよい。俳句は、簡素化されたりなくなりつつある伝統行事を伝える大事な要素も担っている。 |
 |
| 季節によせて vol.167 平成24年8月11日 |
| 汁の実に香りたつもの今朝の秋 晶 |
| 朝のうちは曇っていたが、今日も最高気温を更新しそうな勢いで、ぐんぐん太陽が威力を増してきた。今年は7日が立秋だったが、まだまだ夏真っ盛りである。節電二年目、午前中は意識してエアコンを使わないようにと思っているが、何もしなくても汗がしたたり落ちる。食欲不振ぎみの犬にはドッグフードにお肉のトッピングを、飼い主には紫蘇、茗荷、生姜、葱と香りのよいものをたっぷりと刻んだ冷やしうどんを昼食に用意した。 |
 |
| 季節によせて vol.166 平成24年8月4日 |
| 肘掛に肘をあづけて夜の秋 晶 |
| 8月もお盆近くになると、昼間の暑さや仕事から解放された夜のひと時、ふと秋の気配を感じることがある。それは、風にそよぐ葉擦れの音だったり、草むらから聞こえる虫の声だったりする。眩しい太陽にいじめられた眼より、耳や皮膚の感覚の方が微妙な季節の移り変わりを敏感に捉えられるのかもしれない。食卓の椅子の肘掛が腕に少しひんやりと感じた。 |
 |
| 季節によせて vol.165 平成24年7月28日 |
| 涼しさや渡り廊下を水の上 晶 |
| 家作りは、冬より夏の暑さを考えた家でなければならないと聞いたことがある。蒸し暑い日本の夏、少しでも快適に過ごすために、先人たちはさまざまな工夫をしてきた。襖や障子を外し、簾(すだれ)や葭簀(よしず)をめぐらして、軒には釣忍や風鈴を吊るした。夕方、下駄ばきで打ち水をすると涼しい風が生まれる。蚊遣り香をたきながらの縁台将棋や花火も夏ならではの光景だろう。節電の昨今、また、このような暮らし方が見直されているようである。 |
 |
| 季節によせて vol.164 平成24年7月21日 |
| 眼に力戻りぬ深山清水飲み 晶 |
| 水を当たり前のように買って飲むようになったのはいつ頃からだろう。フランス産の水がスーパーに並んでいるのを初めて見た時には驚いたが、今では○○天然水、△△深層水、はては自治体の水道水まで売られているという具合だ。それぞれおいしいには違いないが、やはり汗水流しながら登った山の水にまさるものはないだろう。体の芯にまで響くような冷たい水に手を入れて水を汲めば、山の気まで体の中に取り込むような思いがするのである。 |
 |
| 季節によせて vol.163 平成24年7月14日 |
| 雨雲の上へ抜け出てお花畑 晶 |
| 夫と山へ行くと必ず雨に逢う。立山に行ったときなど、七月でも歯の根が合わなくなるほど寒い思いをしたが、おかげで雷鳥の親子にも手の届きそうな距離で出会えた。雷鳥は天気の悪い方がよくみられると聞いたが、雛を守るにはガスに覆われたような天候の方が出歩くには好都合なのだろう。翌日、眩しいほどの快晴となった。ガスで何も見えなかった高山植物が雨の滴をつけて輝いていた。 |
 |
| 季節によせて vol.162 平成24年7月7日 |
| お見合の席とおぼしき青すだれ 晶 |
| お食事処や喫茶店では相席にならないまでも、お互いの顔が見えたり、話が聞こえてしまうことがままあるが、そんなときはまちがっても聞き耳を立てたりじろじろ見たりしてはいけない。何年か前、偶然にも掲句のような場面に遭遇してしまったことがある。一人が「あらっ、‥‥」と呟いたのをきっかけに、一瞬私たちのテーブルは静まり返ってしまった。少し離れているとはいえ、と戸惑っているところへタイミングよく料理が運ばれ、もう誰も簾の向うのことに気を留めなくなった。 |
 |
| 季節によせて vol.161 平成24年6月30日 |
| 誰とでもすぐにうちとけ心太 晶 |
昨年の秋、二代目武蔵丸が我が家に来た。初めて見た時は先代と瓜二つと思ったが、やはり顔も鳴き声も少しずつ違う。家に来たのが離乳食の時期だったので甘やかしてしまったと反省していた頃、パピー教室の体験案内があり参加した。誰にでも尻尾を振って、大きな犬にも人にも物怖じしないのは良いのだけれど、トレーニングが始まってもいたってマイペースなのだ。結局、犬ではなく、きちんと叱れない私に問題があると気付き、躾け教室は一度で辞めてしまった。
(心太:ところてん) |
 |
| 季節によせて vol.160 平成24年6月23日 |
| 穂先まで力ゆるめず今年竹 晶 |
| 今年もありがたいことに、掘りたての筍をいただいた。よくぞ見つけたと思う手のひらサイズの物や、包んだ新聞紙からはみ出すような立派に育ったものまでさまざま‥。小ぶりの筍なら姫皮を細く刻んで梅干しで和えても美味しいしと、茹でながら献立を考えるのも楽しい。筍売りのおばさんも姿を見せなくなったこの頃、鍬の一撃を免れた竹の子が、いつの間にか人を見下ろす高さに育っていた。 |
 |
| 季節によせて vol.159 平成24年6月16日 |
| これは美酒これは美女の名薔薇園 晶 |
| 適当に集めた薔薇が今では結構な数になった。インターネットや専門店で買ったほか、挿木で育てたものもある。植え替える時、名札も気を付けるようにはしているのだが、うっかり名札がなくなることも。葉に特徴があるものならまだしも、こうなったら花が咲くまではわからない。インクの文字の消えかかったのや、いただいた挿木など名前の不明な鉢があったが、それもようやくそれぞれ花が咲いて名前を思い出すことができた。 |
 |
| 季節によせて vol.158 平成24年6月9日 |
| 生真面目のときに気づまり栗の花 晶 |
| ある集まりで、優先席しか空いていない電車に乗った時どうするかという話になった。空いているのだから構わず座るという人もいたが、だいたいは、少し気は引けるが、取りあえず座って座席を必要とする人が来たら譲るという人がほとんどだった。先日、そんな場面となり、どなたかが来られるまでと思い四人掛けの優先席に座ったところ、同年輩の二人連れに目の前に立たれてしまった。お二人は優先席だからと遠慮されてのことだと思うが、私は一人肩身の狭い思いで目的地まで座っていた。 |
 |
| 季節によせて vol.157 平成24年6月2日 |
| 薄墨の墨より淡く目高かな 晶 |
| 庭に小さな睡蓮鉢があり、孑孑(ぼうふら)対策に目高を飼っている。冬は氷が張ることもしょっちゅうで目高には良い環境とは言えないが、ありがたいことに今年も何匹かは冬を越してくれた。目高係の主人は、春、目高が動き出す前に、鉢の掃除をして水を替え、新しい目高を仲間に加える。鉢がきれいになって水が光るうえに、目高が透けるほどなので、すばしっこい目高の動きに目がついていけない。 |
 |
| 季節によせて vol.156 平成24年5月26日 |
| 風薫る水面へと跳ね池の鯉 晶 |
| 「青嵐」は、夏、緑の林や草原などを吹き渡る風のことを言うが、「風薫る」は青葉を渡ってくる匂うように清々しい風のこと。和歌の時代には花の匂いを起こす春の風の意味だったようだが、漢詩で夏の南風の意味で用いられていた薫風が近世、夏の季語として定着したようだ。車で15分ほどのところに恩賜池と言うがあるが日に日に濃くなる若葉を映して水面も緑が深まってきた。 |
 |
| 季節によせて vol.155 平成24年5月19日 |
| 石垣を坂もて結び花みかん 晶 |
| ふるさとはみかんのはなのにほふとき 漂泊の俳人種田山頭火の句であるが、生まれ故郷の山口を思っての句であろうか。ふっとただよってきた蜜柑の花の匂いに懐かしく幸せだったころの故郷を思い出したのかもしれない。嗅覚は時に様々な記憶を呼び覚ます。そういえば、祖父の蜜柑山のはずれに、石を積んだだけのお遍路さんの墓があったが今もそのまま残っているのだろうか。 |
 |
| 季節によせて vol.154 平成24年5月12日 |
| 沸くやうに蕾開きて白牡丹 晶 |
| 母のお見舞いにと近所の人が丹精込めて育てた牡丹をくださった。ふっくらとした蕾からはすでに何とも言えぬ良い香が溢れだしている。明日は咲くだろうとの言葉通り、子供の拳ほどだった蕾は、花びらが花びらを押し開くように咲き始め、終にはたなごころ二つ分ほどの見事な大輪となった。こんなに間近でじっくりと見たことがないと目を細める母を病院へ戻るまでの二日間、一輪の牡丹が楽しませてくれた。 |
 |
| 季節によせて vol.153 平成24年5月5日 |
| 駆け上がるやうに日の出て端午かな 晶 |
端午は5月5日の男子の節句で、菖蒲の節句ともいい、菖蒲を尚武にかけて男子の成長や武運長久を祈願するようになったと言われる。かつては菖蒲を軒に吊るす風習があったようだが、近頃ではあまり行われずかろうじて菖蒲風呂をたてるくらいだ。
この菖蒲は花菖蒲とは違いサトイモ科の多年草で独特の香気を放ちその根が薬用になるそうだ。 |
 |
| 季節によせて vol.152 平成24年4月28日 |
| 吹きゐし子もろともに消えしやぼん玉 晶 |
| しゃぼん玉はすぐ壊れるものと決まっていたが、近頃はしゃぼん液に工夫がしてあるようで、つついても割れないものや、人が入れるほど大きなものなど様々なしゃぼん玉がある。しかし、どんなに筒のようなものでも最後に玉になるところがおもしろい。今風のしゃぼん玉も楽しいが、そっと息を吹き込んでどきどきしながら虹色の玉を育てたしゃぼん玉が懐かしい。ふっと消えてしまうのもしゃぼん玉の魅力だと思うのはおばさんになったからだろうか。 |
 |
| 季節によせて vol.151 平成24年4月21日 |
| 春深し綯ひたる縄の渦重ね 晶 |
| 見た目には簡単そうでも縄を綯うという作業は案外難しい。藁(わら)を足しながらてのひらで撚り(より)をかけていくのだが、まず太さと固さが均一にならない。それでもって、藁の初めと終わりがほつれ髪のように縄からはみ出す。自分の髪を三つ編みにしたことさえないのだから初めから無理だったのだ。ごわごわと厚みのある手が綯う縄が生き物のように輪を成すさまを時間がたつのも忘れて眺めた。 |
 |
| 季節によせて vol.150 平成24年4月14日 |
| 下ろしたる帆も風を受け花見舟 晶 |
| 間の悪いことに、舟を予約した日はあいにくの雨。川面から見る桜はさぞかしと楽しみにしていたのに風交じりの雨で覆いがあるにもかかわらずびしょ濡れに。「俳人の俳は人に非ずなんだから」と強がってはみたものの、誰も次第に歯の音が合わなくなって初めの勢いはどこへやら、さんざんな花見になってしまった。後日、通りすがりに見た花見舟のなんと楽しげだったこと。 |
 |
| 季節によせて vol.149 平成24年4月7日 |
| 永き日や箍を外して樽洗ひ 晶 |
| 三年寝かすと言われる八丁味噌の仕込み蔵。大地震でも崩れないという技で円錐に石を積み上げた6尺の樽からは味噌のエキスが染み出す。匂いが充満して蔵そのものが味噌樽のようだ。古いものでは天保年間の樽もあったが、今ではこんなに大きな木の樽を作る職人はいないそうで、現存する樽を修理しては大事に使っているということだ。箍(たが)を外されてばらばらになった板が束子をかけられ行儀よく干されていた。 |
 |
|
|